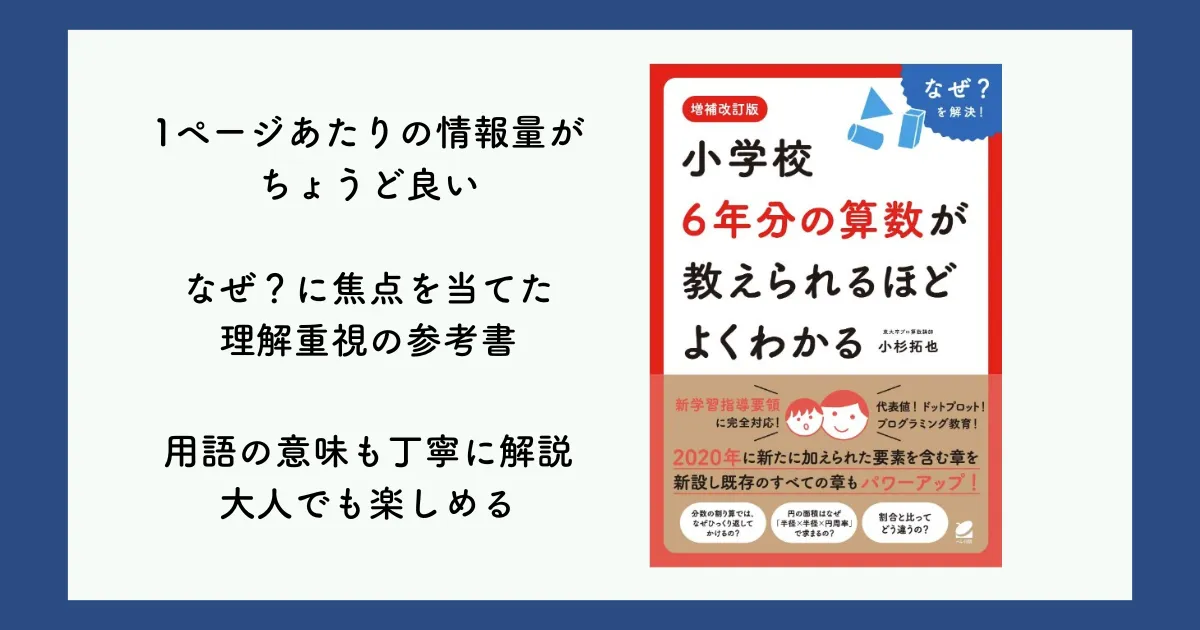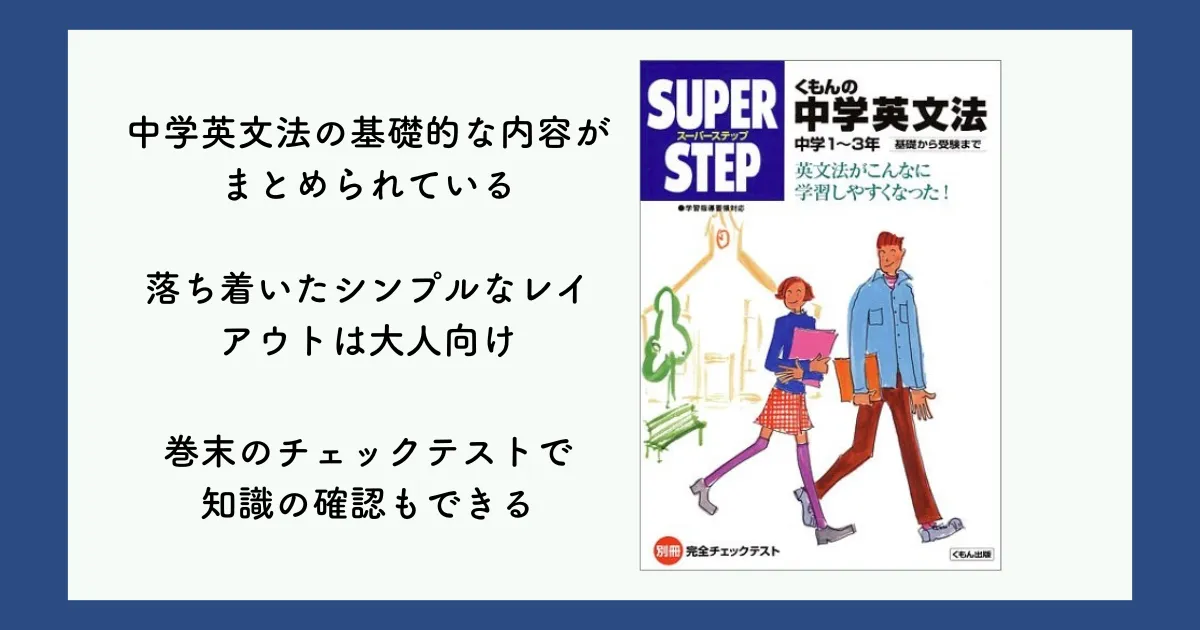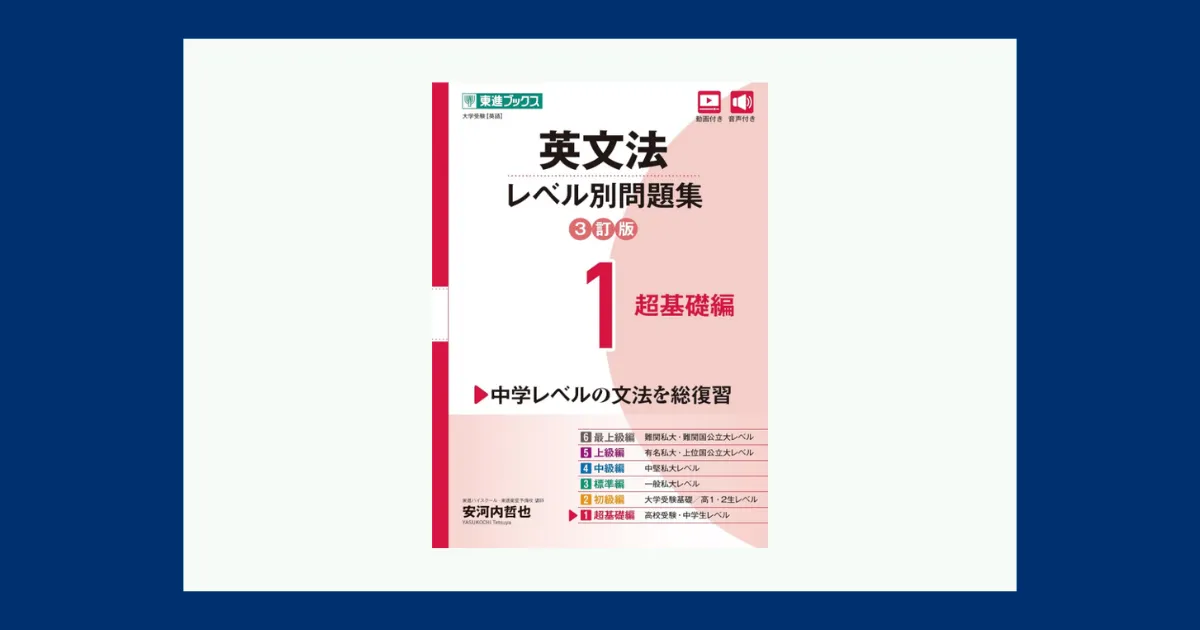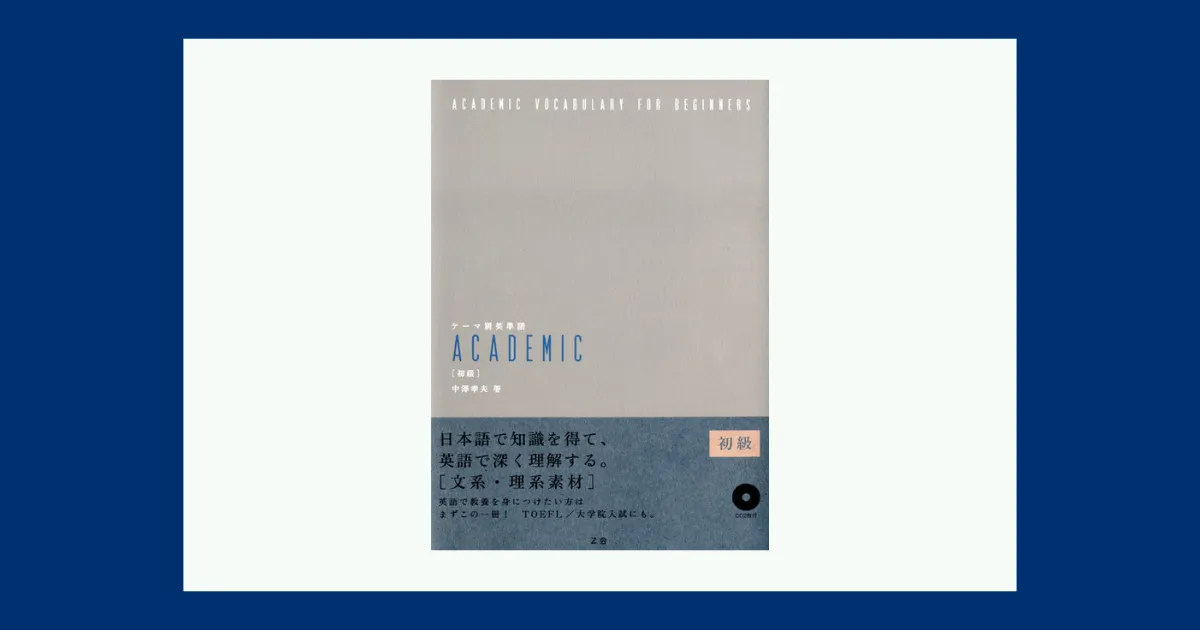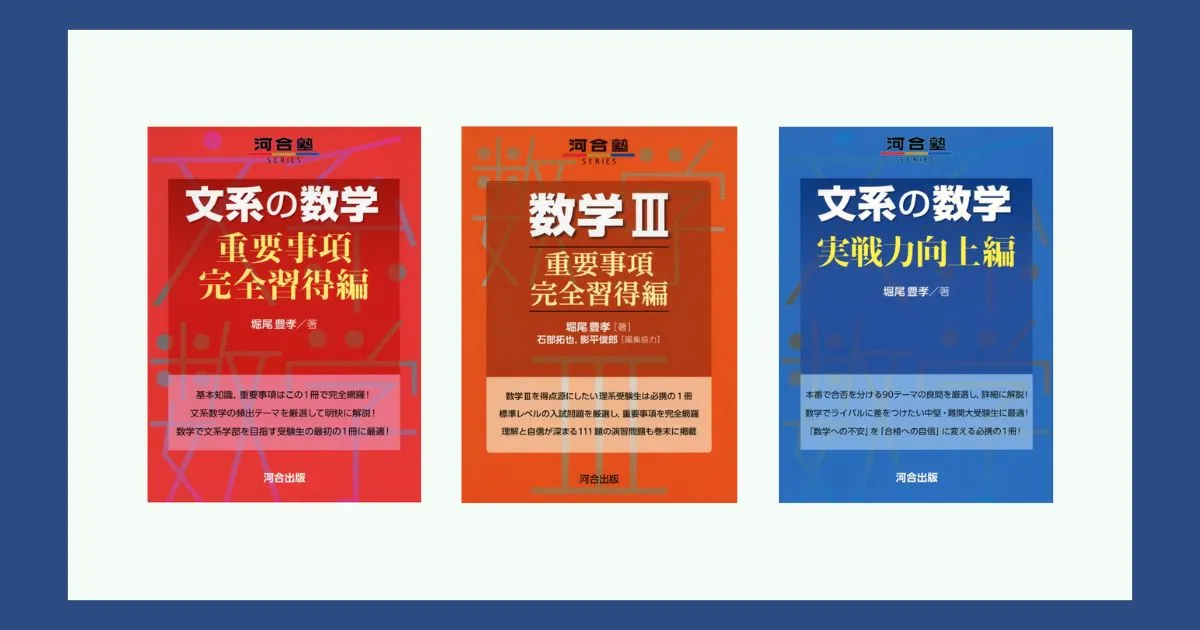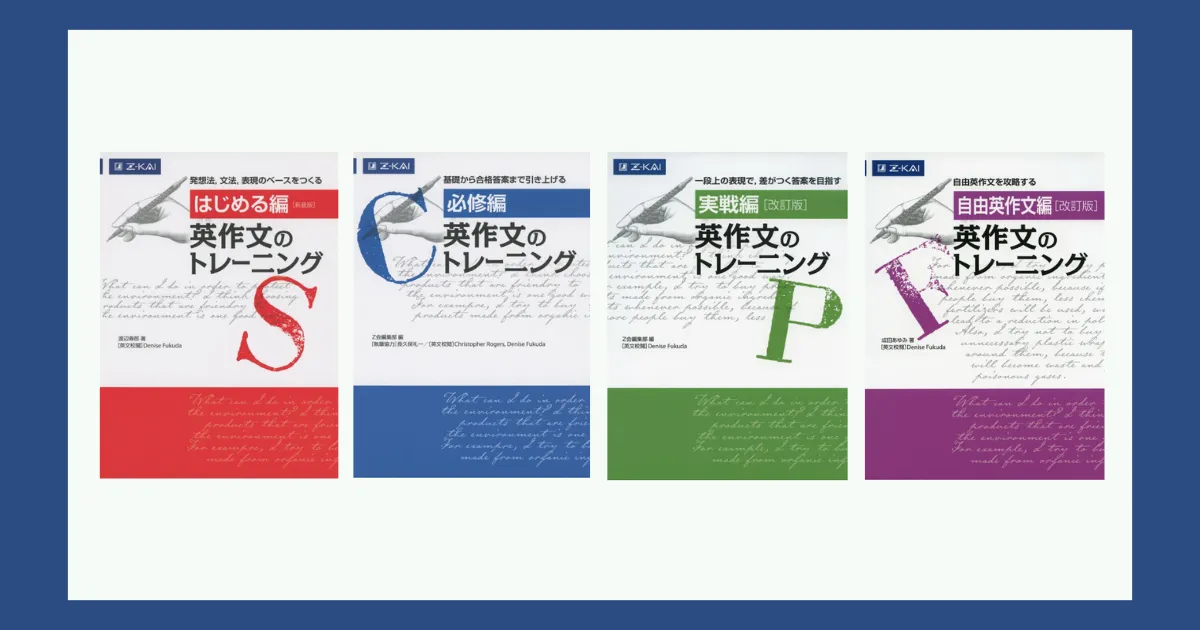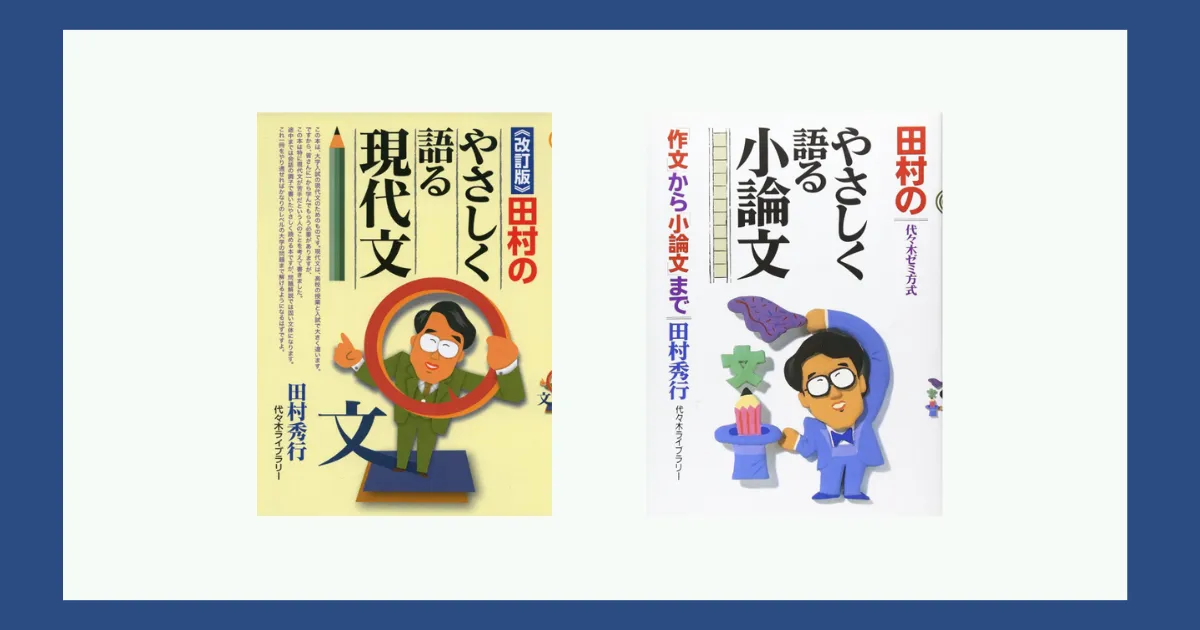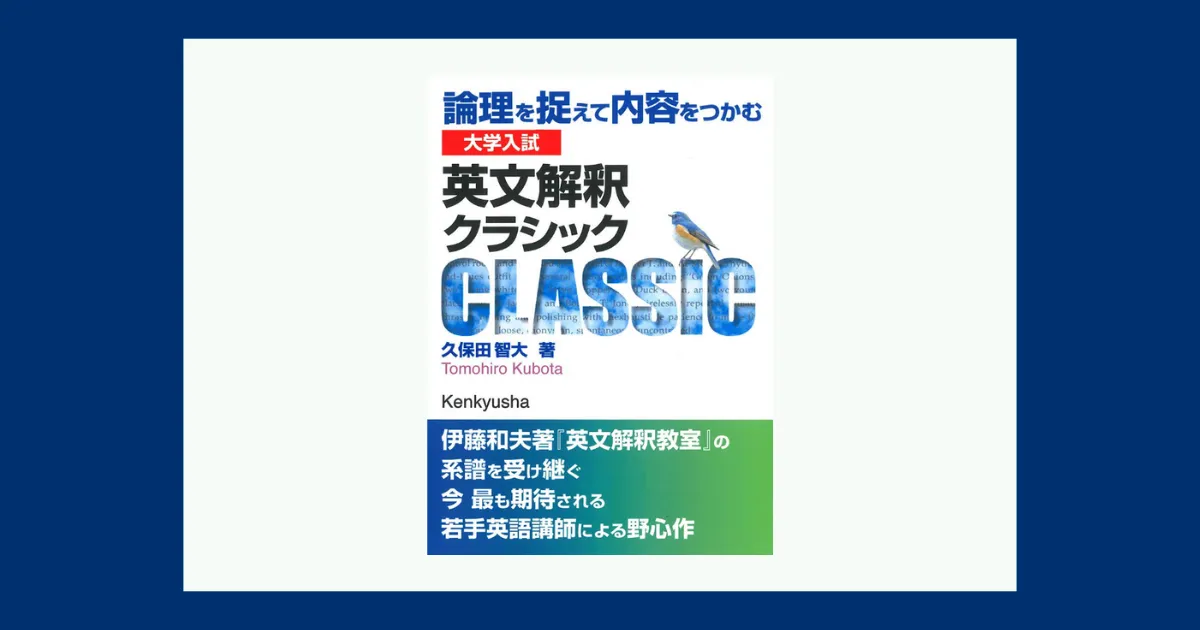| タイトル | 小学校6年分の算数が教えられるほどよくわかる | |||||||||||
| 出版社 | ベレ出版 | |||||||||||
| 出版年 | 2020/7/14 | |||||||||||
| 著者 | 小杉拓也 | |||||||||||
| 目的 | 小学算数の復習 | |||||||||||
| 対象 | 小学算数を学び直したい全ての人 | |||||||||||
| 分量 | 352ページ | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| AI | 単元ごとに問題を生成して定着を促進したい | |||||||||||
| レベル | 小学復習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
小学算数を学び直す
本書は2020年にベレ出版から出版された小学算数を理解するための参考書です。著者の小杉先生は小中学生向けの算数と数学の参考書を出版しており、丁寧でわかりやすい解説に定評があります。当サイトでは、高校生以上が小学算数を復習するために用いる参考書の筆頭候補に挙げています。小学算数は小学校の教科書を取り寄せることで行えますが、小学生向けの文章ですから大人が読むには張り合いがありません。そこで本書です。
本書は“教えられるほど”と冠しているように、算数そのものの理解に重きを置いています。「なぜそうなるのか?」という小学生の何気ない疑問を拾い上げながら解説されています。これは概念的な理解が重要となる算数、および数学にとっては非常に重要です。小学算数は(現役小学生なら)計算力をつける段階と割り切る方針も悪くありませんが、高校生以上の小学復習には概念的な理解が欠かせません。ひとつひとつの用語理解、それがどのような文脈で用いられ、考え方を提示しているのか。これらを確認することは中学数学以降の数学の勉強そのものの質を左右します。
また、小杉先生は本書に似たコンセプトを持つ『小学校6年間の算数が1冊でしっかりわかる』も出版されているのですが、こちらは「解法の習得」に重きが置かれています。現役小学生を中心に、計算力をつける方針ならベストな一冊です。本書は解法というよりは概念の理解。概念の理解から解法の理解も進みますが、あくまで教科書レベルの簡単な問題が解けるようになる程度です。言い換えれば、本書は教科書の代替として機能し、『小学校6年間の算数が1冊でしっかりわかる』は高校数学で言うところの入門問題精講に近いつくりと言えるでしょう。小学算数の計算にそこまで不安がない人には算数そのものの理解を深める本書、算数の計算を中心に復習したい人には『小学校6年間の算数が1冊でしっかりわかる』がオススメです。
単元ごとの問題はAIで補完
本書は教科書レベルの簡単な解法なら身につきますが、問題の絶対量が足りないために解法の定着はあまり促されません。そこで本書の問題集版『小学校6年分の算数が教えられるほどよくわかる問題集』まで加えると盤石。さらに高校生以上の小学算数の復習なら、AIによる解説と問題の補完まで行えると満点です。こうした一冊の参考書を軸に知識を新たに展開したり、整理したりすることは勉強の基本になります。
勉強の基本とは、勉強の仕方であり、個人にとっての当たり前の形です。ただなんとなく問題を解いて終わりではなく、その問題から様々な疑問や発展的な思考に繋げることができるようになるだけで、中学以降の勉強でも躓く確率を大幅に下げられます。逆に言うと、高校生以上で勉強の基本がより良い形で身についていない場合、簡単な小学課程の勉強の中で確立するのも有効です。世間一般から注目を集める東大生などを見ていたらわかるでしょう。一つの疑問からたくさんの思考が展開されています。その思考は直線だけでなく、曲線だったり、別の角度だったりと多種多様な考え方を持っているわけです。いわゆる頭が良い人の典型的な姿がそこにはあります。この意味で勉強は難易度が上がってもやることは基本的に変わりません。
現役の小中学生にAIによる学習サポートは慎重になった方が良い部分がまだあるとしても、高校生以上なら積極的に活用したいところです。そして、自分自身を自動的に成長させられる枠組み(テンプレート)を確立してほしいと思います。ほとんどの高校生や大人は新しい知識を得ても「へぇ、そうなんだ」と頭の片隅に置かれるだけです。受験勉強にしてもフィジカル。目の前の問題を解けるようになることばかりで頭が一杯なのです。そうではなく、もう少しメタな視点から自らの思考を整理すること。新しい知識を得たときに「これはあれに使えるかもしれない、これはあれと関係があるからここに置こう」などと考える癖があるだけで勝手に応用力はつきます。知識の整理が進むと、思考がスッキリして記憶の定着率も上がります。
接続先は同シリーズの中学版
本書シリーズを終えたあとは『中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる』で中学数学の理解を深めながら、解法は同様に『中学校3年間の数学が1冊でしっかりわかる本』と『中学校3年間の数学が1冊でしっかりわかる問題集』に取り組むのもオススメです。しかし他方で中学数学の解法習得の参考書に関しては非常に多くの選択肢があります。例えば『中学数学が面白いほどわかる本』シリーズです。こちらのシリーズは中学3年間分の3冊と高校入試準備用の1冊の合計4冊構成がバランス良く、解説とレイアウト共に余裕があってわかりやすく作られています。偏差値60程度の高校までなら十分に対応可能です。難関高校向けには、東京出版の『レベルアップ演習』や『Highスタンダード演習』も魅力。
こういった魅力的な選択肢が増える中でも『中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる』だけは、教科書の代替として機能する理解重視の参考書として高い地位にあると思います。全体的な傾向として、やはり小中学生には基礎的な計算力と解法を身体に刻み込む方針が多く採用されています。そのため、本書のような教える側に立てるほどの理解は良い意味で珍しいのです。しかも勉強では理解の基準として「他人に説明できる」を用いることもあり、他人に教えられるというのは深く理解している証左であり、他人に教える視点を学ぶ意味でも本書の価値は大きいと言えるでしょう。
だからこそ高校生以降の復習として、改めて中学数学の理解を求めてほしいところがあります。本書シリーズは単純な読みものとしてわかりやすいだけでなく、先生を目指す教育学部の大学生にもオススメできるほど「中学数学とは何か」といった根本的な問いを身近に置きながら解説してくれています。さらに言うと、勉強を教えるというのは高校生よりも小中学生に対する方が遥かに難しいです。算数・数学ならなおのこと。参考書を書けるような人は皆優秀なのですが、その中でもとりわけ難しい事柄に挑戦して成果を挙げている小杉先生の力というのはわかる人にはわかるはずです。本書シリーズの文章や構成は教科書に近い美しさがあります。