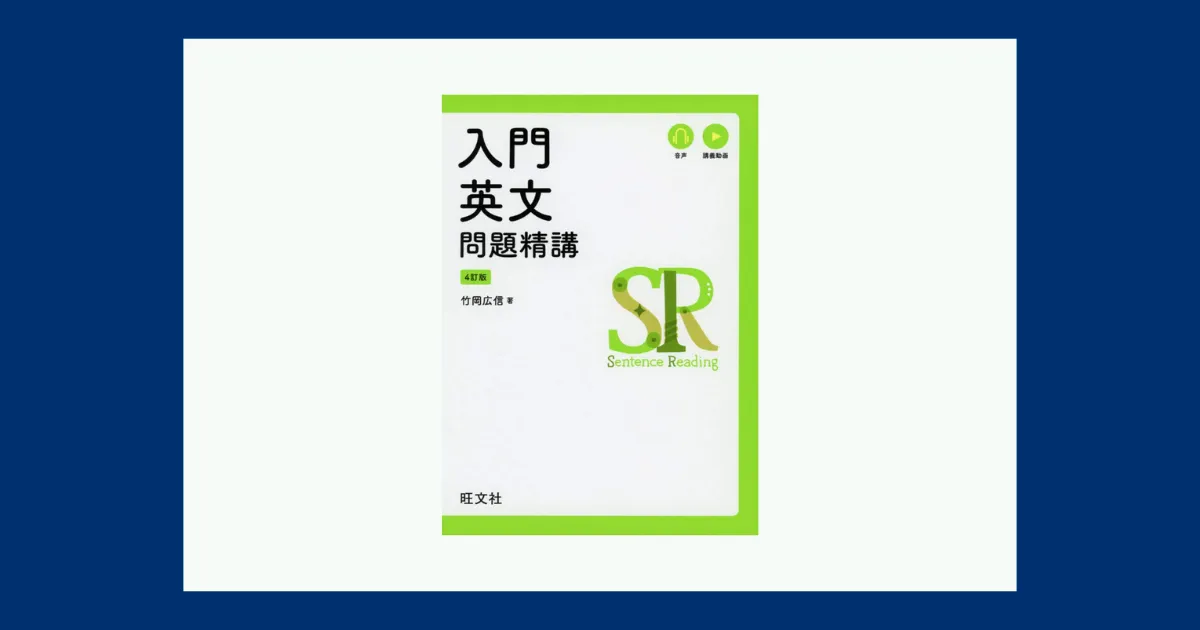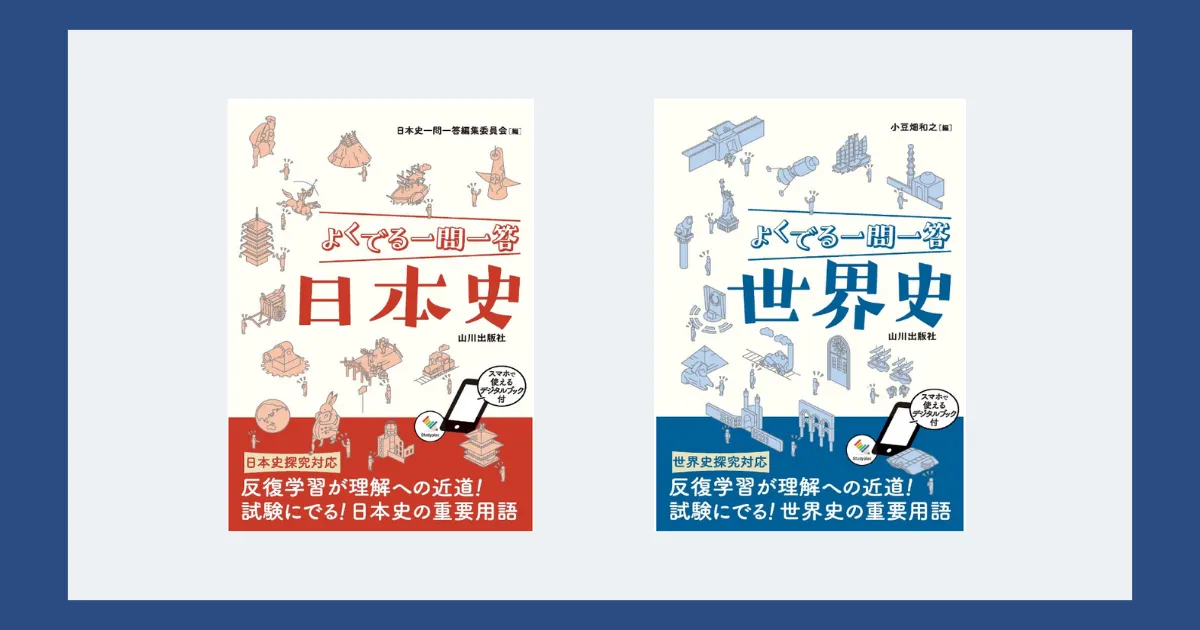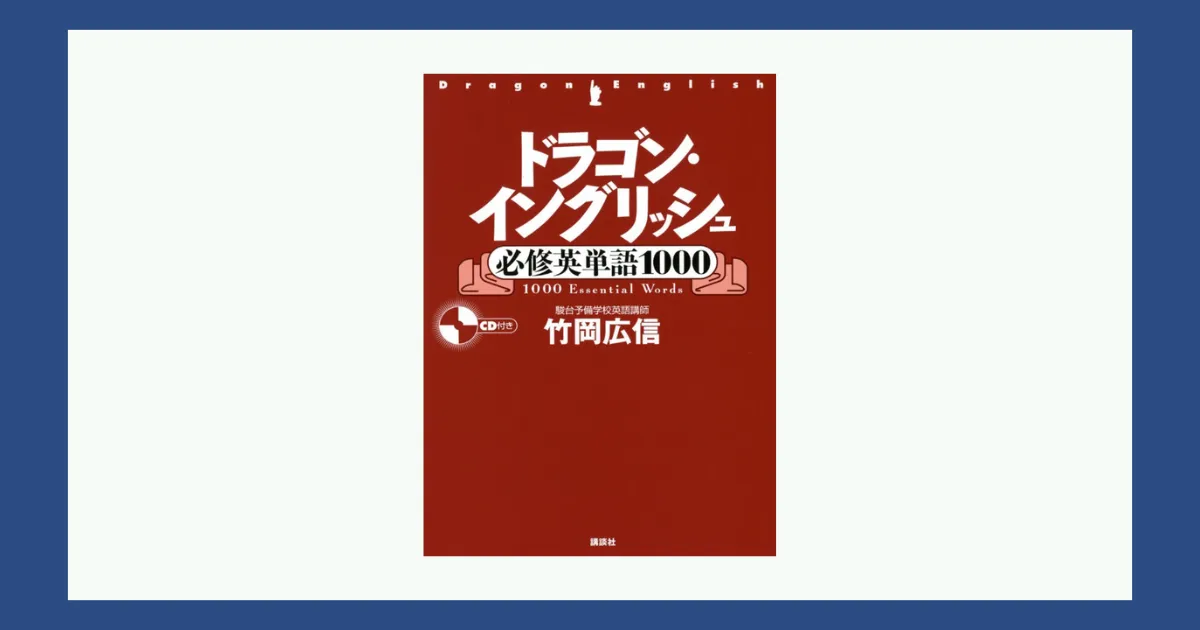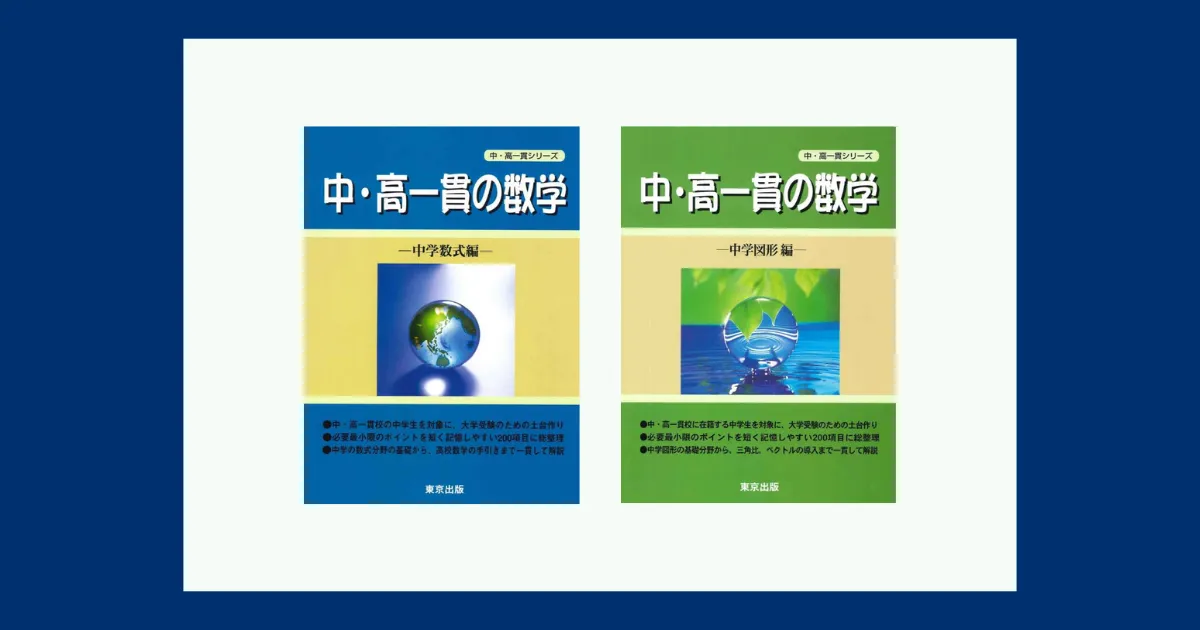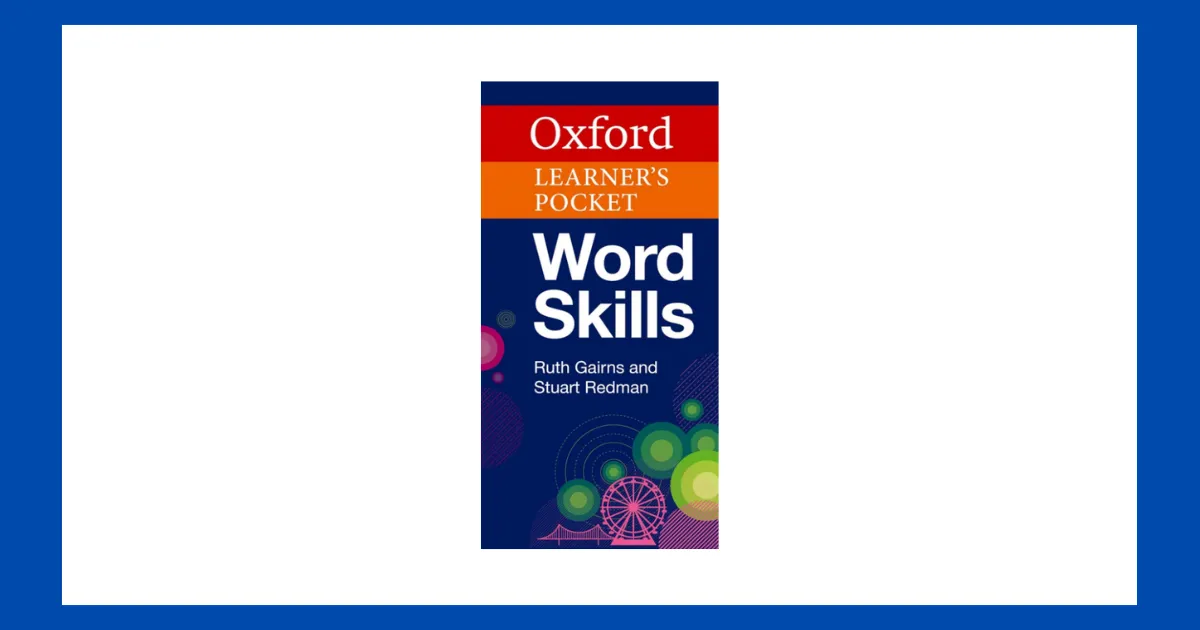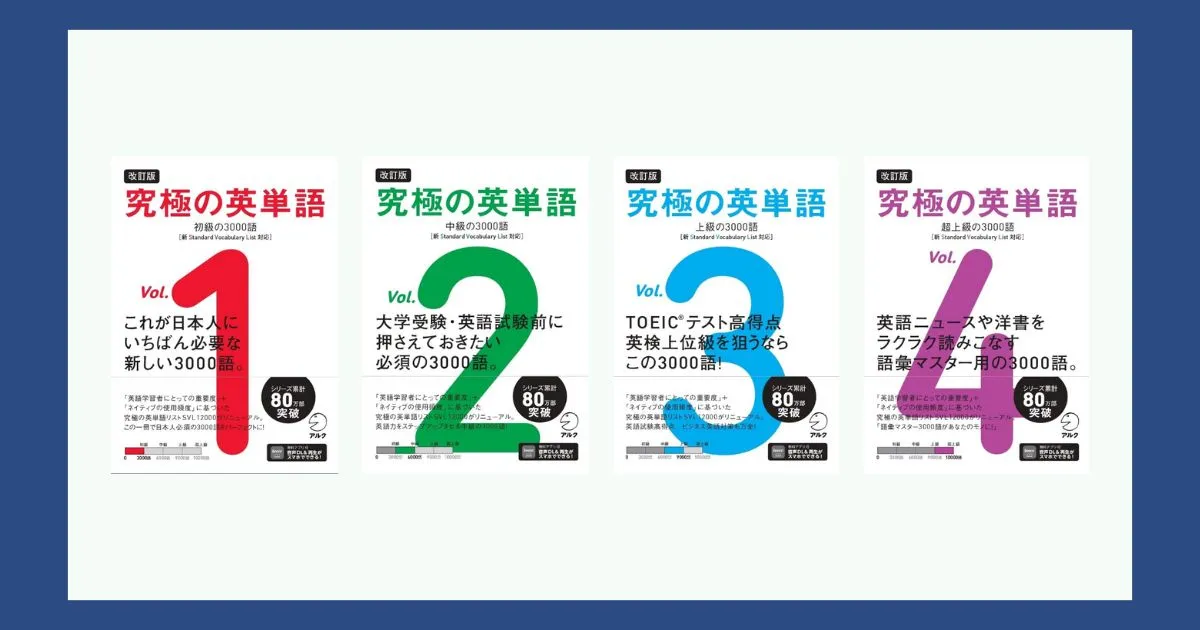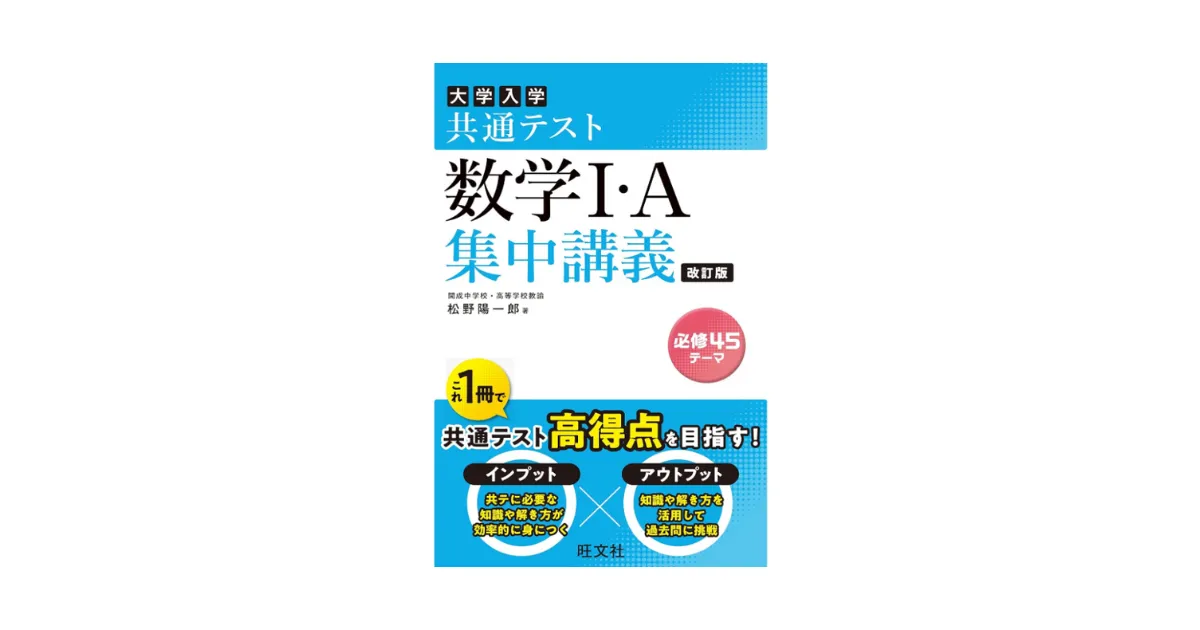| タイトル | 英文解釈Code70 | |||||||||||
| 出版社 | かんき出版 | |||||||||||
| 出版年 | 2024/7/10 1760円 | |||||||||||
| 著者 | 杉村年彦 | |||||||||||
| 目的 | 英文解釈 | |||||||||||
| 分量 | 256ページ | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
加筆修正の履歴
2025/11/04 読みにくい箇所を修正しました。
2025/10/25 対象の表現を偏差値60以降に強調、本書に取り組むまでの複数冊ルートを提示
思考プロセス重視の英文解釈
【対象】
・全統模試偏差値60から
・MARCHレベルの英文を読み始めた人、読める人
・旧帝大、早慶レベルの英文に難しさを感じている人
【到達】
・旧帝大、早慶上理の英文を正確に読むための考え方を学べる
・精読と速読の使い分け(文章予測)も学べる
本書は難関大向けの英文解釈です。著者の杉村先生が本書の中で『英語リーディング教本(以下:リー教)』の影響を受けたと語っているように、品詞分解と構造分析を意識した思考プロセス重視の英文解釈に仕上がっています。例文はほぼ全て難関大の過去問になっており、難関大に必要な英文解釈のポイントを70(60講義+10コラム)にまとめています。
難関大対策の英文解釈と言うと、名著として語り継がれる『英文読解の透視図』や『英文解釈教室』などがありますが、どうしても要求するレベルが高く、さらに現代の入試傾向も反映されていないわけですから、いくら英文の読解方法が変わらないとは言え、現役の受験生にはなかなか推奨できるものではありません。加えて、これは持論になりますが、旧帝大・早慶対策としての英文解釈は“思考プロセス重視”がオススメです。
思考プロセス重視の英文解釈とは、本書や『ポレポレ英文読解プロセス50』のような筆者の読み解き方をリアルタイムで解説してくれるものです。なぜ、思考プロセス重視を推奨したいのかというと、ひとえに頭の良い人の考え方を真似てしまった方が手っ取り早いからです。これは数学でも同じ。問題の解き方を教わるのではなく、その問題を解く姿を実際に見る方が自分にとって必要な考え方に気づきやすい。問題の解き方を学ぶとは、問題を解く姿を見て理解するための下地と言い換えても良いですね。
文章の最初と最後の方、大切なことが書かれてある可能性が高いのはどちらでしょうか?私の指導経験では、「最後の方」と答える生徒が多数派です。しかし、正しい答えは「最初の方」です!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第1パラグラフや第2パラグラフはスピードを上げて読む箇所ではなく、丁寧に、大事に読むべき箇所です。ここでテーマや主張をつかめたら、ゴールがわかり、この文章が進む道筋が見えた状態です。スピードを上げて読み進めましょう。メリハリをつけて読むことで、速さと正確さを両立できます。英文解釈Code70 P141より抜粋
本書は一般的な英文解釈に備わる情報だけでなく、上記の抜粋した文章にあるようなコラムも役に立ちます。常に現場目線と言いますか、杉村先生の解説は生徒に寄り添うような優しい印象を覚え、現役生は全体的に読みやすく理解しやすいと思います。『ポレポレ英文読解プロセス50』の西先生に近い雰囲気を感じました。
ただ、リー教を意識した解説は難関大対策として上手く機能しています。個人的に本書は『ポレポレ』と最も競合していると考えていて、本書を選ぶ最大の利点はここにあると言っても過言ではありません。難関大未満までは「なんとなく」でも得点できることがそれなりにあるのですが、例えば東大英語にある「語を削除する問題」にしても、難関大になるほど曖昧な知識と理解は厳しく追及されてしまうことがわかるでしょう。『リー教』のエッセンス、主に品詞分解と機能の指摘はそこまで精緻に読めていない受験生たちに大きく刺さるわけです。
本書に取り組む前の参考書は?メインターゲット
まず、文法書だけでどこまで正確に読めるか。大学入試で言うと、入試基礎・共通テストレベルなら文法書の知識だけでも読み解けるはずです。例えば、多くの英文解釈では「SVの発見」から始まりますが、こういった基本的な読解法は文法書を読んだら自然と理解できます。その一方で、複雑な構造を持つ英文が出題される難関大では一般的な文法書にある知識だけでは足りない――というより、文法知識の適用が難しくて読み解けなくなります。発見すべきSVが見つけにくくなっているためです。そこで初めて英文解釈が必要になるという考え方が基本です。参考書ルートにあるから英文解釈に取り組むわけではありません。
実際のところ、人によって英文解釈は難関大(特に早慶)を受けるなら必要になるけれども、難関大未満なら必ずしも必要ないと言うでしょう。英文を読み解くためにその都度英文解釈が必要と考えてしまうと、2冊、3冊、4冊と増えるばかりです。英文は読み手を混乱させるために複雑な構造にしているわけではなく、英米的な発想、むしろわかりやすく伝えるために必要な構造になっているという前提があります。とは言え、文法知識を正確に身につけているとは限らない、あるいは最初から読解への適用を想定したい人にとっては肘井先生の『読解のための英文法[必修編]』のような基本的な英文を取り扱った参考書が有用なのもまた事実です。
本書はシリーズ化されていないので前後の接続がうまくできません。できないのですが、その事情から本書一冊だけでも問題ないと言える可能性があります。難関大対策と謳いながらも、そこまで難しいものばかりというわけではありません。例えば「名詞の役割を把握せよ!」や「It is X that ~の判別」などは必修レベルにあってもおかしくないでしょう。しかも難関大対策にして60講義は多めです。
つまり、全統模試偏差値60到達後、旧帝大や早慶の英文に難しさを感じ始めた人が取り組むにはちょうど良い一冊になっています。学校の授業や定期テストに真面目に取り組んだ人にとっての難関大対策の厳選した一冊と言っても良いかもしれませんし、後述するAI時代の必要最小限の英文解釈として採用しても良いと思います。ただし、例えば『入門問題精講』から始めて『英文熟考 上下』を終えてから本書に取り組むような複数冊ルートの方が言うまでもなく安定はします。
AIによる品詞・構造分析の導入
英文解釈は難関大未満なら1冊(人によっては無くても可)、難関大志望なら基本は2冊になると思います。得点できる程度の解釈ができれば十分ですから、ハイレベルな和訳問題が出題される最難関国公立などの例外を除くと冊数はできるだけ減らしたいところです。これは受験生が足りなくなりやすい多読多聴(アウトプット)を充実させる意図もあります。
そこで現在はAIによる品詞・構造分析が非常に有効な手段なので、読み解きにくい英文に出会うたびにAIの力を借りてしまうのも手です。参考書というのは志望校によって必ず過不足が生まれますが、重要事項を押さえることに関しては常に優先できます。本書で難関大の重要事項を身につけ、その後はAIによる品詞・構造分析で枝葉を押さえていけば過不足による効率低下も最小限で済みます。
それなら本書にも取り組まず、最初からAIの力を借りてしまうのはどうか。これは今のところ推奨しません。大学入試の重要事項の知識は参考書にまだ優位性があり、重要事項を身につける過程で伸びる思考力と知識がAIとの対話の質も上げるからです。しかも枝葉だけで押さえていく方針はより良い体系化が為されるとは限らず、優先順位も不明瞭になります。一言で言えば、悪い意味で偏ります。2025年現在の大学受験攻略としては、第一に参考書で重要事項を手早く押さえ、その後はAIを活用しながらアウトプット(過去問や予想問題集など)を中心にする戦略だと思います。