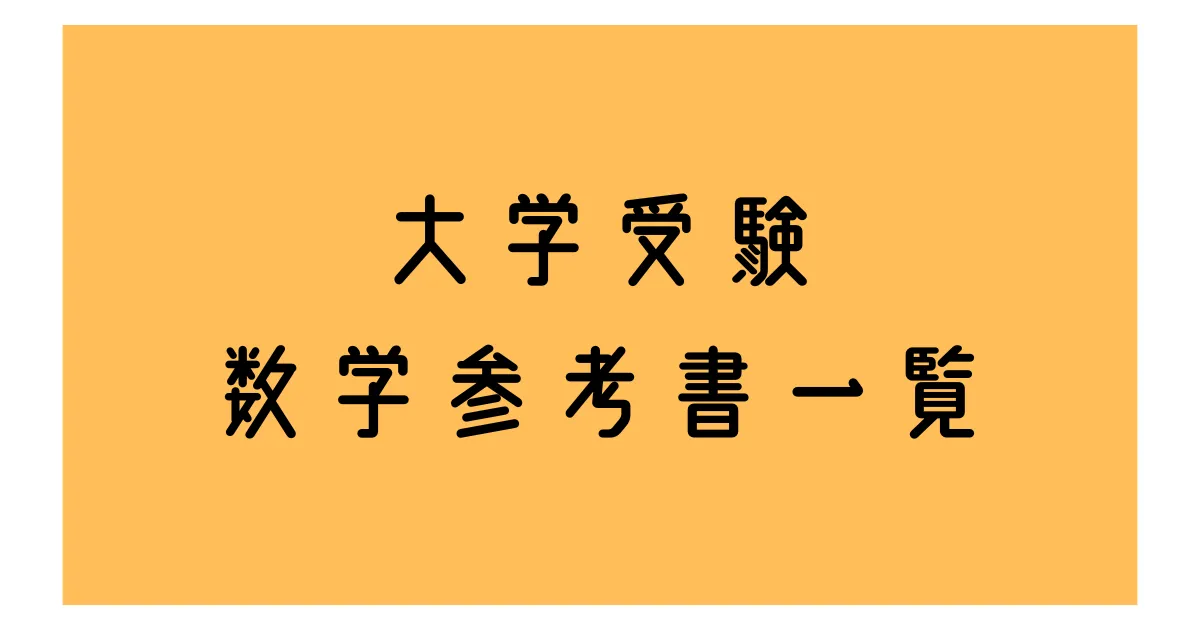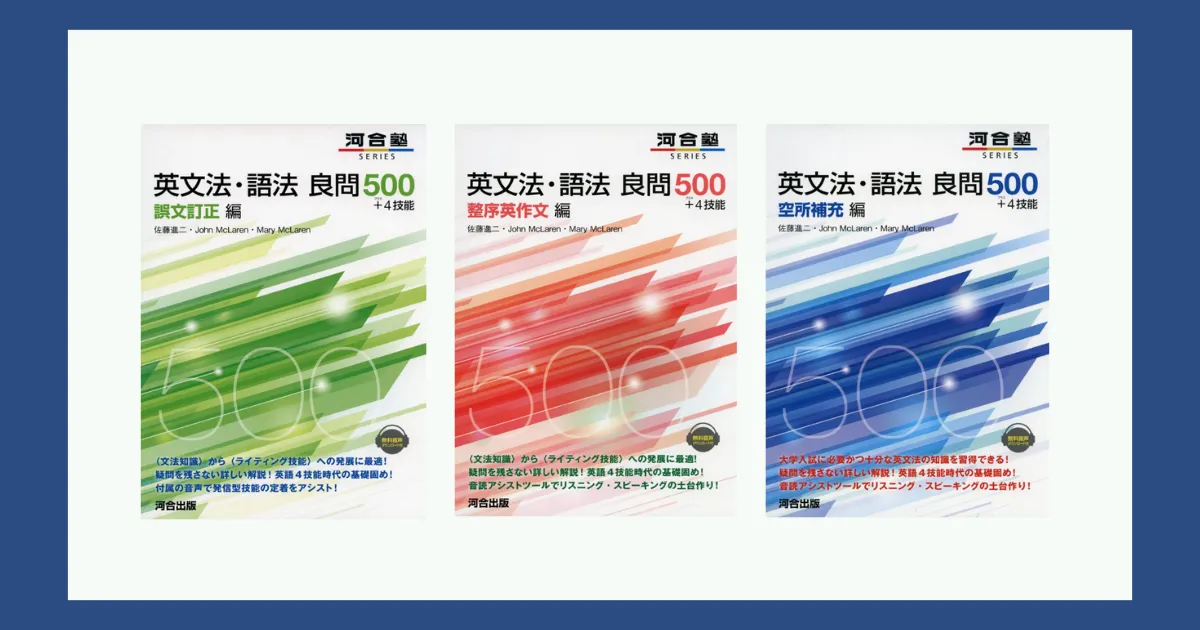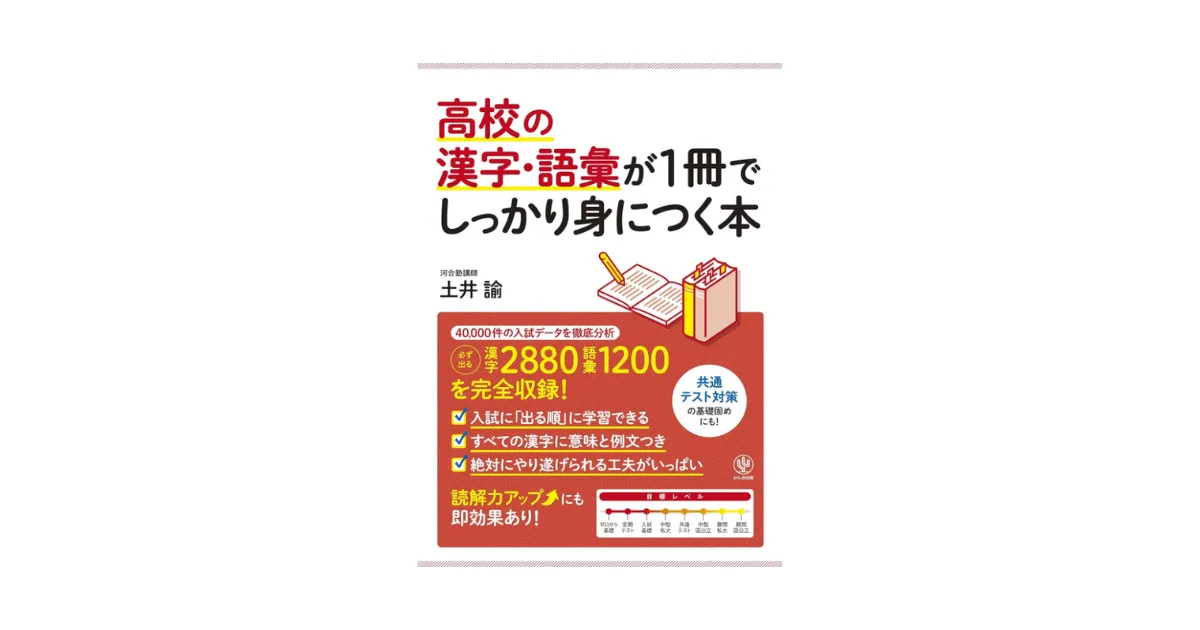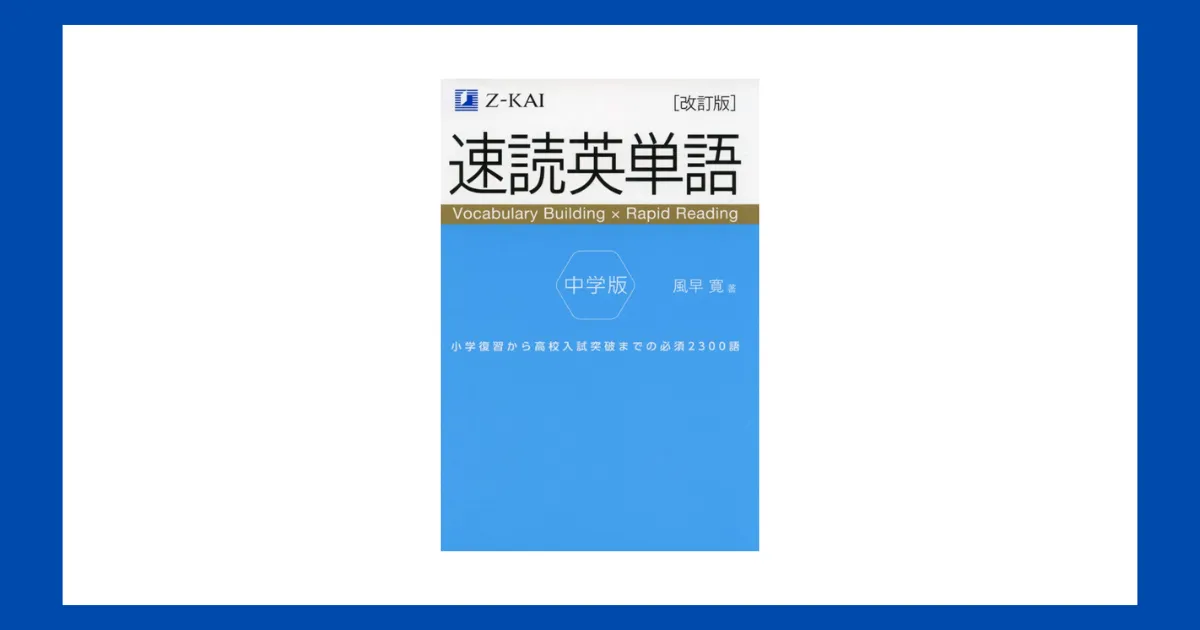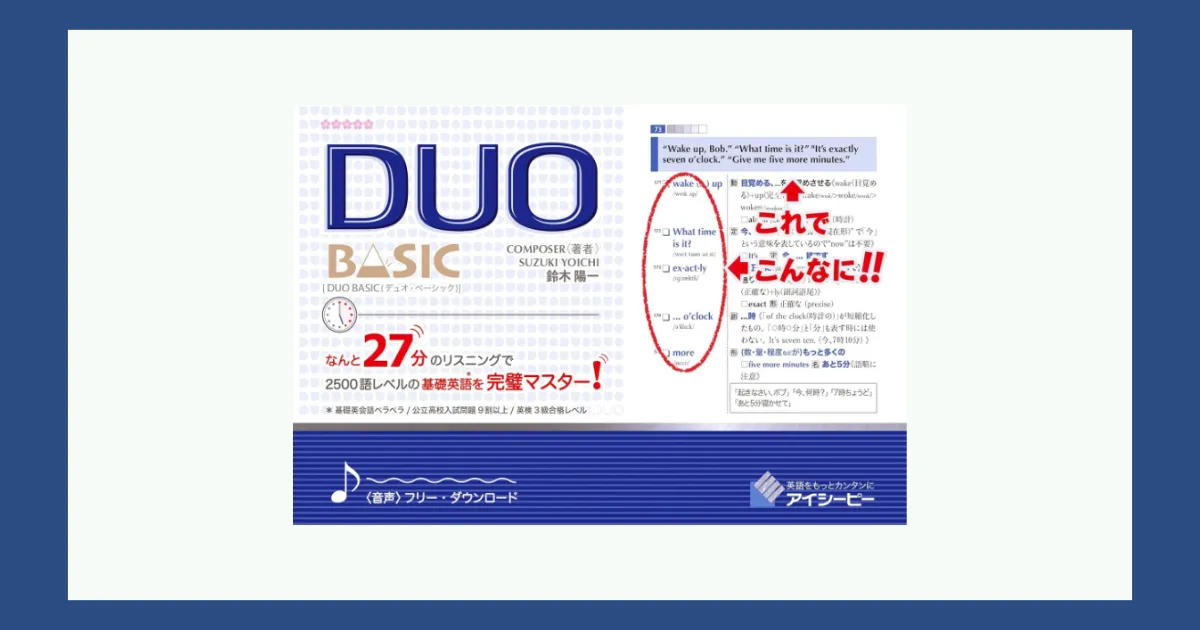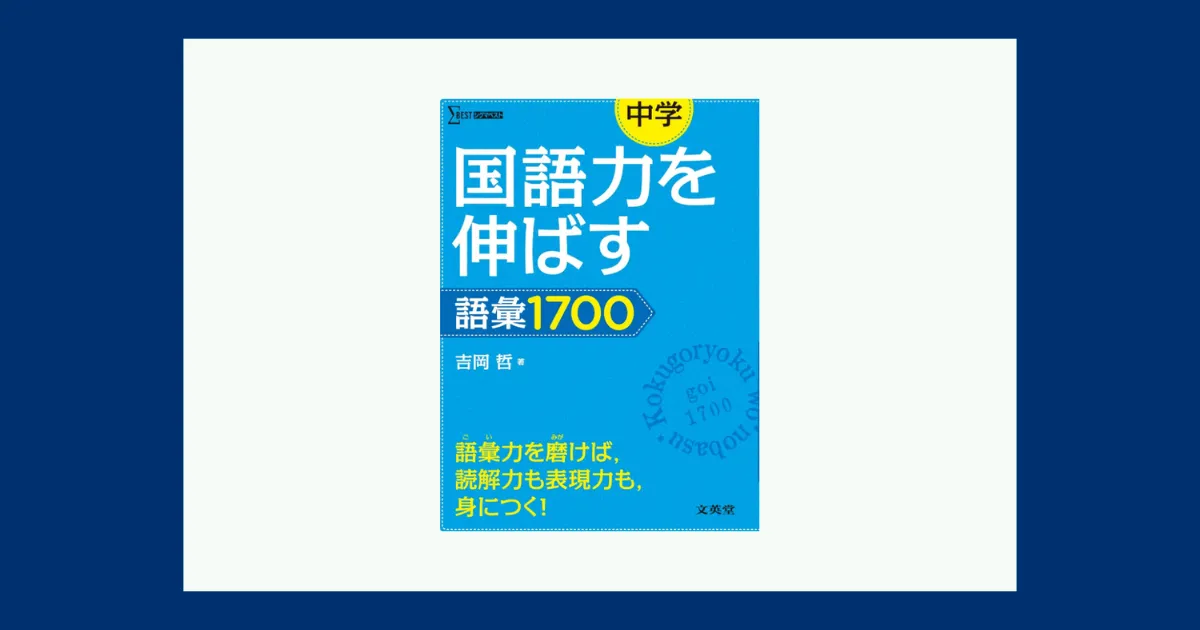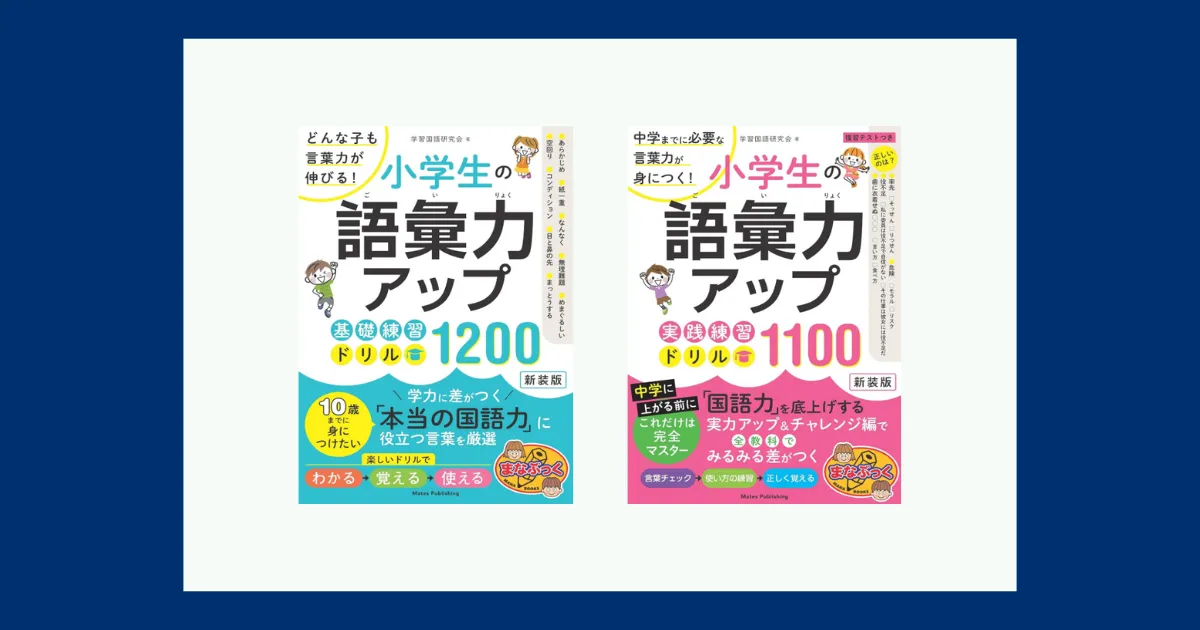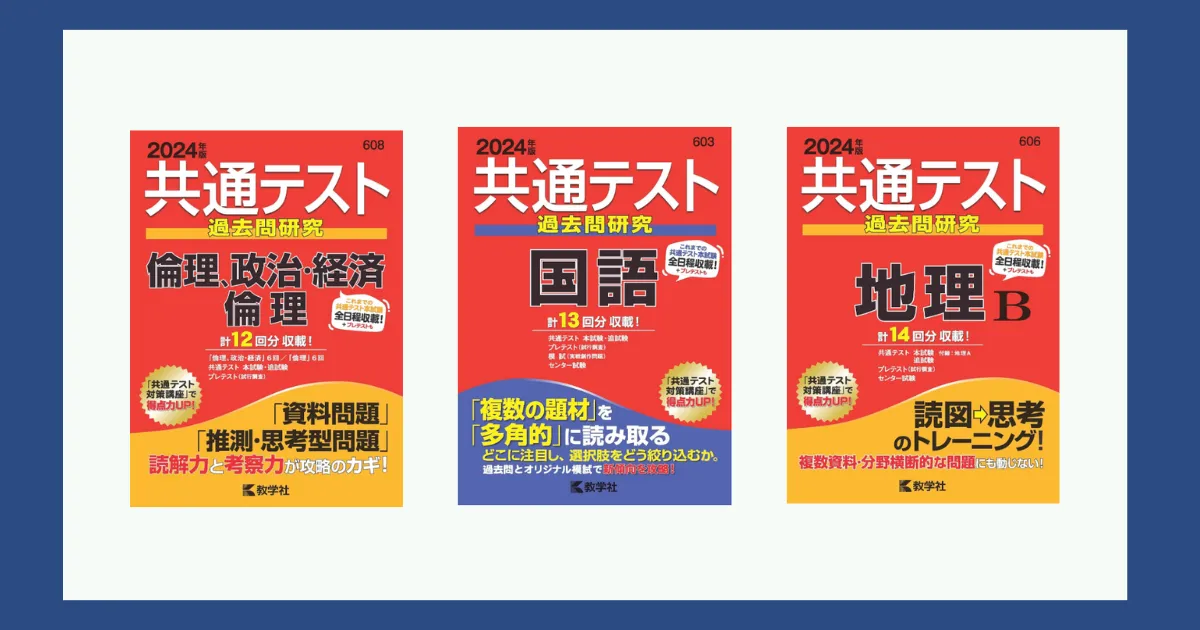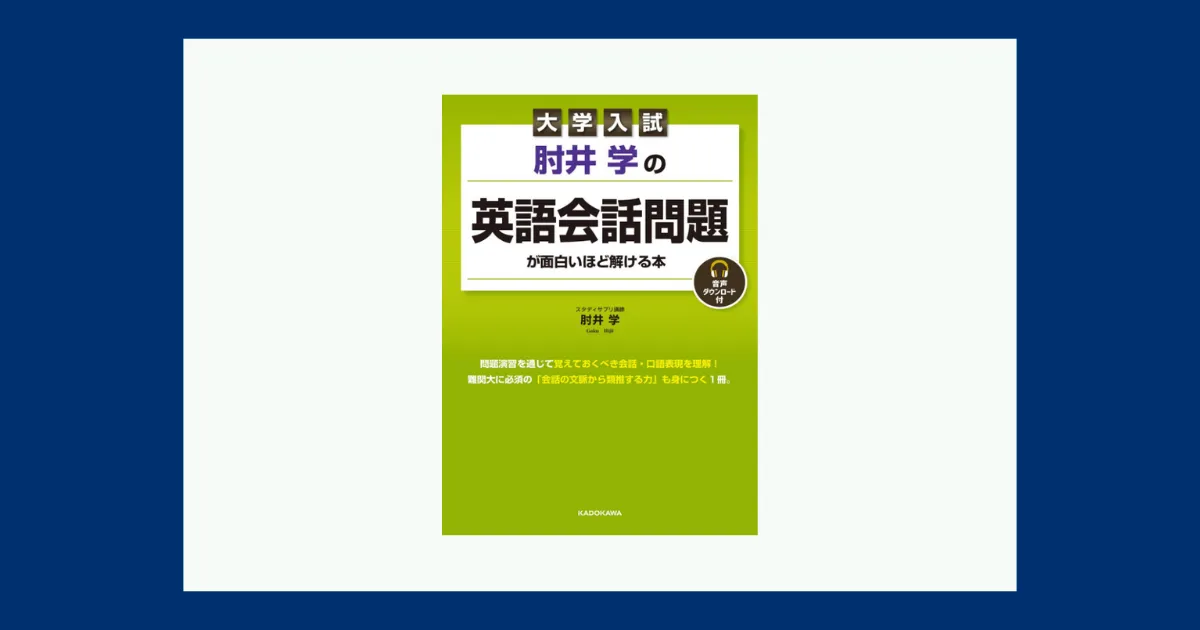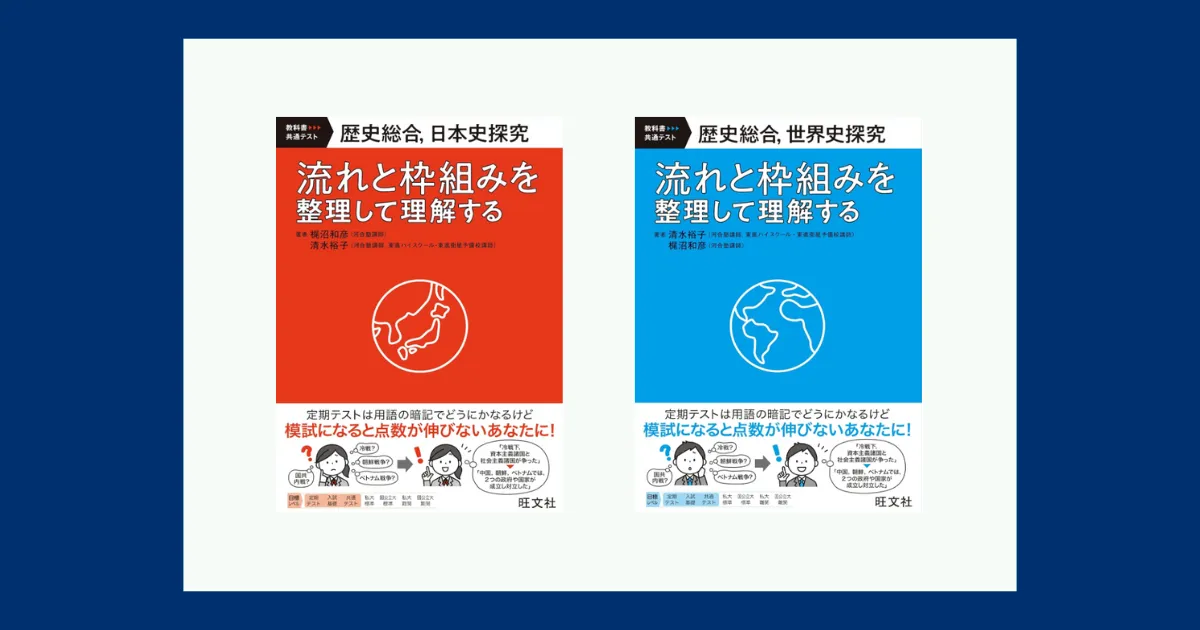| タイトル | 厳選 大学入試数学問題集 理系272 厳選 大学入試数学問題集 文系160 | |||||||||||
| 出版社 | 河合出版 | |||||||||||
| 出版年 | 2024/1 | |||||||||||
| 著者 | 河合塾数学科 | |||||||||||
| 目的 | 入試標準固め・アウトプット型問題集 | |||||||||||
| 対象 | 準難関~難関大志望の現役生 到達:全統模試偏差値65以上 | |||||||||||
| 分量 | 大学入試数学問題集 文系160(212ページ)・理系272(336ページ) | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| AI | 解答をサポート | |||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
加筆修正の履歴
2025/10/31 本書に取り組むレベルの文言を修正しました。
2025/10/28 文系と理系難易度の違い、本書で合格を狙える大学についての文章を修正しました。
入試標準の良問を被りなく精選
本書は2024年に河合出版から出版された入試数学の標準レベルにあたる問題集です。数学の参考書ではチャート式をはじめとしたインプット型が注目を集めやすい中で、本書はアウトプット型として良問が精選されています。アウトプット型は純粋な問題集なので、レイアウトに関しては特筆すべきものがありません。問題と解答が淡々と掲載されているのみです。それでも旧版227ページから本書(最新版)336ページと大幅に増加して別解が充実しました。入試標準レベルは難関大の合否を左右します。
本書は文系と理系で難易度と問題数が少し異なります。文系は入試基礎から標準までを収録している一方で、理系は入試標準を中心に入試基礎も扱っているという印象です。到達レベルに関しては合格点を狙える大学なら「MARCH・関関同立・上智・理科大・準難関国公立(筑波・横国・神戸など)」、それより難しい「旧帝大・早慶」であっても合格点は視野に入れられます。東京一工には心許ない。本書は国公立二次試験向け問題集のような構成なので、どちらかと言えば国公立向きです。ただ、地力をつけたいなら国公立・私立問わずに活用できます。
また、本書に近い問題集としては『入試の核心(標準編)』『新数学スタンダード演習』『数学の良問問題集』『国公立標準問題集CanPass』が挙げられます。レベルの近さで言うと『青チャート』『1対1対応の演習』もありますが、こちらはインプット型・ハイブリッド型の参考書なのでコンセプトが異なります。本書は最新版から別解が充実したと言っても、最低でも教科書レベルは完璧に終えていないと解答を読んでも理解できません。本書に取り組む意義を見出すなら入試基礎レベルにも手をつけていた方が望ましいと思います。アウトプット型は大きく成長できるメリットがある反面、適正レベルにないと逆効果です。数学の受験勉強をまだよく知らない人はインプット型とアウトプット型の選択を間違えないようにしましょう。
類書との比較
| タイトル | 厳選 大学入試数学問題集 理系272 | 入試の核心(標準編) | 新数学スタンダード演習(数学IIICまで) | 数学の良問問題集 |
| 問題数 | 272 | 150 | 430 | 307 |
| 解答・解説 | ||||
| レイアウト | ||||
| 欠点 | 使い方次第で学習効果に差が出やすい | 問題数が少なめ | レイアウトの相性が出やすい | 入試標準を集中的に求めると不一致 |
| その他 | シンプルで被りのない論点が高効率 | 解説が最も丁寧 | 本番で再現しやすい解答を重視 | やや入試基礎寄りながら網羅度は高い |
ここに挙げている問題集はどれも優秀なので、残りの期間から少なくとも3周くらいできるものを選んでしまって良いと思います。ただ、アウトプット型は使い方次第で学習効果に差が出やすいため、必ずひとつひとつの問題の論点をメモして類似問題に確実に対応できるようにする必要があります。アウトプット型に取り組む際の質はインプットの質に左右されますが、今は多少仕上がりが甘くともAIによって理解を深められます。アウトプット中心の学習効果は高いため、本書のような問題集をできるだけ早い段階から上手に活用したいところです。
しかし、それでも使い方が難しい、実力に繋がっていないと直感したときは『入試の核心(標準編)』が無難な選択肢になります。解説が最も詳しい。この中では問題数が少なめですが、過去問+αには使いやすいと思います。他方で網羅性を重視するなら『新数学スタンダード演習(以下スタ演)』がオススメです(数学IAIIBなら約300題)。ここまでの問題数と解法を理解できたら、最難関大の難問を除いて入試数学は完成です。
その中で本書は問題数のバランスが良く、論点の被りもないため、全ての問題を繰り返し解く価値があります。『スタ演』まで取り組めるなら盤石ですが、インプットとして『チャート式』や『1対1対応の演習』などに取り組んだあとに約430問は負担が大きく、かと言って『入試の核心(標準編)』だと心許ないと感じたときには本書が理想的な位置づけになります。また、入試標準は良問を丁寧に考えて正しく力に変えたいので、網羅性を重視することが必ずしも有効とは限りません。基礎問題なら網羅性重視の大量演習を地で行けますが、入試標準は理解重視の良問周回がベストな気もします。特に旧帝大は私大よりもその傾向が強いと思います。
本書のあとに取り組みたい参考書
基本的に本書を終えたら入試数学の勉強は終わりでも良いと思いますが、最難関大の難問対策をする必要があるならオススメしたい参考書があります。それは『真・解法への道』と『ハイレベル数学の完全攻略』です。こちらは難問対策の参考書なので、本書をはじめとした入試標準よりもさらに問題数が少なくなっています。その分、解説が非常に丁寧になっているため、対策しにくい難問の根本的な考え方から学べます。
他にも『やさしい理系数学』などもあるのですが、出版年は古くなり、解説も丁寧とは言えません。入試標準までを早い時期から終えている人が「入試標準の難しめから発展まで」をアウトプットしたいときに使う参考書です。旧帝大志望以外は必要ないと思います。早慶の場合は文系理系問わず、入試標準までを完璧にできたら合格点を狙えますから、もし難問対策したい場合でも第一に過去問、あるいは『早大入試プレ問題集 数学』などの専用の参考書を優先した方が良いでしょう。
また、数学的な考え方が足りないと感じたときには、入試数学の理解度を上げるための参考書に取り組んでおくとより良いと思います。2025年現在なら『数学 方程式・図形・関数からとらえる数学の基礎 分野別標準問題精講』や『総合的研究 公式で深める数学』などがオススメです。入試標準まで解法暗記の方針で問題ない人もいますが、入試基礎よりも深く思考する部分が増えるために悪しき丸暗記に陥って得点に繋がらない人もいます。そういったときには数学的な概念や事象、操作をひとつずつ考え直すことで「自分が何をやろうとしているのか、何を求められているのか」が具体的にイメージできるようになって問題への対応力と安定度が上がります。