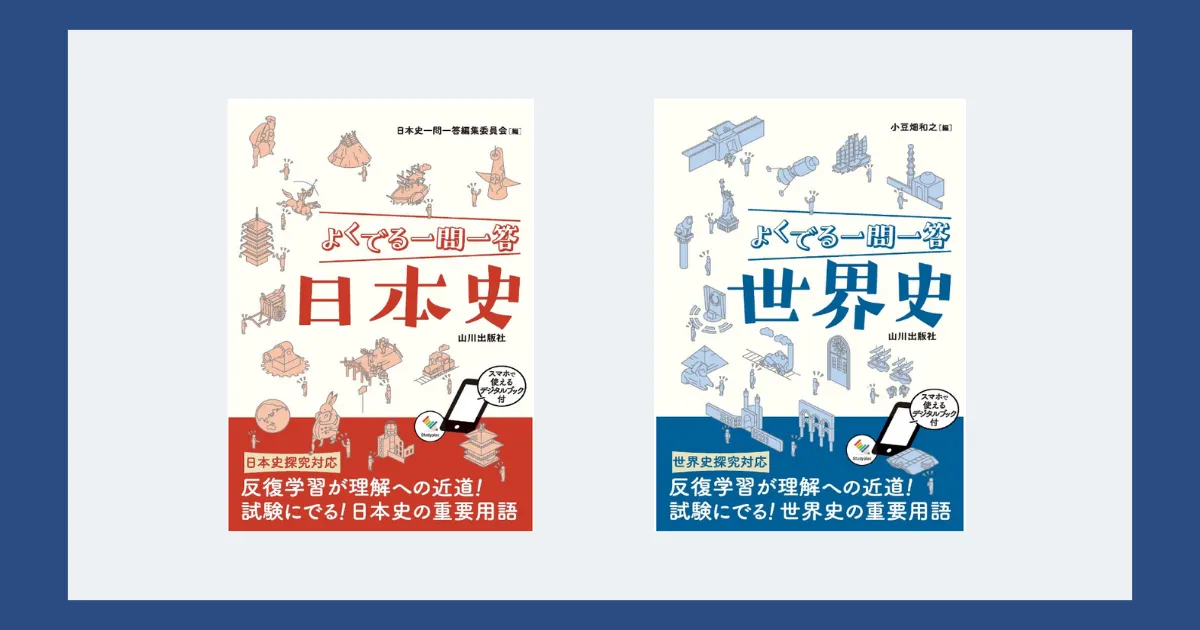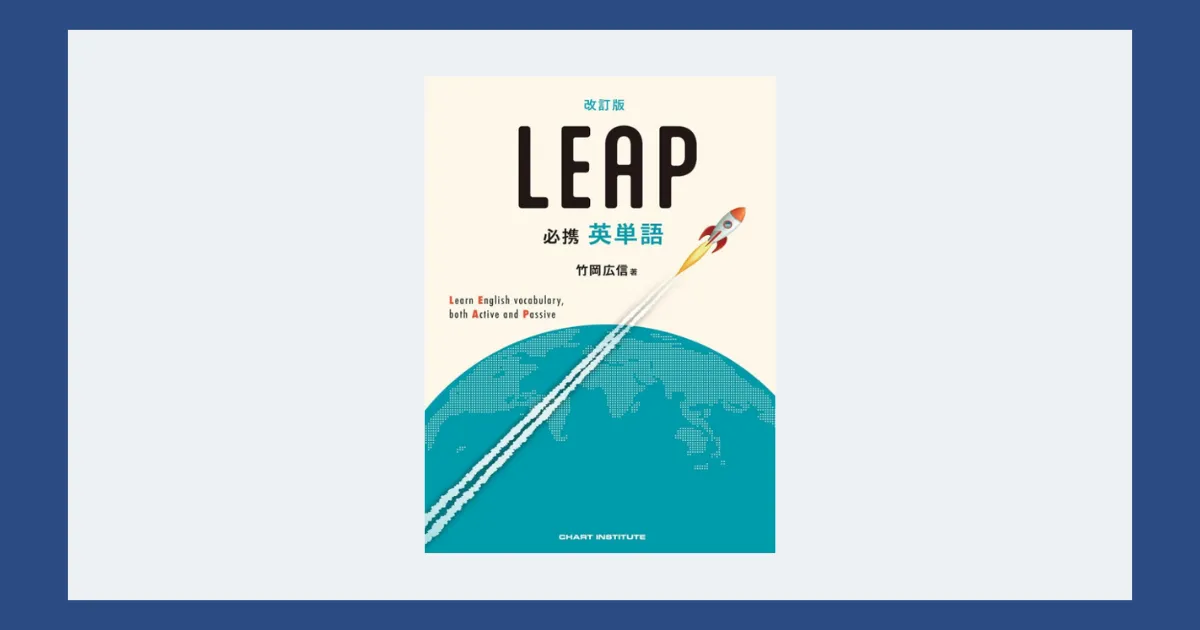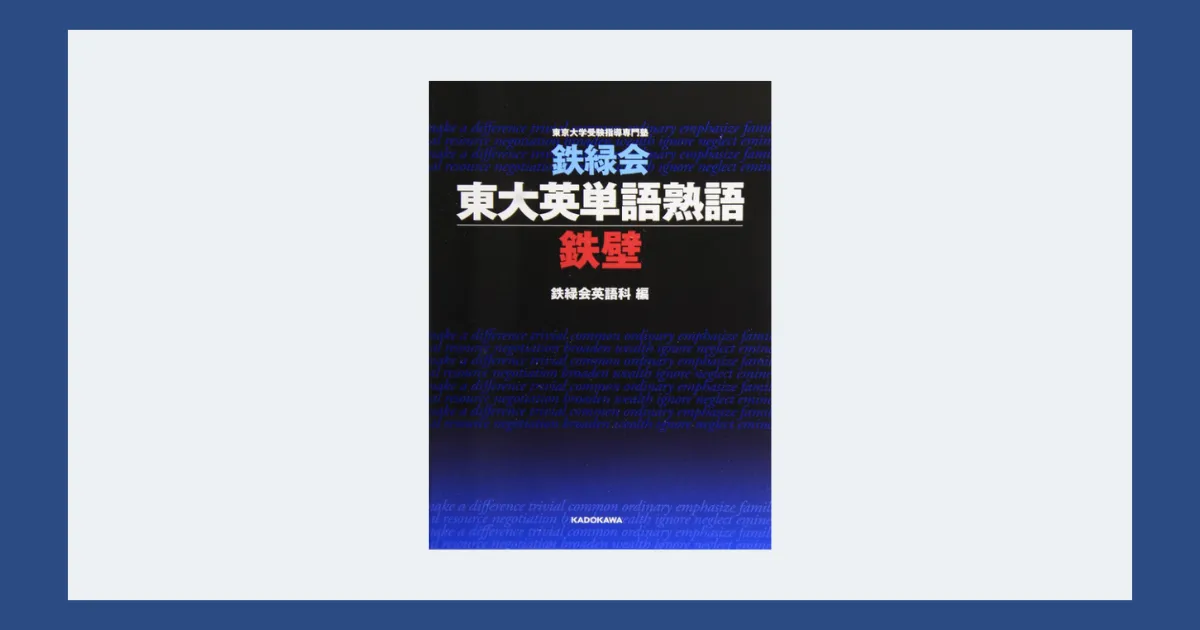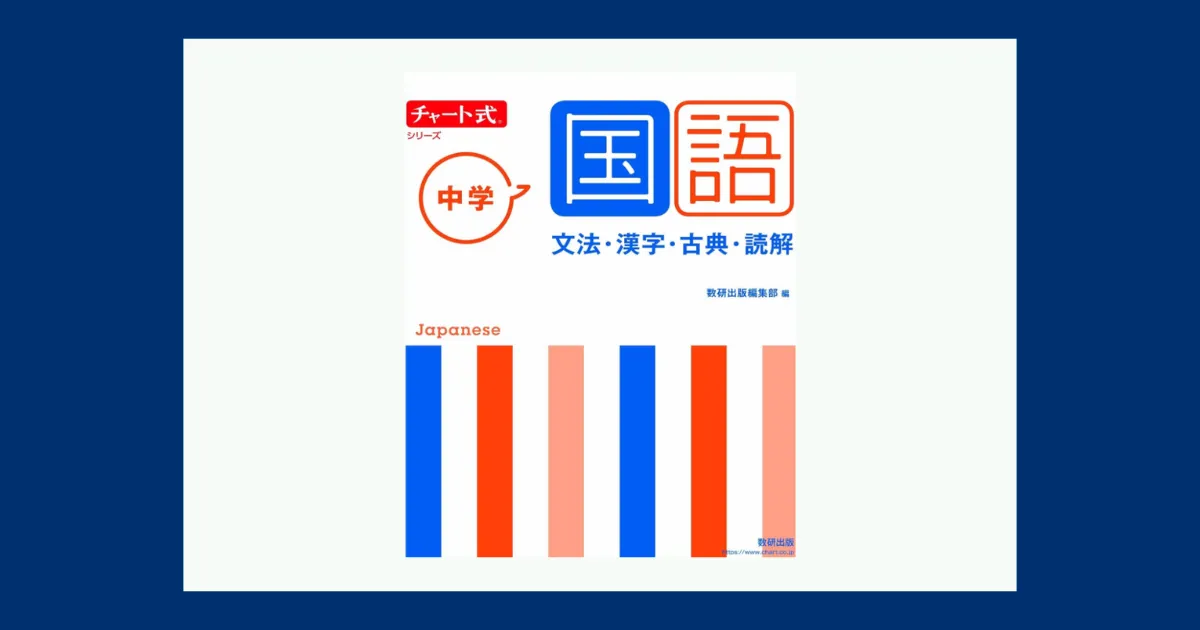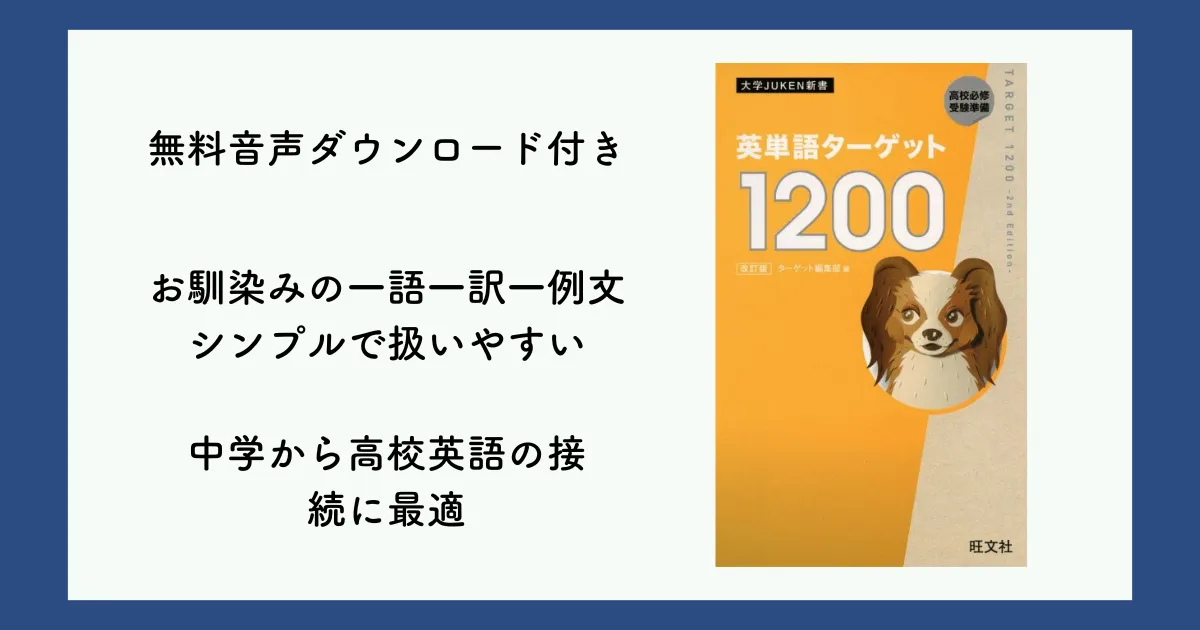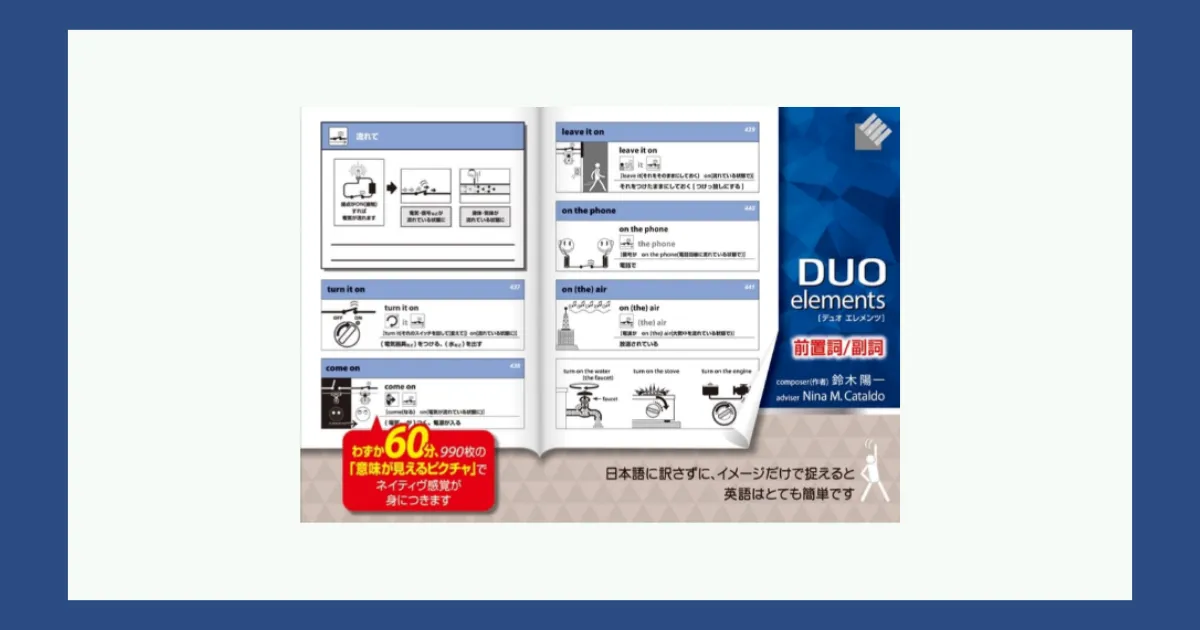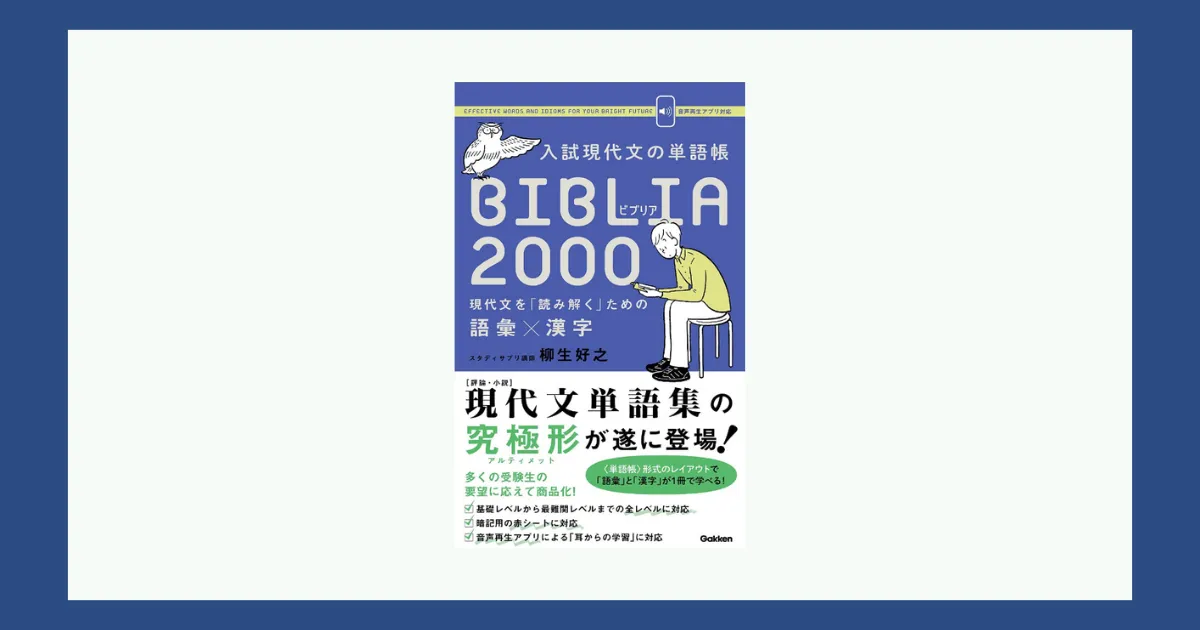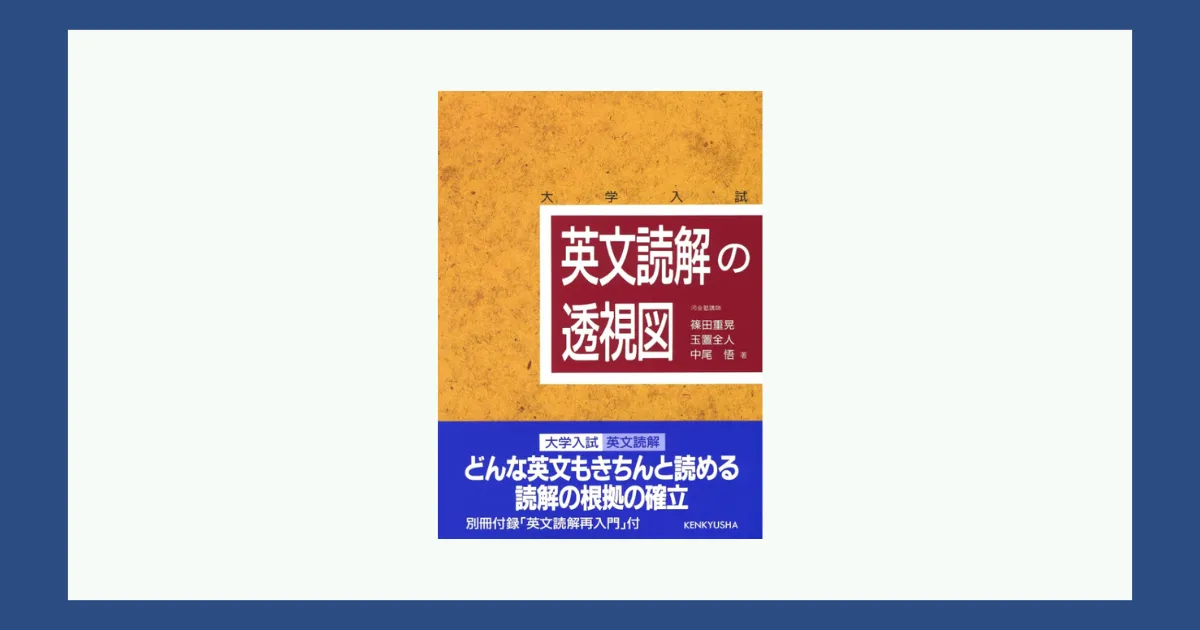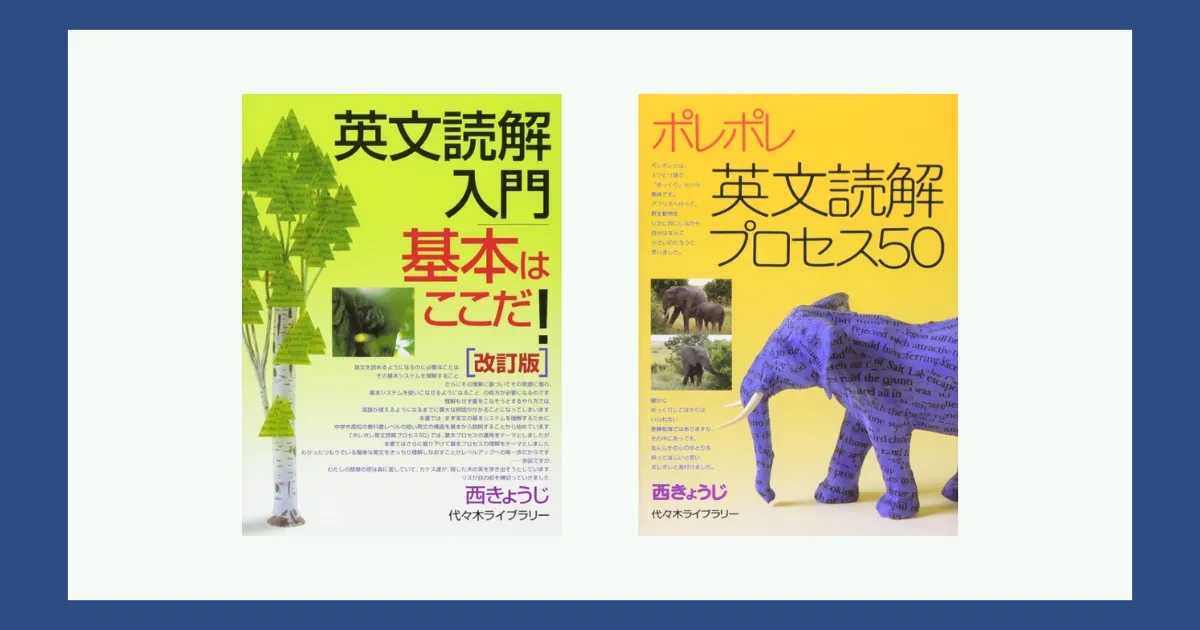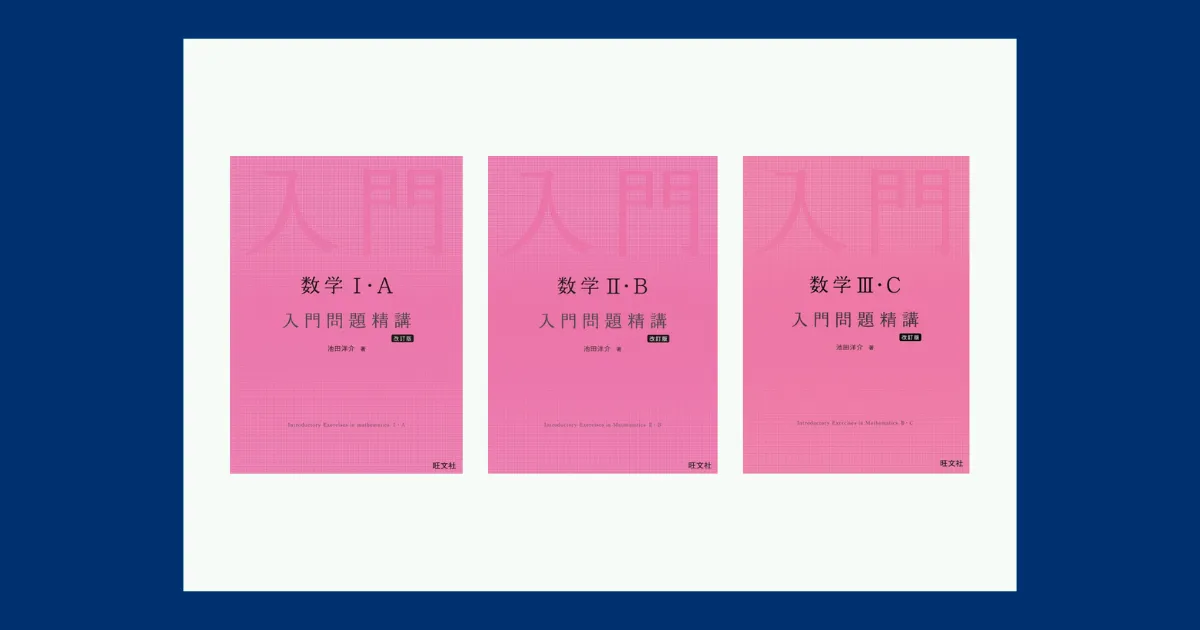| タイトル | よくでる一問一答 日本史 よくでる一問一答 世界史 | |||||||||||
| 出版社 | 山川出版社 | |||||||||||
| 出版年 | 2024/7/26 1100円 | |||||||||||
| 著者 | 日本史一問一答編集委員会、小豆畑 和之(世界史) | |||||||||||
| 目的 | 重要用語に厳選した一問一答 | |||||||||||
| 対象 | 現役生から大人の学び直しまで 到達:偏差値60まで | |||||||||||
| 分量 | 292ページ(日本史)、264ページ(世界史) | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| AI | 気になる用語を深掘りする | |||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
加筆修正の履歴
2025/11/02「受験勉強に不慣れでも使いやすい一問一答」の文章の一部を読みやすいように修正しました。
重要事項に厳選した一問一答
本書は2024年に歴史教科書で有名な山川出版社から出版された一問一答です。こちらは新しい学習指導要領にある「日本史探究/世界史探究」に対応した参考書になります。
かつての高校歴史は「日本史A/世界史A」と「日本史B/世界史B」に分かれていましたが、学習指導要領の改訂により2025年現在は「日本史A/世界史A→歴史総合」と「日本史B/世界史B→歴史総合+日本史探究/世界史探究」に変更されました。「歴史総合」では日本と世界の近現代史を学び、日本史探究/世界史探究では日本と世界の歴史を原始から現代まで詳細にまとめています。今は歴史総合が必須なので、日本史選択だったとしても世界の近現代史について学びます。ちなみに日本史B/世界史Bから日本史探究/世界史探究に変更されたとは言え、学ぶ内容にほとんど差はありません。
ただ、共通テスト以降の思考力・判断力を問う問題の増加に伴い、学習指導要領でも単なる暗記科目にしない歴史科目ならではの思考を養える工夫が施されるようになりました。具体的には史料や図表の読み取り、歴史の流れ(因果関係)と枠組みを押さえるような問題です。今でも難関私大では一問一答に集約される細かな知識を問う問題は残っているものの、そうした問題は徐々に減っていくと予想されています。今でも『山川一問一答 日本史』や『日本史一問一答【完全版】』のような早慶を想定できる約4000問を超える問題を収録した一問一答の使用者は多いですが、そうした予想もあって本書のような約2300問(日本史)の厳選した一問一答も有力な選択肢になりつつあります。
受験勉強に不慣れでも使いやすい一問一答
大学入学共通テストは、重要用語に加え、図版や文字資料、地図などを読み込み、その情報を多角的に考察できる力を求めています。しかし、過去の大学入試センター試験や大学入学共通テスト、および私大入試の問題を分析してみると、どのような出題形式であれ、重要用語を正確に理解していれば十分対応できることに気づきます。本書は、これらの入試問題を分析し、解答に必要と思われる頻出用語を整理することにより、日常の学習や定期考査においてはもちろんのこと、大学合格をめざす皆さんの自学用になるよう構成されています。
よくでる一問一答 世界史 冒頭 ii-iiiより引用
英語の文法問題然り、確かにかつては一問一答にある単純な知識を問う問題が多く、とりわけ難関私大では細かな知識の差によって合否を決める風潮がありました。歴史科目は暗記科目と呼ばれる所以。知識の問われ方が似通っているため、一度覚えてしまえば得点が安定するという認識が広まっていたように思います。
しかし、今ではそんな一問一答の位置づけに変化があります。まず、センター試験から共通テストに移行してから単純な知識問題が減った一方で、思考力・判断力問題として因果関係や周辺情報から解答を導ける(導く)問題が増えました。加えて、大学入試の全体的な傾向としても、それこそ難関私大で細かな知識を問うてきた早慶を想定しても、単純な一問一答の知識のみで解ける問題は減っています。
では、現在一問一答はどのように位置づけられているのかというと、前提知識の確認です。問題文に含まれる歴史の用語はよほど難解なものを除いて注釈がなく、用語と背景が一通りわかっていなければ解答できません。一問一答はその確認にちょうど良い。そして、約4000問以上を収録する網羅性重視の一問一答に比べて、本書は2/3の量で挫折しにくく、受験勉強に不慣れな層にはベストな選択肢になり得ます。それに一問一答以外にも『HISTORIA』のような問題集形式の充実した解説で定着できることも想定したら、一問一答の参考書としては十分な量です。ただ、早慶を受験する場合に限り、絶対に落とせない基本問題を文字通り完璧に解答しなければならないため、安定合格、および歴史科目を得点源にしたい層には網羅性重視の一問一答も否定しません。細かな知識にこだわりすぎて優先順位を見失う恐れがあるなら、早慶志望であっても本書を段階的な学習の一冊として推奨します。
本書とセットで使いたいオススメの参考書
一問一答は知識の土台。それに加えて歴史科目で得点するには、歴史の流れと枠組みを押さえる必要があります。そのための参考書として『流れと枠組みを整理して理解する』がオススメです。こちらも定期テストから入試基礎、共通テストまでを対象としているため、本書と合わせて使うことで理想的な知識体系を築けるようになります。歴史は偏差値60程度までならエコに目指せる科目です。
そもそも歴史の流れと枠組みとは何か。簡単に言うと、時代や出来事の関連性と整理です。歴史は覚えることが多いため、目の前の知識がどの時代の、分野の、何と関連する知識だったのかを明確に意識できなくなります。常に歴史の流れと枠組みに沿って知識を配置する必要があります。大人の学び直しらしい言い方をすると、歴史科目からの学びは知識の体系化の仕方です。知識を得たときに頭の片隅に放り投げるのではなく、メタ的な思考整理を行うということ。こうした関連づけが適切に行われると、覚えることの多い歴史科目の負担が大きく軽減されます。知識そのものだけでなく、ネットワークによって支えられるからです。
しかし、勉強に不慣れな人はそうした歴史科目の本質的な勉強になかなか気づけません。頭の良い人はテストで得点するためにどうしたら良いのかを無意識に考え、結果としてそうした知識の整理の仕方を獲得しますが、もとから勉強への興味関心も低ければそこまでの工夫を行えないわけです。そして、歴史科目の膨大な暗記に囚われてしまいます。確かに覚えることは多い科目ですが、できるだけ簡単に忘れにくい知識にする工夫、それに気づかせてくれる参考書とも言える『流れと枠組みを整理して理解する』は優れた参考書です。