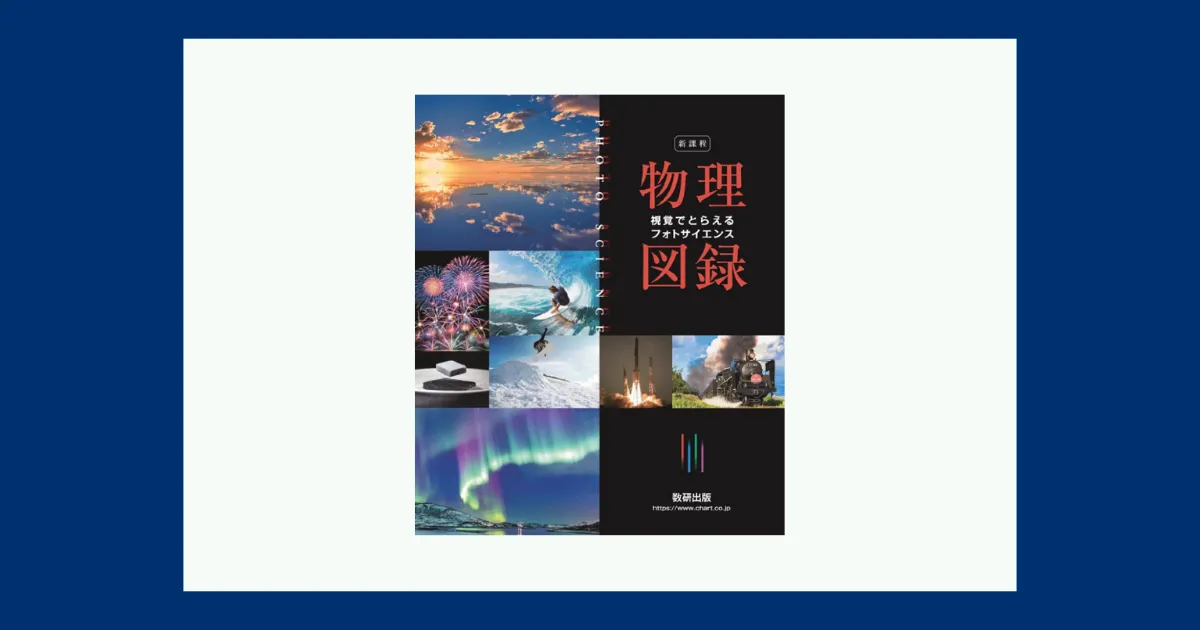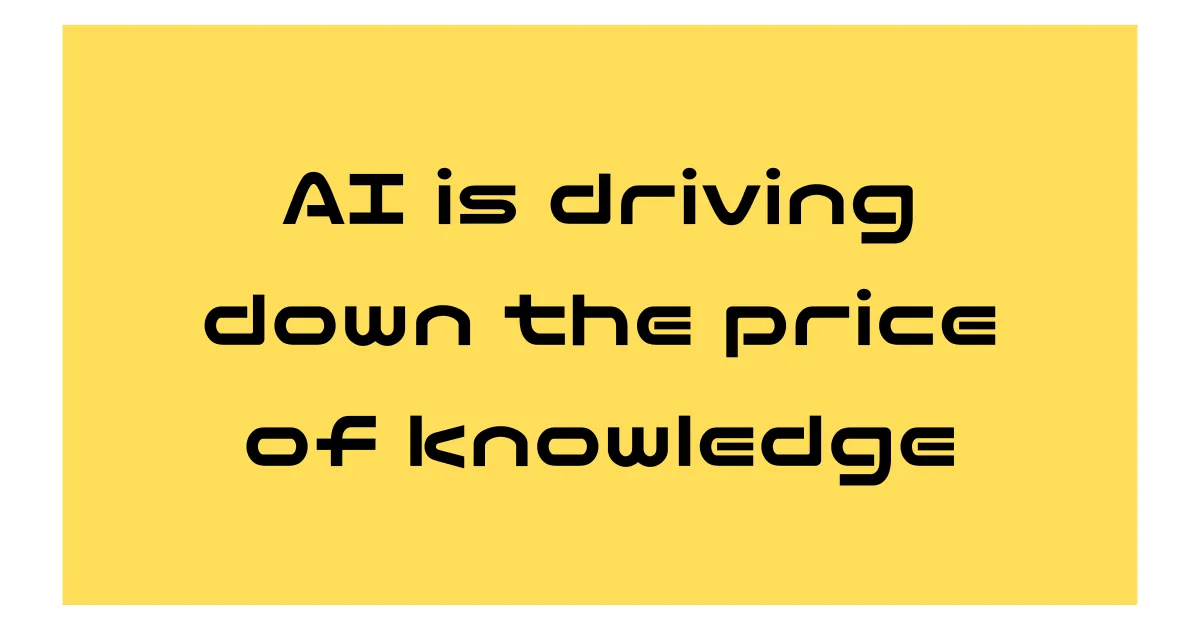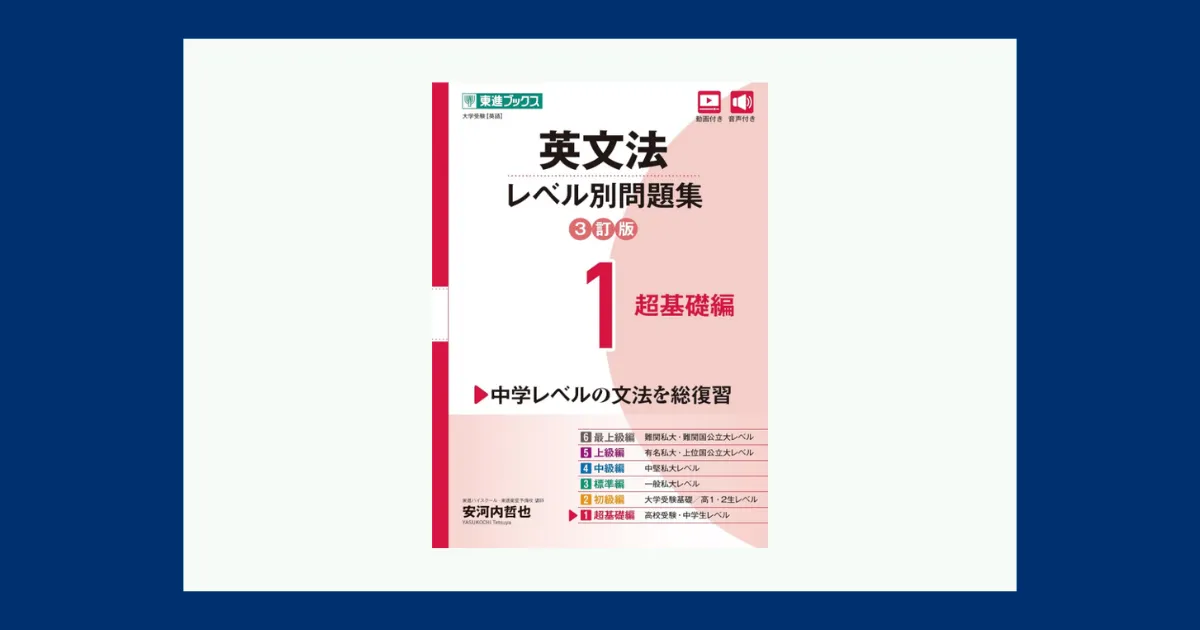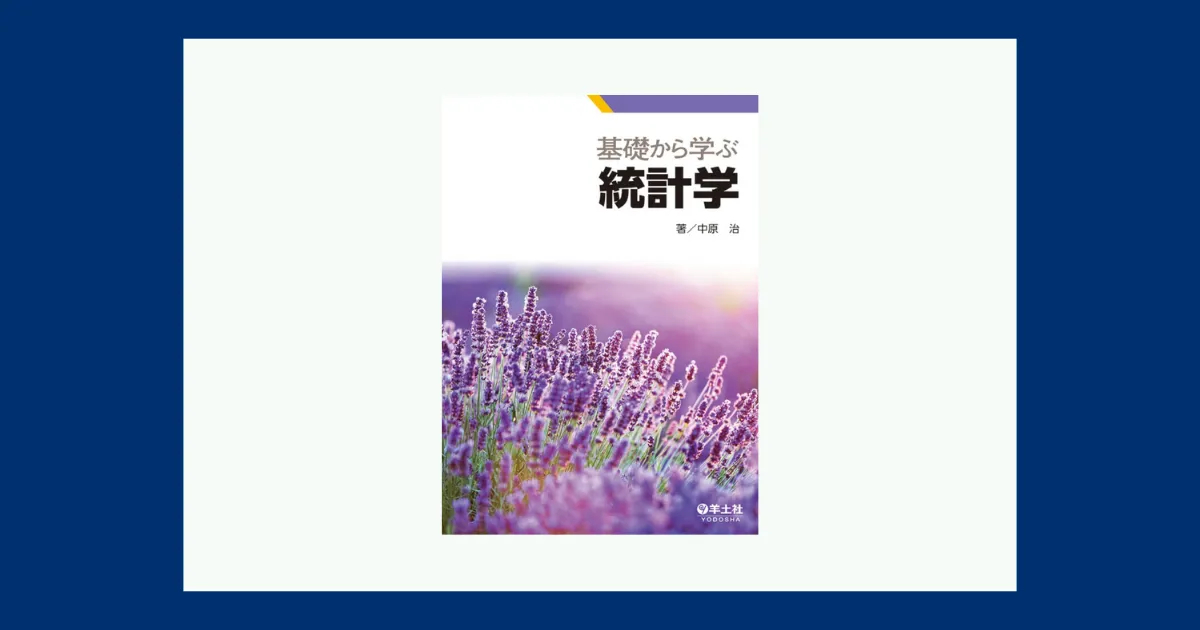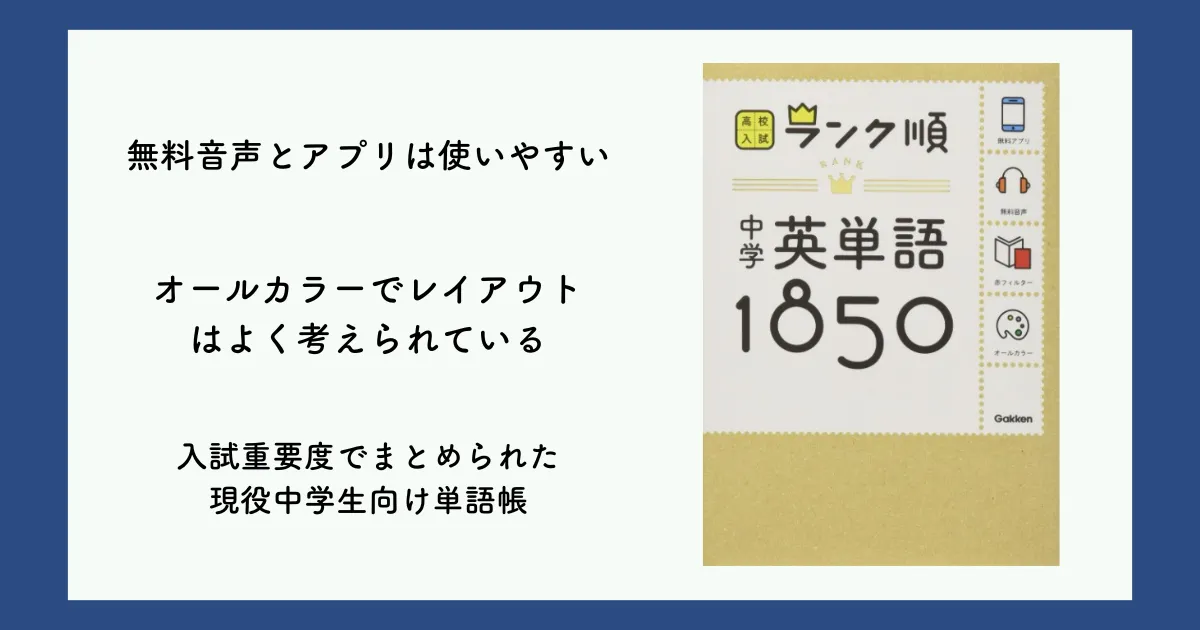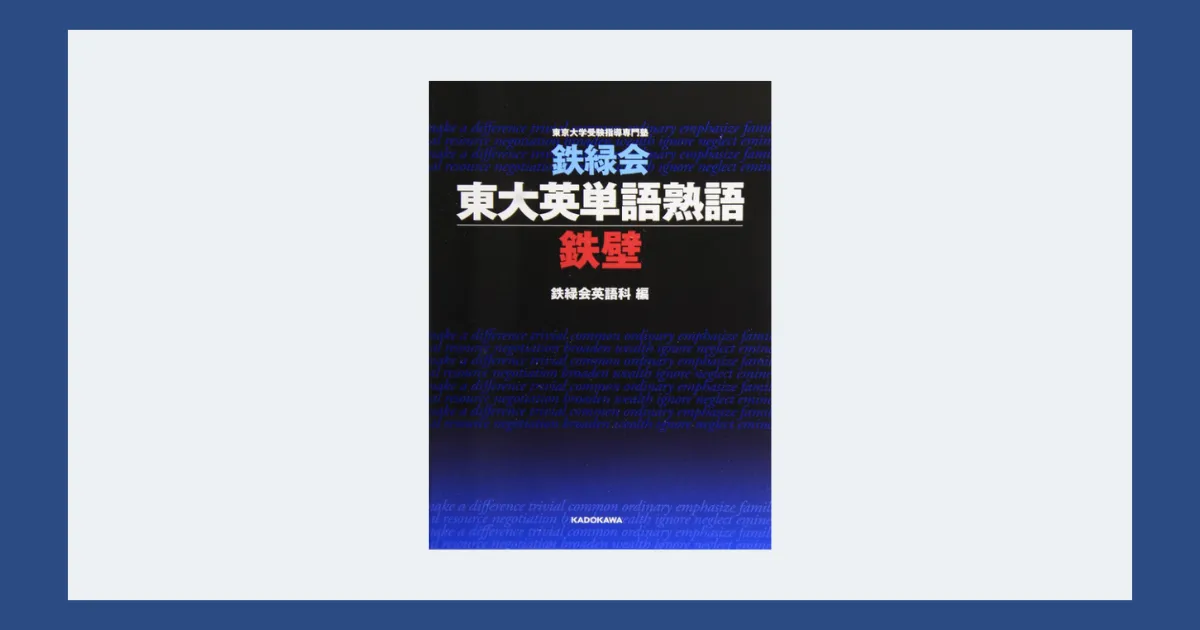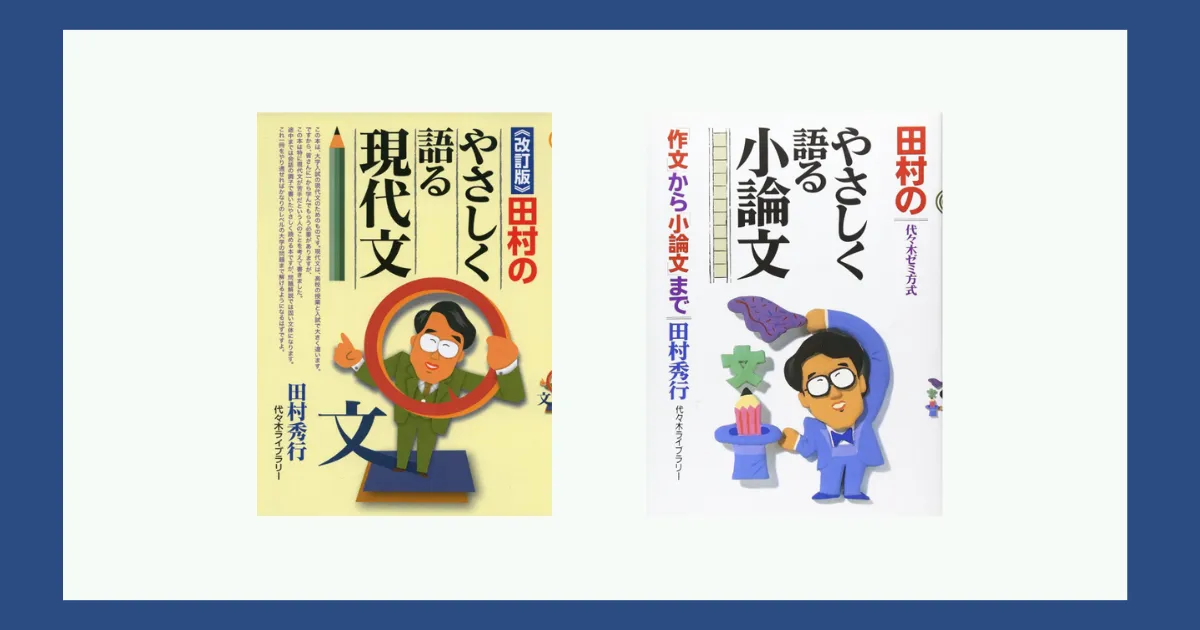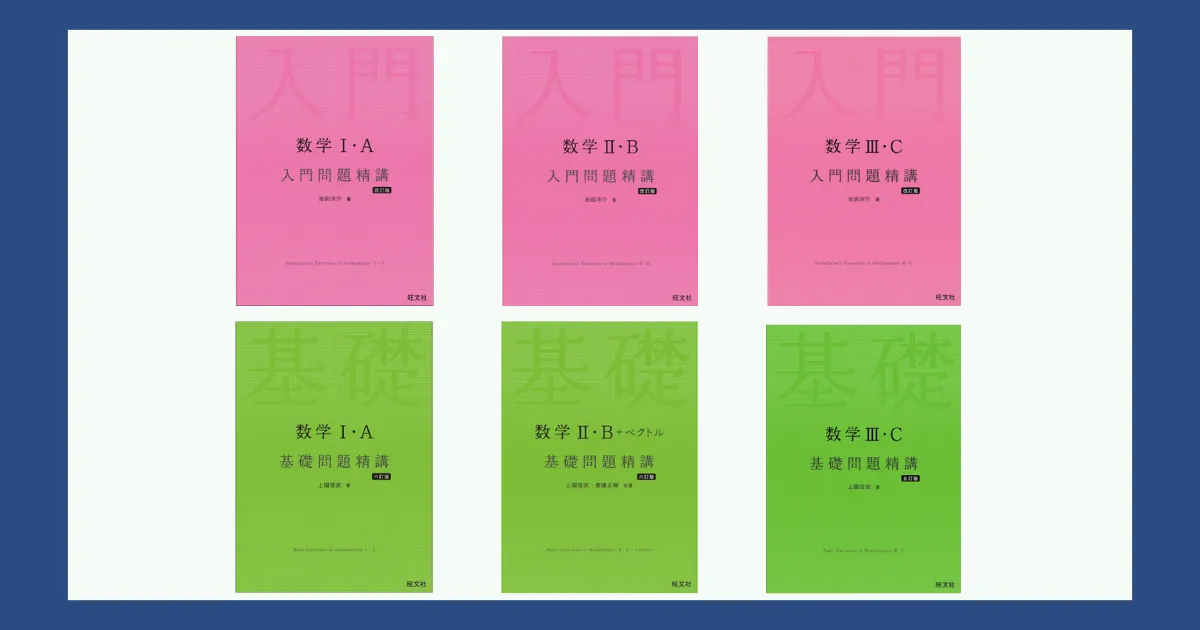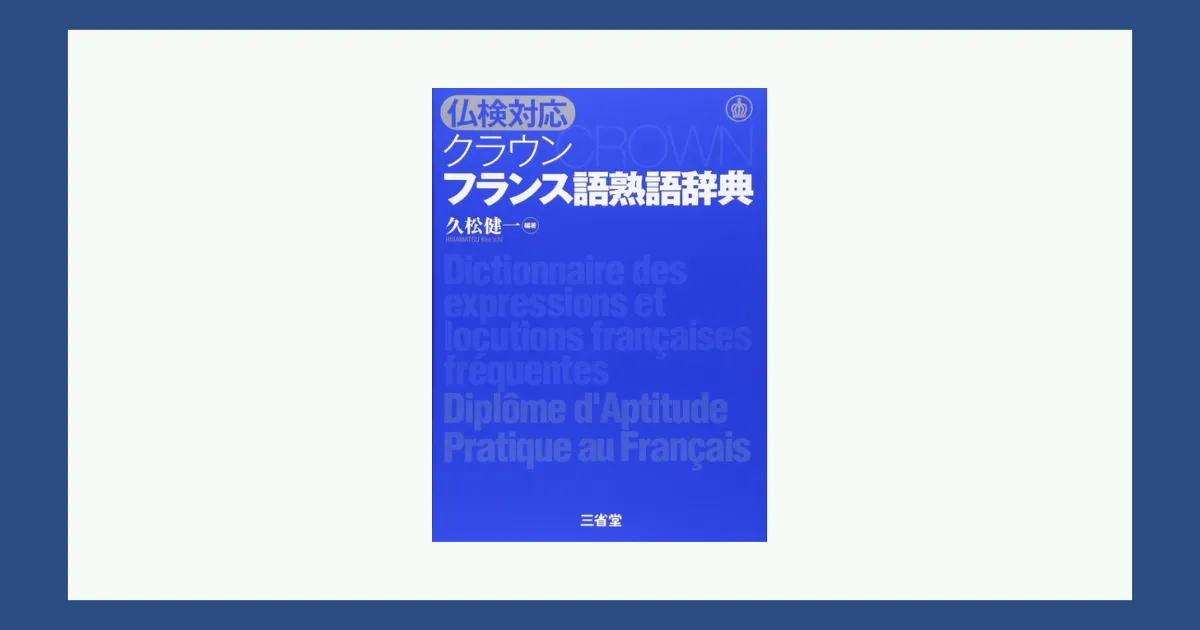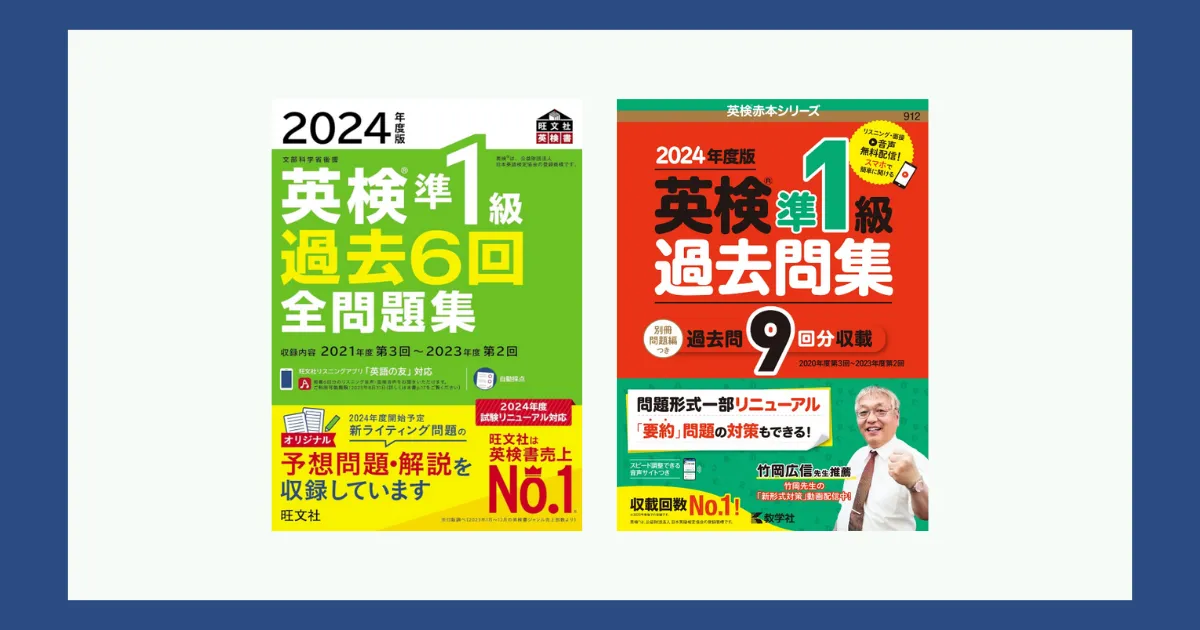| タイトル | パラグラフリーディングのストラテジー 読み方・解き方編 | |||||||||||
| 出版社 | 河合出版 | |||||||||||
| 出版年 | 2005/8/26 | |||||||||||
| 著者 | 島田 浩史、米山 達郎 | |||||||||||
| 目的 | 英語長文読解 | |||||||||||
| 分量 | 200ページ | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
加筆修正の履歴
※本記事は公開以降、内容に変更はありません。
対象・到達
【対象】
・これから英語長文読解の学習を始める人
・英文解釈を終えて英単語もそこそこ身についた人
・全統模試偏差値55から
【到達】
・英語長文を構造的に理解できるようになる
・ディスコースマーカーに着目しながら読解できる
本書は2005年に河合出版から出版された英語長文の参考書です。サイズはコンパクトながら充実した王道の内容です。以前に紹介した『現代文の解法 読める! 解ける! ルール36』に近い印象を覚えます。対象は「英文解釈を終えてこれから長文読解に入ろうとする人」です。英語長文読解の最初の一冊として、英語長文を読むとはどういうことかをイメージしやすくなっています。本書シリーズには続いて『実戦編私立大対策』『実戦編国公立大対策』があり、志望校に合わせたそれらを終えると全統模試偏差値65以上も視野に入りますが、本書は実力を伸ばすよりも現代文と同様に“構造的な理解”をアプローチに加えて安定させる意味合いが大きいと思います。
ではパラグラフリーディングとは何かというと、一昔前に流行した構造的な読解法です。接続語や指示語を手掛かりにパラグラフごとの関係(論理展開)を把握します。英語長文は一文の意味を積み重ねるだけでも内容を理解できますが、語数が多くなるほど短期記憶の容量を超えて全体の理解が不明瞭になります。そこで文章を段落というブロックごとに整理しながら読めるようになれば、一文を積み重ねる読み方よりも安定するという趣旨がパラグラフリーディングです。特に英語は日本語よりも構造が把握しやすいため、パラグラフリーディングを極端に謳う参考書だとほとんど英文を読まなくても内容がわかるとまで言うものもあります。
実際にそれは言い過ぎとしても、パラグラフリーディングが一文を積み重ねる読み方を補完するものになるのは間違いありません。一文単位の理解しかできない人より、一文に加えたパラグラフ(段落)単位、および関係性の理解も加われば、よりいっそう全体を理解できるのは当然です。なお「英文解釈」では一文以上の英文に触れますが、あれも長文読解前には必要な演習になっています。英文の単位で英語学習を見ると、単語帳や文法書の例文は一文、英文解釈は一文以上一段落未満、当サイトが推奨する『速読英単語』はだいたい三段落の文章、そして本書のような長文読解がそれ以上の複数の段落という段階的な学習になっています。
本書の構成
パート1 パラグラフリーディングの基本ストラテジー
→パラグラフリーディングとはどのような考え方なのか。基本ストラテジーとは何なのかを理解するパート。
パート2 「論理マーカー」の働き
→論理マーカーとは、論理展開を明示するつなぎ言葉のこと。本書ではパラグラフリーディングに必要な5つの論理マーカーについて1つずつ例を挙げて解説しています。
パート3 長文問題の解法ストラテジー
→これまでのパートでマスターしたパラグラフリーディングが問題の解法と直結していることを理解してもらうパート。大学入試で狙われる問題(空所補充、パラフレーズ問題、内容一致問題、説明問題、要約問題)への対処法を解説しています。
パート1では「第1章 評論文の性質を知ろう」から始まり、「第2章 パラグラフの基本4原則を知ろう」「第3章 パラグラフリーディングの基本ストラテジーを知ろう!」と続いています。
プロの書いた評論文の特徴
その1 はっきりとしたテーマがある!
その2 そのテーマについて専門的知識をもとにした独自の主張を展開!
その3 論理展開がしっかりしており、破綻のない構成になっている!
その4 表現方法が豊かで難解な語句や表現を用いることが多い!
パラグラフリーディングのストラテジー 読み方・解き方編 P10より引用
こうした内容はほとんど現代文の解法と同じですね。科目の相乗効果は軽視されやすいのですが、英語の長文読解ができるようになると現代文の成績も上がるということが珍しくありません。これは論理的な訓練を積みやすい英語学習の隠れた利点です。
パラグラフの基本4原則
その1 パラグラフとは筆者のイイタイコトのまとまりである。
その2 1つのパラグラフでは筆者のイイタイコトは1つ。
その3 パラグラフが変われば筆者のイイタイコトも変わる。
その4 パラグラフ同士は互いにつながりを持ち英文全体を構成する。
パラグラフリーディングのストラテジー 読み方・解き方編 P12より引用
文章読解は入れ物と中身。試験特有の事情に加えてプロの書いた評論文は論理構造(入れ物)を明確に持っているため、もはや論理構造から中身を推測できてしまうという理屈です。しかも英語は一文単位でも論理構造がはっきりしていて無駄がありません。日本語は母国語ゆえのバイアスのせいか、解釈の幅から誤読しやすい気がします。例えば、本来「適当」という熟語は「ちょうど良く合うこと」ですが、日本語の日常会話では「テキトー=いい加減」と使用されることの方が多いために文章で見かけると読解が揺らぎます。その点で英語は第三者目線で常にフラットに読めます。外国語を学ぶと客観的な思考が養われるというのはその通りだと思います。
そして、パート2では「論理マーカー」についてまとめられています。
マーカー1 対比・逆接マーカー
マーカー2 具体例マーカー
マーカー3 言い換えマーカー
マーカー4 追加マーカー
マーカー5 因果マーカー
パラグラフリーディングのストラテジー 読み方・解き方編 P64より引用
こうしたマーカーを頼りに論理構造を把握します。現代文にはなく英語特有の事情として例えば「対比表現」なら「one ~ the other…(2つの要素について)一方~他方…」「the former ~ the latter…前者は~後者は…」といった表現を覚えておかなければなりません。本書にはマーカーごとの表現が一通りまとめられています。
パラグラフリーディングの参考書は一時期かなり多く出版されていましたが、大袈裟に語るものもある中で本書は謙虚な内容になっています。パラグラフリーディング一辺倒ではなく、無意識に読み流してしまうようなマーカーが重要な意味を持ち、英文全体の構造を把握できる手法を順序良く解説しています。英語長文読解の準備として用いても良いですし、最後の多読多聴を行いながら取り組んでも良いと思います。ただ単に一文を積み重ねたものが文章ではなく、全体の輪郭や骨格があってこその文章という文章(評論文)の本質がわかります。
ただし、この手の参考書を読む際の注意点として、パラグラフリーディングによって読み解ける文章というのは恣意的な可能性があることです。現代文の解法にしても、テクニックにだけ満足する現役生を大量に生み出しかねない懸念があります。英語の場合は大学受験と言っても、ネイティブの小学6年生や中学生レベルの文章であるためにそうした懸念が特別大きいわけではありません。日本語の文章でも、その学年なら素直に読み解けるものが多いからです。ですが、テクニックを文章読解の中心に置くのはオススメしません。文章を正しく読むとは、一文を正しく読み重ねること。一文を正しく読み重ねるためには、接続語や指示語を把握する必要があります。すなわち精読のための参考書として本書を認識してほしいと思います。