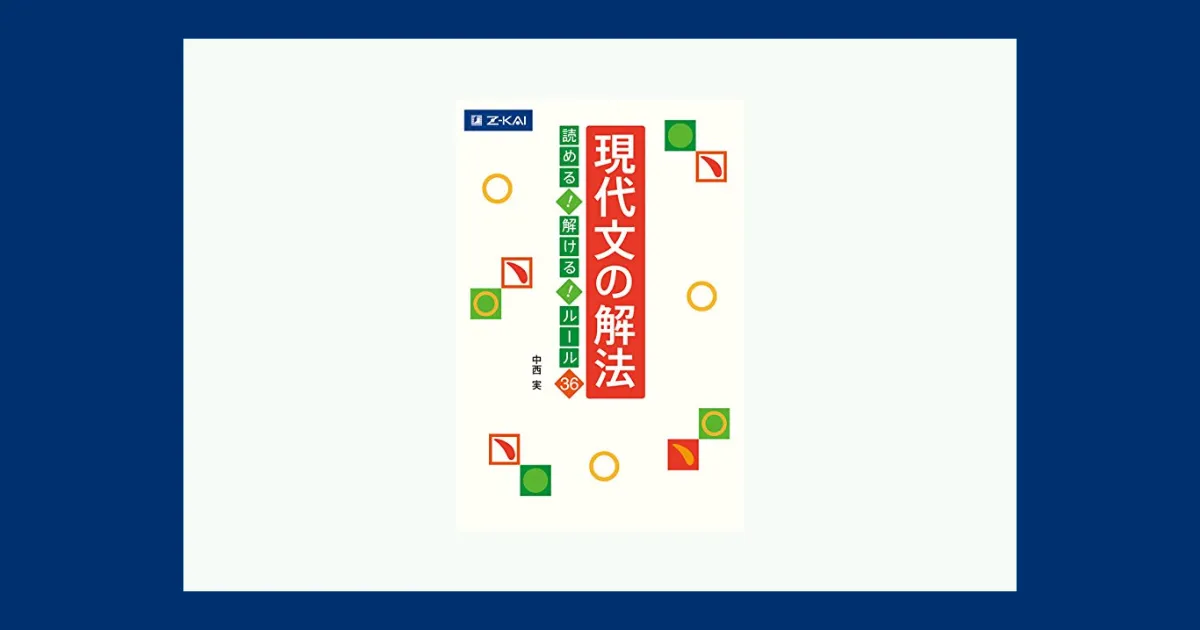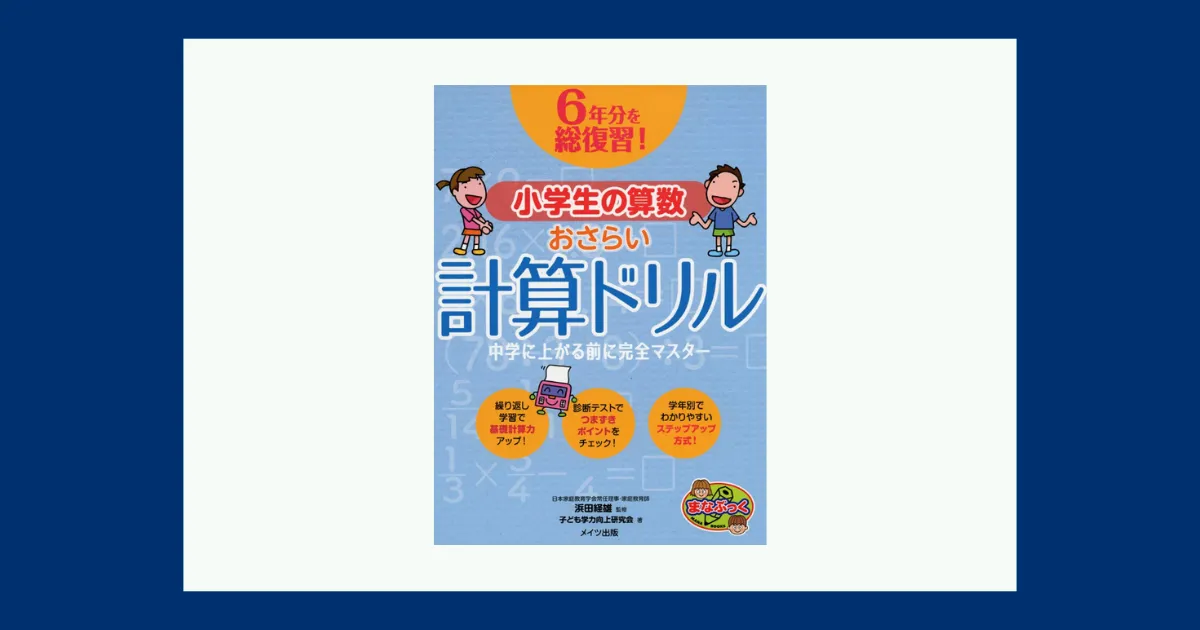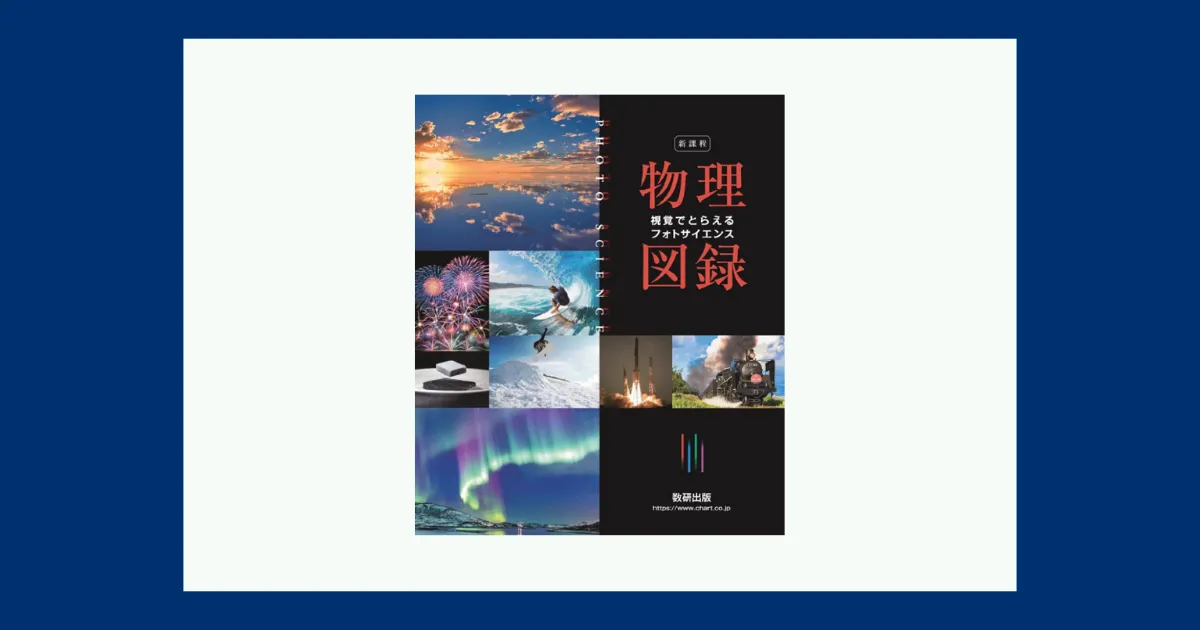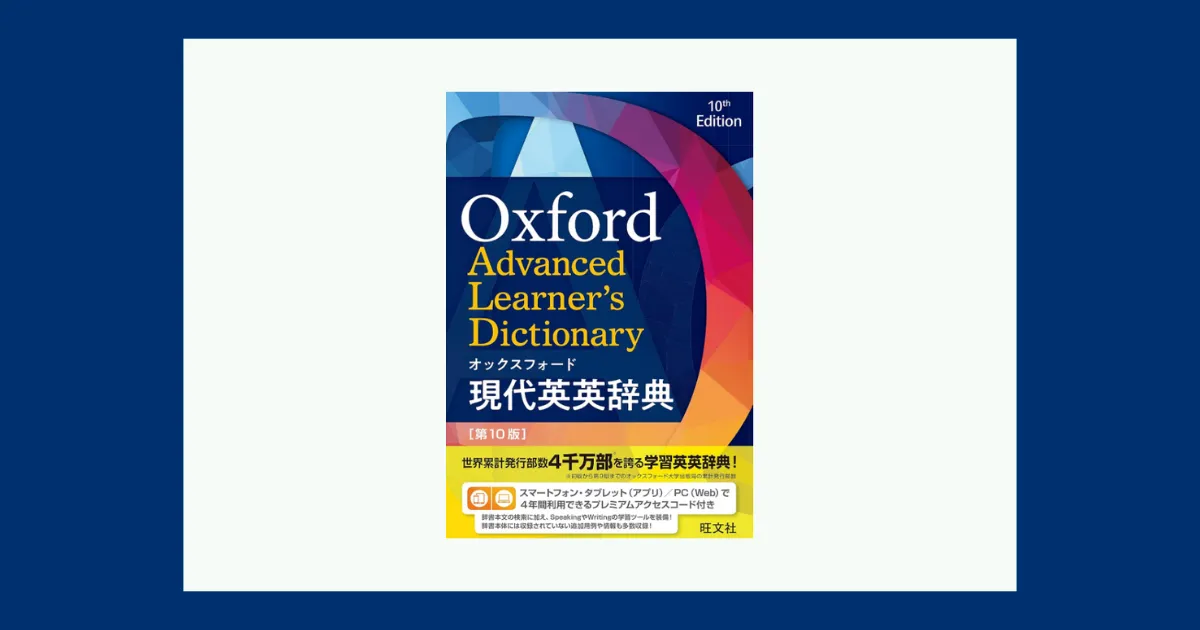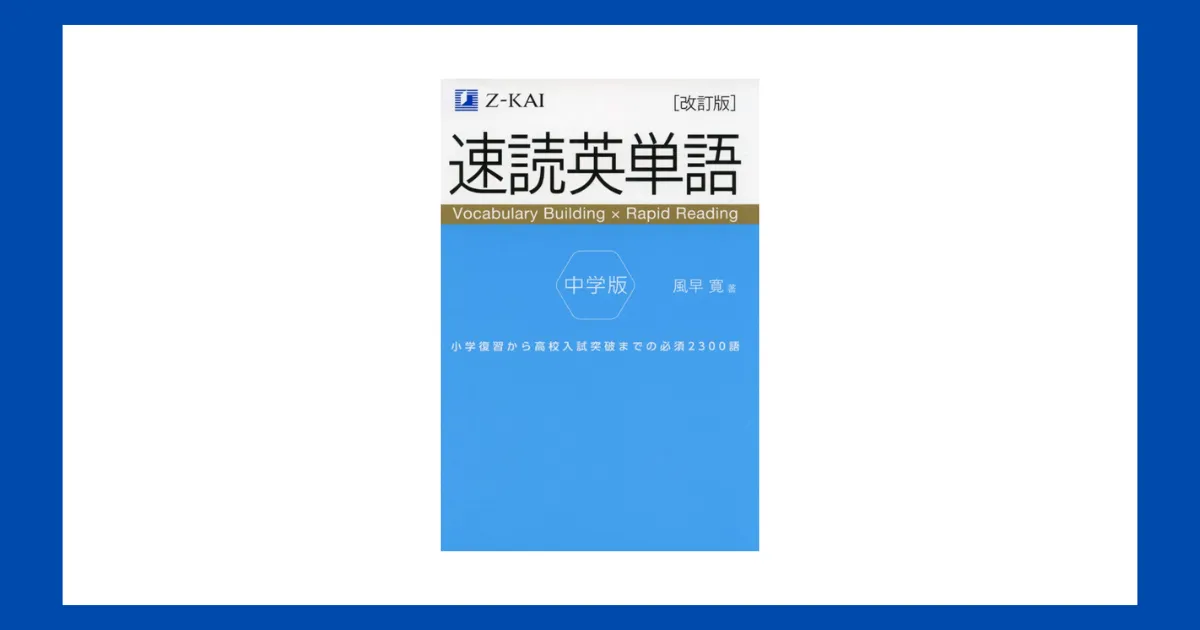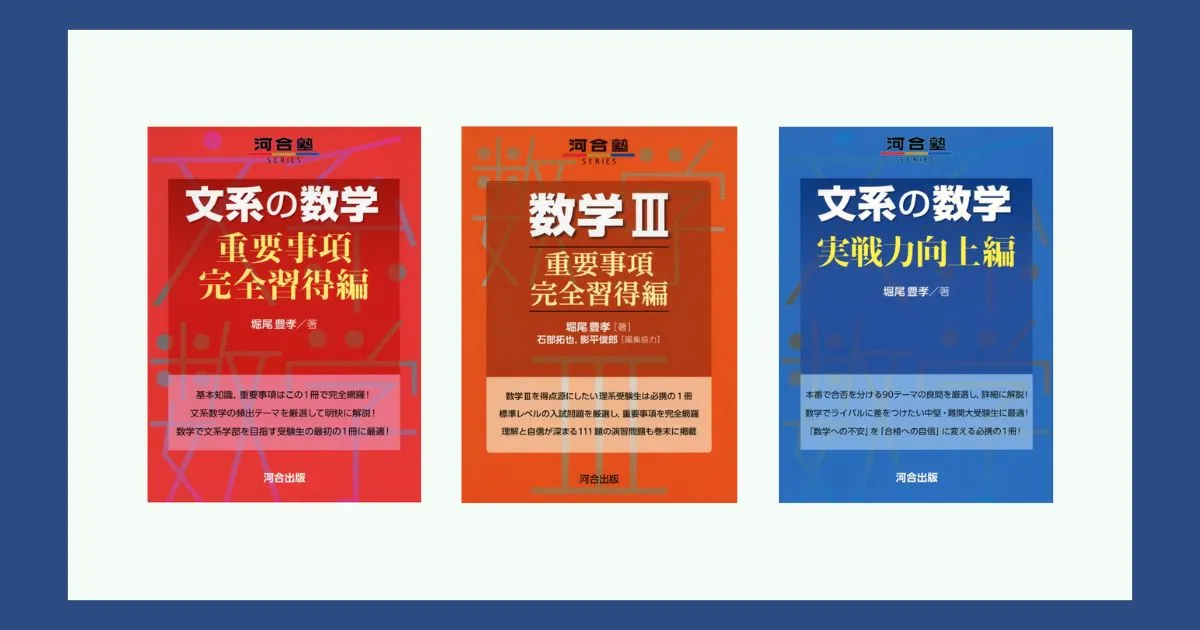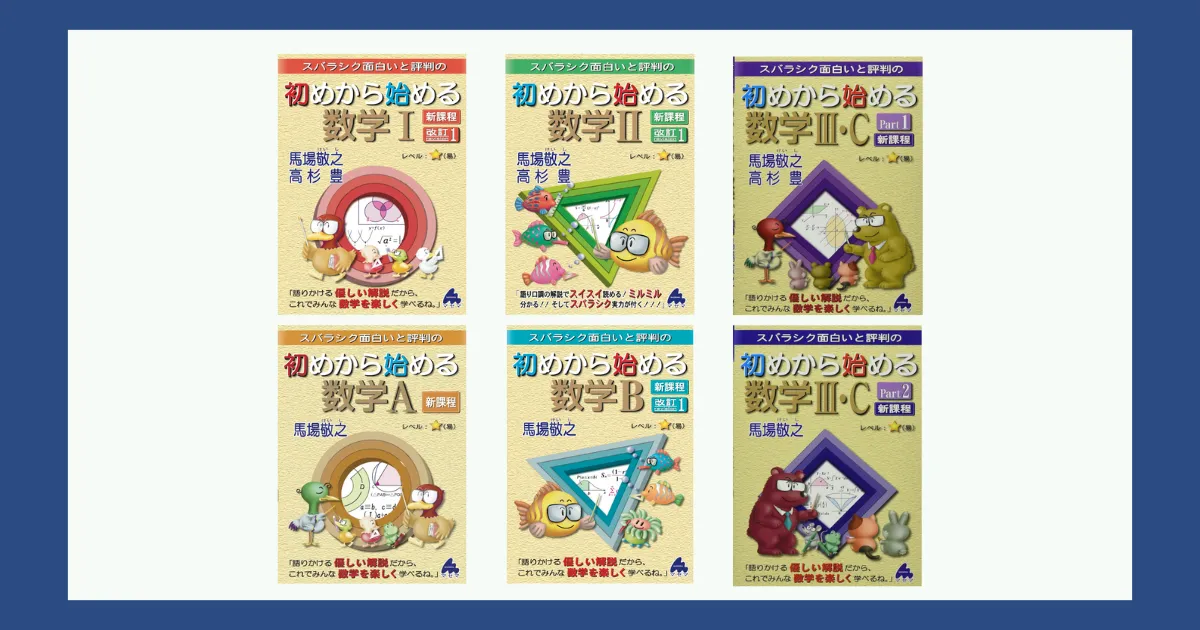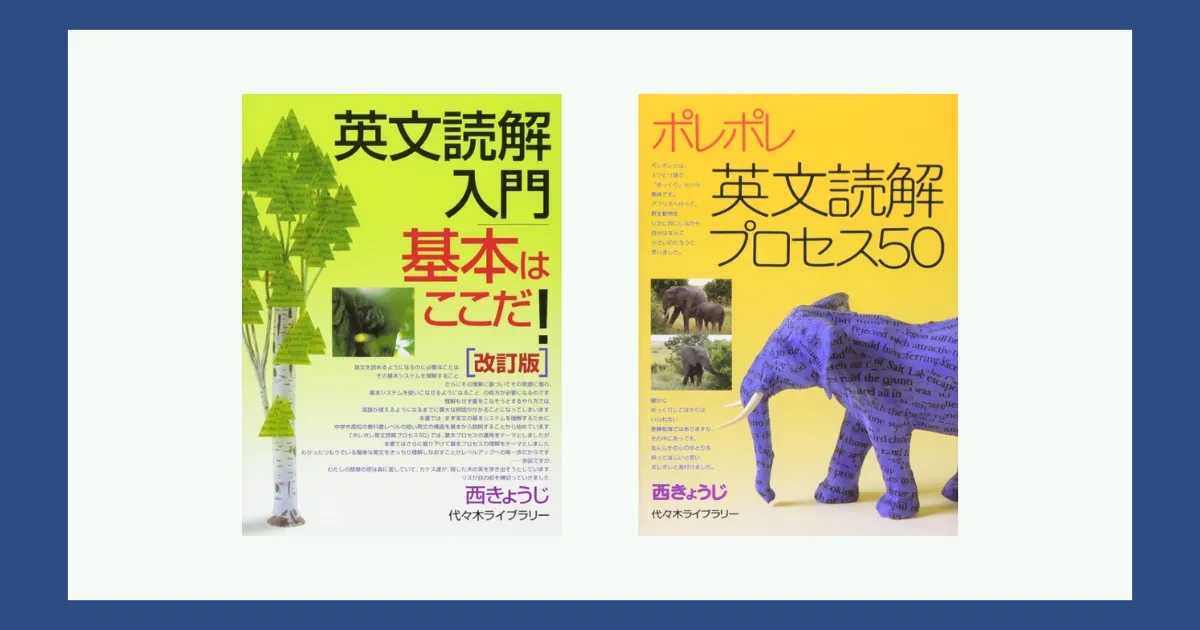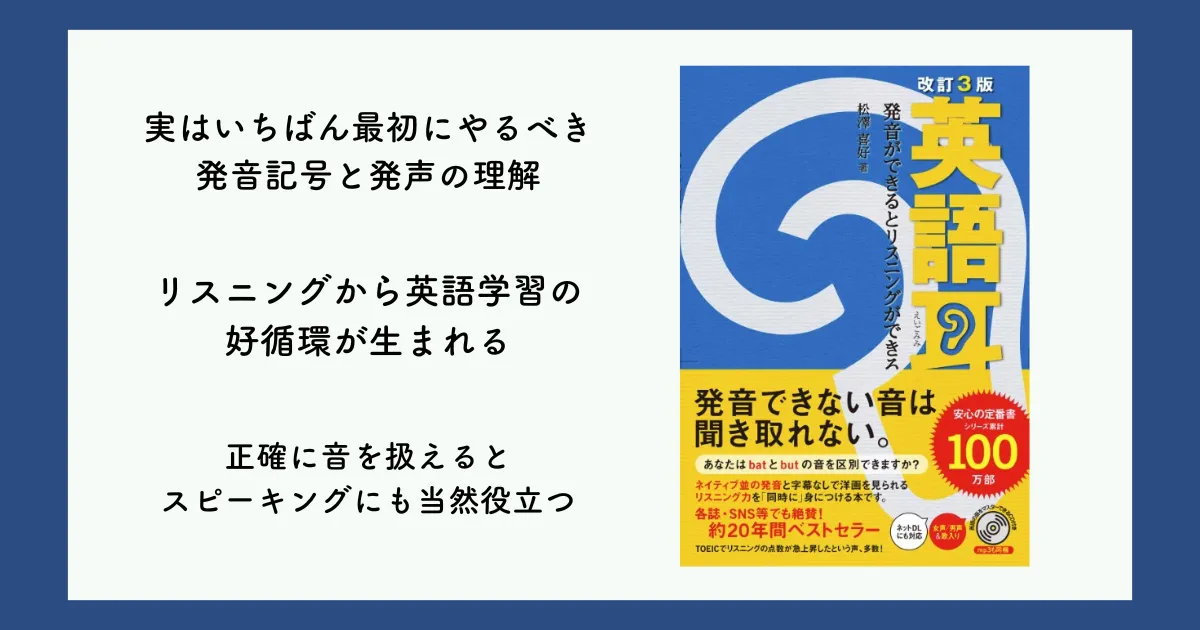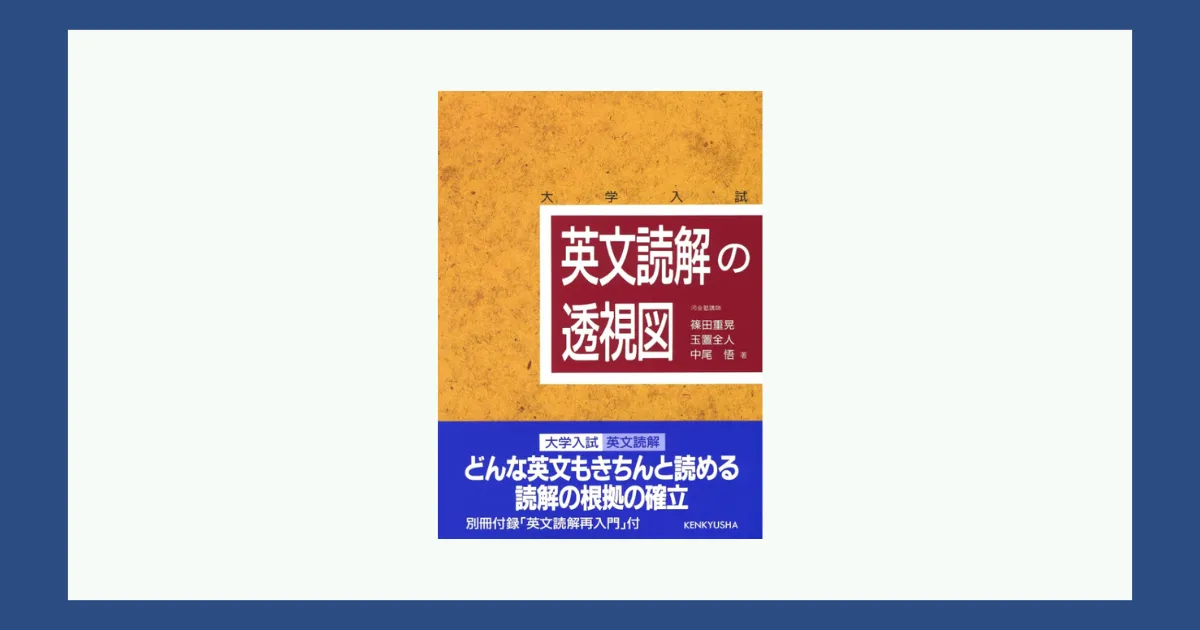| タイトル | 現代文の解法 読める! 解ける! ルール36 | |||||||||||
| 出版社 | Z会 | |||||||||||
| 出版年 | 2013/3/1 | |||||||||||
| 著者 | 中西 実 | |||||||||||
| 目的 | 高校現代文の読解 | |||||||||||
| 分量 | 256ページ | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
対象・到達
【対象】
・現代文の読解が苦手な人
・一文を正確に読めていない人
【到達】
・一文を正確に読む初歩的なルールを知ることができる、精読できるようになる
本書は2013年にZ会から出版された高校現代文の参考書です。Z会が出版する現代文の参考書は『現代文キーワード読解』がとても有名な一方で、現代文の解法を扱った『正読現代文 入試基本編』と『正読現代文 入試突破編』はパッとせず、最近では現代文に精通したイメージを持っていない人は多いと思われます。古文と漢文であれば『古文上達 基礎編 読解と演習45』と『漢文道場 基礎編』が覇権を握るほど有名です。
そんな中で本書は2013年と出版年が古くなってしまったものの、高校現代文の入門向けにまとめられた比較的珍しい参考書になっています。『正読現代文 入試基本編』が要約問題も含む総合的な入試基礎レベルの参考書であるのに対して、本書は定期テスト寄りに位置づけられます。入門と言っても中学と高校の現代文に明確な線引きはあるようでないため、現役中学生であっても問題なく使用できるほど初歩から始まっています。
本書のレベルに近いものは意外と少ないですが、現代文の解法を扱った参考書に関してはかなりの数があります。例えば、船口先生の『船口のゼロから読み解く最強の現代文』や柳生先生の『ゼロから覚醒 はじめよう現代文』は有名です。当サイトでも紹介した難関大向けの『現代文 読解の基礎講義』は名著として語り継がれています。解法とは少し異なりますが、『現代文読解力の開発講座』も非常に有名です。船口先生と柳生先生の著書はどちらも構造的な理解を促すもので本書の内容も含まれています。本書は精読するための初歩的な解説で占められているため、大雑把に読み進めてしまう現役生には刺さる一冊です。ハンドブックサイズで扱いやすく、内容も軽く目を通すだけで十分であることを考えると万人受けしやすいと思います。
本書の構成と利点
本書の利用方法
1章 文章を正確に読むとは?
・読解とは何か
・読解の着眼点
2章 読み方の基本【評論編】
・指示語を押さえて読む
・接続語を押さえて読む
・繰り返し表現を押さえて読む
・論と具体例を押さえて読む
・比喩表現を押さえて読む
・二項対立を押さえて読む
・譲歩表現を押さえて読む
・一般論を押さえて読む
・因果関係を押さえて読む
3章 読み方の基本【小説編】
・心情表現を押さえて読む
・人物描写を押さえて読む
・情景描写を押さえて読む
4章 読み方の演習 トレーニング1~8
付録 ルールのまとめ
本書を取り上げた理由は、構成がシンプルで初歩から始まっているからです。船口先生や柳生先生の著書は講義調でわかりやすいと言えばわかりやすいのですが、内容としては本書+αの読解のポイントをまとめたものに過ぎません。現代文の構造的な理解を目的とするなら、本書のように淡々と書かれてある方が整理しやすいのではと思いました。以下の引用(指示語を押さえて読む)のように初歩から始まっています。
文章中では、机の上の本を指差して、相手に見せることはできません。「(机の上の本を指差して)」というように、指示する内容を明記する必要があります。つまり、指示語の内容は、必ず本文中にあるということです。一見簡単なことですが、指示語だけを何となく見ていると、つい忘れてしまうもの。基本は、本文から離れないことです。
Z会 現代文の解法 読める! 解ける! ルール36 P31より
また、本書は一つの短い文章(300文字前後)に対して問いを複数立てている点が取り組みやすさと理解の両立に繋がっています。例えば「二項対立を押さえて読む」では、最初に二項対立の解説と表現を押さえたあとに沢田允茂『哲学の風景』の一節が与えられます。その一節の中に3つの問題、問1「傍線部と対比されている言葉を一語で抜き出しましょう」、問2「人間だけがもっているものを全て選びましょう」、問3「傍線部の理由として最適なものを選びなさい」が設定され、あらかじめ解説した二項対立を実践形式でそのままチェックできるような構成になっています。文章だと伝えにくくて申し訳ないのですが、要するに数学で言うと「三角関数とは何か→基本計算の方法→例題」という形式になっているということです。
この形式で36個のルールを学びます。例題の文章はルールの確認のために恣意的に調整されたものなので、文章の意味を理解するまでは踏み込みません。例題の解説はあってないようなものです。そのため、本書によって読解力が向上するまでの効果は望めず、文章を読む際の36の視点を獲得するに留まります。ただ、これが現代文の入門としてはちょうど良く、現役生から大人まで使いやすくなっています。現代文で高得点が獲れる人には当たり前なことばかりですが、現代文が苦手な人、これからの人にとっては文中の注目すべき表現にアンテナが張れるようになる優れた参考書になっています。
読解のための2つの視点
そもそも「現代文の読解はどのように行われているか」にも触れておきます。現代文の読解は「一文の意味を積み重ねること」と「文章全体の構造把握」の2つの視点から行われています。簡単に言えば、中身と入れ物。中身とは、語彙と文法の集まった一文のこと。私たちは中身だけでも正確に読み重ねれば、文章全体の意味を理解することはできます。一方、構造とは指示語や接続語などによって形作られる論理の流れのこと。構造は筆者の主張を理解する助けになります。試験ではそれら2つの視点を補完し合って盤石の解答に結びつけるわけです。
しかし、私たちにとって日本語の文章を理解することの多くは無意識や感覚に基づいて行われているため、再現性が高いとは言えない場合があります。これは「勉強法と参考書の決定版」にて「音と論理の類似性」で述べたように、人間は環境から無意識に論理性を身につけるところがあるため、もし正しい論理性が身につけていない場合には本書のような参考書で精読を学んで訂正する作業が必須になります。「読めているようで読めていない自分」を自覚しなければ勉強による成長は絶対にありません。
また、本書は一文の意味を正確に読み重ねるための参考書ですが、誤解なく分類するなら「構造把握」を促す参考書です。この手の参考書を力に変えるなら、前提として語彙と文法はある程度押さえておかなければなりません。一文の意味(=内容)を理解するには「語彙と文法」が第一に必要です。本書のような参考書は現代文が苦手な人を引き寄せやすいのですが、実際は文法を正しく押さえたあとに語彙力を強化して文章を読み慣れる方が遥かに力になります。ただ、今度は語彙を身につけたことによって“知っている単語を拾い上げて満足する状態”に陥る場合もあるため、本書のような構造把握を促して精読を意識する必要があります。読解力の成長にはこの2つの視点からのアプローチが重要です。