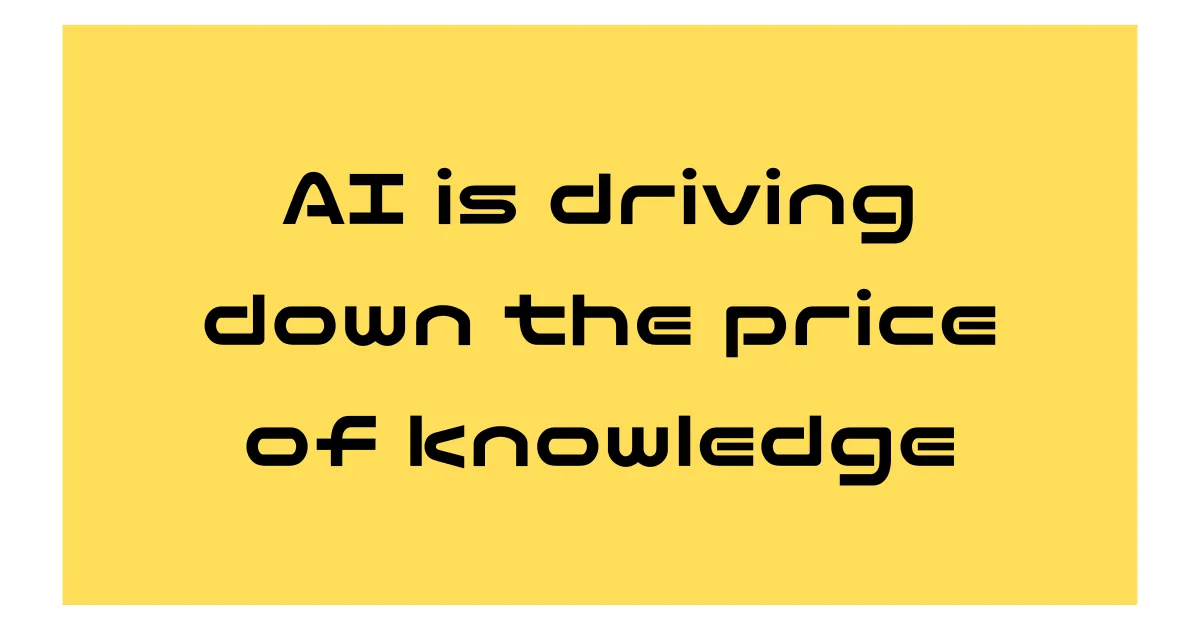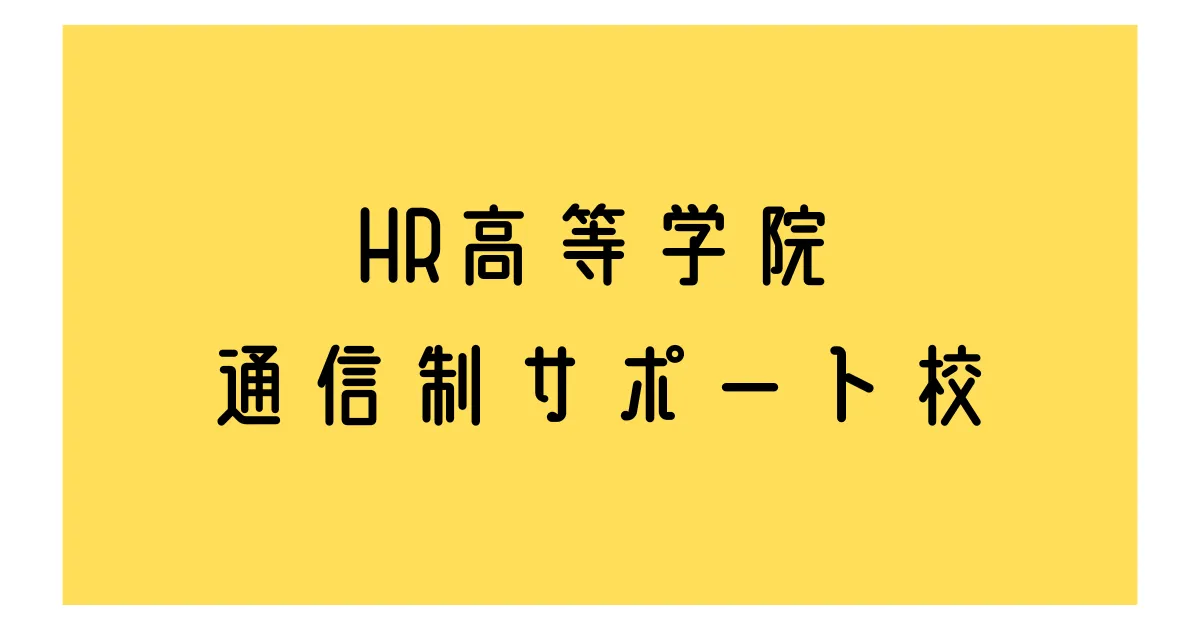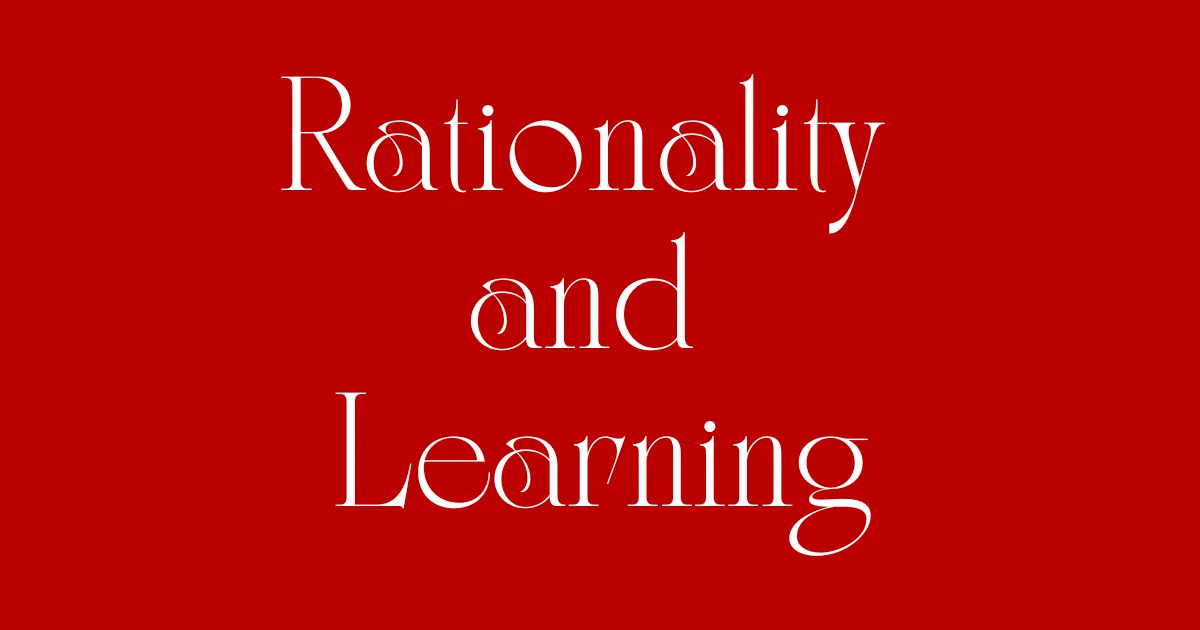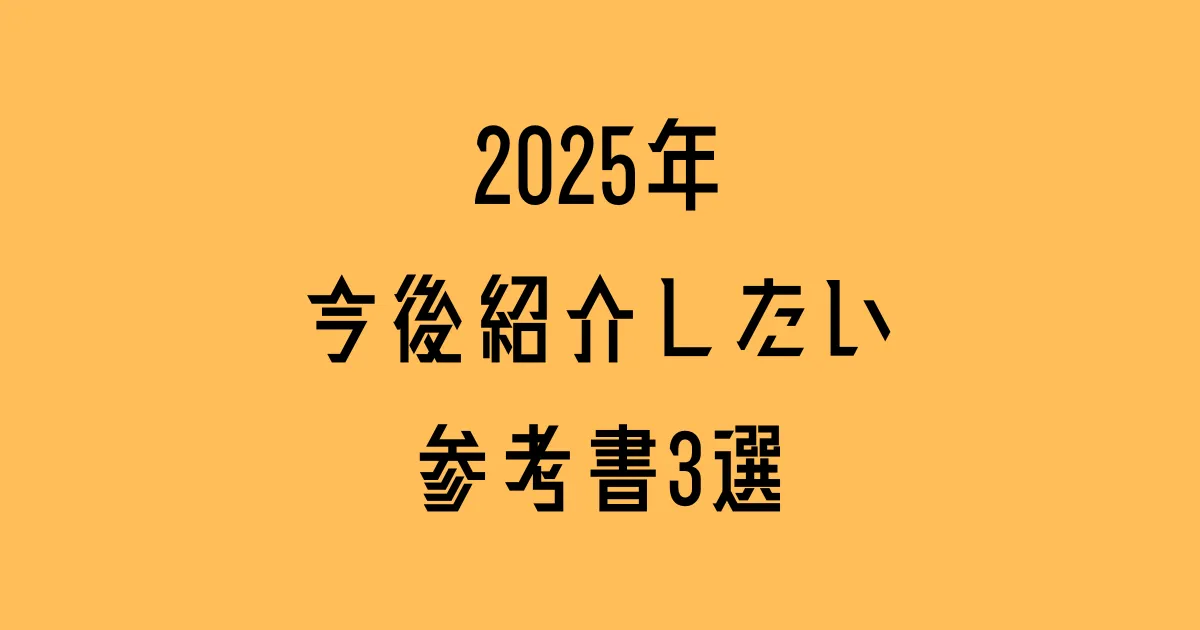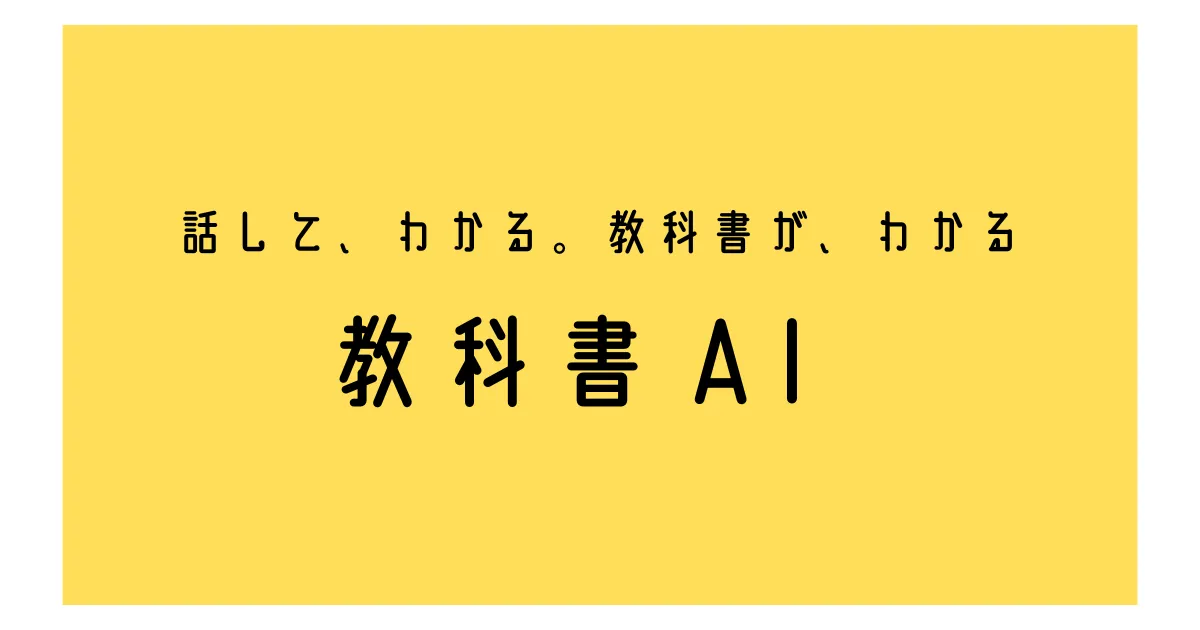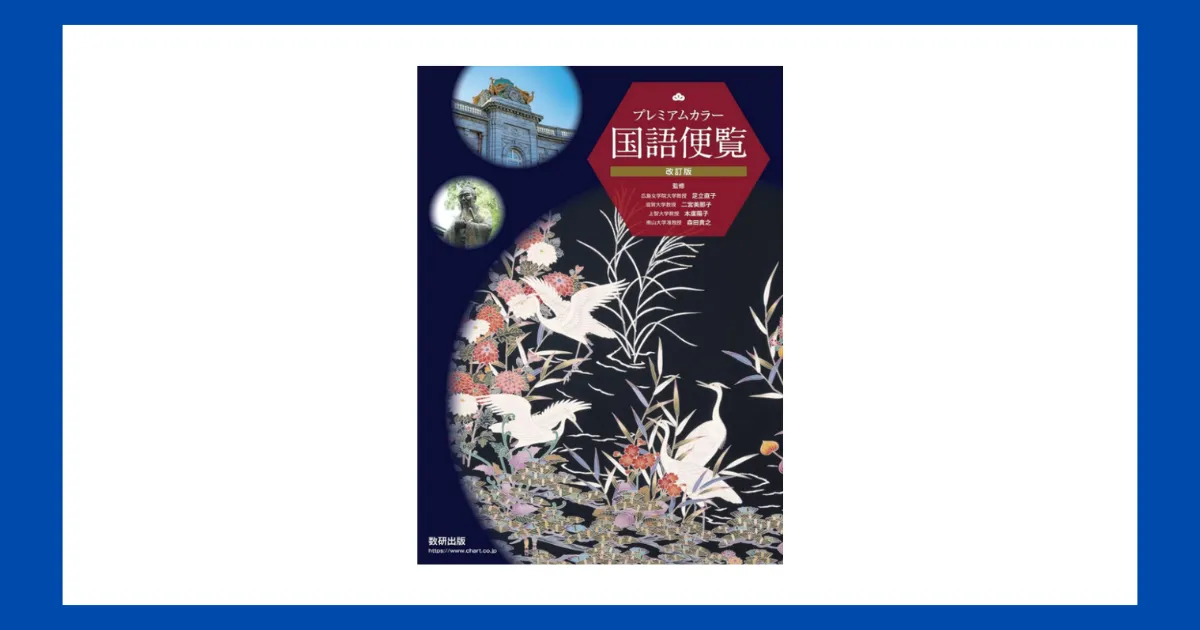| タイトル | AI is driving down the price of knowledge | |||||||||||
| 日本語訳 | AIが知識の価値を変える:大学の再考 | |||||||||||
| 投稿日 | 2025/07/08 | |||||||||||
| 著者 | Patrick Dodd | |||||||||||
| 分量 | 約700語 | |||||||||||
加筆修正の履歴
※本記事は公開以降、内容に変更はありません。
AIが知識の価値を変える – 大学の再考
リンク先は個人的に気になった海外記事です。当サイトは大人の学び直しに主眼を置くサイトですが、学びの形態を大きく変化させていく生成AIの存在はかねてより注視しています。高校課程までの大人の学び直し、および現役生の大学受験は基礎教養と思考訓練の場として有力視しているものの、AIが学びの大部分を代替し、AIを有効活用できるかどうかによって大きな差を生むようになった現実をどう受け止めたら良いのかまだまだわからないからです。そんな中で偶然見つけた海外記事を引用しながら考えてみたいと思います。
For a long time, universities worked off a simple idea: knowledge was scarce. You paid for tuition, showed up to lectures, completed assignments and eventually earned a credential.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Now the curve has shifted right, as the graph below illustrates. When supply moves right – that is, something becomes more accessible – the new intersection with demand sits lower on the price axis. This is why tuition premiums and graduate wage advantages are now under pressure.
theconversation.com「AI is driving down the price of knowledge」より引用
この記事は海外の大学について語っていますが、日本も同様に大学に進学しないと得られない知識があります。それがAIによって誰もが安価に大学レベルの知識をわかりやすく得られるようになったために、大学が従来提供してきた知識の価値の低下が著しい状況にあり、今までとは違った価値を提供しなければならないと述べています。まず、この点については文理問わず「最先端」という意味ではまだまだ価値が残っていると思います。
しかし、そもそも大学の勉強の大部分(特に文系学部)は市販の書籍でもカバーできてしまう現状に加えて、AIによるサポートがあれば大学が提供できる知識、かつそれを丁寧に指導してもらえる価値は低下していると言って差し支えないでしょう。ただ、理系に関しては専門分野の入門である3年生以降の知識は専門書が限られており、情報の信頼性や体系化のコストなども考えていくとAIによる影響は小さいと思われます。以前からある文系学部への批判は拡大し、大学進学の知識的な意義を求めていくと理系学部以外はよりいっそう考えにくくなりました。
AIが変える大学と労働市場:知識の価値低下とスキルの再評価
According to global consultancy McKinsey, generative AI could add between US$2.6 trillion and $4.4 trillion in annual global productivity. Why? Because AI drives the marginal cost of producing and organising information toward zero.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
So yes, baseline knowledge still matters. You need it to prompt AI, judge its output and make good decisions. But the equilibrium wage premium – meaning the extra pay employers offer once supply and demand for that knowledge settle – is sliding down the demand curve fast.
theconversation.com「AI is driving down the price of knowledge」より引用
マッキンゼーの調査によると、AIによって2.6兆から4.4兆ドルの生産性向上をもたらす可能性があると試算されているそうです。これはAIによって「the marginal cost of producing and organising information (知識の生産と整理にかかる限界費用)」を「toward zero (ゼロに近づけている)」が理由と述べています。
また、他方で価値ある人材に関しては大学よりも労働市場が敏感です(Markets react faster than curriculums.)。ある英国の企業では新卒求人が1/3減少し、米国での複数の州で学位要件が外されています(In the United States, several states are removing degree requirements from public-sector roles.)。これは未経験の新卒でもできる雑務(コード化可能なタスク)がAIによって代替されやすいため、労働力を再評価せざるを得なかったためだそうです。言い換えれば、新卒入社して段階的に成長する機会がAIによって現在進行形で奪われています。ただ、これは単なるコストカットという見方もできますが、今まで新卒として評価していた人材ではない人材を評価する過渡期にある一時的なものと考えることもできます。AIによって知識だけではなく、人材の評価も変化しているということ。
そして、反復可能な専門知識に依存する中間レベルの知識労働者が賃金圧力(wage pressure)に最もさらされるリスクが高いと警告しています(mid-level knowledge workers, whose jobs depend on repeatable expertise, are most at risk of wage pressure.)。もともとアカデミックとビジネスでは要求される能力、高く評価される人材に乖離がありましたが、この記事を読むと中間レベルの知識労働者になり得る多くの大卒に居場所があるのか疑問に思います。大学を含む教育機関全般と労働市場の変化速度の差は気がかりです。
希少な資源は「情報」から「人間的なスキル」へ:大学の新しい役割
Herbert Simon, the Nobel Prize–winning economist and cognitive scientist, put it neatly decades ago: “A wealth of information creates a poverty of attention.” When facts become cheap and plentiful, our limited capacity to filter, judge and apply them turns into the real bottleneck.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The opportunity is clear. Shift the product from content delivery to judgement formation. Teach students how to think with, not against, intelligent machines. Because the old model, the one that priced knowledge as a scarce good, is already slipping below its economic break-even point.
theconversation.com「AI is driving down the price of knowledge」より引用
では、どういった人材が今後は評価されていくのか。まず現在の状況を端的に言い表すと、ノーベル賞受賞者であるハーバート・サイモンが述べる「情報の富は注意力の貧困を生む(A wealth of information creates a poverty of attention.)」という状況にあります。この膨大な情報が溢れる中で重要な能力は「注意を集中する力」「的確な判断力」「強い倫理観」「創造性」「協調性」といったAIが苦手とするものです。
そして、それらをこの記事の筆者は「C.R.E.A.T.E.R.」というフレームワークでまとめています。
・Critical thinking (批判的思考)
・Resilience and adaptability (回復力と適応力)
・Emotional intelligence (心の知能指数)
・Accountability and ethics (説明責任と倫理観)
・Teamwork and collaboration (チームワークと協調性)
・Entrepreneurial creativity (起業家的な創造性)
・Reflection and lifelong learning (内省と生涯学習)
これは親として子供をどのように育てるかという問いの答えとしても参考になるでしょう。当サイトとしては「内省と生涯学習」の項目があることに安堵しています。いつの時代も学びの恩恵には適応がありますから、どんなに変化の激しい時代であっても重視されるのは肯けます。心の知能指数、いわゆるEQがAIにはできないチームワークと協調性を発揮するために重要なのもわかりますし、これは日本社会特有なのか、SNSをきっかけに人間関係の感情コストが増大していますから、余計な心配もなく、建設的なやりとりのできる人間関係の価値が急激に上がっています。EQの高さを感じさせる人材の評価は高まるはずです。
さらに大学が生き残るためにできることとして、筆者は「カリキュラムの見直し(Audit courses)」「学習体験への再投資(Reinvest in the learning experience)」「重要なスキルの証明(Credential what matters)」「産学連携(Work with industry but keep it collaborative)」の4つを挙げています。AIが高いスコアを挙げられるような知識の提供には価値がほぼなくなり、AIを活用しながら問題解決できる講義を増やすこと。AIによって代替されない能力を持つことを証明する客観的なもの(資格や証明書)を用意すること。これはある分野の知識の証明として学位があったわけですが、それがAIによって代替できないかどうかわからないためです。企業と大学が連携して社会的に価値ある人材の育成や方針を考え、実践的な学習機会を創出すること。
それでも大学進学を前提にすると、それら4つの改善点は一般人にとっては大学進学の指標になります。社会の変化にできるだけ対応しようとする大学もあれば、頑固に従来通りの教育を提供する大学もあるでしょう。それはどちらが良い悪いではなく、自分の将来を大きく変える選択には確実になります。一昔前であれば、偏差値至上主義的に有名大学への進学が何だかんだ無難な選択になっていましたが、今は先に挙げた能力を養成できる大学、大学以前の勉強も実用的な観点や社会的な応用可能性をよりいっそう重視するようになっていくと思います。結局、横並びでどこの大学も変わらないとなりそうな気がしなくもありませんが、であるなら自分で自分の能力をどのように伸ばしていくかという話になります。