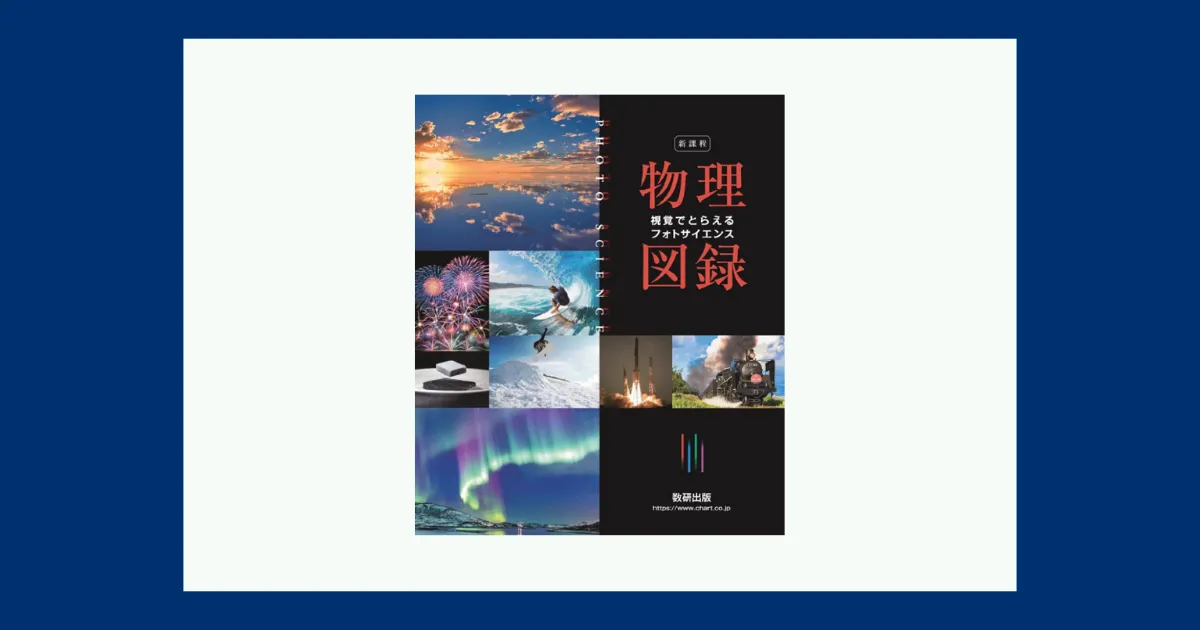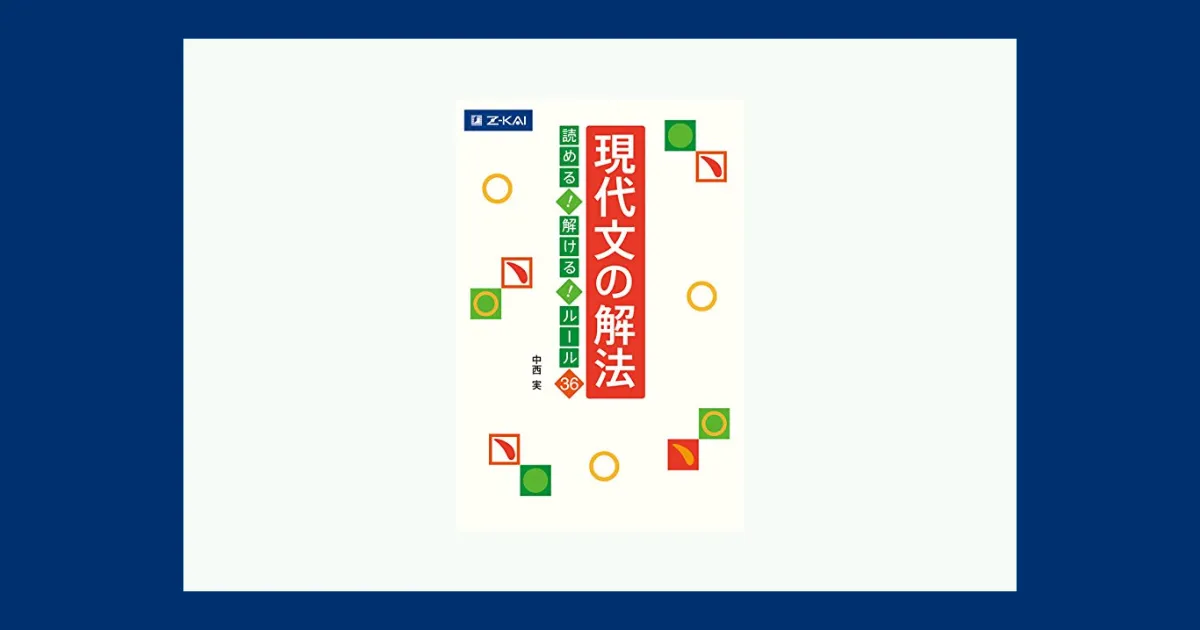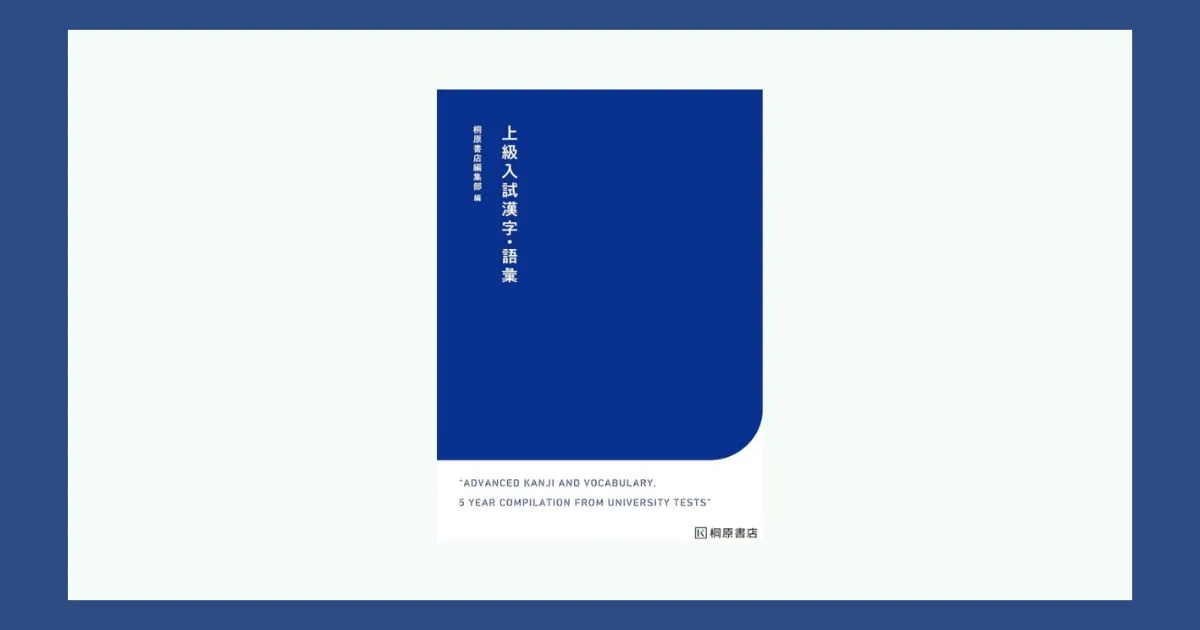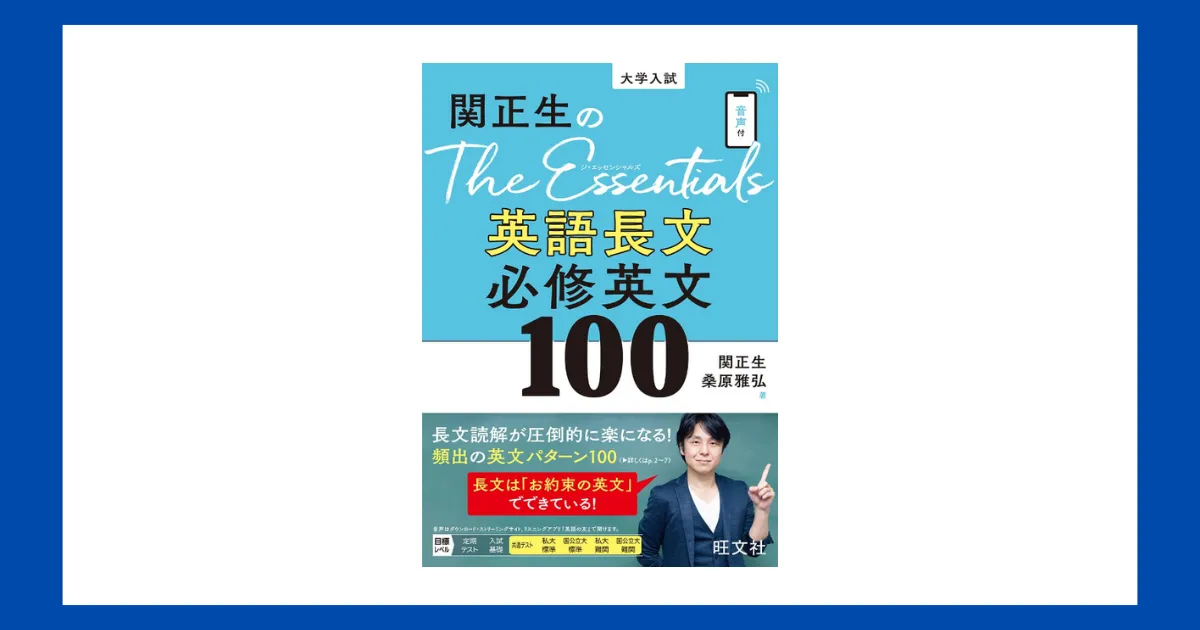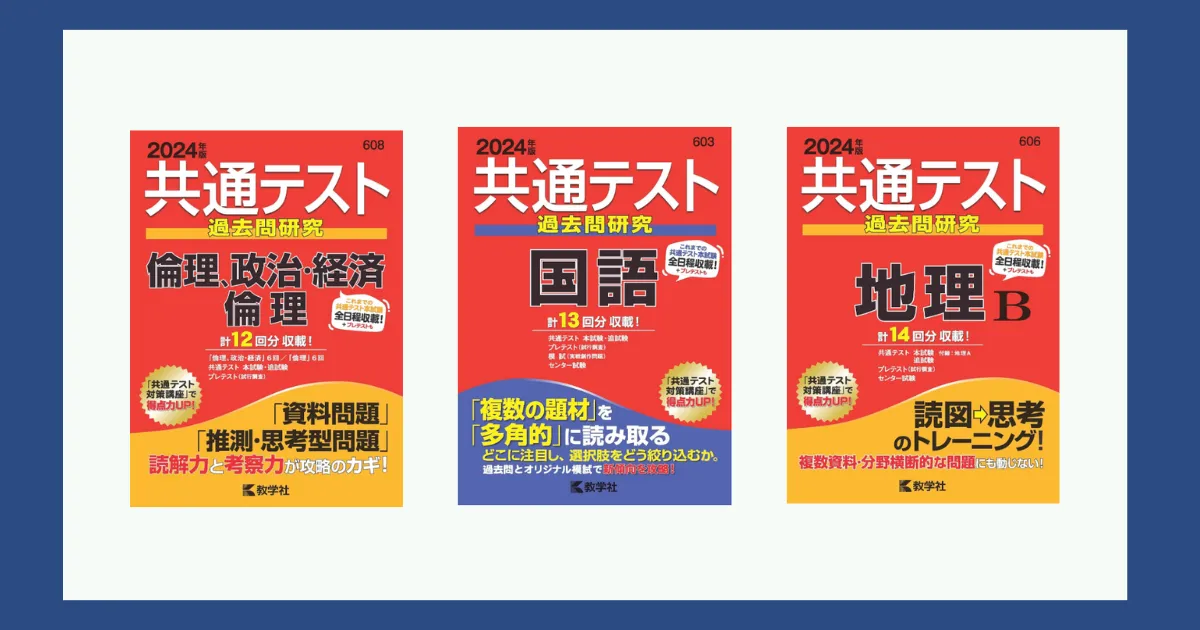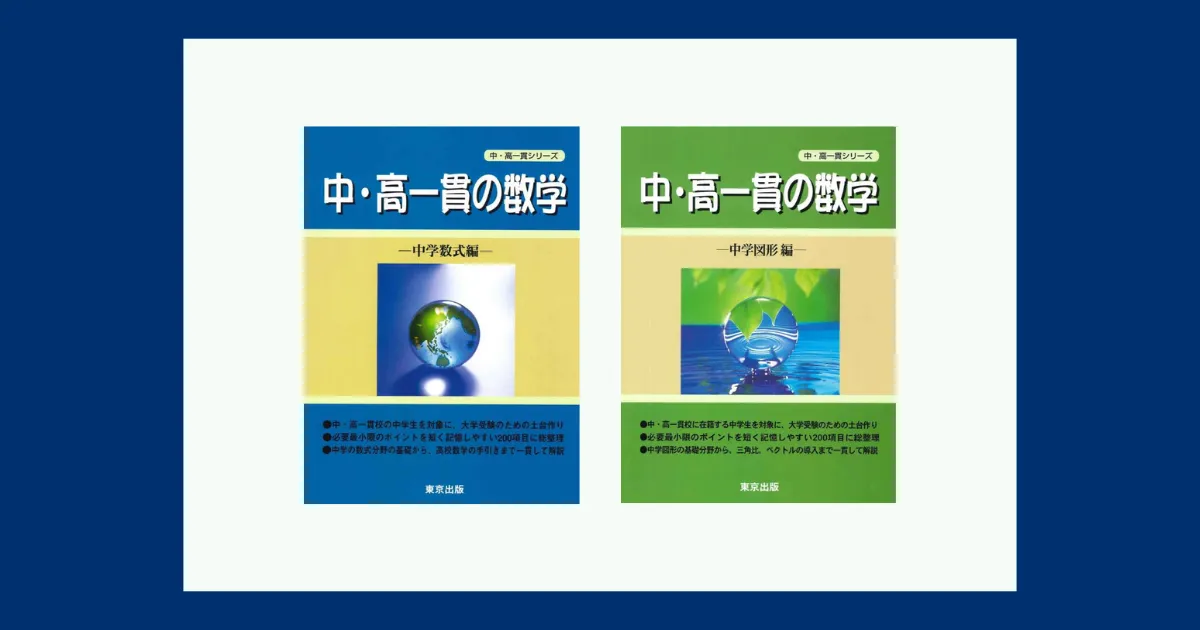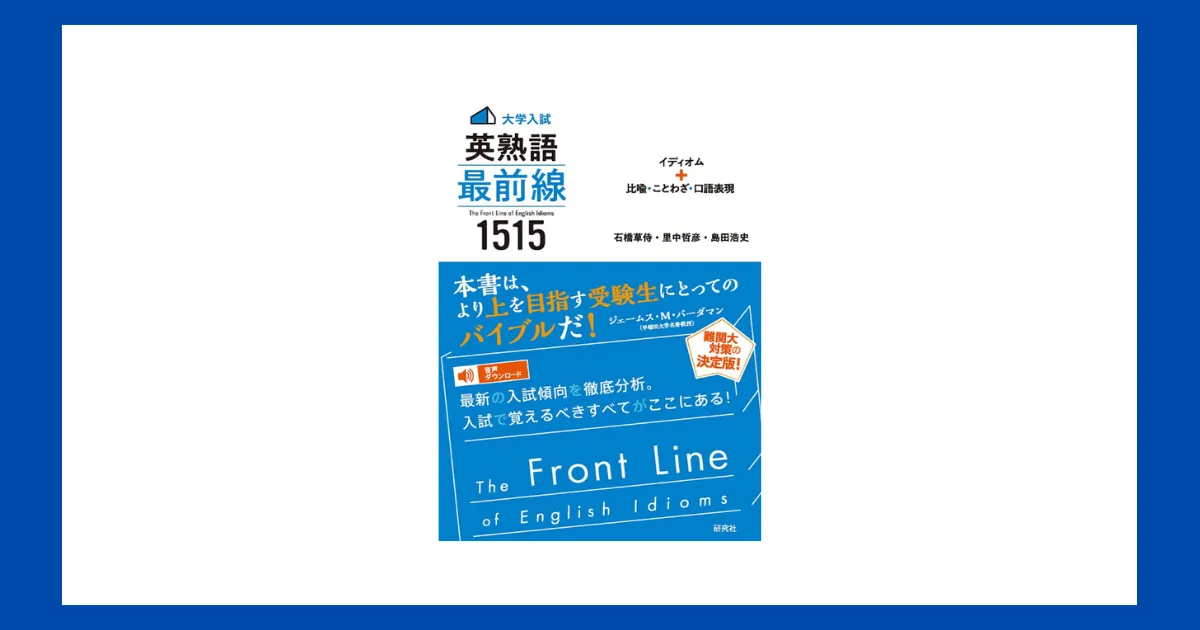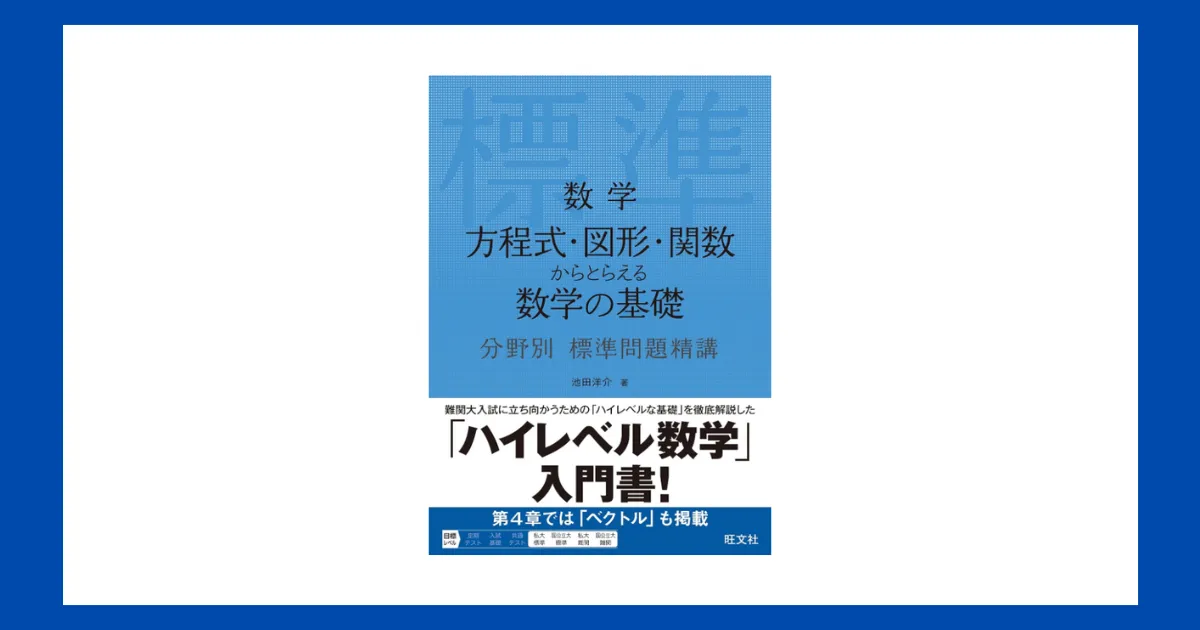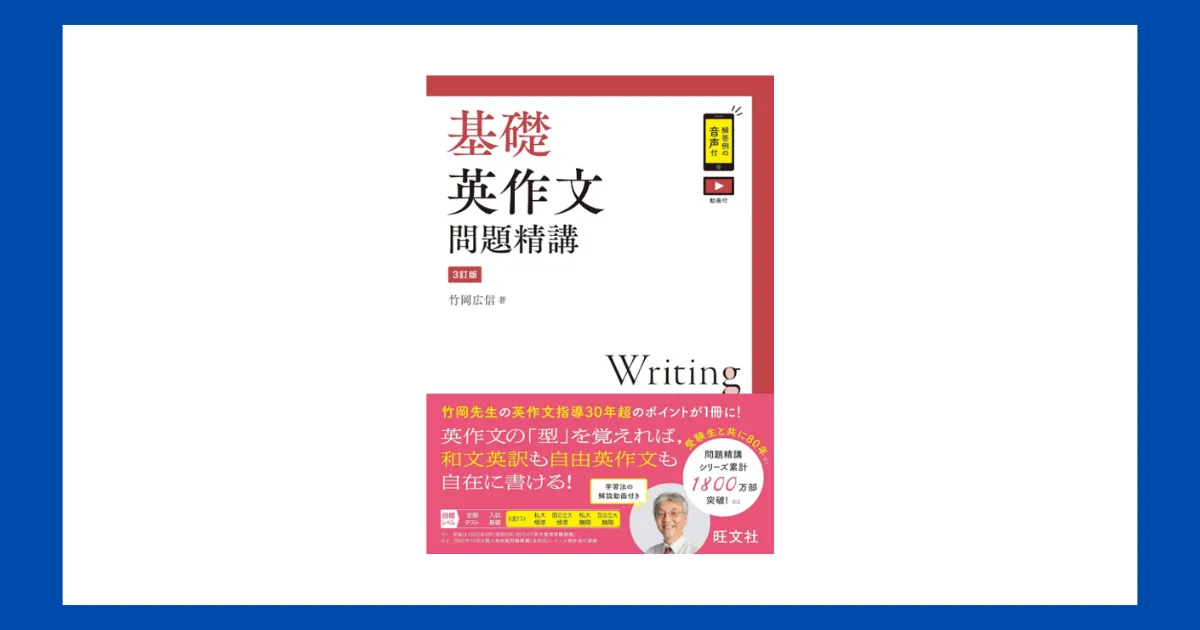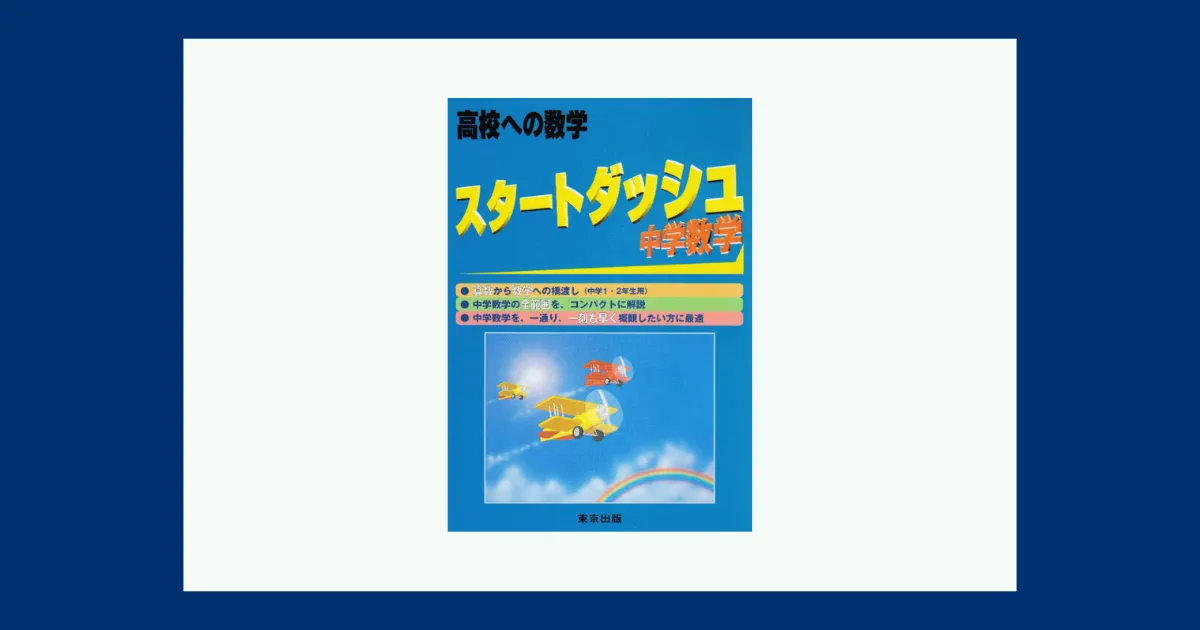| タイトル | 新課程 視覚でとらえる フォトサイエンス 物理図録 | |||||||||||
| 出版社 | 数研出版 | |||||||||||
| 出版年 | 2023/2/10 | |||||||||||
| 著者 | 数研出版株式会社 | |||||||||||
| 目的 | 高校物理の資料集 | |||||||||||
| 分量 | 192ページ | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
加筆修正の履歴
※本記事は公開以降、内容に変更はありません。
対象・到達
【対象】
・物理の理解に苦労している人、視覚的にイメージしたい人
・難関大理系志望、教科書よりも発展的な知識を得たい人
・教科書を理解できる国語力を備えている人
【到達】
・教科書全般の知識を発展的な形で体系化し直せる
本書は以前に紹介した『改訂版 視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録』と同じシリーズの資料集です。わざわざ同じシリーズのものを取り上げるか悩みましたが、物理は視覚イメージがしにくいことが理解を妨げることも多いので、とりわけ資料集の価値が大きいことから紹介することにしました。生物や化学は私たちの身の回りの具体的な事象とイメージが理解に結びつきやすい一方で、物理は数学のように抽象度が高いために意識して視覚イメージを取り入れないと苦労します。
加えて、後述するような勉強による長期的なパフォーマンスを考えると、入試対策以前の興味関心の土台を大きくできるに越したことはありません。受験期にわざわざ本書に取り組むのは直接的な入試対策が少ないために推奨しませんが、それでも興味関心の土台、すなわち内発的な動機を刺激する教材として本書の価値は大きなものがあります。
ここ最近よく考えていることに「勉強とは知識の体系化が全てなのでは?」という振り切った問いがあり、要は一つの知識を獲得したときに「AをAとして覚えて終わる」よりも「AからB、Cと枠組みを意識しながら整理する」が習慣化されるだけで頭が良くなるということです。言い換えると「入試対策」というのは1対1対応の勉強が主になりがちなので、応用力を逓減させることは必然、先生と生徒や予備校と生徒のように主従関係に近い要素が加わると主体性まで失わせる危険があります。言ってしまえば、伸びしろがあるようでない勉強です。記憶の定着も悪い。これを防ぐには本書のような資料集が役に立つのではないかと考えています。
本書の構成
序編 実験の基本操作
第1編 力学
・運動の表し方
・運動の法則
・仕事と力学的エネルギー
・運動量の保存
・円運動と万有引力
第2編 熱力学
・熱と物質
第3編 波
・波の性質
・音
・光
第4編 電磁気
・電場
・電流
・電流と磁場
・電磁誘導と電磁波
第5編 原子
・電子と光
・原子と原子核
研究室紹介
資料編 巻末資料(物理史や誤差と有効数字、数学の基礎知識、単位、日本各地の重力加速度、電気用図記号、摩擦帯電列、個体の線膨張率、三角関数の表など)
映像・アニメーションコンテンツ
内容に関しては★10個付けても足りないほど文句のつけようが全くありません。価格に対して内容がとんでもなく充実しているので、学び直しを考えている大人なら問答無用で買って損はない一冊です。親であれば、子供へのプレゼントにもオススメ。小学生の子供でも読もうと思えば読めますし、小学生で本書に興味を持てる子は勉強に関しての心配はほとんどなくなるでしょう。
Zoom up「摩擦力は抵抗力?」
運動している物体に摩擦力がはたらくとき、摩擦力は抵抗する力としてはたらき、速さが減少していくイメージがある。しかし、場合によって摩擦力は物体を加速させる力としてはたらく。例として、自転車などがあげられる。自転車を漕ぎだすと、後輪は写真の時計回りの咆哮に開店する。このとき、後輪は地面からの摩擦力が回転運動を妨げる方向、つまり、進行方向にはたらく。そのため自転車は加速する。しかし、前輪はペダルを漕いでも回転させられないため、進行方向とは逆に摩擦力を受け、時計回りに回転する。
新課程 物理図録 P32より引用
本書は全体的に情報量が多く、難関大志望の入試対策として採用しても挫折する懸念があります。そのため、まずは辞書利用で通読は避けた方が無難かもしれません。通読自体は非常にオススメ。
Column「宇宙での体重測定」
宇宙などの無重量状態では、地球で使う通常の体重計は役に立たない。国際宇宙ステーション(ISS)では、ばねで押し返されるときの加速度 a をはかり、加えた力の大きさ F と運動方程式 F=ma から体重(質量m)を測定している。宇宙飛行士は健康管理のために、定期的に体重測定することが義務付けられている。
新課程 物理図録 P31より引用
この「Column」のように本書には知的好奇心を刺激する工夫が散りばめられています。本書をはじめ、高校理科の教科書を学び直しに強く推奨する理由は、子供たちに興味を持ってもらえるように身近にある自然現象を取り上げた上で学術的に正確な解説が施されているからです。高校レベルなら大人が読んでも遜色ない点も挙げられます。優秀なAIサポートと比べても、本書にはまだまだ優位性があります。
視覚的なイメージを理解に組み込む視点
理解と記憶の定着の観点から言うと、人間は五感をフルに使って覚える方がより良いと言われています。笑い話のように感じるかもしれませんが、机に向かって英単語を眺めるよりも、スクワットしながら覚える方が記憶には残りやすいのです。物理的な本を推奨する理由も触覚や嗅覚が働きやすいからです。アナログな勉強は意外と否定できません。
物理は視覚的なイメージがしにくい科目特性があるので、本書を利用してイメージできるようにまでなれば勉強も有利に進められます。この点は数学だと限界があり、自然現象を具体例に挙げられる理科は高校レベルなら比較的苦手になりにくい科目になっています。特に生物は文系にも受け入れられやすく、理科科目の中では苦手な人が少ない印象です。
別の言い方をすると、勉強において“理解の仕方”を追求する人はそこまでいません。子供は特にそうです。小学生の頃のなんとなく身につけた勉強法を、そのまま高校生になっても続けてしまっているのではないかと思います。それでうまくいっているなら良いのですが、基本的に難解な事柄になるほど理解のアレンジが求められます。簡単に言うと、より良い情報を足すこと。「勉強が得意な人は頭が良いから」ではなくて「わからないときにきちんと情報を足しているから」という話です。先に述べた「体系化が全て」というのは自分自身を枠組みとしたときの知識の在り方のこと。これを追求していくとき、自然と選択肢に入るのが本書です。
基礎固め以前に興味関心の土台を大きく設ける
数々の経験を経た大人にとって学び直しの意欲は理想的な動機(アウトプット→インプット)ですから、子供よりもある意味では勉強の旬の時期です。大きな興味関心が土台にあれば、理解するために粘ることも覚えることも難しくないと感じるでしょう。子供の頃以上に勉強に充実感を覚えます。
一方、子供は有り余る体力からして動き回る事が好きだったり、単純な刺激の強さに導かれたりする面があるため、いくら本書が高いコスパで充実した内容になっていると言ってもなかなか伝わらないと思います。本書は図録と言っても、テキストもふんだんに盛り込まれているので、推奨できるとしても偏差値65以上の高校生か、それ未満では物理に強い関心がある子に限られます。しかし、現実に勉強を効率良く進めていくためには、興味関心の土台が大きく影響する事実には誰もが向き合わなければなりません。興味関心が土台に無い状態では、いくら理想的な勉強法や優れた参考書、予備校を採用しても効率は間違いなく落ちます。これに関して異論がある人はいないと思います。楽しいことには誰もが夢中になりますから。
大人の学び直しは趣味としても、大学受験はもはや仕事と捉えて子供を積極的に大人扱いしていくとき、では自覚的に興味関心を高めるにはどうしたら良いのか?という疑問が当然出てきます。本書を素直に推奨したいと思える層は限定的でも、教科書準拠で体系化され、物理への興味関心を刺激してくれる質の高い教材としては唯一無二です。また、興味関心というのはあるだけでは先に進まず、興味関心をきっかけに動き出したときに思考や気持ちを繋げる必要があります。これは焚火の火起こしと同じ。興味関心は火種に過ぎず、燃え移るものがないと、燃え移ろうにも燃えにくいもの(難解)だと消えてしまいます。つまり、興味関心を高めること、高めたあとの受け皿として本書は効果的に機能する可能性があり、物理を勉強するなら持っておいて損はない一冊です。