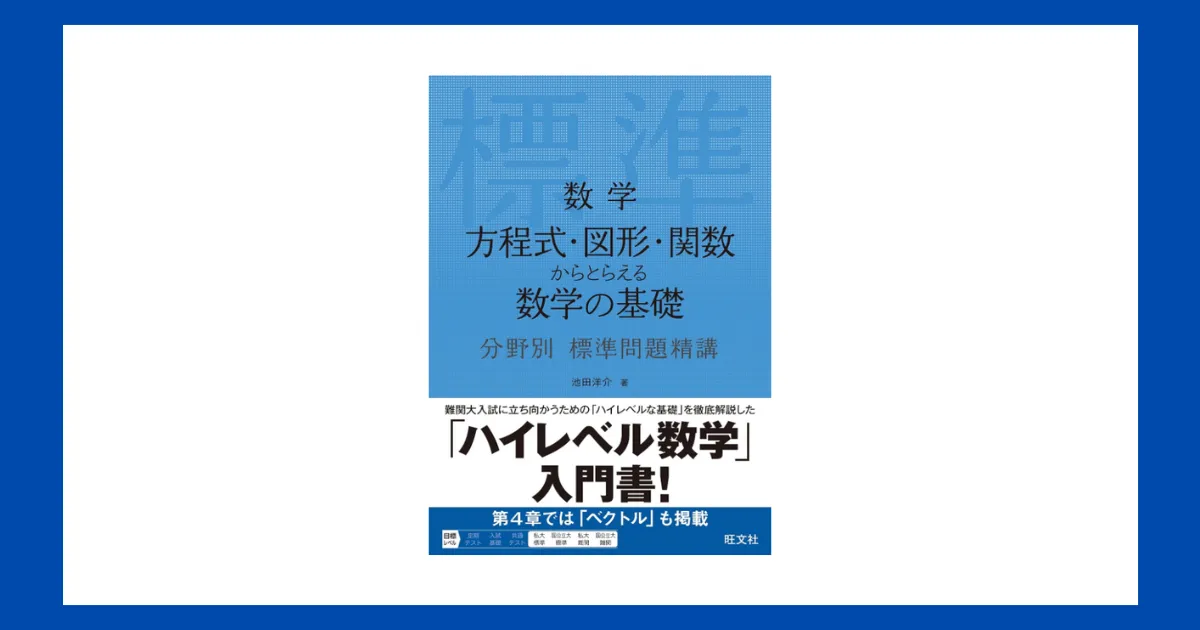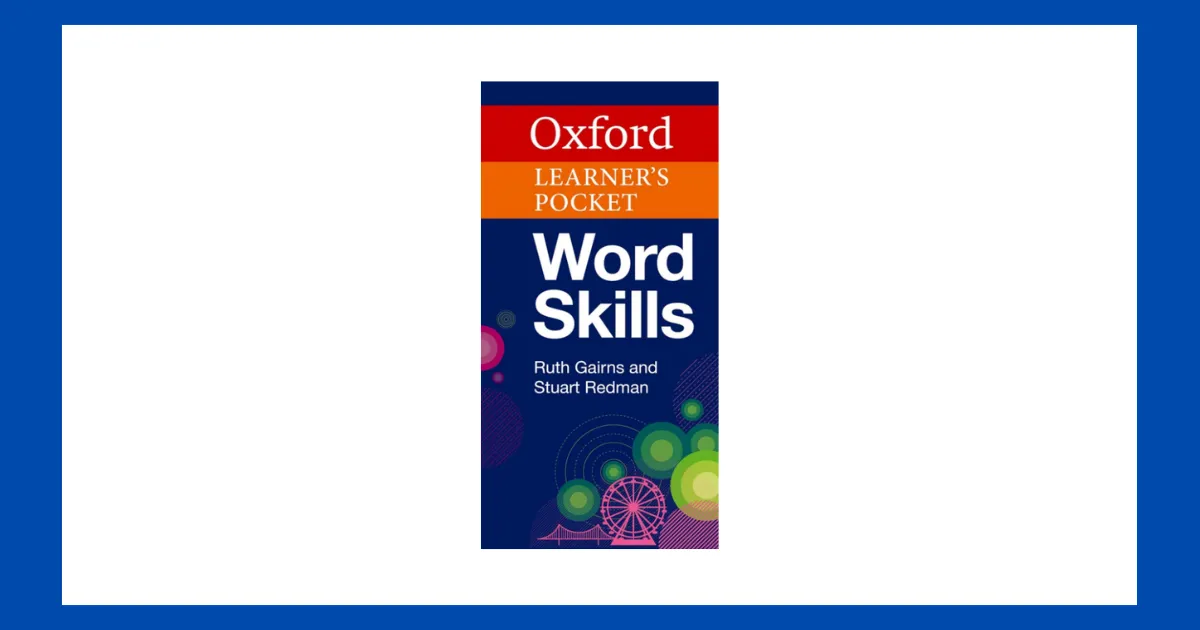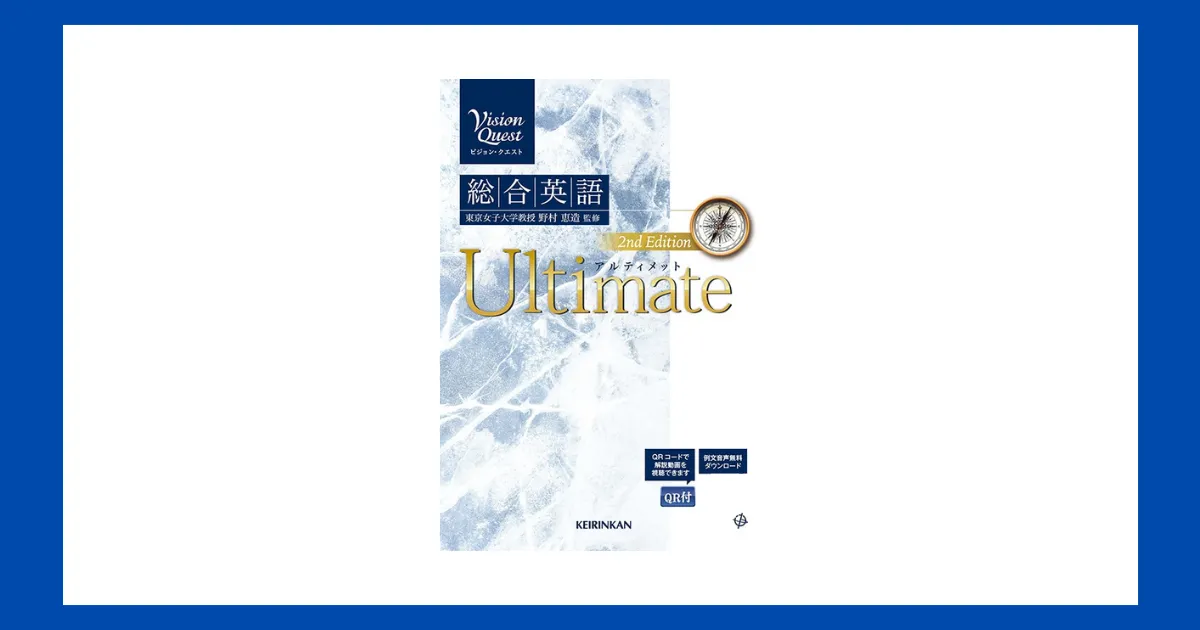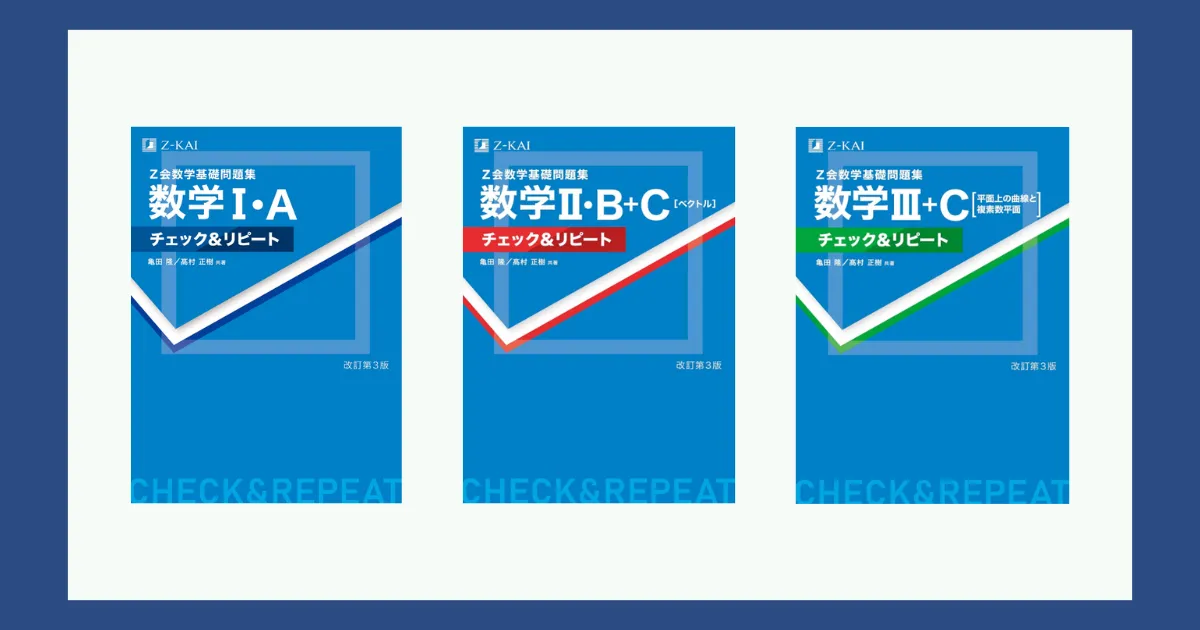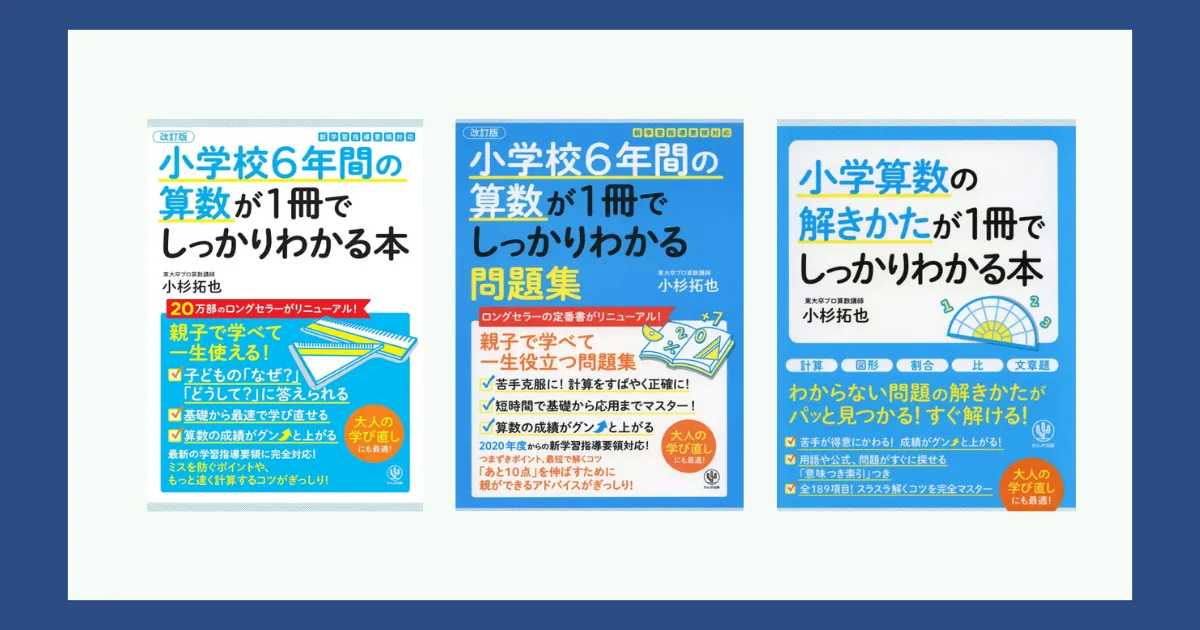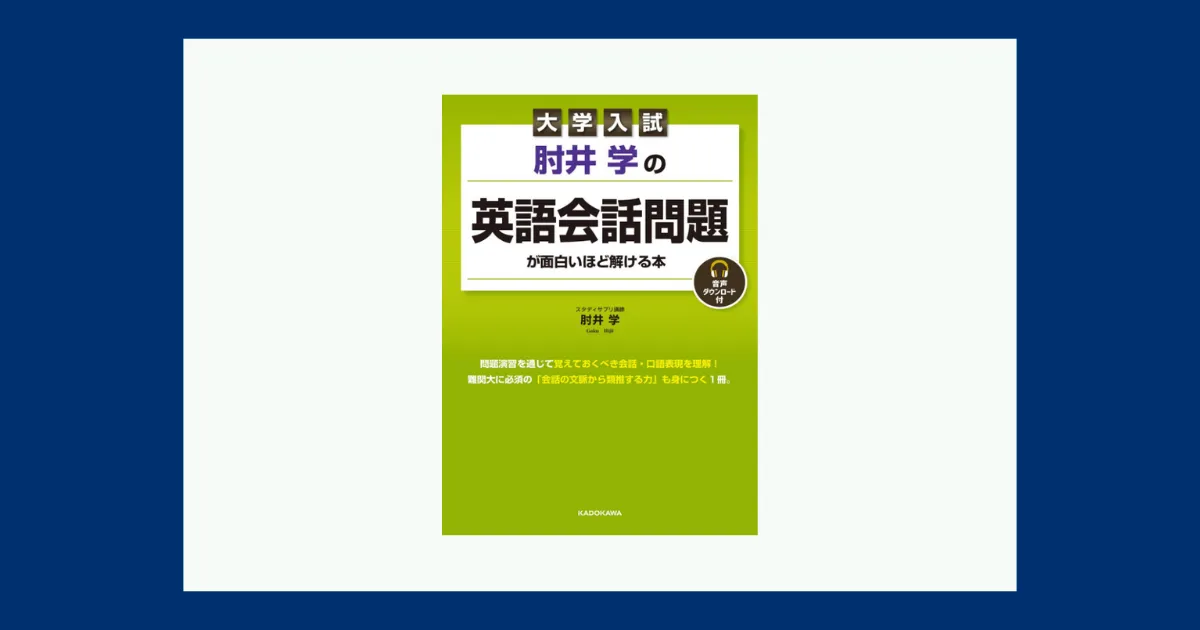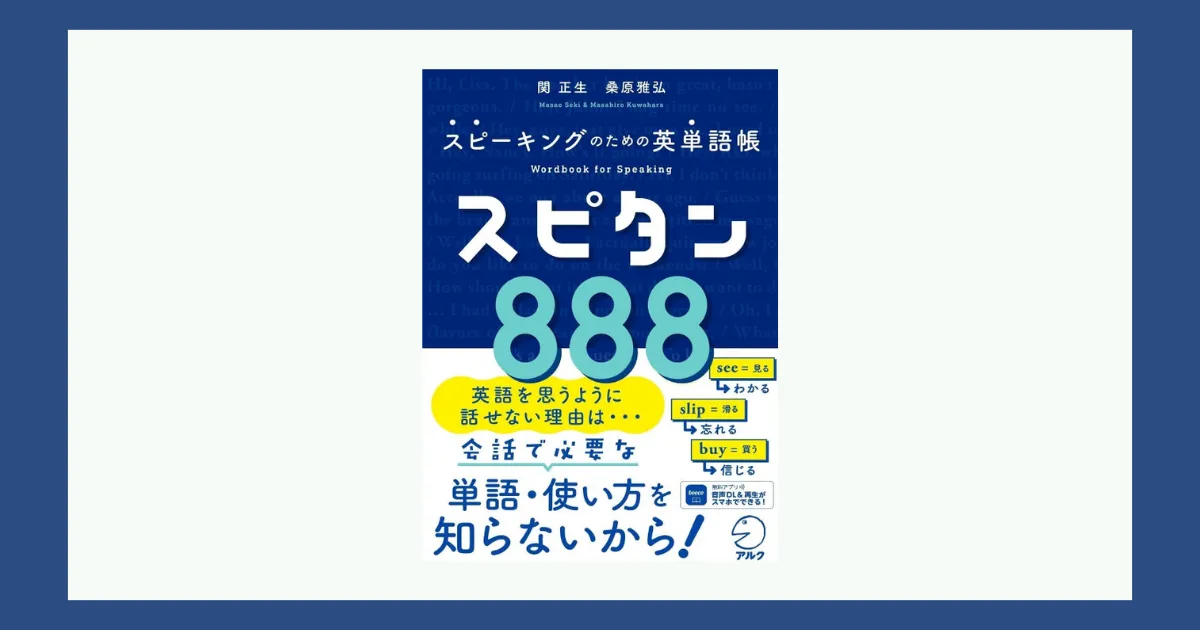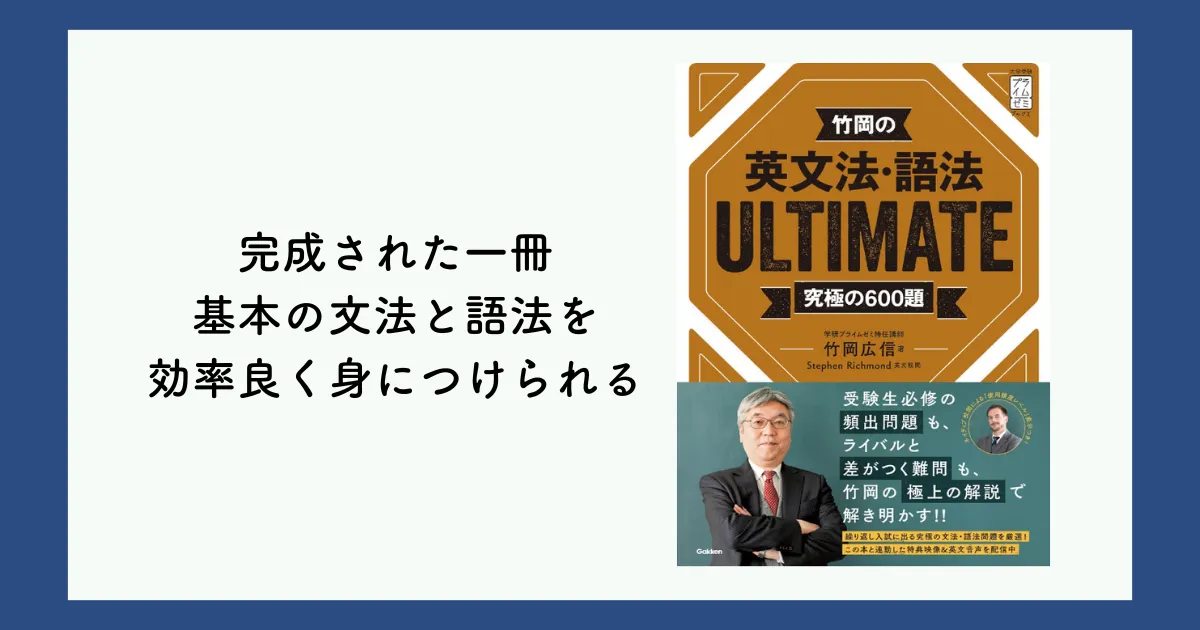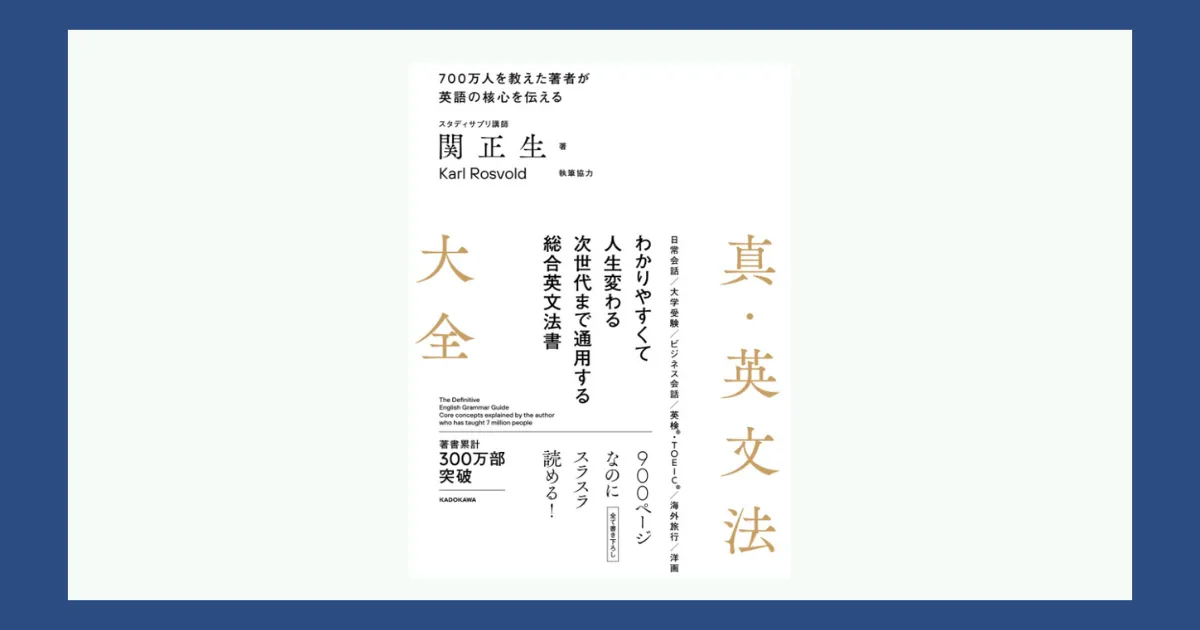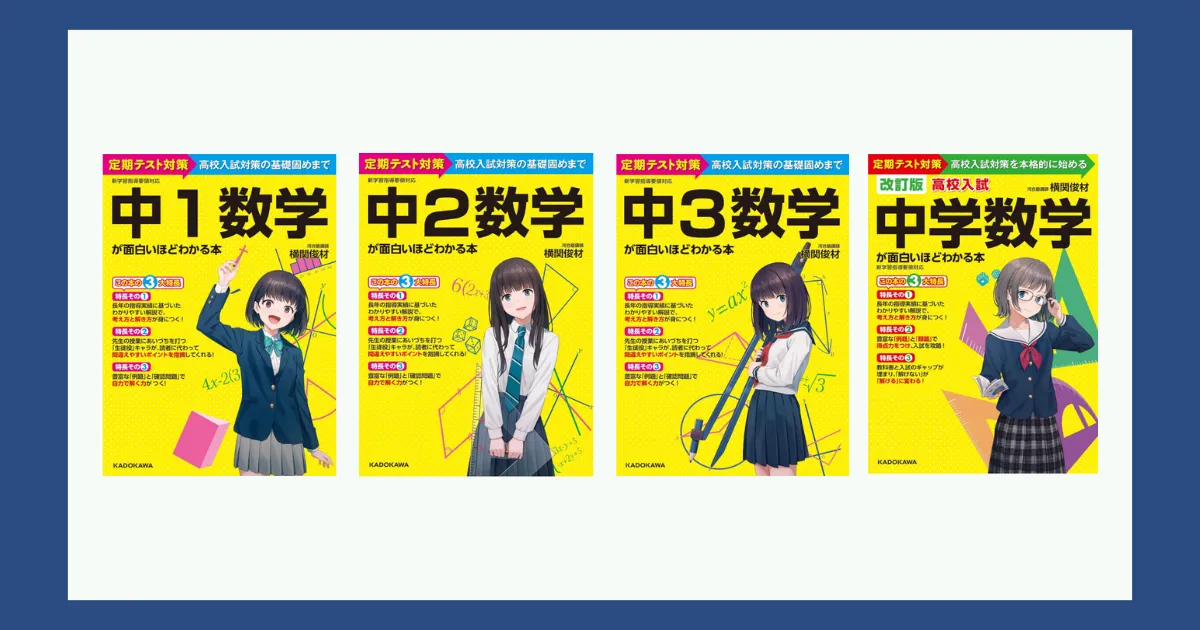| タイトル | 方程式・図形・関数からとらえる数学の基礎 分野別標準問題精講 | |||||||||||
| 出版社 | 旺文社 | |||||||||||
| 出版年 | 2025/9/29 | |||||||||||
| 著者 | 池田 洋介 | |||||||||||
| 目的 | 高校数学の考え方を深める | |||||||||||
| 対象 | 難関大志望の現役生から大人の学び直しまで | |||||||||||
| 分量 | 400ページ | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| AI | 文章読解のサポート | |||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
加筆修正の履歴
2025/11/06 読みにくい箇所を全体的に修正しました。
2025/11/02「入試標準以降を円滑に進めるための基礎力」の冗長的な部分を修正しました。
2025/10/31 本書とのコンセプトの違いを明確にした上で『数学を決める論証力』と『総合的研究 論理学で学ぶ数学』『数学の真髄』に関わる文言を誤解のないように修正・削除を行いました。さらにコンセプトの近い『公式で深める数学IA』を追記しました。
2025/10/26 「理解を深める参考書の筆頭になり得るか」の説明に追記
入試標準以降を円滑に進めるための基礎力
本書はつい先日旺文社から出版された入試数学の基礎的な考え方を学ぶ参考書です。著者の池田先生は高校数学の入門書である『数学入門問題精講』も執筆しています。こちらはここ数年の入門書の中で最も支持されていると言っても過言ではなく、教科書の代替として機能するほど、教科書以上に易しくありながらも応用力を高める大切な考え方に気づかせてくれる良書です。池田先生は現役生が悩みやすいポイントを押さえ、その上で発展的な考え方への道筋を構築する解説が長所にあるように感じます。
そういった長所は本書でも発揮されており、難易度的には入門から大きく離れているように思うかもしれませんが、実はとても近い位置にあります。というのも、数学の問題を解くという操作を今一度改めて構築する内容になっているからです。それは問題を解けるようになるための解法やテクニックではなく、数学の概念や事象、操作といった点を整理し直す原理的な基礎のことです。入試数学は解法暗記で乗り切る人も多いと思いますが、それは入試基礎までなら地で行くことはできても、入試標準以降はそれなりに深い思考力を要求されて詰まる人が少なくありません。「なぜ、そうなるのか」を本当の意味で理解できず、どこか誤魔化しながら解法を丸暗記するだけになってしまうのです。
本書にはそうした問題を解決できる可能性があります。いわゆる横割り本とは少し異なり、解法的な思考から数学的な思考を目覚めさせるような内容です。その方法というのが基本を問い直すこと。これは率直に指導の発想としても素晴らしいと思いました。今までにあるようでなかったコンセプトです。全体的に講義が多いので、大人の学び直しなら読み物として楽しみやすく、数学を単なる問題を解く科目と考えている人ほど有益かもしれません。指導者にもオススメ。あえて近い参考書を挙げるなら、旺文社の『公式で深める数学IA』です。
解説の一例―練習問題102題を通じて学ぶ
本書は全章を通じて「そもそもどういうことなのか?」と根本的な意味を確かめる内容になっています。例えば「3x+5=11」の方程式を解くと、誰もが「x=2」と苦労なく解答を導けると思います。しかし、そもそも方程式を解く作業とはどういうことなのか。これに答えられる人はほとんどいないでしょう。
当たり前のようにしている「方程式を解く」という作業の意味を見直してみましょう。
3x+5=11 ……①
は,「 x についての条件」と見ることができます. 方程式①の「解」とは, この条件が成り立つような x のことであり, 「方程式を解く」とは, その解をすべて求めることです. つまり, 「方程式①を解く」というのは
条件①の真理集合を求めること
なのです.
方程式・図形・関数からとらえる数学の基礎 分野別標準問題精講 P38より引用
本書は予備知識から始まり、第1章「命題と条件」で「集合と論理」を復習しつつ、方程式について捉え直しています。第2章「全称命題と存在命題」と第3章「写像」では論理命題を学び、関数を発展させた写像という概念を用いて数学に現れる多様な事象を統一的に捉えることを目指しています。そして、第4章「ベクトル」では、図形分野における強力な武器となるベクトルについて解説しています。
方程式 ……条件 p
方程式を解く……条件 p の真理集合 P を求める
方程式の解 ……真理集合 P の要素
方程式を解くときは, 同値変形を繰り返しながら, 最初の条件と全く同じ意味を持つ, より簡単な条件に置き換えていきます.
方程式・図形・関数からとらえる数学の基礎 分野別標準問題精講 P38より引用
こうした数学的な考え方の整理は必ずしも必要になるものではありませんが、難関国公立の証明問題で求められる方針の探索や試行錯誤、論理の厳密性、抽象的な問題文の理解では必要になるものです。入試数学の難問が別次元と言われる理由もよくわかります。
「方程式 3x+5=11 を解く」とは, その真理集合
{ x | 3x+5=11} ……②
を求めることです. ところが, この形のままでは集合の具体的な要素はわからないので, それがわかるように同値変形していきます. ここで重要なのが
同値変形は真理集合を変えない
ということです. 3x+5=11 を同値変形して x=2 が得られたのですから,
{ x | 3x+5=11}={x | x=2}={2}
つまり, 方程式①の解は2(のみ)ということがわかるのです.
方程式を解くことは, 「絵画修復」の仕事を連想させます. 最初の条件のままでは, ぼんやりとしていて実体がよく見えない真理集合を, 同値変形というブラシでほこりや汚れを取り除いて, その輪郭がはっきり見えるようにしていく, というイメージですね.
方程式・図形・関数からとらえる数学の基礎 分野別標準問題精講 P39より引用
第4章で一から解説されている「ベクトル」は『入門問題精講(約50ページ)』でも取り扱われているのですが、本書では約160ページにわたって解説されています。『入門問題精講』はベクトルの易しい解説と解法暗記的な基本問題を取り扱っているのに対して、本書では入試標準までの問題を扱いつつ、第1章から第3章で学んだ知識を活用しながらベクトルの概念を解説(再構築)しています。
ちなみにそれは一から理解できると言えばできる解説ですが、本書のコンセプトからして初心者向けというわけではありません。また、練習問題は難しくとも旧帝大志望にとっては標準・定石問題と言えるレベルですが、それ以外にとっては難しく感じられるものもあると思います。ただ、ベクトルは『入門問題精講』などで基本問題だけ解けるようになっても、入試基礎、標準と進むと根本的な理解が足りずに躓きやすいので、全ての問題に取り組まなくとも本書で理解だけ深めるのはありかもしれません。
理解を深める参考書の筆頭になり得るか
本書は難関国公立志望に広く役に立つという意味で『公式で深める数学IA』と並んで、本質的な理解を深める系統の参考書として2025年現在筆頭候補になると思います。本書が「方程式・図形・関数」から再構築するものなら、『公式で深める数学IA』は文字通り「公式」から基礎を再構築しています。コンセプトは異なりますが、他にも同じ旺文社から出版されている『記述式答案の書き方』は数学的な表現を学ぶ過程で、東京出版から出版されている『数学を決める論証力』は記述・証明問題で必要となる論証の考え方を通じて理解が深まるかもしれません。『論理学で学ぶ数学』や『数学の真髄』も理解を深める系統ではあると思うのですが、かなり難しい参考書で一般向けではありません。
本書は『問題精講』シリーズでレイアウトも見やすく、池田先生の解説は現役生には特に受け入れられやすいと思います。AIにもまだまだ代替できない領域です。何より「今までの当たり前を改めて考え直す」というコンセプトが非常に優れています。人間の思考力を向上させる際に、メタ認知を促進させ、客観的に自らの思考を再構築する方針は有力です。例えば「なぜ、私たちは仕事をするのか」「なぜ、私たちは家族や友人を求めるのか」といった根本的な問いは思考を強く刺激します。人間は一つの行動に良くも悪くも傾倒しやすいため、解法暗記なら解法暗記さえやっておけば良いという方針に飛びつく人は多いでしょう。しかし、それが見る見るうちに柔軟性を失わせ、そもそも自分がやっていることを言語化できない、分解できないとなったとき、今までの知識を応用できず、難問に対応できないという結果を招きます。本書のような基本に立ち返らせてくれる参考書の価値というのは想像以上に大きいのです。
他方で本書を難問対策として捉えると、難問の解法と考え方を学べる『真・解法への道』のような直接的な効果はありません。入試標準レベルまでの問題をより安定して解けるようになる効果はありますが、それは実質的な復習と数学的思考が高まった結果に過ぎません(本書にとってはこれが大事)。本書の内容は大学以降の数学でも大切な考え方なので、受験を終えてから取り組むのもありです。競合する参考書がすぐに思い浮かばないという意味では、ひとまず買っておいても損はありません。