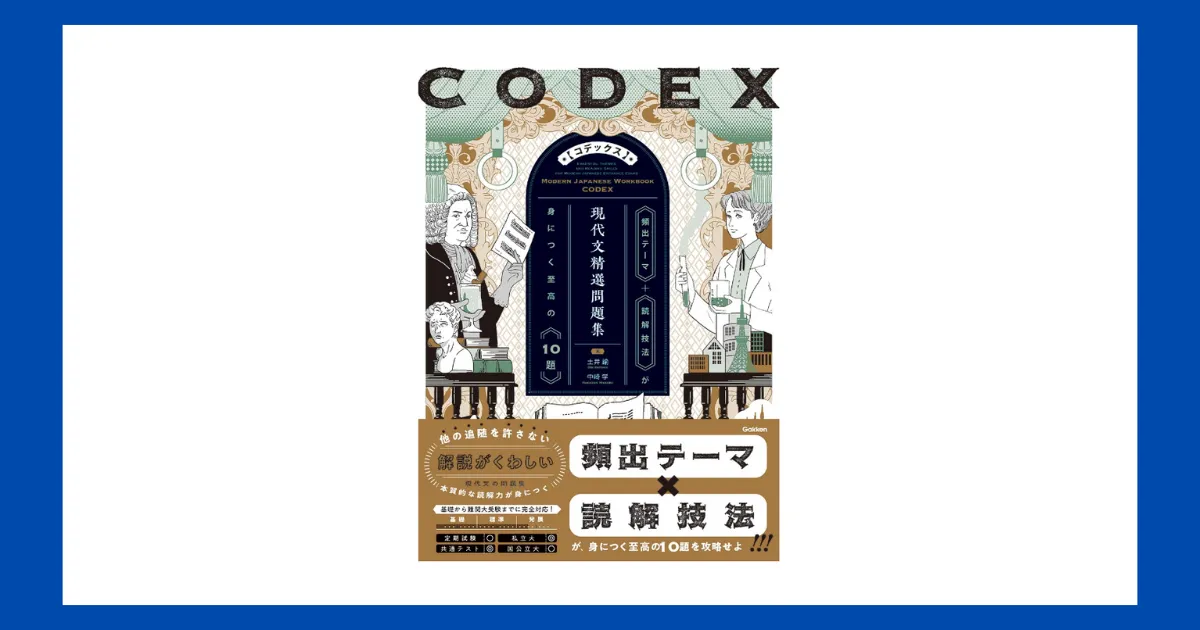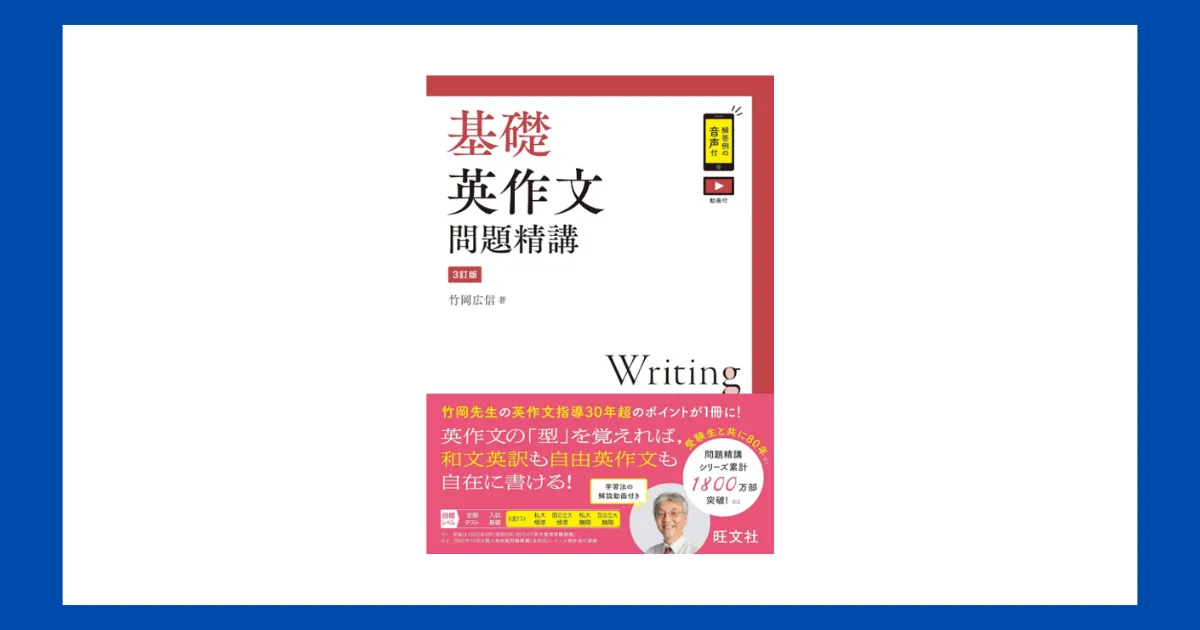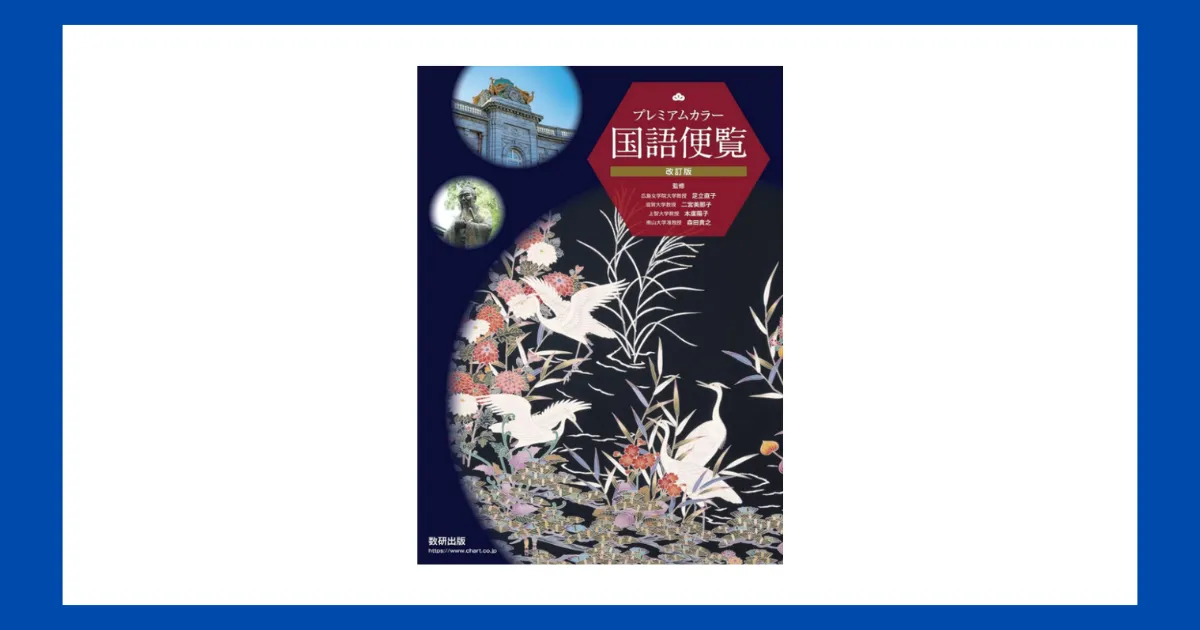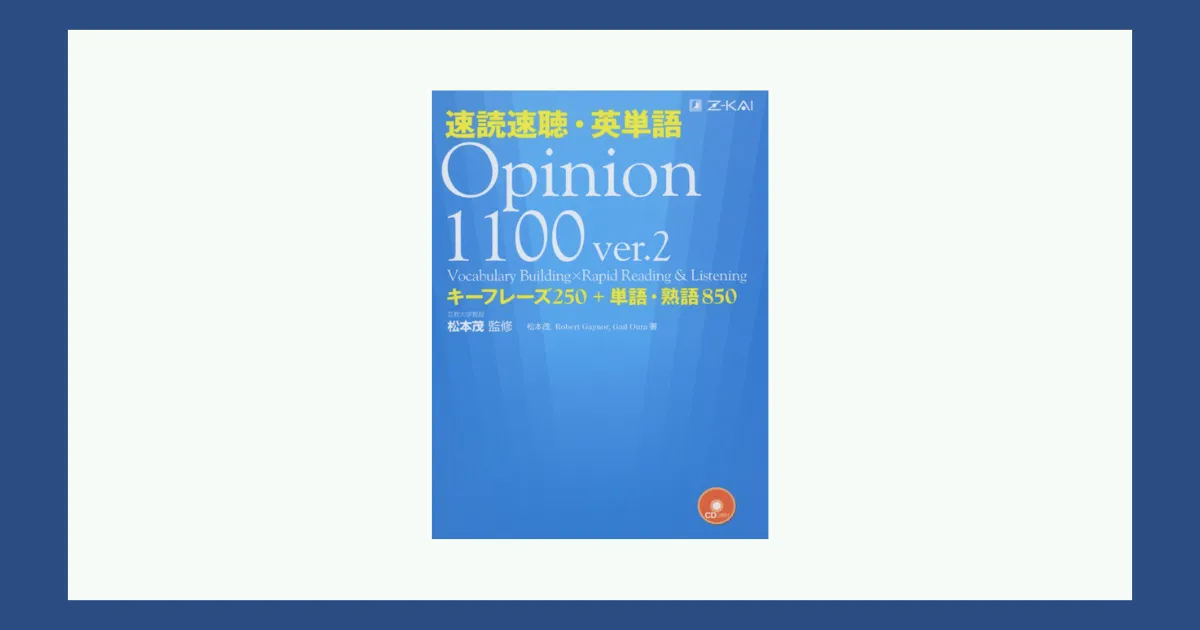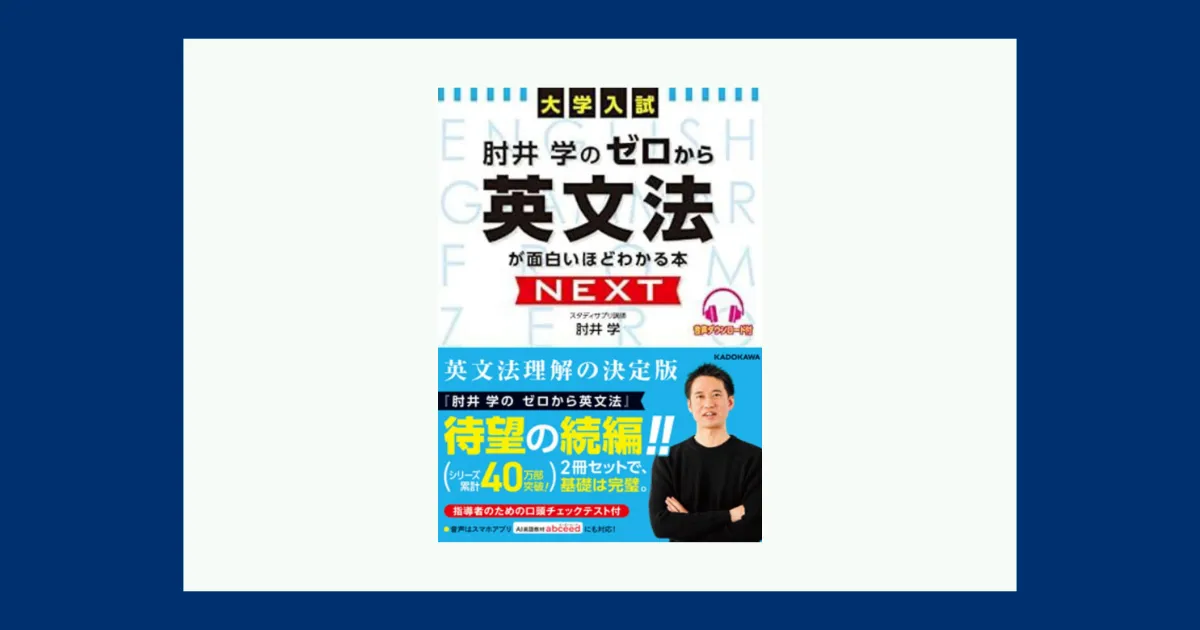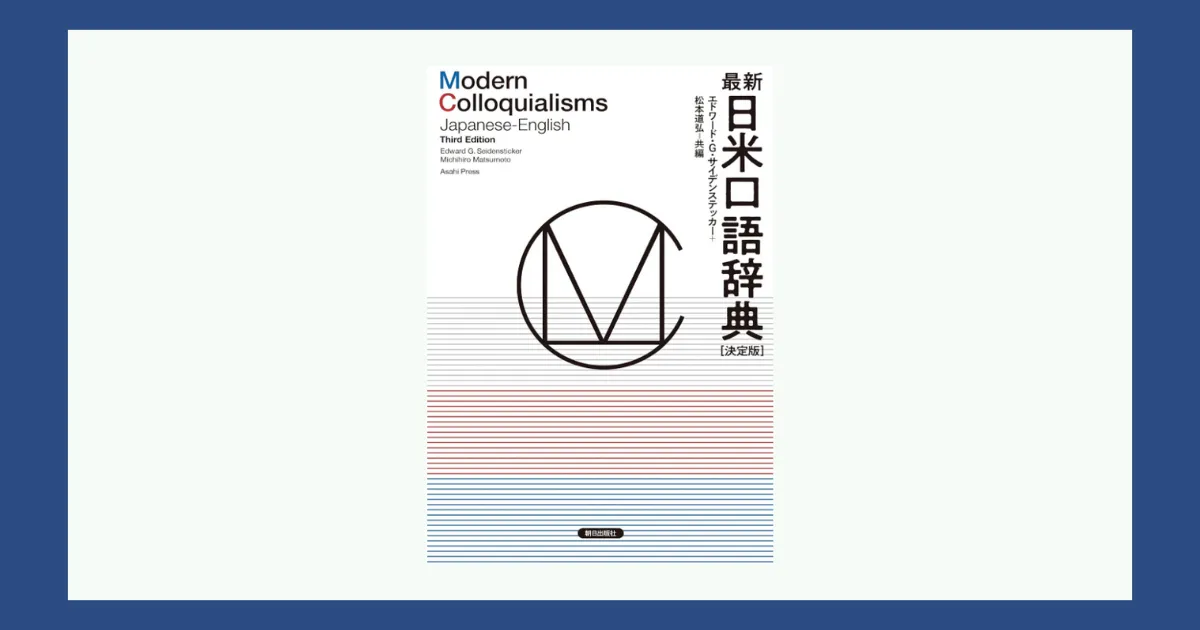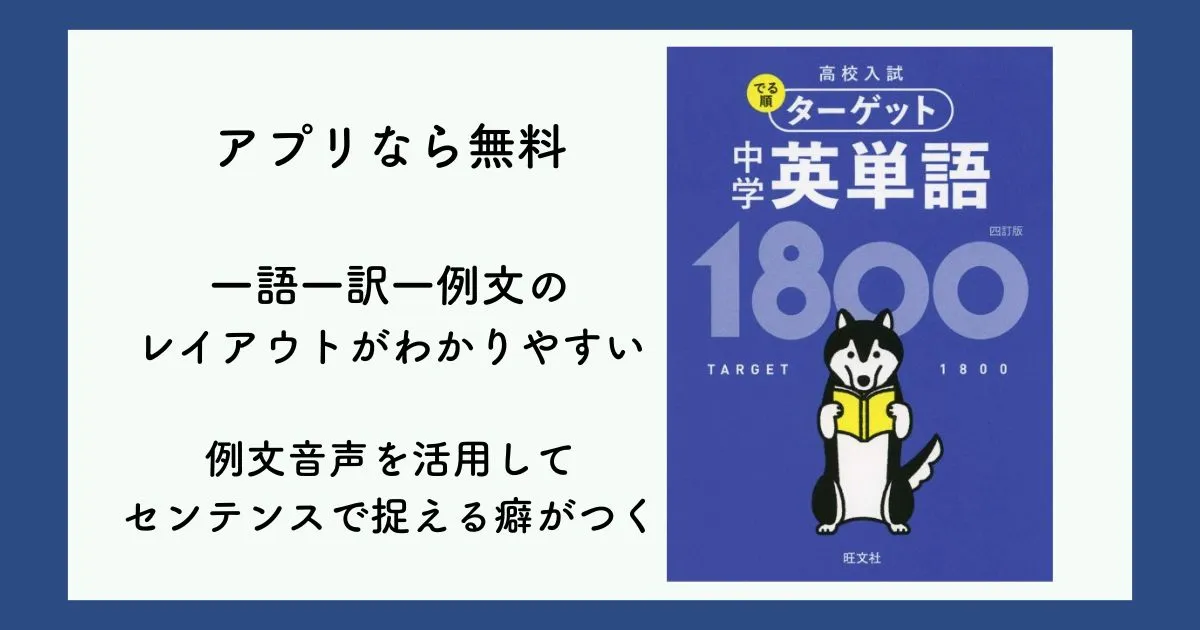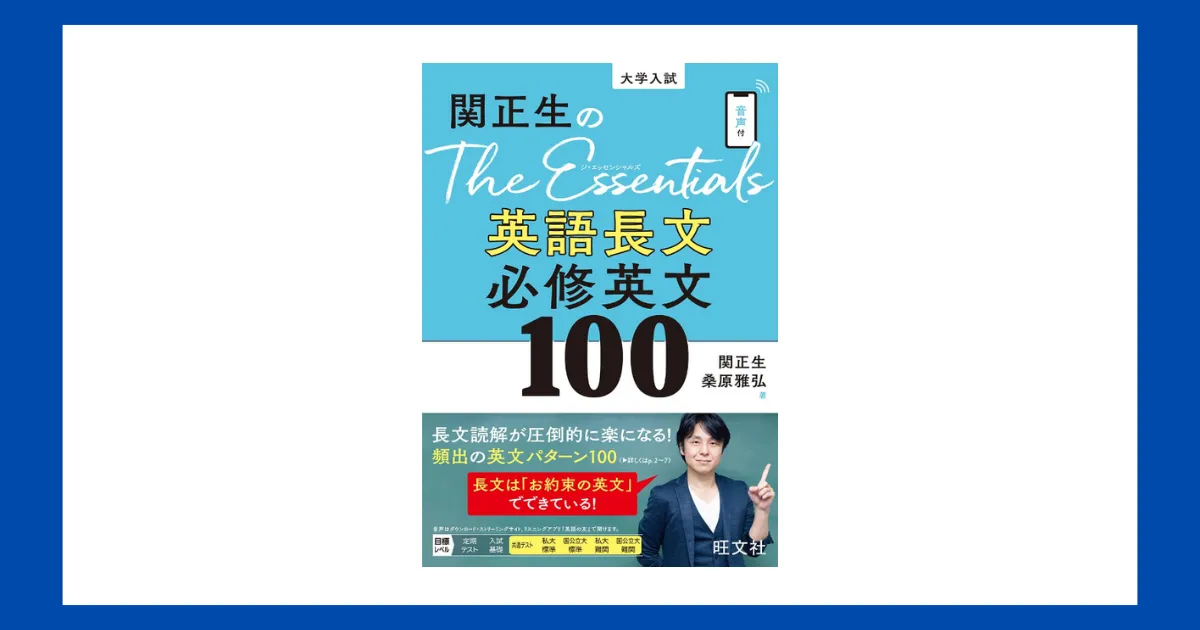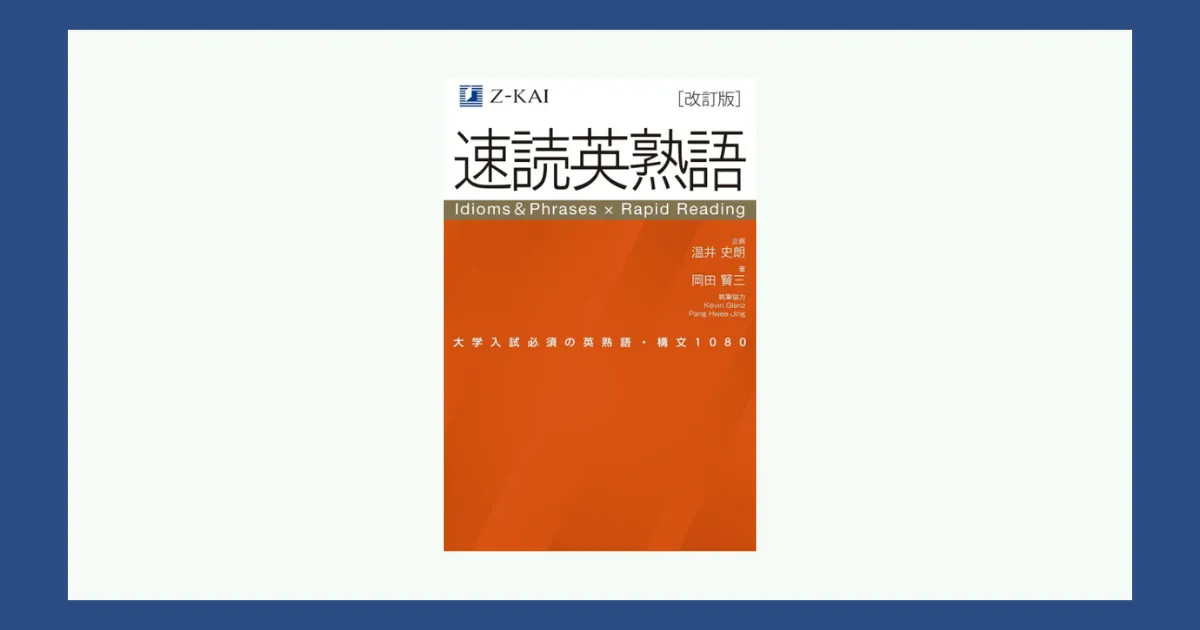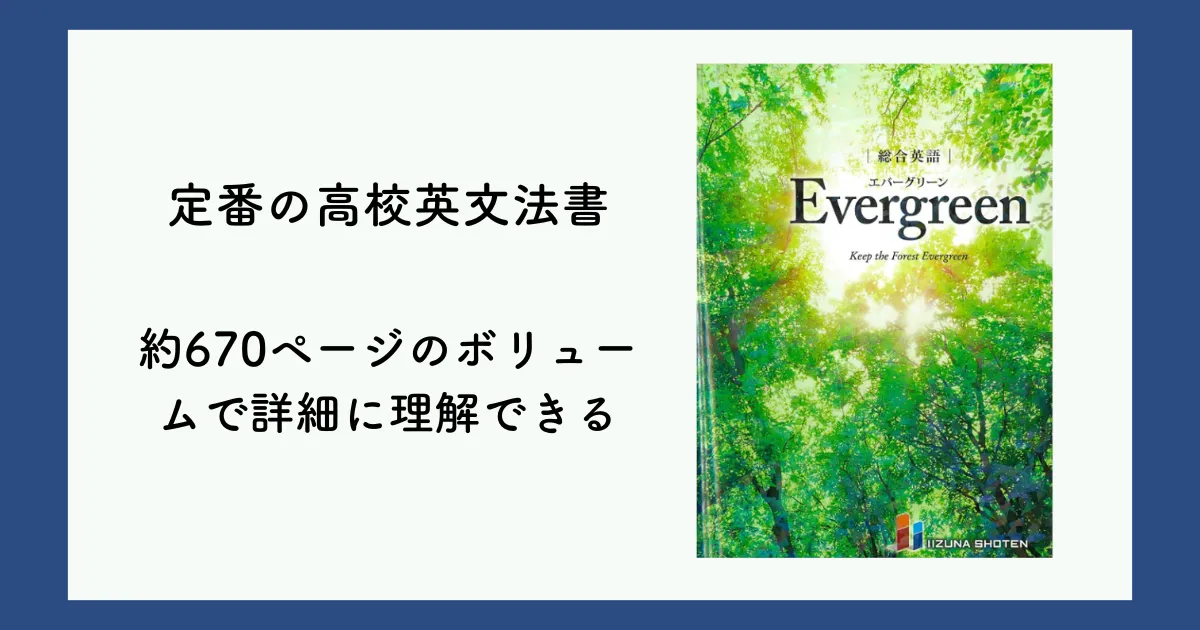| タイトル | CODEX[コデックス] 現代文精選問題集 | |||||||||||
| 出版社 | Gakken | |||||||||||
| 出版年 | 2025/8/7 | |||||||||||
| 著者 | 土井 諭、中崎 学 | |||||||||||
| 目的 | 現代文問題集 | |||||||||||
| 対象 | 現役生から大人まで | |||||||||||
| 分量 | 476ページ | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| AI | 背景知識の拡張 | |||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
加筆修正の履歴
2025/11/06 読みにくい箇所を修正しました。
本質的な読解力が身につく新定番か
本書はつい先日Gakkenから出版されたばかりの現代文の参考書です。装丁を『HISTORIA 世界史探究精選問題集』と『HISTORIA 日本史探究精選問題集』に似せたところからコンセプトには何らかの共通点があることが窺えますが、それは類書を圧倒的に超える解説の量かもしれません。現代文の参考書には本書のような問題集型のものが数多くあり、例えば『入試現代文へのアクセス』は問題と解答で約260ページ、『柳生好之の現代文ポラリス』は約300ページと収録問題数10題なら200~300ページくらいに収められていることが多い印象です。それに対して本書は476ページ。これは充実した解説と入試現代文に必要な知識を総合的に詰め込んだ結果です。
本書はいわゆるテクニック的な読解本ではなく、漢字・語彙・背景知識を前提知識にして読み解く正統派の内容になっています。これが個人的には高く評価するポイントでもあり、やはり現代文は第一に正統派、すなわち真正面から読解を試みることが大切だと思っています。というのも、特に現役生は明らかな語彙力不足、文章を読み慣れていないことによって得点できない場合が多々あるからです。加えて、そうした国語力不足が他科目にも悪影響を及ぼし、勉強しているつもりなのに伸びなくなってしまうわけです。
大学受験の需要は非常に大きいため、そうした国語力不足に陥った人にもわかるような文章で解説してくれる参考書は多々ありますが、それは数理科目ならまだしも、国語の現代文に関しては私たち日本人にとっての母国語であり、ある意味で最も深い思考力を要求しなければならない科目です。漢字・語彙・背景知識を無視したテクニックに走るのではなく、むしろそれらの知識を十分に要求する参考書の方が信頼に足ります。もっとも大学・学部の特徴的な問題や共通テストの得点率を少しでも上げるために最終的にテクニック、特に多読によるメタ的な視点で補完する方針は否定しません。精読を学ぶ意味では、大人の学び直しにも推奨したい一冊です。
本書の構成と解説の一例
本書はレイアウトもよく考えられており、テーマに基づく文章はどれも取っつきやすくて読みやすい。1ページあたりの情報量も抑えめで、全体的に難しく感じさせない配慮を感じます。これなら漢字・語彙を押さえたあとに現代文を丁寧に読み解く方法を学ぶにちょうど良く、高校現代文の基礎に位置づけても良いと思います。これは同種のコンセプトを持つ『現代文と格闘する』と比較すると顕著です。本書の方が全体的に易しい。コンセプトは少し異なりますが、以前に紹介した『現代文の解法 読める! 解ける! ルール36』は本書よりもさらに易しく、教科書レベルの基本です。
みなさん、こんにちは。いよいよ今日から講義が始まります。現代文の文章を読むための「頭の使い方」を一緒に身につけていきましょう。本文解説の「厚さ」に驚くかもしれませんが、現代文の読解を上達させるためには、本文を丁寧に読み、正確に理解する訓練を積み重ねるという地道な学習法以外にはありません。ただやみくもに多くの問題を解くのではなく、厳選された良問を丁寧にじっくり理解していくことが学習の初期段階では不可欠です。
CODEX 現代文精選問題集 P55より引用
本書の何が優れているのかというと、段落ごとに順を追って思考プロセスを丁寧に提示していることです。勉強において思考プロセスの提示は有力。ひとえに頭の良い人の考え方を真似てしまった方が早いからです。真似られないギャップが成長のための課題。そして、その思考プロセスが王道です。これは本書P85より文章の精読のポイントとして「①あくまで本文に書いてあることを忠実に理解すること・②主観的な決めつけや飛ばし読みをしないこと・③自分が理解したことをしっかりと踏まえた上で、先を読み進めていくこと」からもわかります。
一見迂遠(遠回り)に見えても、厳選された良問の本文を、自力で的確に理解できるまで時間をかけて読み込むという作業が、結局は最もスピーディに現代文の底力をつけることにつながるのです。
CODEX 現代文精選問題集 P85より引用
ちなみにこれはシンプルで当たり前の方針ながらも簡単ではありません。というのも、そうした客観的・論理的に読むためには自らの先入観や感情を排し、自分ではない他人の思考を丁寧に追わないといけないからです。この思考作業には感情的にならない理性=相手の言葉の意味や背景を冷静に読み解くことが不可欠なので、自分という思考の枠組みから出られない人はいつまでも出られない、すなわち現代文を本質的に解けない問題があります。簡単に言うと、世間一般では常識的に「悪い」とされるものを「正しい」と論理展開する文章があったらそうした人は誤読するでしょう。これを矯正する作業が現代文をはじめとした勉強なのですが、一筋縄でいかない人はいかないため、上記の方針は当たり前ながらも徹底的にチェックする必要があります。※数学の論証力が高い人が現代文も得意になる理由はここにあります。
| CODEX 現代文精選問題集 | |
| 現代文読解に必須の知識 | 評論読解に必須の用語 読解に効く二字熟語100 読解に効く重要語100 |
| 評論 | 科学論―文章を精読する姿勢を身につける 文化論―具体例から説明の流れをつかむ 言語論―主張と例の関係を読み取る 芸術論―意味のまとまりを把握する 近代論―因果関係を読み取る 歴史論―主張を正確につかむ 現代社会論―比喩表現を理解する |
| 随筆・小説 | 随筆―文学的文章を読む 小説①―心情を把握する 小説②―表現に着目する |
| 読解の技法 | 1~28 読解のために必要な心構えや考え方を解説 |
| 解答の技法 | 1~22 設問の種類ごとの解き方と対策を学べる ・漢字語彙問題 ・選択肢問題 ・抜き出し問題 ・空欄補充問題 ・脱文挿入問題 ・記述問題 ・内容合致問題 |
| その他 | 解説の最後に要約あり |
本書は最初に精読の、その後に設問の講義という構成になっています。現代文の設問ごとの対策を一通り押さえているため、本書で学んだあとに過去問や問題集で足固めするとより良いと思います。それまでただなんとなく読んで解いていた人からすると、本書の影響力は良い意味で大きく、得点のための課題や安定化の見通しが一気に立つでしょう。現代文の読解と言えば『現代文読解力の開発講座』が有名ですが、こちらと比較すると本書の方が整理されていて現役生には取り組みやすいと思います。大人なら古き良き属人的で肉厚な文章を好む人はいるかもしれません。
なお、比喩表現の読解で一番難しいのはここです。比喩表現からどのようなイメージが換気できるかは、読む側の経験や知識などに左右されるからです。とはいえ、入試問題としてはそこまで難解な知識などを下敷きにしたような比喩表現の問題はほとんど出題されません。比喩というのはなんといっても読者のイメージ喚起力に依存した表現技法ですから、書き手も読者の多くに馴染みのあるであろう比喩的な説明を試みるでしょうし、問題作成者も大学受験生であれば十分にイメージを想起することのできるような比喩表現を設問にしようとするからです。
CODEX 現代文精選問題集 P267より抜粋
最難関大まで想定するなら『現代文と格闘する』に繋ぐのもありですが、入試現代文の精読による慣れの方が多くは得点に寄与します。詰まるところ、一文を正確に読み解けない原因の多くは知識(テーマ背景、漢字、語彙、設問理解など)の欠如に依るということです。それを踏まえた上で、もっと抽象的な文章や複雑な構造に耐え得る思考力を手に入れたいときに初めて検討すると良いと思います。難関大向けの問題集としては『現代文標準問題精講』がオススメ。
まずは漢字と語彙、必要ならば中学国文法まで押さえ、その後に本書で入試現代文の重要事項を学び、教科書や問題集を時間無制限で精読すれば、テーマごとの知識と論理への慣れによって自然と完成に近づいていくと思います。テーマごとの知識は他科目でも得られます。必ず精読を学んだあとに多読すること。論理とは何か。論理の感覚が掴めない人は数学に力を入れるのも手ですが、それが難しいならAIとの対話で論理的思考力を向上させるのも良いかもしれません。入試現代文から外れるものの、『読書の教科書 精読のすすめ』も効果があるかもしれません。なお、本書だけでは用語と背景知識は十分と言えないので、『Z会 現代文キーワード読解』や『読解を深める 現代文単語 評論・小説』を追加するのがオススメです。漢字と語彙なら『上級入試漢字・語彙』や『語彙力をつける入試漢字2600』がオススメ。
本書の稀少性と注意点
本書は今後のスタンダードになっていくかもしれません。冒頭で述べた『HISTORIA』のように大学偏差値50~65のボリューム層を的確に捉え、そこに適した解説と見やすいレイアウトで支持を獲得していきそうです。何よりこのAI時代に本書の存在感は大きい。これは単なる内容の評価ではなく、思考の起点としての評価です。重要語句を押さえるところから始まり、段落ごとの意味を明確化、複数段落の整理、構造の考察、そして最後に要約といった順を追った思考プロセスは誰もがその流れに沿えば自然に精読できます。それは今までの参考書にもあったのではないかというと、本書のように思考プロセスを強調した上でここまで充実した解説はほとんどなかったように思います。
ただ、気になる点もあります。本書では問題文を読んだり、選択肢問題を解いたりする際に「予測しながら読むこと」を推奨しているのですが、これはそれまでのアウトプットの量と質が下支えする一種の直感ではあるので、最初から予測を立てることができるのか、立てても良いのかといった疑問はあります。例えば、初対面の人と友人とでは会話の予測の精度には大きな差がありますよね。慣れた上での予測なら時間制限のある試験の中で有効ですが、慣れる前の予測は勝手な解釈を誘発しないか不安です。全体的に真っ当なアドバイスばかりで勉強になりますが、少し混乱させてしまうものもあるかもしれません。
これは本書がそうというわけではありませんが、現代文の参考書では結果論に過ぎない解説や恣意的で応用可能性が低いものが散見されることがあります。ここは現代文参考書の共通の注意点。現代文の基本方針は漢字・語彙・文法、そこから一文ごと、段落ごとの理解に努め、背景知識の不足があれば補っていくことです。参考書の解説から迷いが生じたときには、いつでもその基本に立ち返ること。さらに、個人的には「小論文を書くこと=書き手の立場に立ってみること」と前述した「大人たちへの理解=大人の視座の獲得」を加えた方針を現代文攻略の三本柱として考えています。