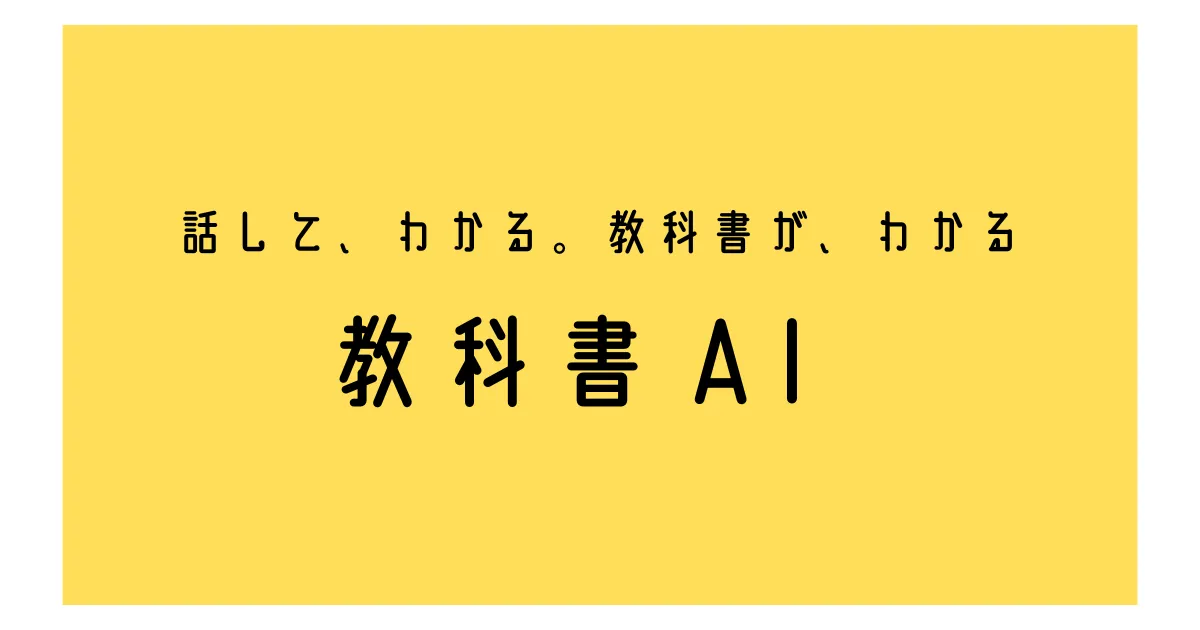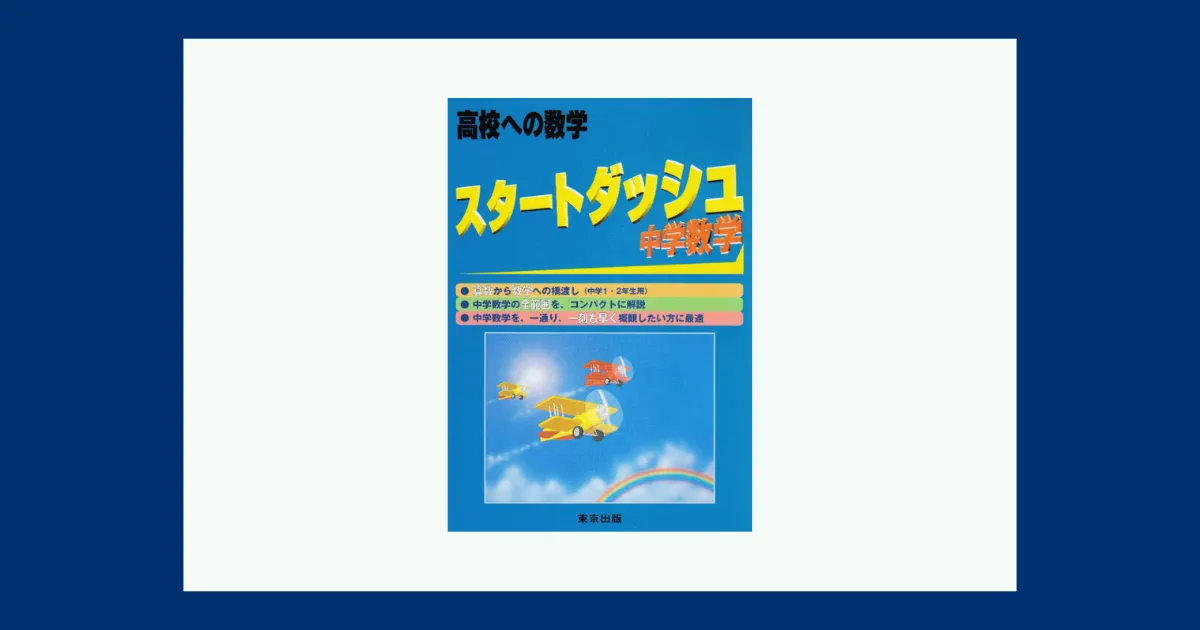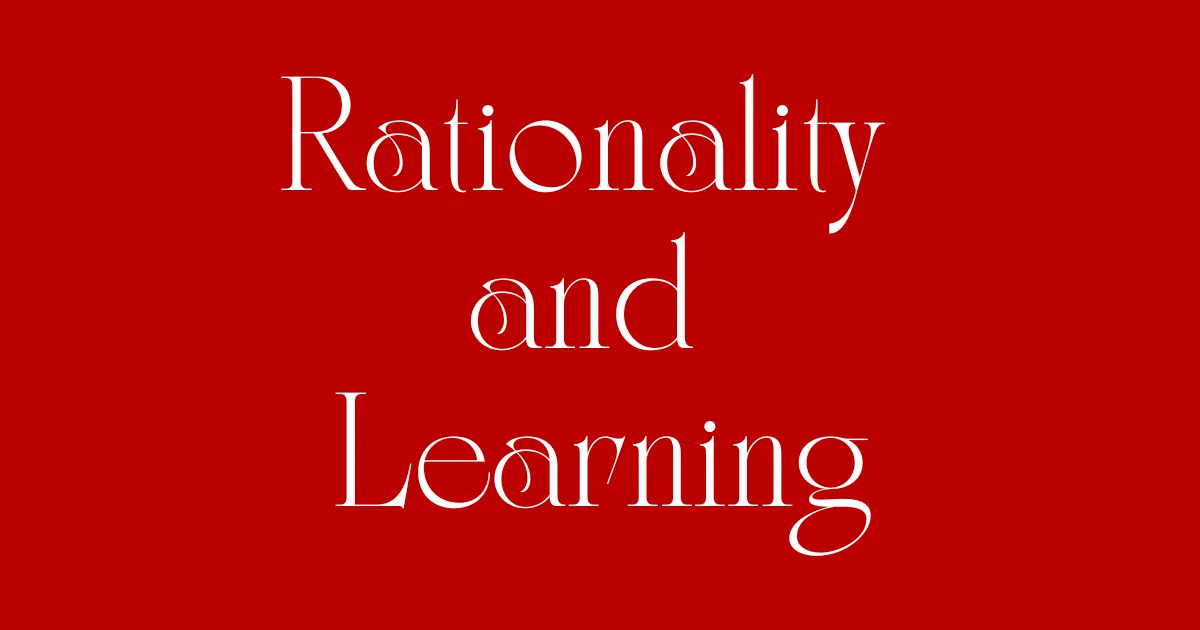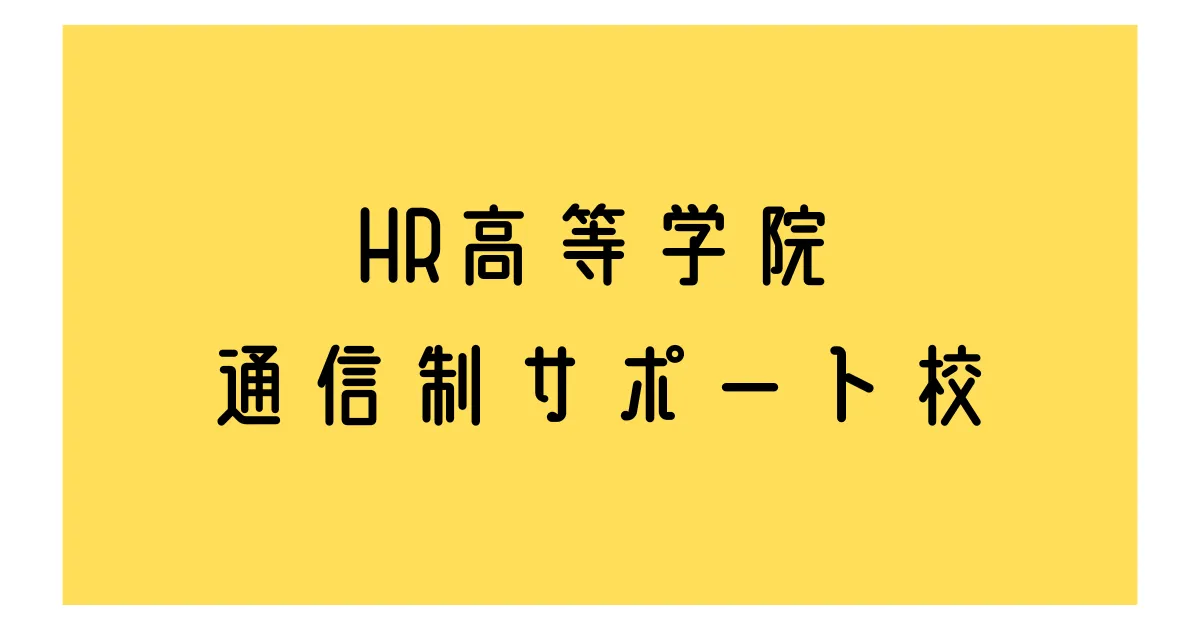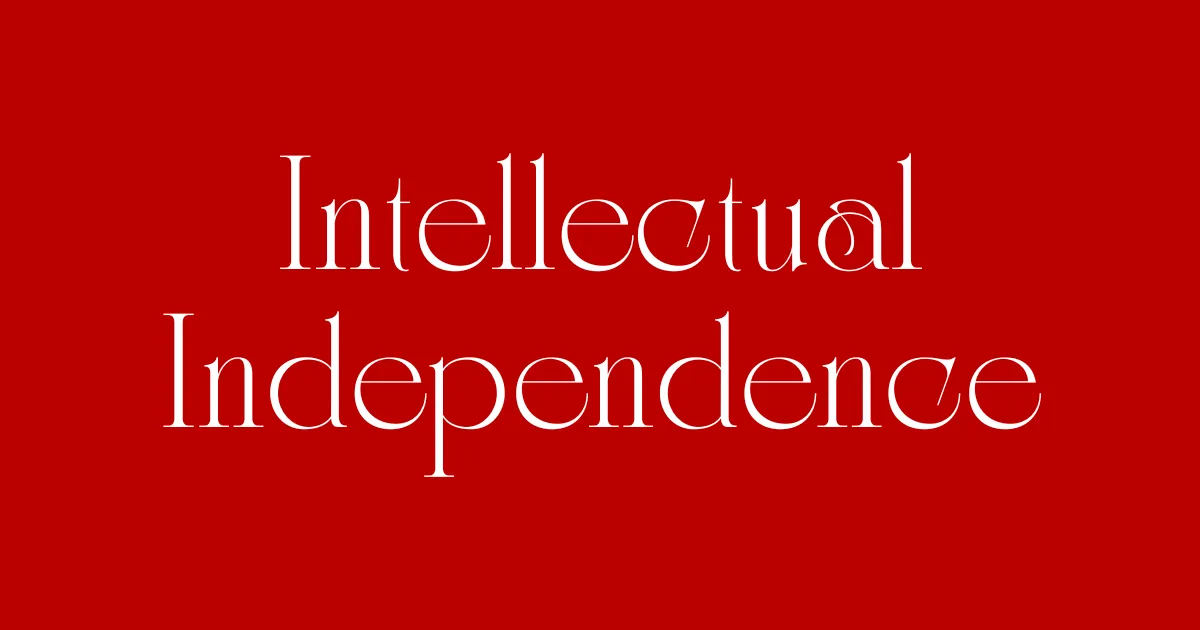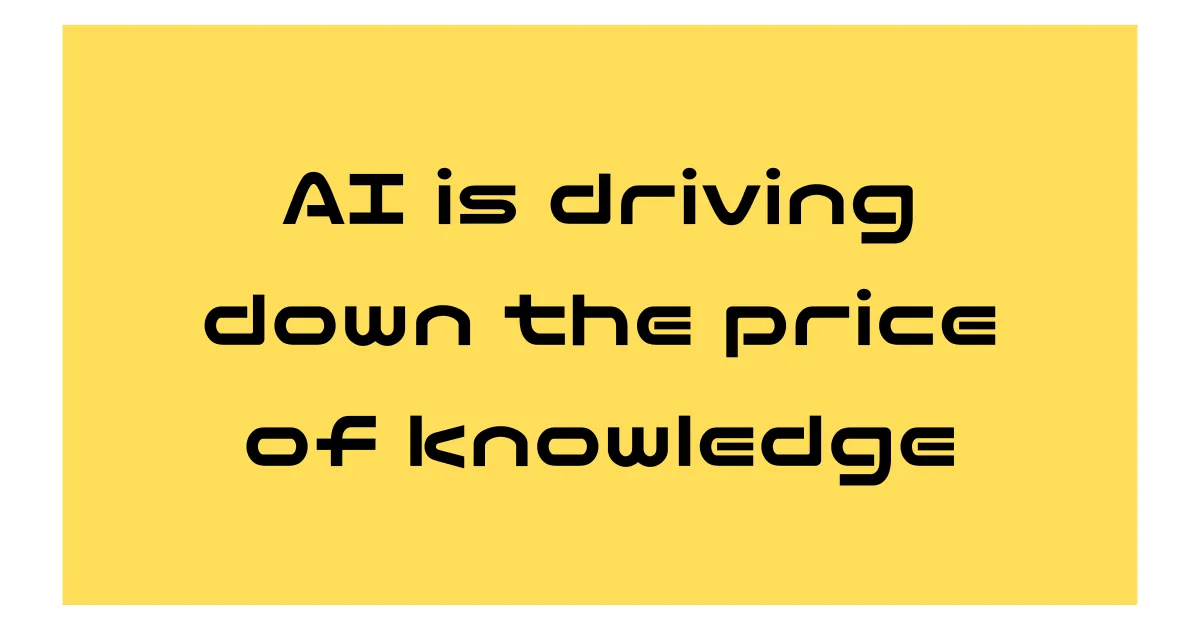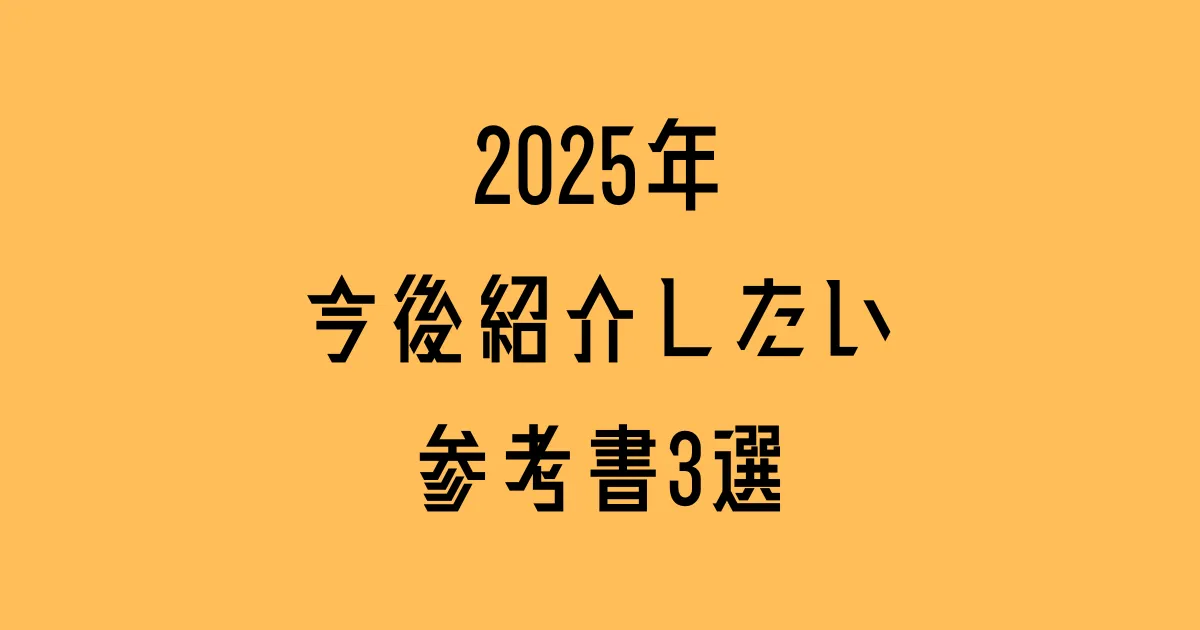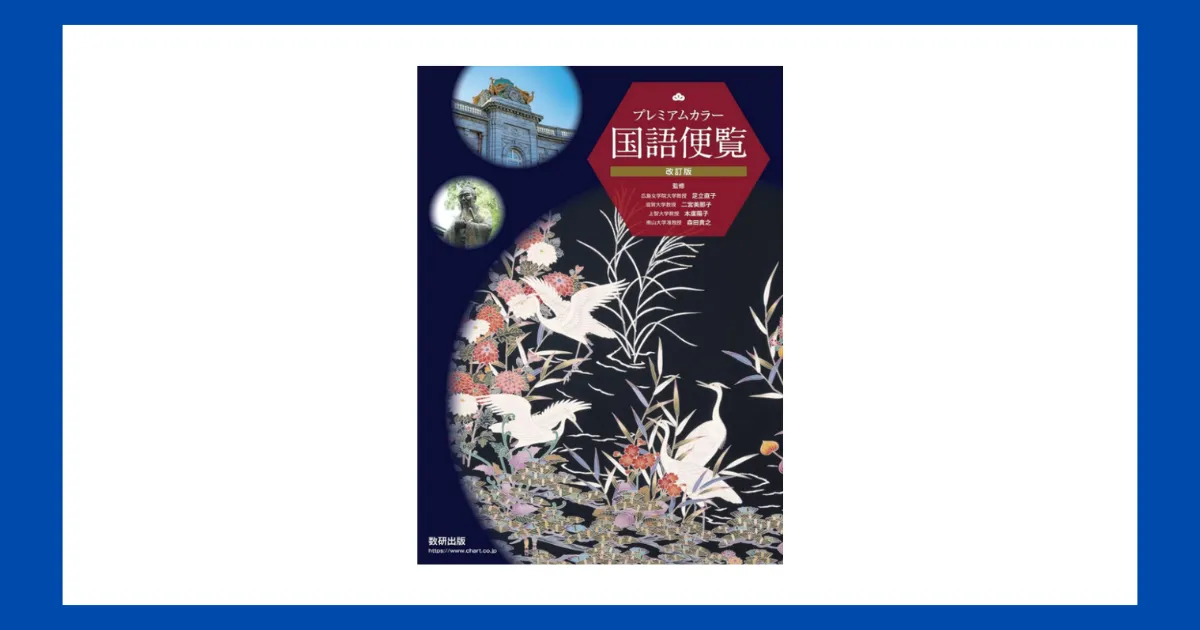| タイトル | 教科書AIワカル | |||||||||||
| 出版社 | 東京書籍 | |||||||||||
| 出版年 | 令和7年度版の教科書から対応 | |||||||||||
AIと共に学習する時代
このニュースは当サイトでも取り上げるべきだろうと考え、普段とは違った趣ながら書き留めたいと思います。単刀直入に一体どんなニュースなのか?というと、教科書で有名な東京書籍から教科書準拠の生成AIアプリが登場したというニュースです。一般的に流通する生成AIとは異なり、教科書準拠になっているので教科書を読みながら抱いた疑問点を即座に解決したり、問題作成したりできるようになっています。隣に専用の家庭教師をつけながら勉強できるというわけです。
今まで教科書の疑問点を解決するには先生や親に質問したり、友人に教えてもらったり、自分で調べたりする必要がありましたが、正直どれも子供にとっては手間がかかりました。ただでさえつまらない勉強のために、遊びの時間を削ってまでできる子はそう多くなかったでしょう。加えて、質問したり、教えてもらってもすぐに理解できるとは限らず、また新たな疑問点が出てきたときには面倒になって投げ出してしまうのも容易に想像できます。そうした中で昨今の生成AIは無限に対話しながら理解を深められるということで、特に教育関連事業への影響は大きなものとなっていました。
いずれこうしたサービスが出てくることは予想していましたが、いざ教科書で有名な出版社から出てくると勉強の在り方がはっきりと変わっていくことを強く実感します。2025年秋から有料版がリリースされますから、現時点で実際にどれほどの利用者数になるのか、サービスの質はどうなのかはわかりませんが、当然、東京書籍以外の出版社からも類似サービスは提供されるでしょう。日本全国の親子にとっては喜ばしいニュースと思います。しかし、AIを上手に活用できるかどうかによって理解度に差が出る時代とも言えるわけですから、果たして全体の底上げになるのか、二極化が進むだけなのか。この辺は注視していく必要があります。
AI時代に必要な能力と勉強
これについては様々な議論がありますが、勉強に関して言うと「言語化能力(≒コミュニケーション能力)」は以前よりも遥かに重視されてきていると思います。現状、勉強におけるAIサポートは対話に集約されますから、自分の疑問点を言葉にする力とAIの答えを理解する力、理解を深めるポイントの発見と抽出など言語化能力、広く言うと論理的なコミュニケーション能力が成長に大きく影響します。当サイト的には「国語力」と言っても良いですね。教科書を理解するための国語力から、AIサポートを最大化するための国語力にまでなりつつあります。
ただ、AIとの対話の質は知識に依存します。その知識をゼロから獲得することにAIはまだ向いていないと思っています。やはり学校の授業や参考書のように正確性が担保され、ある程度体系的に理解した上でAIサポートを活用しなければ、本当に自分にとって意味のある質問ができないからです。例えば、英文法を全く知らない人がAIに一から教えてもらうとして、どれほど時間がかかるか。それなら大雑把でも良いので下地をつくり、文法用語で会話できるくらいになってほしいのです。ゼロからコアの部分を手早く押さえられる従来の勉強の必要性は感じています。※AIがもはやそうした参考書(体系的な理解)を即座に作成でき、人間が参考書を買って読むよりも手間がかからないなら話は変わります。
また、論理的なコミュニケーション能力には「数学」の存在感も大きい。数学は実用性の観点から軽視されることもありますが、単に数字に強くなるだけでなく、あれほど論理性と抽象性をダイレクトに学べる科目はありません。極端に言えば、国語しか勉強していない人は冗長的な文章をひたすらに書くだけで一切の整理が施されないのですが、数学を学ぶと要約や省略を適切に行えるようになります。記号論理学の前身として数学を捉えると言っても良い。日本語の文章はハイコンテクストであることも手伝って論理が捉えにくい面があり、国語の中では比較的論理性を学びやすい評論(論説)にしても数学には遠く及ばないと思います。論理を捉えられないと、正しく次に進めません。AI時代に必要な能力の養成には「国語」と「数学」といった基礎科目の重要性は変わらないのではないかと思います。当サイトと絡めれば学び直すことに遅すぎることはなく、現代をより良く生きる上で勉強は欠かせないなと改めて感じています。
学習塾や予備校に価値はあるのか
今の時代に学習塾や予備校は本当に必要なのか。学習塾や予備校に対する見方は大きく変わりつつあります。というのも、例えば受験勉強のコアの部分であれば教科書や参考書によって足りますし、理解の難しい部分は全てAIによるサポートで十分だからです。自立的な勉強と目標達成は、全ての親が理想とする子の姿でもあるでしょう。学習塾や予備校は受験以降の人生をサポートしてくれません。
つまり、わかりやすく教えてもらう価値は著しく低下している状況なのです。もはや現代ではかつての昔気質な先生、必勝のハチマキをして生徒を熱く鼓舞するような先生の方が価値は上がっている気さえします。パワハラ然り、些細な注意であっても何だか重くなってしまった現代において、他人に上手に働きかけられる人は稀少になりつつあるからです。生徒と信頼関係を築きながら勉強の重要性を説き、受験を通じて思考力の成長と自己管理を促していく。社会で必要とされる自立的な人間になれるようなサービスを展開する方がきっと現代には合っています。東大や医学部に行く価値は逓減しにくいとしても、それ以外の大学を目指す人にとって受験勉強にだけ振り切るのはリスクになっているかもしれません。
優れた参考書が誰でも気軽に購入できる時代からそうですが、AIの登場によって個人の指導の枠組みに生徒を押し込むリスクはよりいっそう認識しなければならなくなりました。優れた人やモノを知った時点で、自分自身は中継ぎとして振る舞う方がより良くなってきています。当サイトとしては「参考書+AI」をもっと意識しながら、実用性とも両立し、しばらくは高校課程までを効率良く学習する方法を確立したいと思っています。