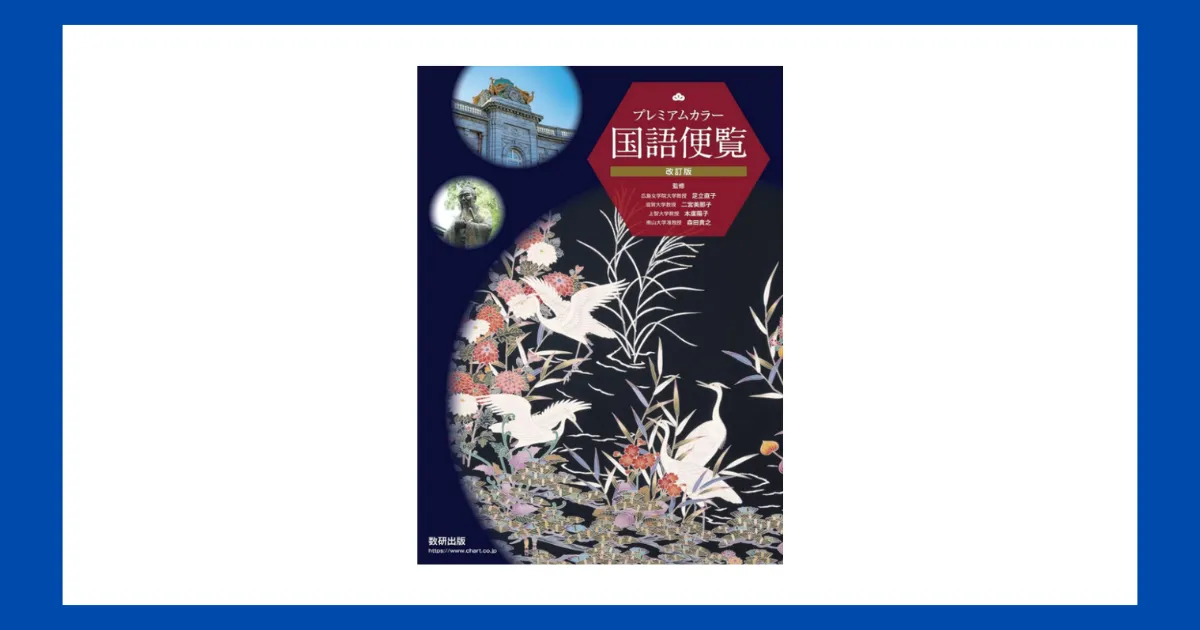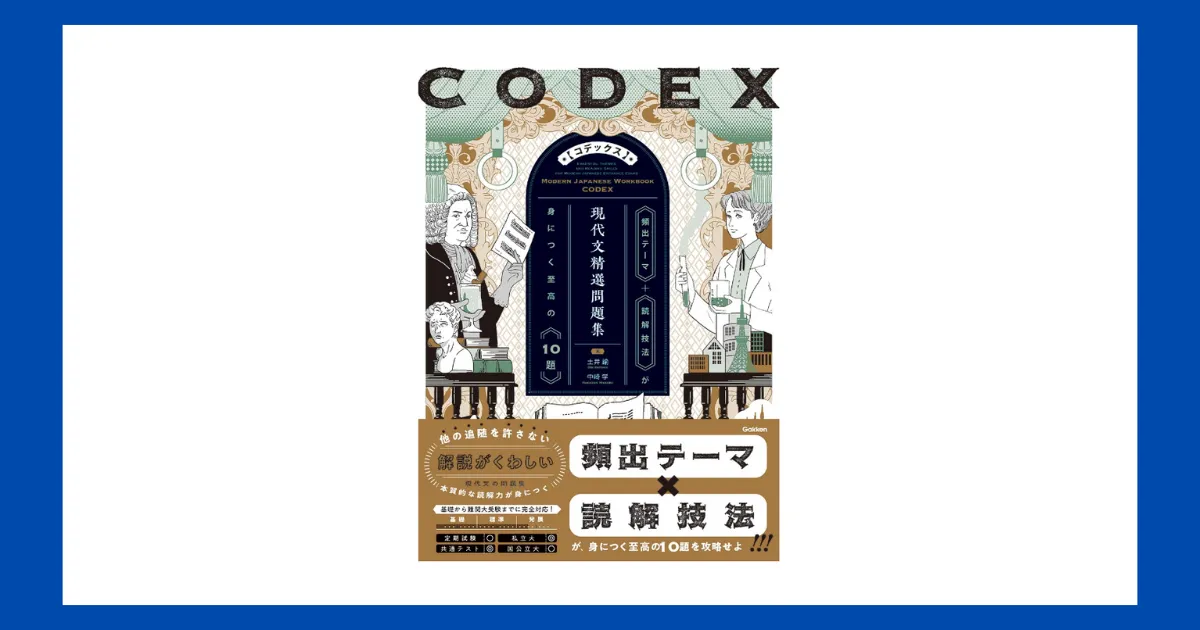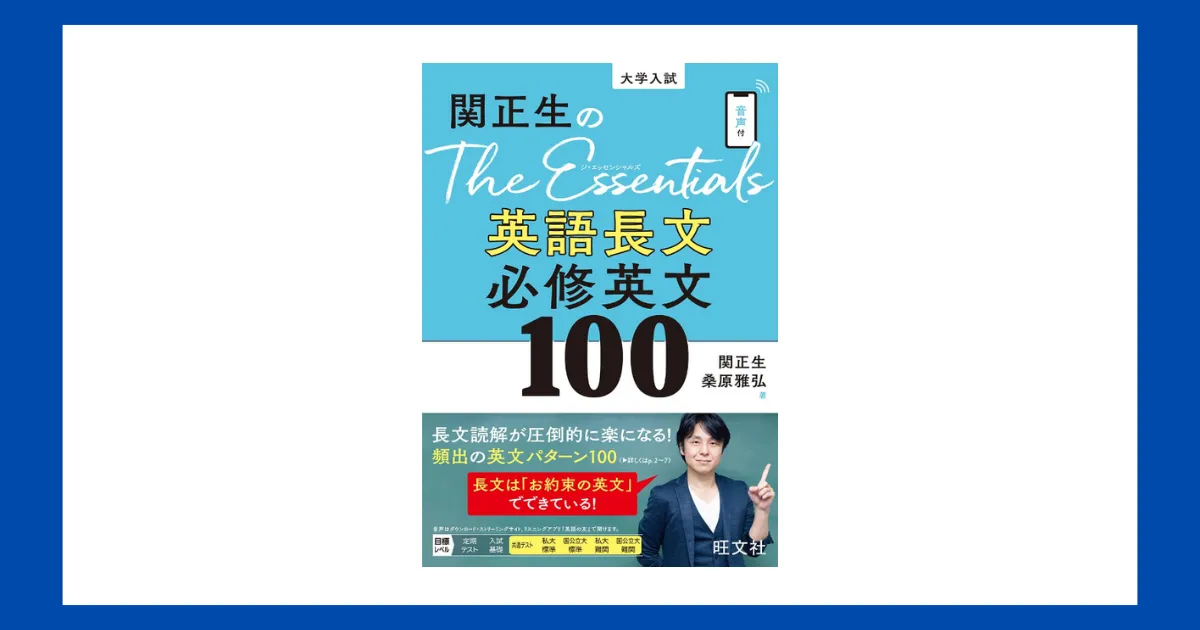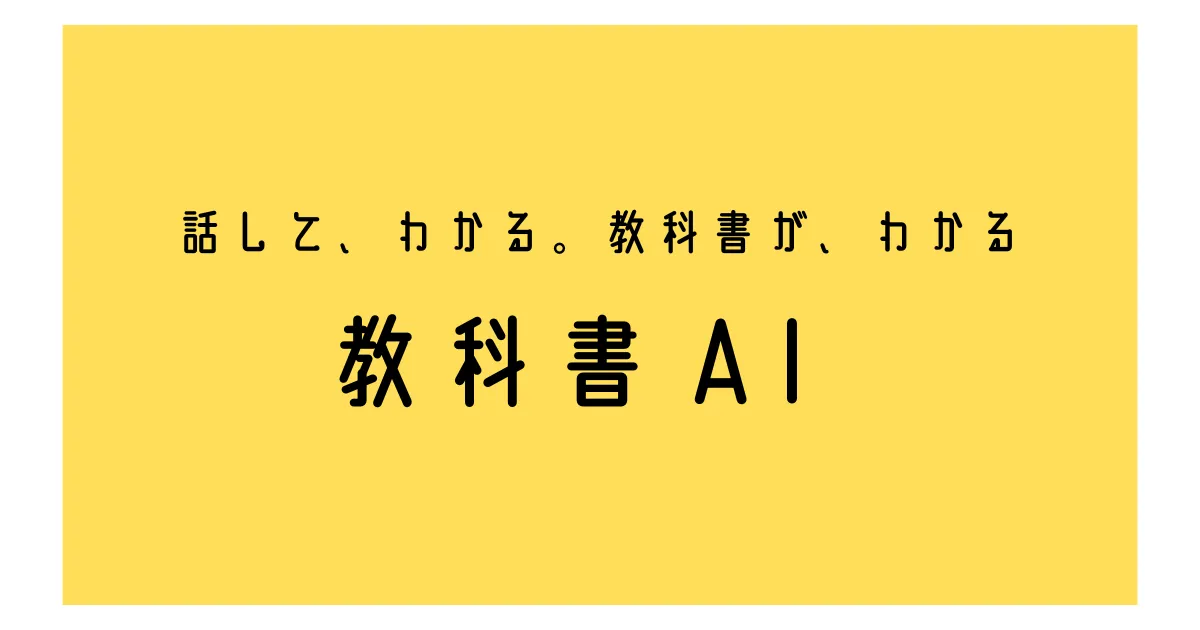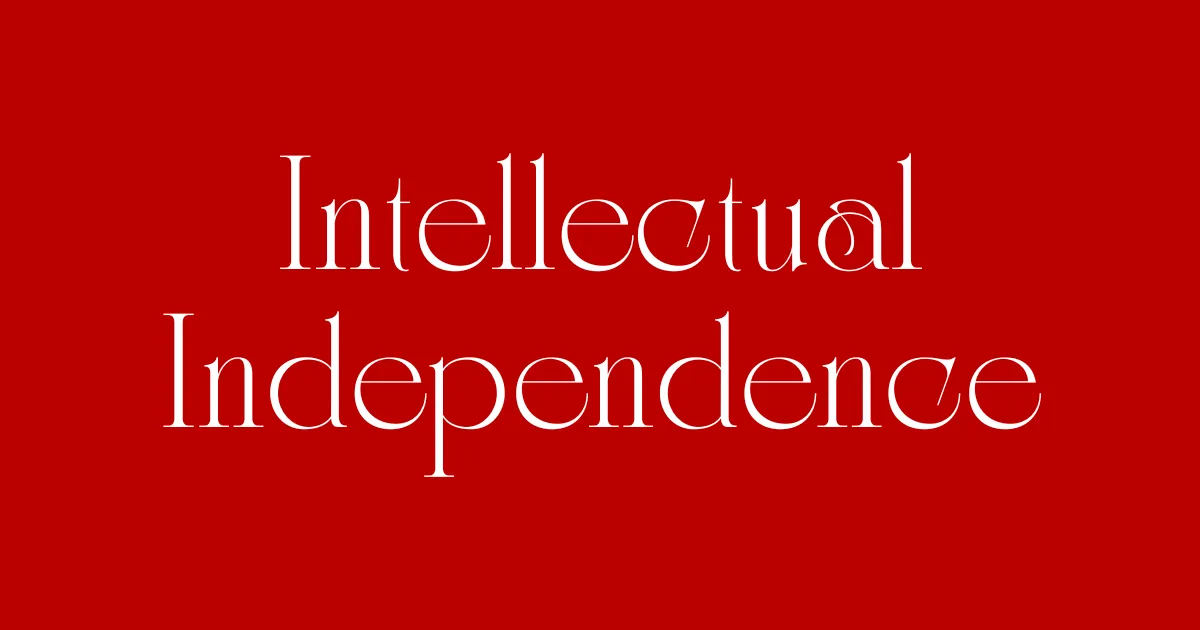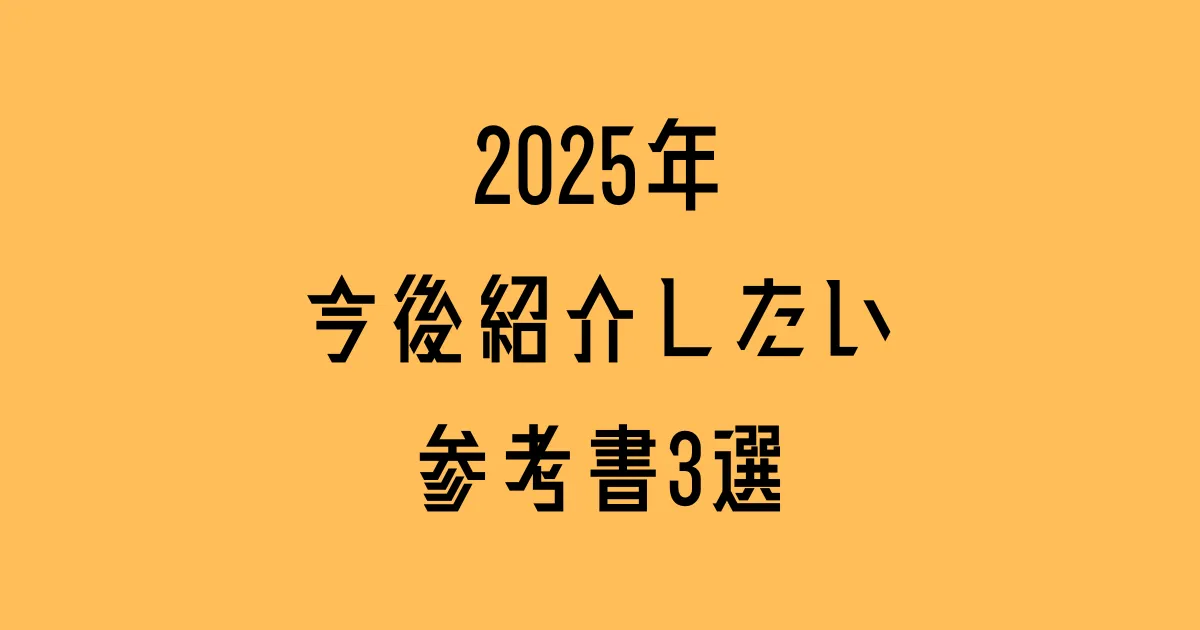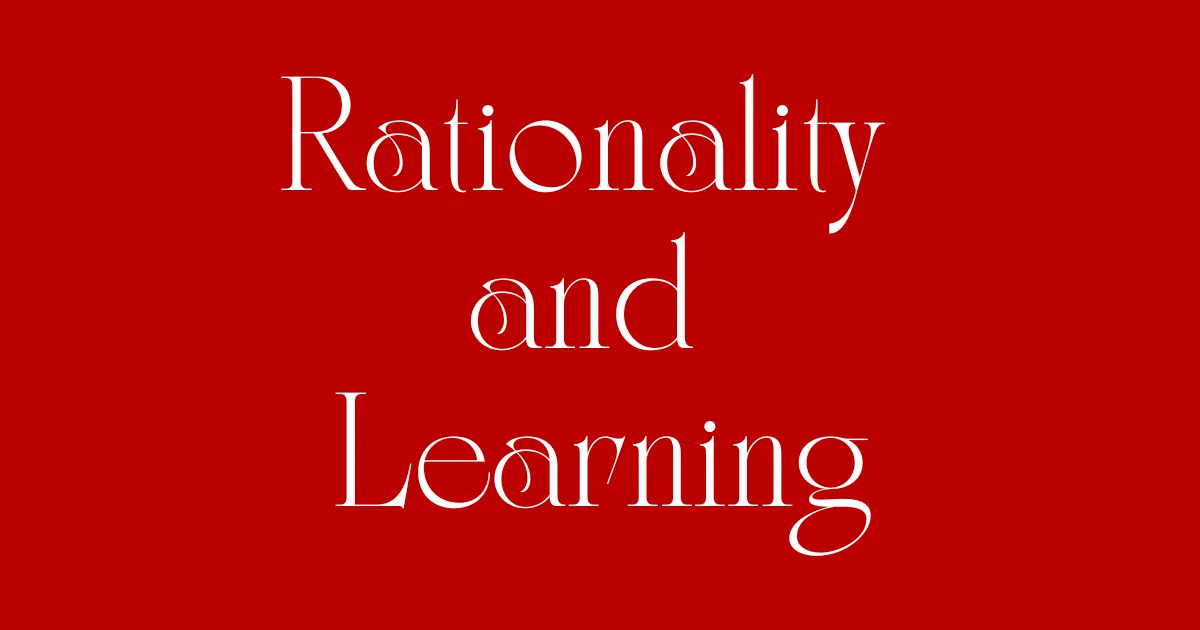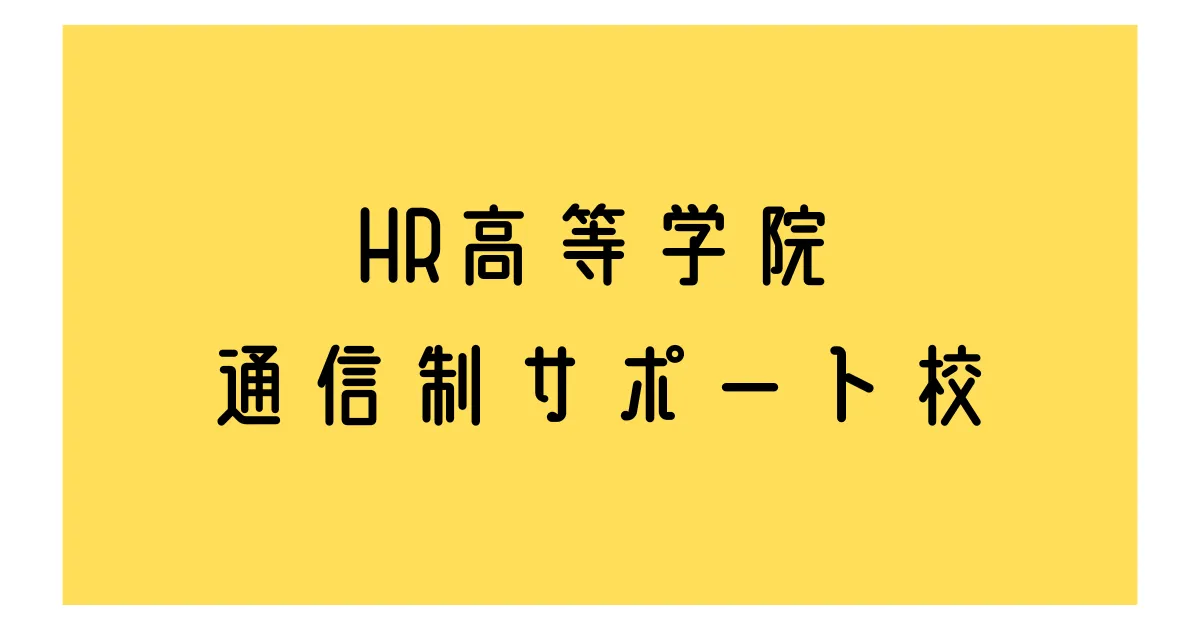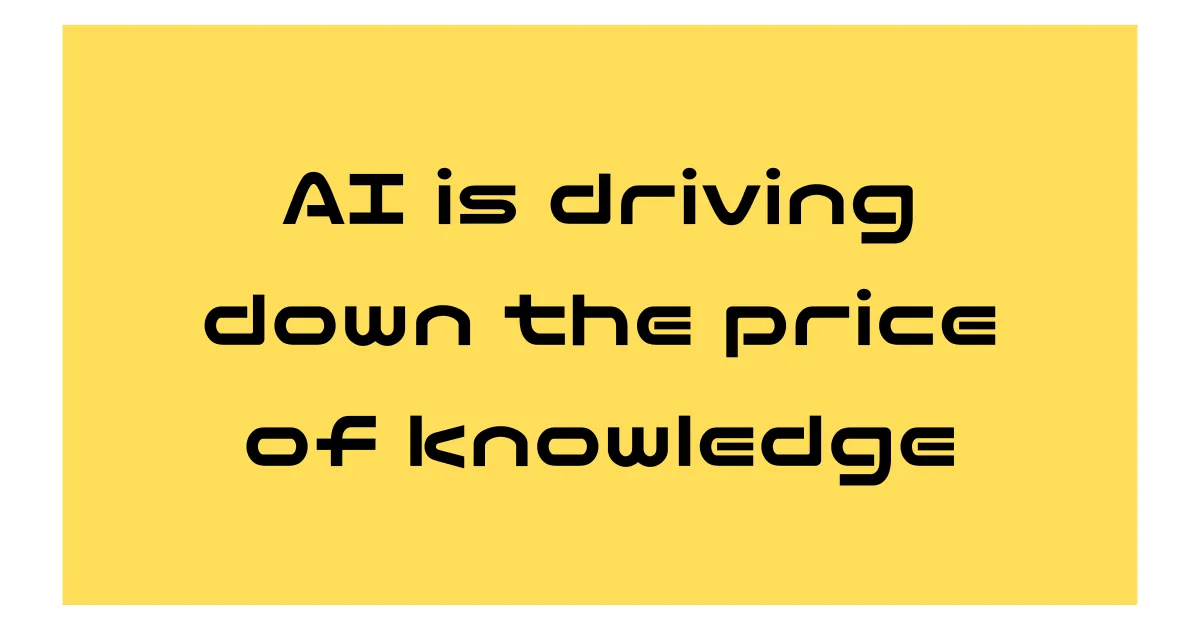| タイトル | 改訂版 プレミアムカラー国語便覧 | |||||||||||
| 出版社 | 数研出版 | |||||||||||
| 出版年 | 2024/2/13 | |||||||||||
| 著者 | 足立 直子、二宮 美那子、本廣 陽子、森田貴之 | |||||||||||
| 目的 | 言語文化を深く知る | |||||||||||
| 対象 | 現役生から大人の学び直しまで | |||||||||||
| 分量 | 520ページ | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| AI | 気になる知識は拡張して興味関心を高める | |||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
加筆修正の履歴
2025/11/04 読みにくい箇所の修正を行いました。
言語文化に関わる資料を多数掲載
本書は2024年に数研出版から出版された国語便覧です。国語便覧とは何か。簡単に言うと、教科書の補助教材として言語文化に関わる資料や情報を集めた事典と思って差し支えありません。歴史で言うと『詳説世界史図録』をイメージするとわかりやすい。収録内容については後述しますが、率直に現役生から大人の学び直しにおいても非常にオススメの一冊です。このボリュームで990円は考えられません。
本書には現代文・古文・漢文の文学史から資料、作品、作者の情報が多数収録されているため、現役生には今までなら『読んで見て聞いて覚える 古文攻略マストアイテム76』のような古典常識を押さえる参考書を推奨していたのも本書だけで十分になりました。漢文においても同様。対義語や類義語、同音異義語、同訓異義語、四字熟語・三字熟語、難読語、ことわざ・慣用句、古典文法、漢文句法、要約の仕方なども収録していて手厚い。他方で約220語の評論キーワードやテーマに関する情報もそれなりにまとめられていますが、『Z会 現代文キーワード読解』などと比較すると一つのキーワードに対する解説が弱いので完全に代替できるほどではありません。ただ、現代文のキーワードや背景知識は他科目の知識が活用できる上に、その都度AIなどで補完する方針でも問題は小さいかもしれません。
大人の学び直しでは「日本文学」に興味のある人なら必携の一冊になると思います。古典文学では主要な作品は見開き1ページで紹介され、作者、成立、内容、評価がわかりやすく解説されています。現代文の章では明治、大正、昭和、平成、令和と時代ごとの文学の流れがわかるようになっているなど言葉で説明し尽くせないほどの情報量です。明治から昭和中期までは文学がエンタメの中心と言っても過言ではない時代ですから、今なお有名な文豪たちの資料は読み応えがあります。他にも「文学散歩」として文学作品にゆかりのある地が紹介されていたり、昔と今の比較資料が掲載されていたりします。そして、そういった情報を淡々と紹介しているのではなく、例えば「太宰治」なら「道化の文学者」から始まり、「県内屈指の大地主、退廃的な日々、実生活の破綻と創作開始」と生誕から作品発表、場合によっては没後の評価まで読ませる文章になっている点も嬉しい工夫です。
本書の構成と解説の一例
| 改訂版プレミアムカラー国語便覧(一部抜粋) | |
| 古文編 | ■図説資料 古都の史跡、平安京、男性の服装、女性の服装… ■文学史 古典文学の系譜、古文評論キーワード、上代文学の流れ、中古文学の流れ… ※この他にも史書「古事記」、和歌「万葉集」、物語「竹取物語」、日記「土佐日記」、説話「今昔物語集」、劇文学「人間浄瑠璃・歌舞伎」など古典文学作品や作者の情報が多数取り上げられています。 |
| 現代文編 | ■図説資料 文学散歩、生活用品、住居、服装、交通、経済、娯楽、学校制度… ※現代文編の図説資料では明治から令和までの比較資料が多数掲載されています。 ■小説 明治文学の流れ、大正文学の流れ、昭和文学(前期)の流れ、昭和文学(後期)の流れ、平成・令和文学の流れ… ※明治から平成・令和までの主要な作品と作家、時代の流れについて様々まとめられています。 ■韻文 ■評論 ※評論キーワードから始まり、評論文で取り上げられるような作家と作品の情報が多数掲載されています。 ■外国文学 |
| 漢文編 | ■図説資料 漢文学の世界、年中行事… ■思想 孔子、孟子、老子、孫子…他多数 ■史伝 史記、三国志… ■詩文 詩経、李白、白居易…他多数 ■小説・逸話 ■日本漢文 ■各種作品・作家 ■ことば 故事名言 |
| 表現編 | ■基礎活動 言葉でキャッチボールをしよう、理解する・要約する、小論文、さまざまな資料を読む、小論文テーマ理解(情報、環境、社会、生命、国際)… ■実践 ※実践では読書感想文や履歴書の書き方、敬語の使い方、俳句の書き方など国語的な表現力に関わる知識をまとめています。 |
| 資料編 | ■言語知識 日本語の特色、漢字の知識、対義語、類義語… ■文法・古文知識 ■漢文知識 ■総合索引 |
| その他 | QRコードからNHK for schoolの動画を閲覧可能 |
言語文化に関わる情報と資料がフルカラーで多数掲載されています。本書にある古典文法と漢文句法は一覧で整理されているのみなので、一から学ぶなら準拠している教科書、あるいは参考書を参照した方が無難です。その場合、授業で補完される教科書に対して、単体でわかりやすいのは参考書(演習ノート)になります。『基礎からのジャンプアップノート漢文句法』などで実践的に慣れた方が早いかもしれません。
昭和末から平成の初頭にかけてバブル経済が崩壊し、長期にわたる不況と社会不安の時代となった。出版界も打撃を受けて小説の売れない時代が到来した。そのような平成の幕開けにおいて例外的だったのは、村上春樹(→300頁)と吉本ばなな(→308頁)である。春樹の『ノルウェイの森』、ばななの『キッチン』などがベストセラーとなった。現在に至るまで、文壇から距離をとるスタンスで小説を書き続けている彼らは、一方で多数の外国語に翻訳されており、今や世界文学としての姿を現している。さらに現代日本文学のグローバル化の象徴であり、また平成の文学における大きな出来事は大江健三郎(→293頁)のノーベル文学賞受賞である。
数研出版 改訂版プレミアムカラー国語便覧 P236より引用
これは「日本と外国を越境する作家たち」からの引用です。時代背景に触れながら当時の文学的な流れを解説しています。教科書的な文体には相性もあるかもしれませんが、個人的には全体的に読みやすく感じました。時代背景や生い立ちがわかると作品に投影される思想に納得し、その後の時代に全く反対の思想が流行したり、歴史が繰り返されたりする理由もよくわかります。これは単に一つの知識を丸暗記するだけでは得られないもので、勉強には急がば回れの精神が本質に近いのかもしれないと改めて思いました。
また、文学が隆盛した時代というのはまだまだ大きな物語として語れる余地が大きく、文学作品=時代と言ってもおかしくない捉え方ができるおもしろさもあります。令和の時代と比較すると、今は小さな物語が乱立する時代で作品と時代の関係が捉えにくく、時代の言語化はなかなか難しくなった気がします。そんな様々なことを思い巡らせながら読める本書はオススメではあるのですが、そうは言っても頭から通読するものではなく、雑誌を眺めるように疎らに、勉強の過程で気になることがあったら参照する使い方が主になるでしょう。問題の題材となった作者やその時代の情報、流れを確認するならとても使いやすく、それによって特に古文と漢文への興味関心が高まる期待も持てます。
学校制度と文芸雑誌についての感想と余談
ここに紹介しきれないくらいに全体的におもしろかったのですが、その中で学校制度(旧制高校)と文芸雑誌(早稲田文学と三田文学)についての感想を述べたいと思います。まず、旧帝大という呼称は大学受験では広く当たり前に使われていますが、正しく言うと「旧帝国大学」、旧帝国大学とは東京帝国大学をはじめとした7つの帝国大学のことで当時最高の国立総合大学群でした。でしたというか、今でも優秀な人材が集まる大学です。
そして、その大学に進学するためには旧制高校に合格する必要がありました。旧制高校とは、大学の基礎教養課程を担う教育機関で、旧制中学校(現在の高校に相当)卒業後に試験を受けて入ります。旧制高校の一高(第一高等学校)に入ると東京帝国大学までほぼ無条件*で進学できます。※ほぼ無条件=東大の進振りのようなイメージ。今よりもずっと学歴が重視された時代ですから、エリートには一高合格が宿命づけられていたことが窺えます。今でも就職活動において学歴には一定の価値がありますが、面接を経て、正しく採用される人材の多くは学歴そのものというより思考訓練によって成長した能力が決め手になっていて当時とは意味合いが大きく異なります。当時は東大卒業後の待遇や地位まで保証されていたようです。
おそらく現在の東京大学の2年生までの教養課程は旧制高校の名残りなのでしょう。大学の歴史を今更ながら実感する些細な情報ではあるのですが、他にも名称変更の歴史として「札幌農学校→北海道大学、東京商業学校→東京商科大学→一橋大学、東京物理学校→東京理科大学、明治法律学校→明治大学」が紹介されたところからは看板学部の看板である理由を窺い知れて興味深かったです。一橋大学の商学部は有名ですね。
次に文芸雑誌として「早稲田文学(創刊時の主宰:坪内逍遥)」と「三田文学(創刊時の主宰:永井荷風)」の対比です。今の現役生であっても早稲田と言えば「文学」という評判はどこかで聞いたことがあると思います。本書では文芸雑誌の一つとしてそれぞれ紹介されているのみなので、作者に関する情報の掲載はあれど個人的な推察が多めの感想だと思って読んでください。文芸雑誌の「早稲田文学」とだけ聞くと、単なるサークルの出版物のように感じるかもしれませんが、当時は大学と教授の権威が極めて強かった時代で、大学の機関紙(公認の出版物で書店でも買える)には大きな需要がありました。平たく言うと、今なら高級ブランド品を買い求めるように、誰もが権威のある教養に最高級の価値を見出していた時代だったのだと思います。
そして、この「早稲田文学」というのは創刊時はそうでもなかったのですが、西洋作品の影響で自然主義文学(人間の醜い部分も生々しく描く)の色を強めていき、その後におそらくそれに対抗する形で「三田文学」が反自然主義、耽美主義文学(人間の醜い部分も美として昇華する)の大学機関紙として創刊されたのだろうと推察します。少なくともそのように評価してもおかしくはないはず。そう、この対比というのがいわゆるバンカラの早稲田、ハイカラの慶應の評価が昔からずっと続いていたようでおもしろかったです。もともと早稲田大学は創立者である大隈重信の「在野精神」からもわかるように庶民に開かれた大学イメージが強く、一方で慶應義塾大学は知的で洗練された都会のエリートというイメージが強い。
本書は言語文化に関わる資料集ではあるのですが、高等教育機関である「大学」が全国的に設立され始めたのが1900年前後であり、その時代は文学の時代でもあったわけです。しかも文学界にはエリートが多く、大学の設立に、あるいは設立後に中心的な人物として活躍し、ひとえに文学界と大学は密接に関わっていたと言っても過言ではありませんでした。今では「文学」というと「作者や作品を知る」に集約されてしまうところがありますが、時代を投影する先が文学にあったことは日本文学への興味を高めるきっかけにもなります。余談ですが、そうした「大学の歴史を知る」というのは自分に合った大学・学部選びにおいても重要な情報になり得ます。オープンキャンパスなど行ったらわかるように、体感できるくらいに大学ごとに雰囲気は違います。これは偏差値至上主義で大学を選んではいけない理由でもあり、間違いなく自分の気質や性格に合っている大学に進学した方が過ごしやすいです。大きく言うと、国公立と私立に向いている子もそれぞれ違うと思います。