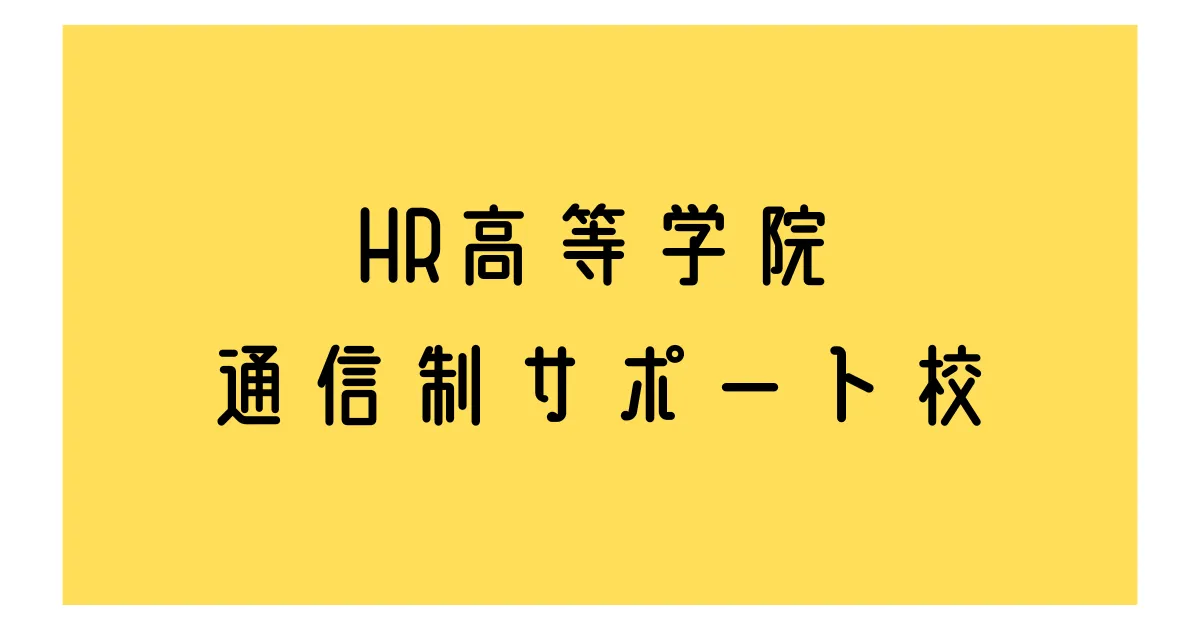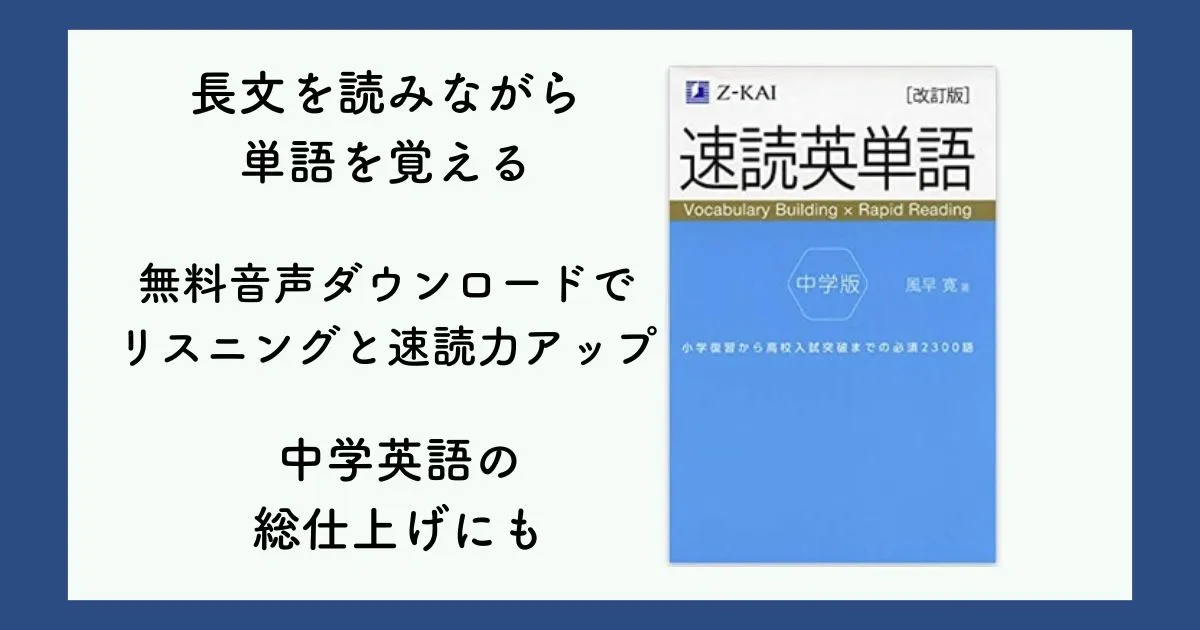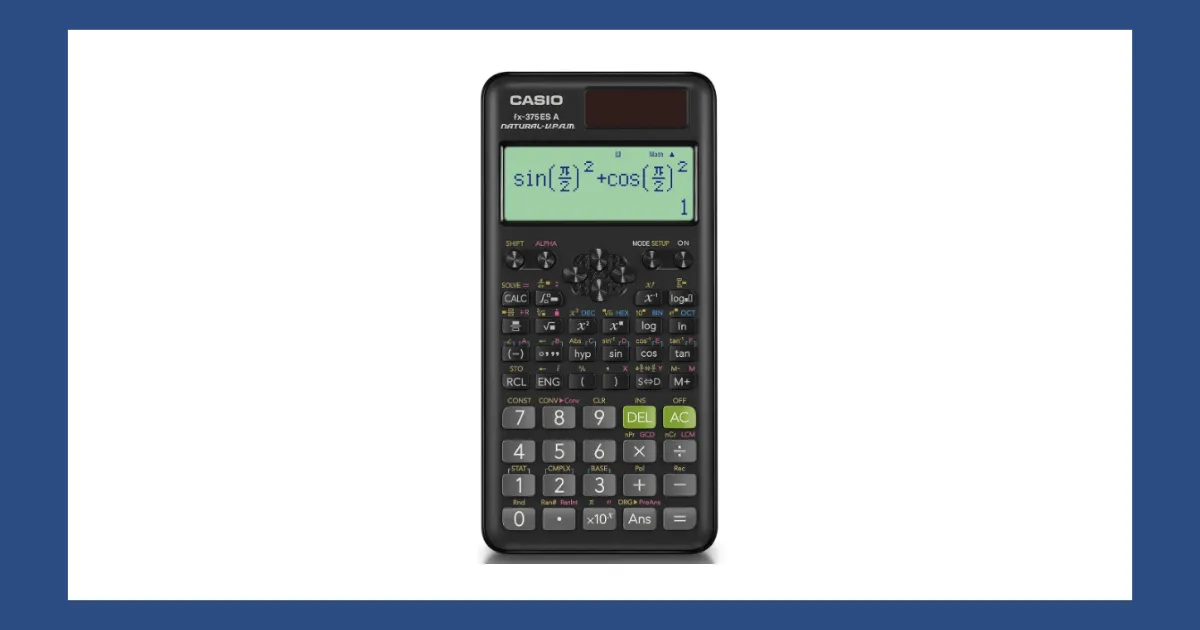| 製品名 | スリーエム(3M) PELTOR イヤーマフ | |||||||||||
| メーカー | スリーエム(3M) | |||||||||||
| 素材 | ヘッドバンド:ステンレス、熱可塑性樹脂、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタール樹脂 カップ:ABS樹脂、熱可塑性樹脂 インサート:ポリウレタン 耳あて:ポリウレタン/塩化ビニル/ABS樹脂 | |||||||||||
| 重量 | 220g | |||||||||||
| 遮音値(NRR) | 24dB | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
加筆修正の履歴
2025/10/30「本製品以外と同程度の価格帯――」→「本製品と同程度の価格帯――」に訂正しました。
イヤーマフ+耳栓で集中力を最大化
本製品はスリーエム(3M)から販売されているイヤーマフです。イヤーマフとは遮音性を高めた耳当てのこと。一般的には耳栓がポピュラーですが、イヤーマフは耳栓よりも音の振動を伝わりにくくする多重構造になっているために遮音性は頭一つ抜けて高くなっています。「耳栓+イヤーマフ」の組み合わせで限りなく無音の世界で勉強できるようになります。
イヤーマフはマイナーメーカーからも多数販売されているため、どれを買った良いか悩む方もいると思います。その点ではスリーエムが最も有名で無難な選択肢です。私はスリーエムとマイナーメーカーのもの(どちらもamazonでは高い評価)を購入したのですが、耐久性と遮音性に関しては正直どちらもあまり変わらず、デザインや値段で決めてしまっても問題ないと思います。個人的にはスリーエムが好み。
勉強をする際にイヤホンで音楽を聴きながら取り組む方もいるかもしれませんが、歌詞のある曲を聴くと脳のリソースを奪われて集中力を下げると言われています。これは人間の脳はマルチタスクができているようでできていない、シングルタスクを高速で切り替えているに過ぎないからです。要するに人間は一つの物事にしか集中できません。車の運転中に話しかけられると集中力が下がる実感があるでしょう。物事に慣れれば慣れるほど“ながら作業”ができるように感じますが、それは集中力を必要としない作業に限り、高い集中力を必要とする勉強では現実的ではないのです。なお歌詞のない曲(できたら感情を動かさない穏やかな曲)であれば、集中力を高める効果があると言われています。
本製品の遮音性能
| 製品 | スリーエム(3M) PELTOR |
| 遮音性能 | 24dB(デシベル) 例:地下鉄車内(80dB)で本製品を装着すると「80-24=56dB」となります。56dBは道端での日常会話くらいの大きさ |
| イヤーマフ+耳栓 | 約30dB 耳栓を加えても遮音性能は単純な和ではなく、約20%アップくらい |
| 通常のイヤホンと耳栓の遮音性能 | イヤホン―15~20dB 耳栓―10~15dB |
| 注意点 | 長時間の装着は外耳炎のリスクに繋がるため、連続使用は2~3時間に留めること |
| ノイズキャンセリングイヤホンとの比較 | 2025年現在、有名メーカーのイヤホンに備わるノイズキャンセリング機能は非常に優秀なので、イヤーマフの代替として期待することもできます。ただ、厳密に言えば、ノイズキャンセリング機能は騒音を遮断するというより聴くべき音に焦点を当てるための機能であり、物理的に外界の音を遮断しようとするイヤーマフとは違った質感と言えます。 |
| その他 | 本製品と同程度の価格帯では33dBの遮音性能を備えるものもある |
集中とパフォーマンス
無音の環境で高い集中力が発揮されること自体は良いことですが、本番の試験では雑音を遮断することができません。それなら「雑音の中で普段から勉強して集中できるようになれば良い」と考えるかもしれません。確かに東大に合格するような子の中には普段から雑音の多いリビングで勉強する習慣があったから、どんな環境でも高い集中力を発揮できるといった話を聞くこともあります。しかし、全ての子に当てはまるわけではなく、そもそも雑音は集中力を阻害するものであることには変わりません。集中したいのに雑音によって集中できないと、どんな環境であっても集中できない子になってしまうかもしれないわけです。
では、どうすれば良いのか。個人的な結論として、試験会場では誰であっても多かれ少なかれパフォーマンスは落ちる前提で取り組むことです。自分自身が最も集中できる環境でのパフォーマンスを「100」としたら、試験会場では「70~80」になってしまうことを最初から受け入れます。ある意味、集中することを諦めて得点だけは落とさない実力を身につける方針です。覚悟も想定もしないまま、例えば試験会場で激しく咳き込む人と隣り合っただけでパフォーマンスが大きく落ちてしまうのはもったいない。他方で「集中する方法」に関しては様々な理論があるので、自分に合った方法を見つけておくのも手かもしれません。
しかし、集中する方法は意識的に身につけるものではなく、何か好きなこと楽しいことに夢中になっていたら勝手に身につくという線が濃厚な気もします。つまり、試験を心から楽しむ気持ちをつくる方が大切です。少なくとも私は集中しようと思ってもできないと割り切ってしまっています。イヤーマフによる集中も、無音に近い環境が勝手に集中状態へ導いてくれる感覚です。集中状態は無意識的。「集中するぞ!」と意識的な集中を試みるのではなく、意識的に無意識を準備する方が効果があるだろうと思います。