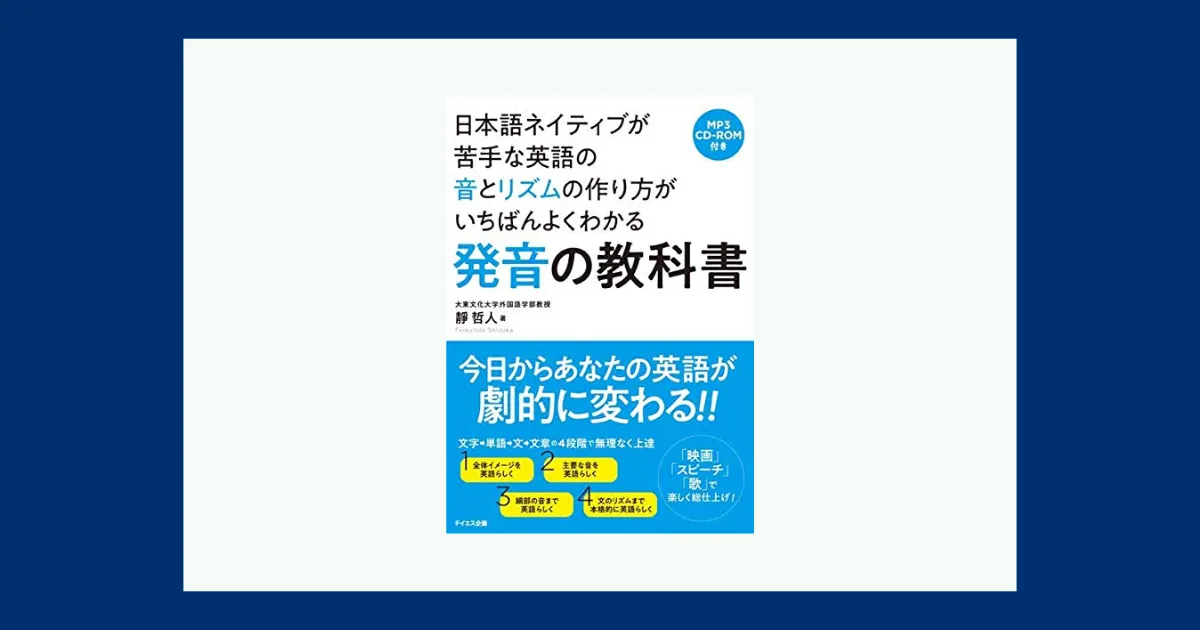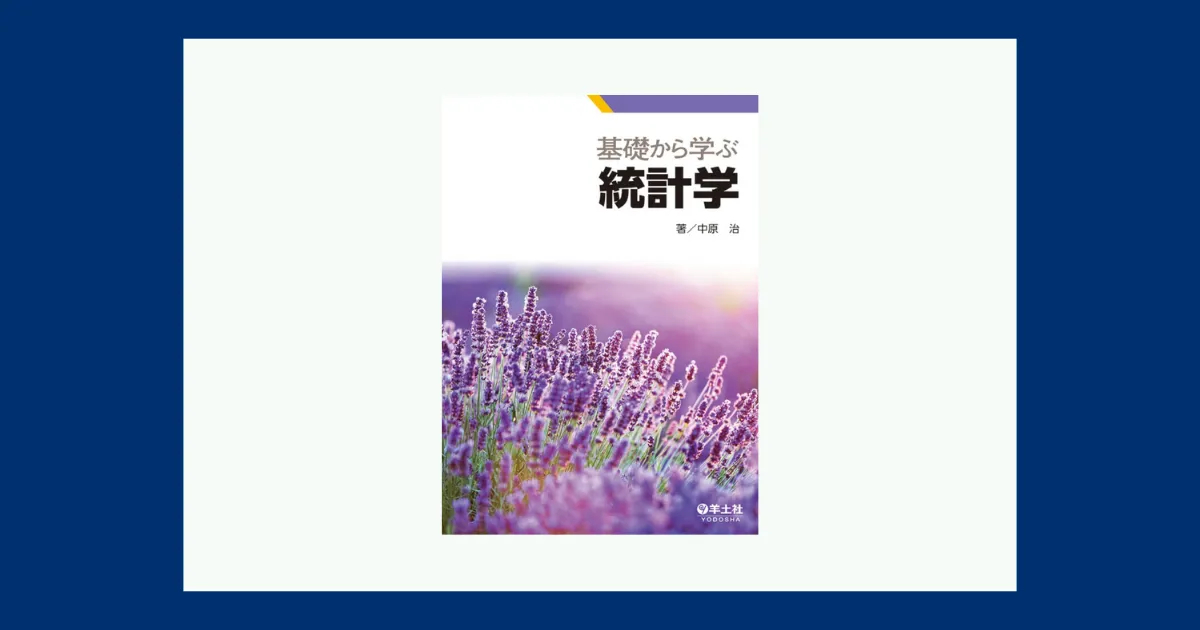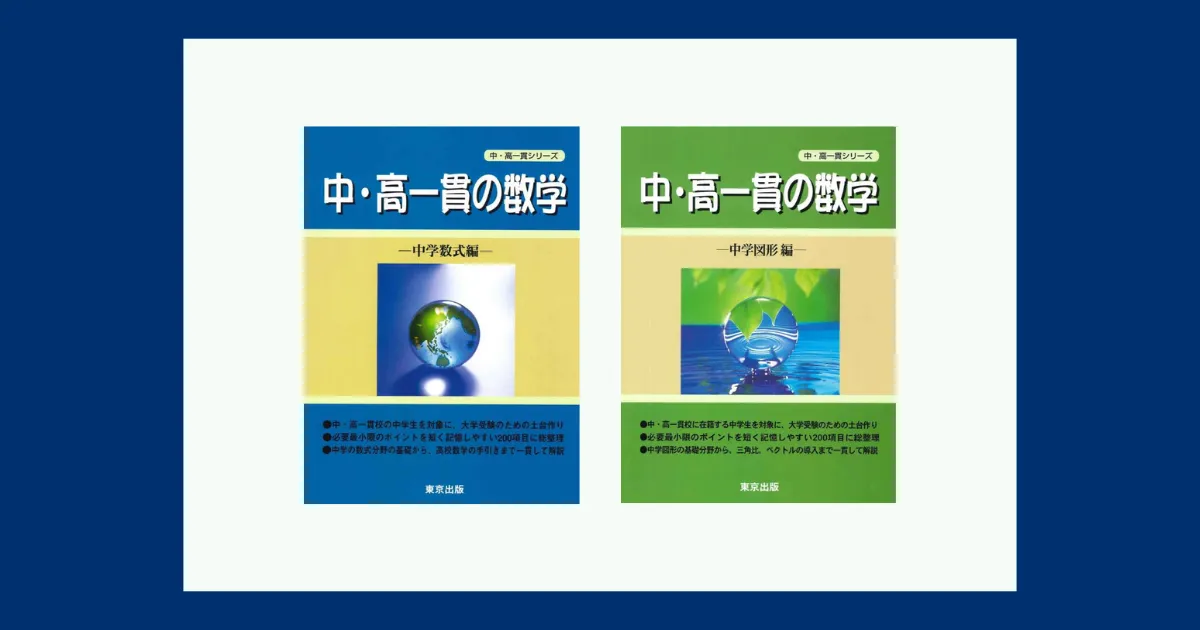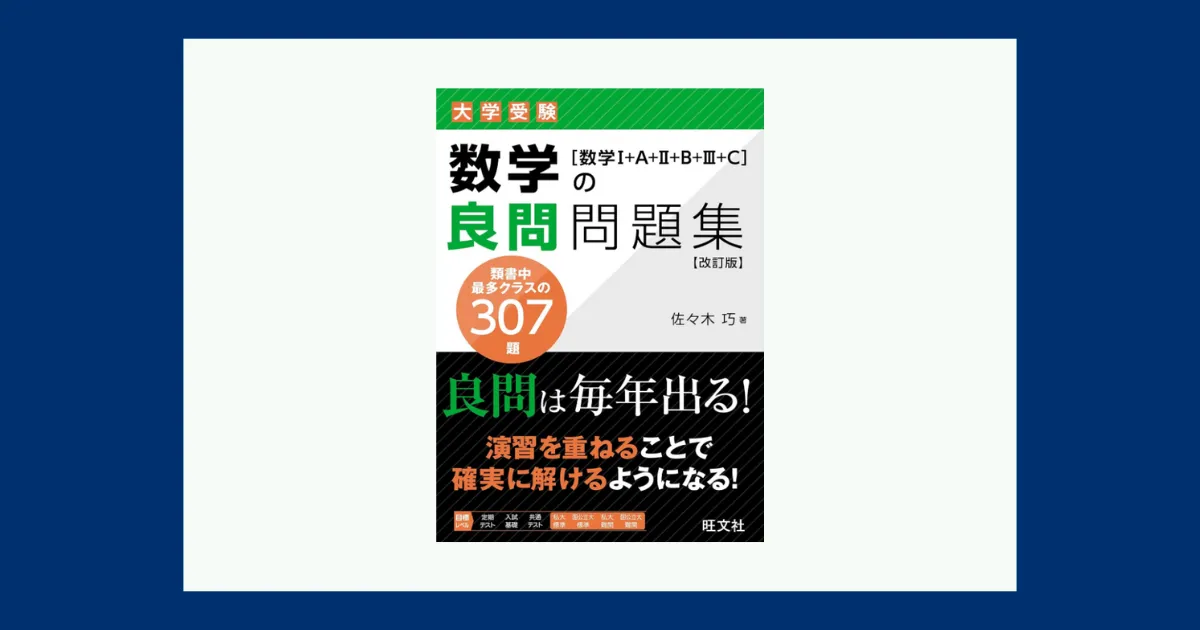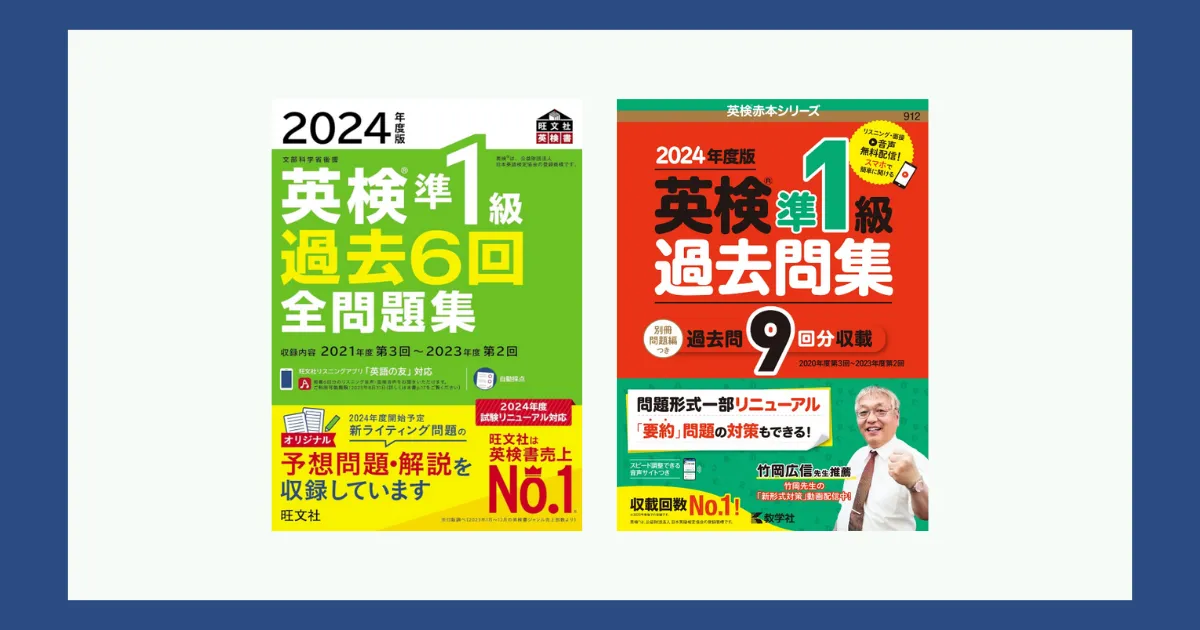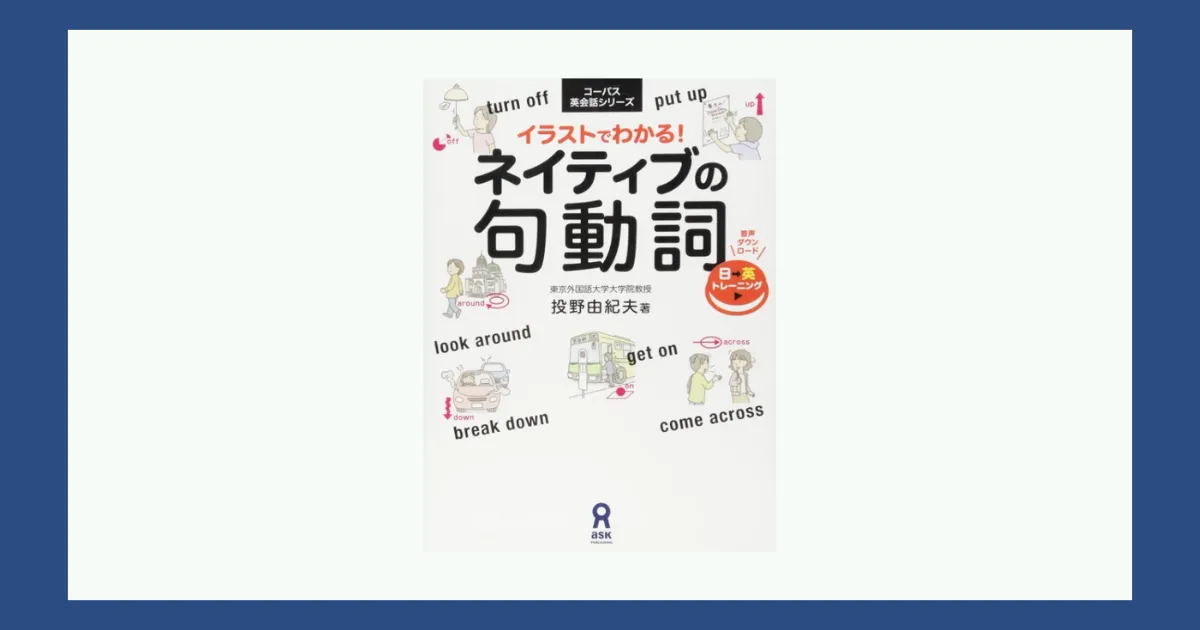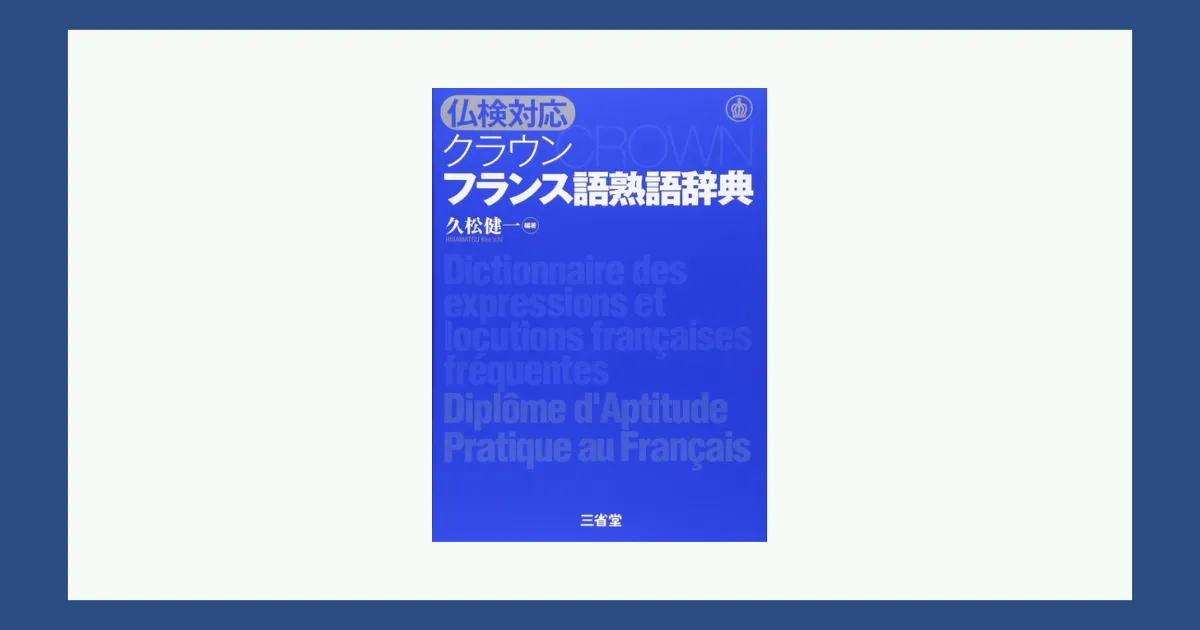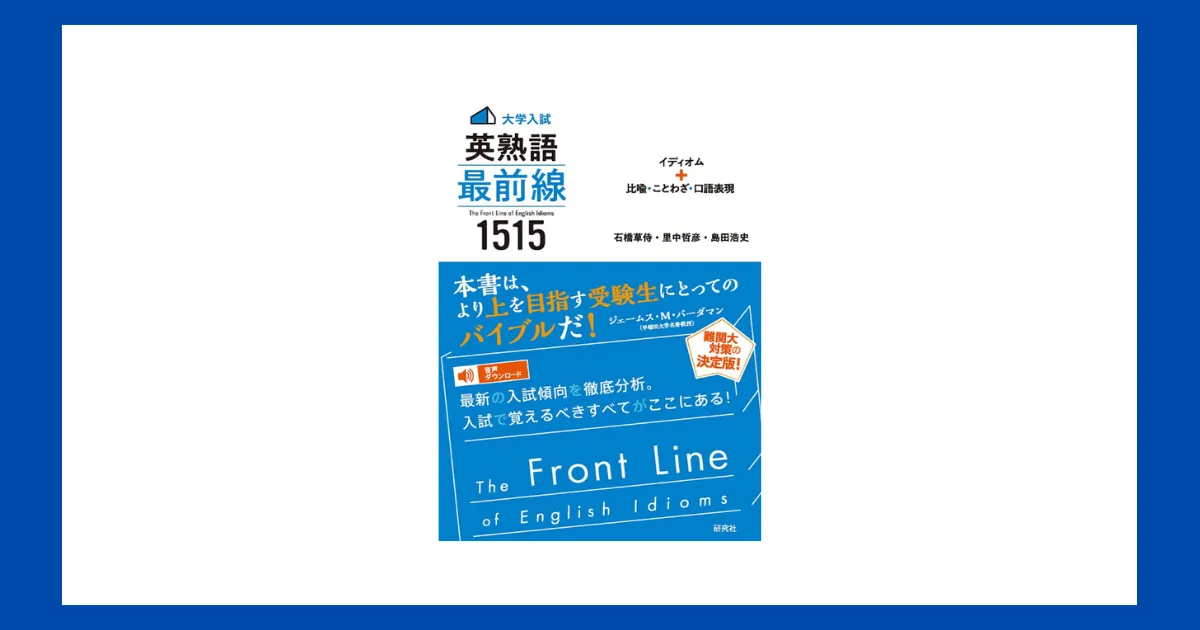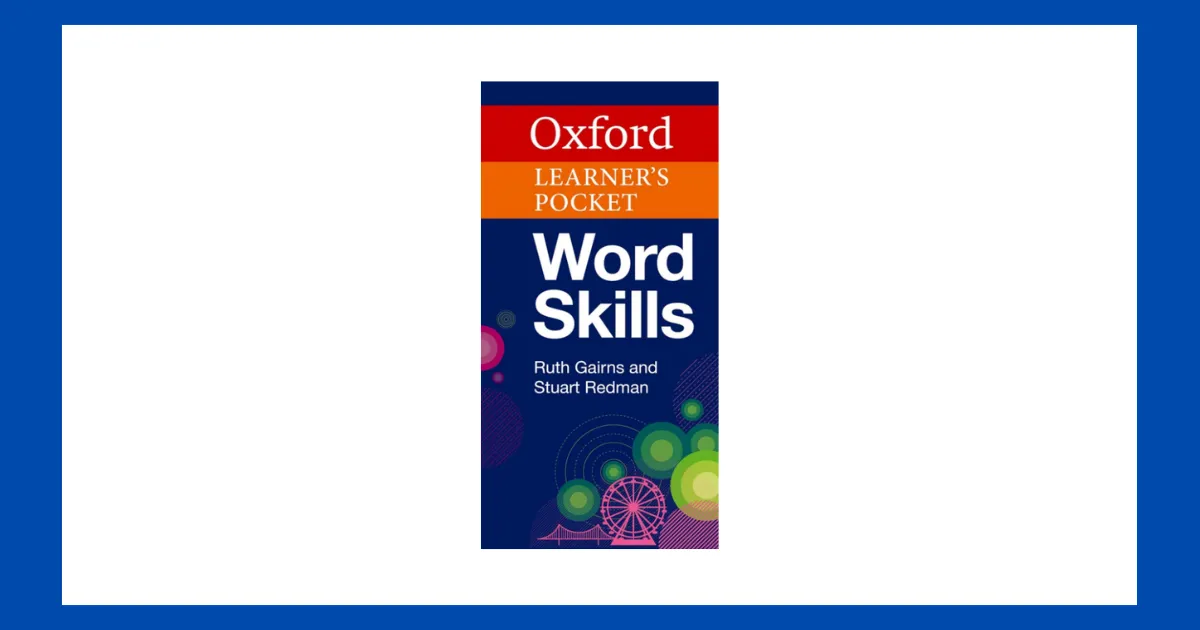| タイトル | 発音の教科書 | |||||||||||
| 出版社 | テイエス企画 | |||||||||||
| 出版年 | 2019/1/19 | |||||||||||
| 著者 | 靜 哲人 | |||||||||||
| 目的 | 英語の発音 | |||||||||||
| 分量 | 240ページ | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
対象・到達
【対象】
・発音の学習をしたい全ての人
・座学だけでなくトレーニングもしたい人
【到達】
・発音に関する基礎的な知識が身につく
本書は2019年に出版された発音(主に単音)の参考書です。当サイトでは「英語学習の初期段階に推奨する参考書」としての地位を確立しました。専門的すぎず、日本語と英語の差異を中心に解説するため、橋渡しするにはちょうど良い難易度とトレーニングになっているからです。日本人にとってわかりやすい発音の教科書。
注意点として、本書の解説では発音記号が用いられていません。発音と言えば、発音記号の理解が重要ではあるものの、いきなり発音記号との1対1対応は初心者に易しくないとの著者の意向が反映されています。この点は各Lessonの横にでも表記するだけで済むと思いましたが、今や単語帳の冒頭でも発音記号の解説はあるので問題ありません。第一に英語学習に必須の音声利用の効果を大きく損なわないポイントを押さえれば良く、その点で日本人が誤解しやすい発音全般の課題を全70Lessonに分けている方がわかりやすいとも思いました。
どちらかと言えば大人の学び直し向きの解説ですが、現役生であっても高校生以上なら問題なく採用できます。本書の解説は「リスニングで聴き取れない失敗体験がある人」や「将来本気で英語を話したいと思う人」には特に刺さると思います。また、英語の発音学習は本人のやる気もありますが、学校の授業でどれほど力を入れているか、先生の解説ひとつで成長率が異なるため、どこかで本書のような参考書一冊に取り組んでおくのがより良いでしょう。
本書の構成
第1章 発音について知っておきたい12のポイント
第2章 まず全体イメージを英語らしく
第3章 主要な音を英語らしく
第4章 細部の音まで英語らしく
第5章 文のリズムまで本格的に英語らしく
第6章 これまでの学習の総まとめ
Column 英語の歌で発音がよくなるのはなぜ?/「English 日本語」のすすめ/英語の名言でブラッシュアップ/メトロノームに合わせて/リンガ・フランカ・コア
本書は主に単音に焦点を当てた参考書ですが、シリーズ4冊の予定はなかったためか、本書だけで他の『リスニングの教科書』『単語の教科書』『音読の教科書』の内容を含んだ発音の総合参考書に仕上がっています。リスニング対策したいから『リスニングの教科書』を最初の一冊にするとしてもそこまで問題ありませんが、本書を土台に他3冊があるというイメージが正確だと思います。
発音学習のメリットの一つとして「発音ができるとスペリングが覚えられる」に触れておきます。
単語のスペリングを覚えるとき、発音を無視してスペリングを機械的に覚えようとする人がいます。極端な例では baseball のつづりを「バセバジュウイチ(11)」などという語呂合わせで覚えようとする中学生さえいるのです。実は英語だって文字は音を表している、という当たり前の事実を知ってか知らずか、スペリングを書かせるテスト対策として、つづりを記号として丸暗記してしまおうという笑えない戦略です。しかしこの戦略は大きな無駄を生み、すぐに限界が来ます。
発音の教科書 P3より引用
日本人にとって英単語のスペルは必然性が乏しいため、引用にあるようなその場しのぎを誰しも思いつきます(記憶法としては悪くない)。英語ネイティブは音から正確なスペルを書けますが、これは英単語がアルファベットの音の連結によって表されているため、単音と連結、発音の知識があれば、聴き取った音の情報を正確に分解できるからです(※例外はある)。この点は『フォニックス発音トレーニングBOOK』で詳しく述べられています。
ちなみにこの点に関して著者は「アブクド読み」を推奨しています。アブクド読みとは簡単に言うと、単語の中で読まれる音のまま読むこと(覚えること)です。例えば、通常の読み方では「A=エー、B=ビー、C=シー、D=ディー」としていますが、アブクド読みでは「A=エァ、B=ブッ、C=クッ、D=ドゥ」となります。アブクド読みを覚えておけば、例えば「baseball」は「ブッエァスーエブッエァル」となって実際の発音に近い発音ができるようになり、初めて耳にする単語でも正しいスペルを推測しやすくなります。
発音学習はただ発音が綺麗になるだけではなく、聴覚から得られる情報の質が向上することで様々な効果をもたらします。その一つとして、単語のスペリングもそうですし、リスニングやリーディング、スピーキングにおいても力を発揮します。発音とアルファベットの関係性の理解が深まれば、単語やフレーズの暗記も捗るでしょう。言語学習は音声を中心に据えるだけで2倍、3倍の効率に繋がるのではないかとまで思います。
-bel: [ベル]でなく[ボウ]――
Abel (アベル、男子の名) [エイボウ]、label (ラベル)、libel (名誉棄損)、rebel (反乱軍)、Campbell (キャンベル、姓)
発音の教科書 P46より引用
本書の目指すところはネイティブ並みの発音ではなく、非ネイティブの中での綺麗な発音です。だからこそ無理がなく、取り組みやすい。本来であれば、この引用にあるような「カタカナ→カタカナ」の訂正は推奨されませんが、凝り固まった日本語脳になっている人の段階的な学習なら積極的に推奨できるものです。もちろん、単なるカタカナ表記ではなく、前提として英語の発音らしさを押さえたあとの便宜上の表記に過ぎません。本書を読まないと単なるカタカナの訂正にしか見えませんが、意図としては訂正されたカタカナ表記を頭の片隅に意識しておくとわかりやすいというだけです。本当に日本語のカタカナのまま発音するわけではありません。
英語学習の最初の一冊に推奨したい
小中学生のような全くのゼロから英語を学ぶ場合を除き、高校生以上の英語学習には本書を推奨したいと思っています。音声学習の質を第一に向上させた方が長期的に大きなメリットがあるからです。それに単語や文法にただ詳しいよりも、綺麗な発音をアピールできた方が羨ましいと思うはず。
アクセントやリズムを理解できれば、必要最低限の音だけで意味を理解することもできます。例えば、省略に関すること。日本語で言うと「おはよう」は「はよう」でも通じますよね。言語コミュニケーションの効率は誰もが意識するところで、速く読むことと伝えることの両立などはおそらくどんな言語であっても意識されています。その結果、音変化が生じるというような事情を理解した上で、英語学習の最後に位置づけられる多読多聴に取り組むと、脳が瞬時に意味を形成してくれるようになります。いわゆる「慣れ」です。識別できる単語を増やすだけでは足りず、必ず単語同士の結合と文のリズムまで含んだ音変化を知らないと効率が落ちます。
もっと広く言うと、勉強という行為は「訂正」と言い換えてもいいもので、どういう形であれ、まずは正しさを知ることに全力を注いだ方が効率は良いのです。幼少期のピアノレッスンで絶対音感が備わる話に近い。スポーツなら綺麗なフォームの選手を参考にすること。数学なら数式を書き写すこと。正しさが頭にでも感覚にでも刻まれれば、間違ったときに差異を感じられるようになります。しかし、英語の音に関しては日本語の完成と共に正しさがわからなくなります。聴き取れなくなるわけですから、識別できないものに正しいも何もありません。そう、私たちの日本語脳の中で英語を学ぶには限界があるため、本書のような発音を最初に学んで日本語脳を柔軟にすること、および英語の正しさを刻んでほしいのです。