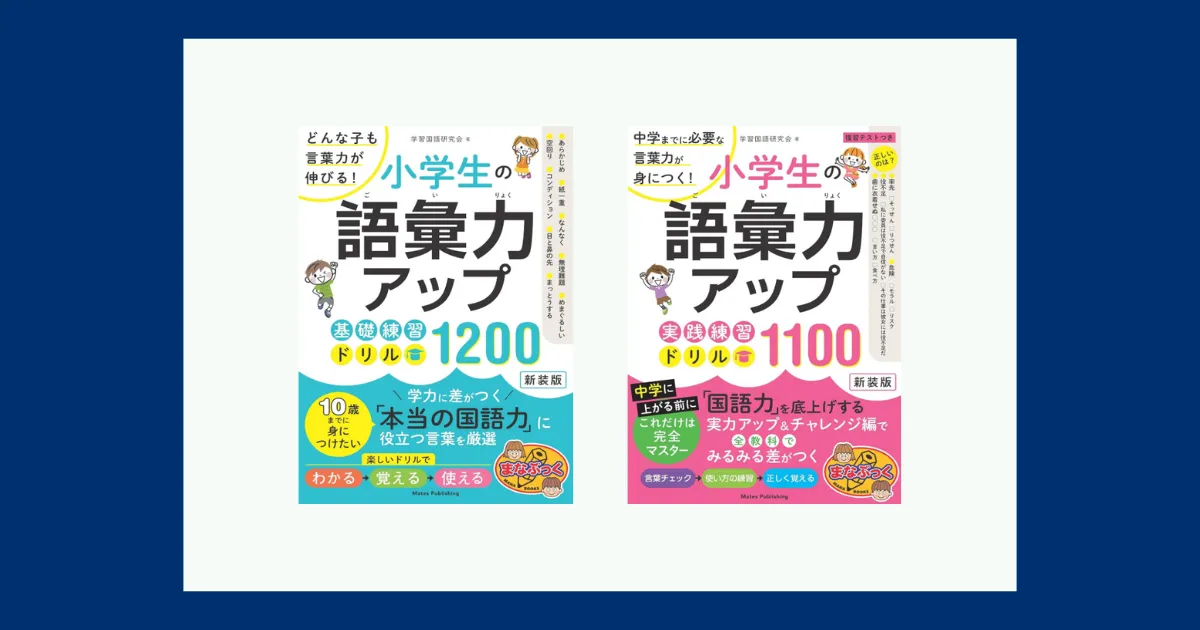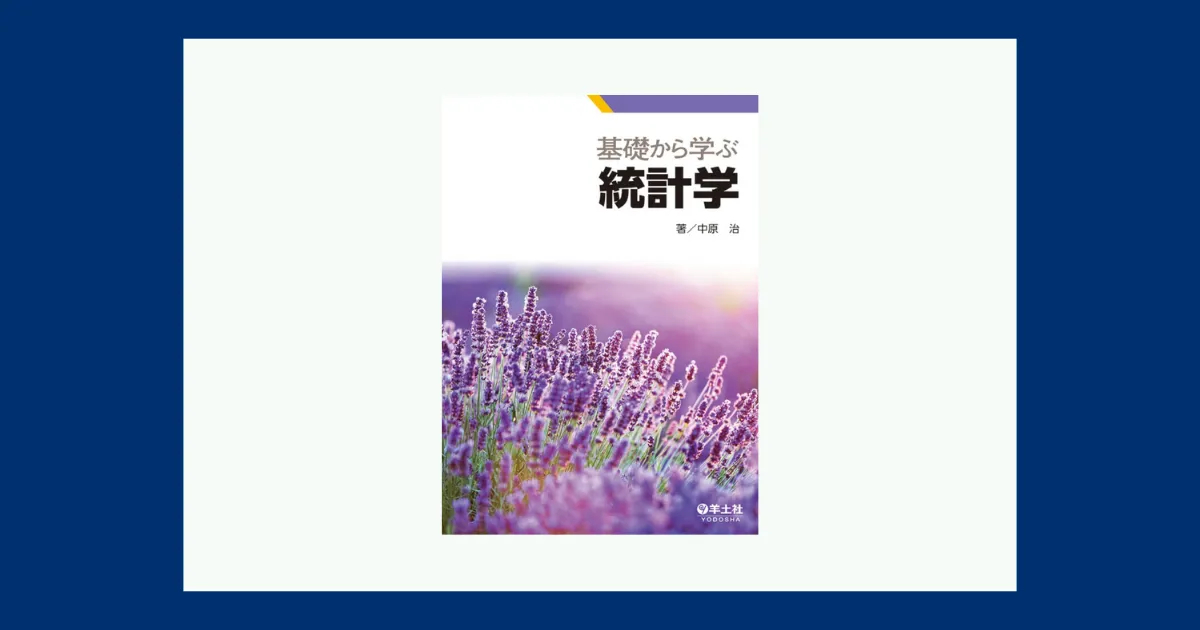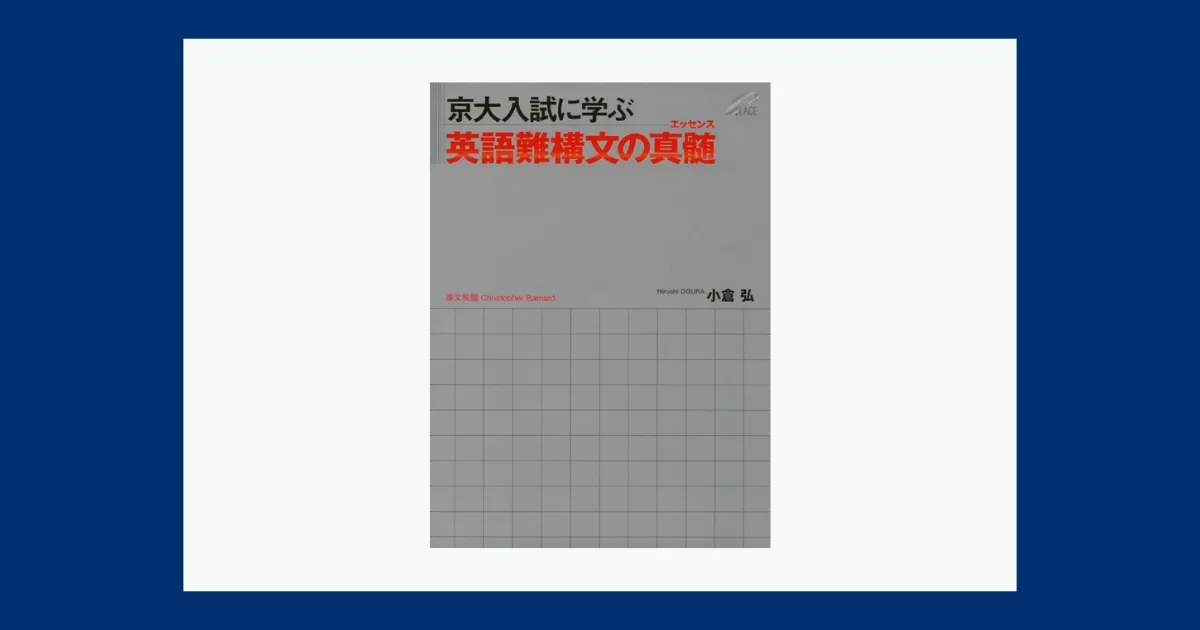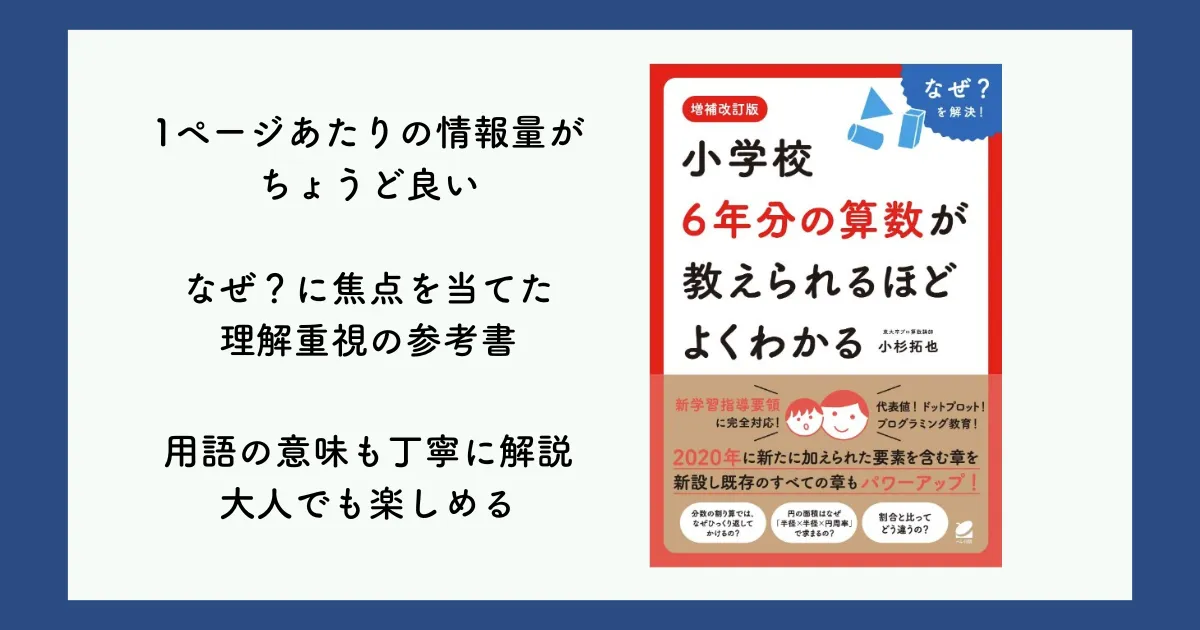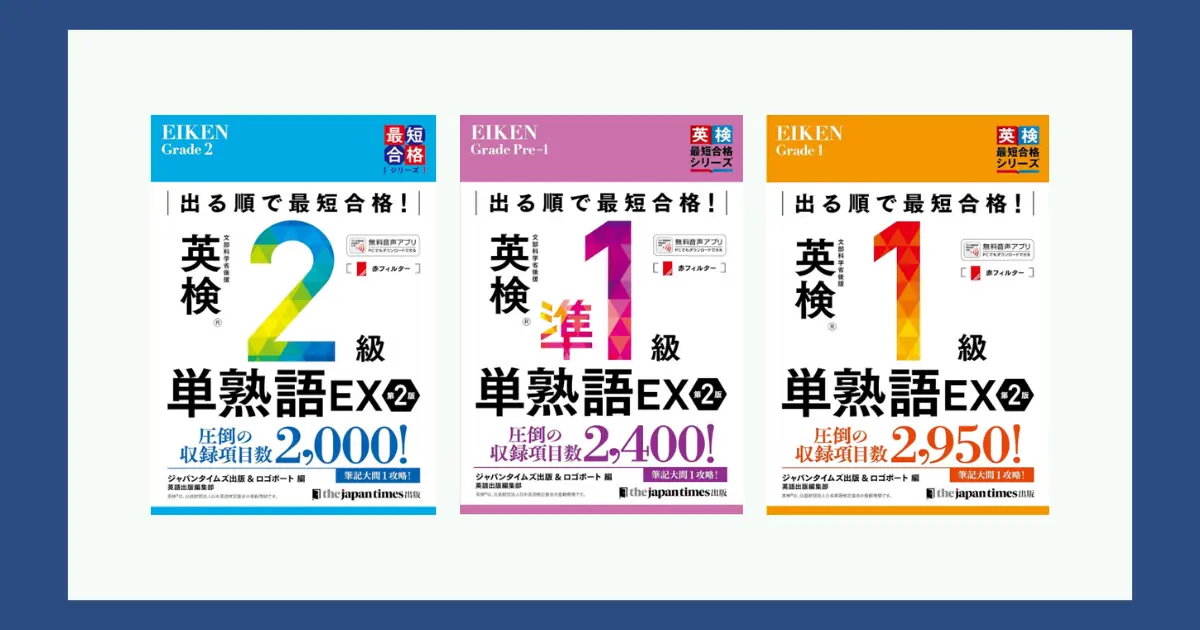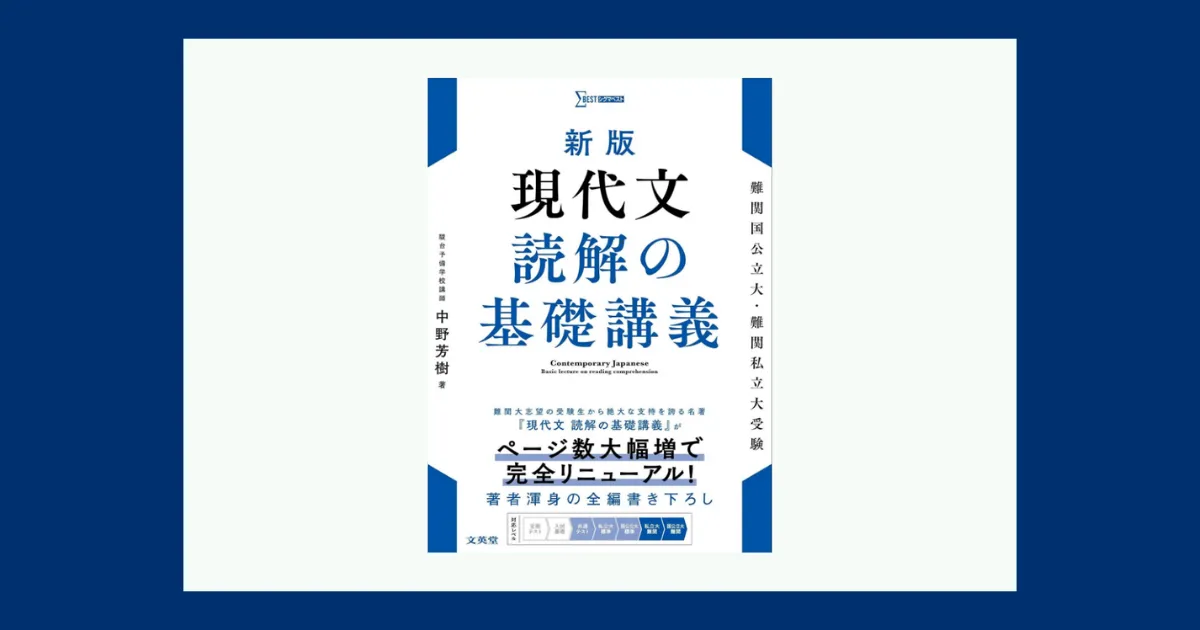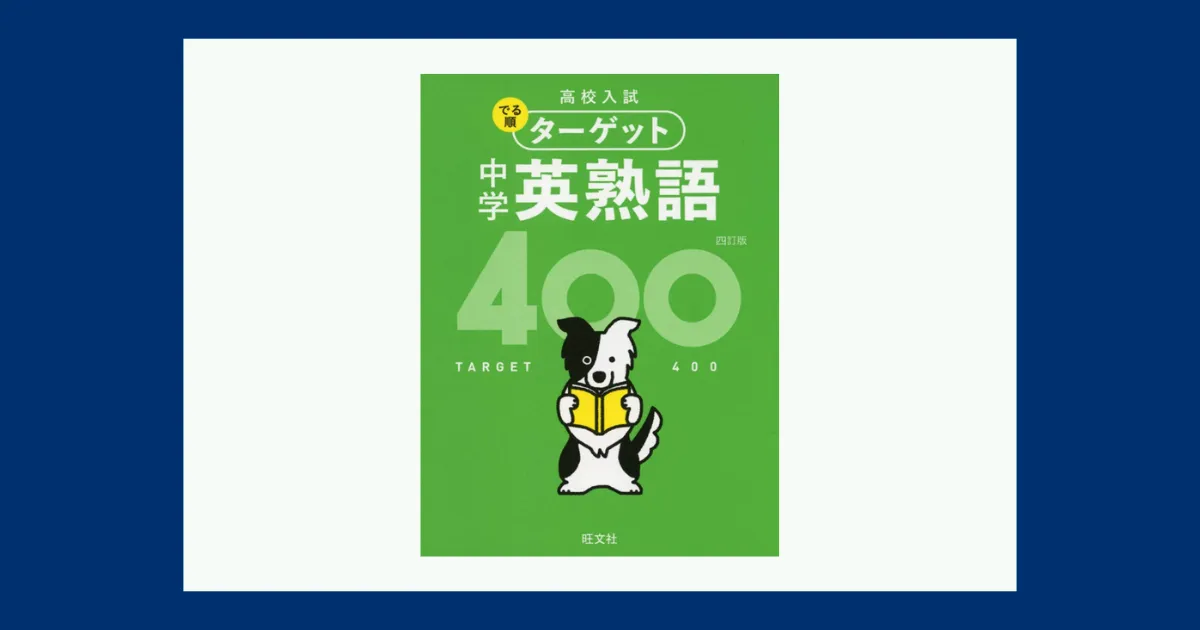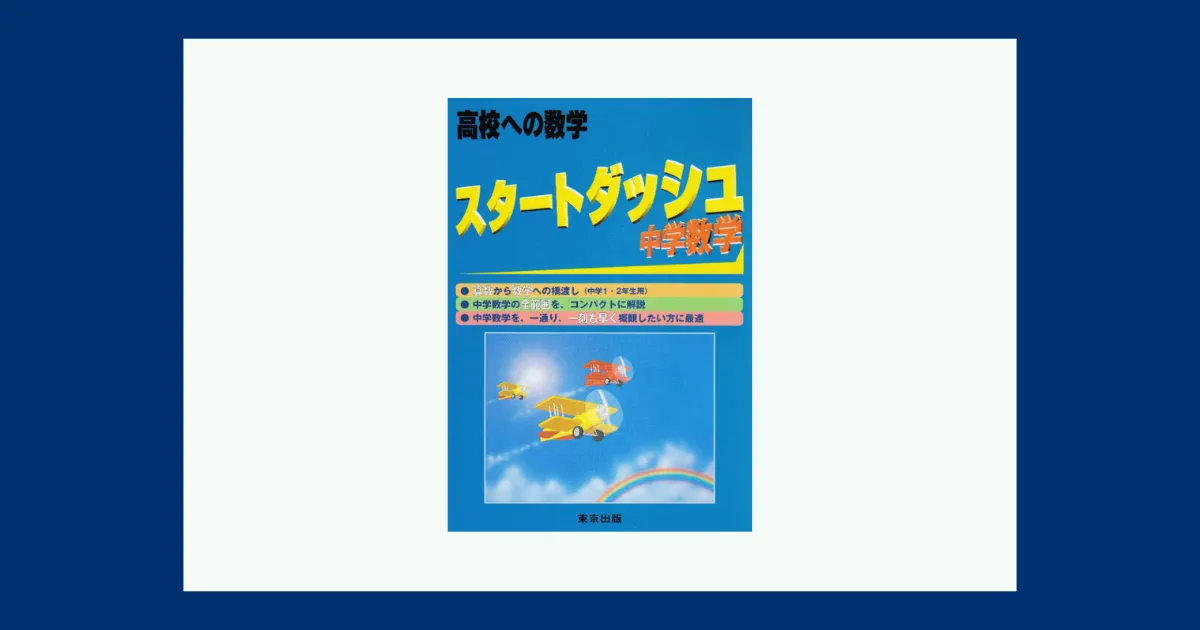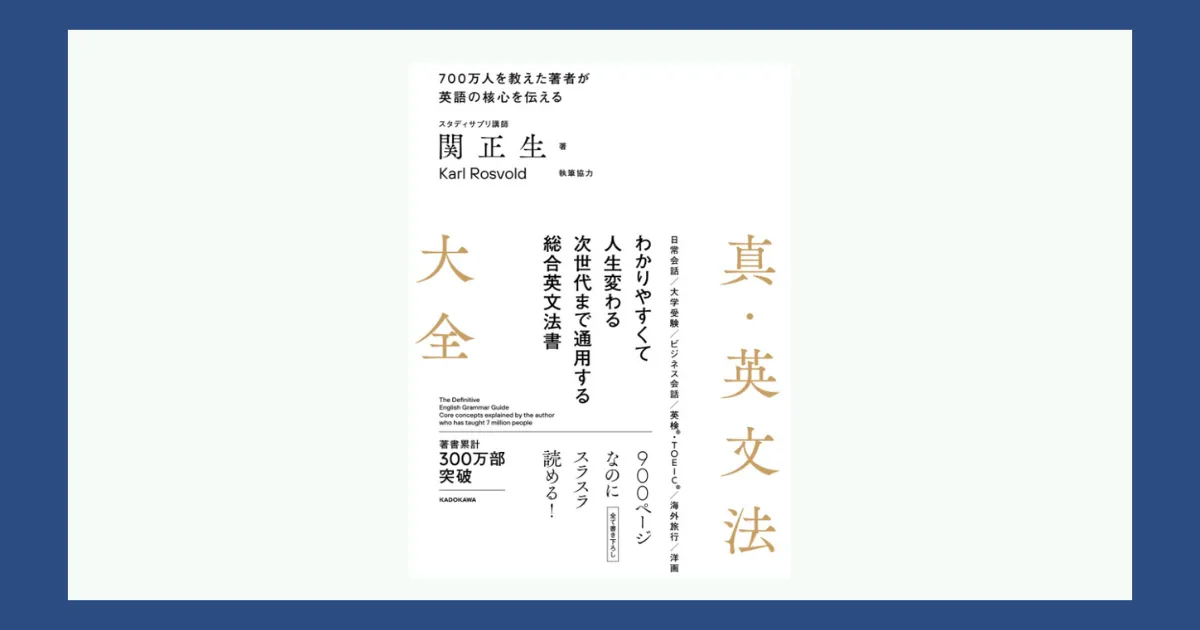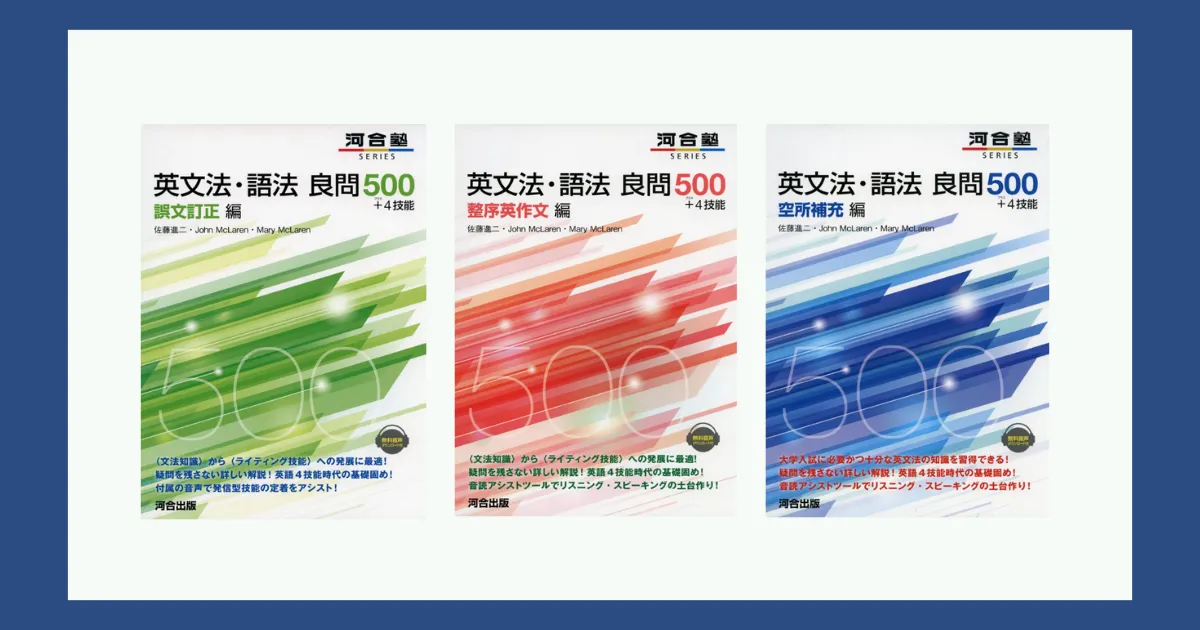| タイトル | 小学生の語彙力アップ 基礎練習 ドリル1200 小学生の語彙力アップ 実践練習 ドリル1100 | |||||||||||
| 出版社 | メイツ出版 | |||||||||||
| 出版年 | 2021/4/15 | |||||||||||
| 著者 | 学習国語研究会 | |||||||||||
| 目的 | 小学語彙 | |||||||||||
| 分量 | 144ページ | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
対象・到達
【対象】
・小学語彙を身につけたい人、大人の学び直し
・シンプルな問題形式を探している人、語彙だけ勉強したい人
【到達】
・小学語彙が身につく、日常生活に必要な言葉を覚えられる
本書は以前に紹介した『小学生の漢字1026字 読み取りドリル』『小学生の漢字1026字 書き取りドリル』のメイツ出版から出版されている問題集です。メイツ出版の問題集は子供向けでありながら、大人の学び直しでも使い勝手の良いものになっています。シンプルで必要十分な量、かつ国語力を養うのにちょうど良い問題文になっているからです。これは「復習」と位置づけられているためにできることで、だからこそ大学受験や高校受験などで中学生以上が用いても差し支えありません。
中学以降の漢字・語彙では、以前から紹介している『高校生の語彙と漢字 ゴイカン』と『中学国語力を伸ばす語彙1700』を推奨していますが、小学語彙に関しては特別推奨したい参考書が見つかっていませんでした。当サイトで繰り返し言っているように、国語力は全ての科目の基礎(※厳密には数理能力と分ける)。小学校から高校までの漢字・語彙を完璧に押さえたときには、勉強が苦手な子の成績も大きく改善する期待が持てるほどです。
そこでまずは小学漢字・語彙として、同じメイツ出版の『小学生の漢字1026字 読み取りドリル』と『小学生の漢字1026字 書き取りドリル』で小学漢字を、本書で語彙をマスターするのがわかりやすいと思います。さらに『小学生の算数おさらい計算ドリル』も加えれば、小学算数まで押さえられて小学復習は終わりです。これは大人の学び直しにおいても同じ。第一に小学漢字・語彙、算数を完璧にします。
本書の難易度と接続先
本書は中学受験を想定しない一般的な小学生向けの難易度です。ですが、本当に現役の小学生が本書の言葉を完璧に覚えたとしたら、勉強が苦手になることはないのではと思います。まず間違いなく偏差値50未満になることはなく、常に偏差値60以上(上位15%)はキープできるはずです。国語力は複利のように効いてきますから、これだけの語彙力を小学生のうちに備えていたら学校や塾の授業での成長率は平均以上になります。直接的な知識だけでなく、本書を通じて言葉に対する感度が高まることに大きな価値があります。言葉の感度が上がると文章から得られる情報の質も上がり、情報の質が上がると思考のエンジンがかかるようになります。思考のエンジンがかかれば、疑問点が生まれ、疑問点の解消によって知識の獲得と理解が進みます。※言葉もわからない状態では考えることすらままならない。
どうしても勉強の苦手な子ほど単純化思考が強いため、例えば漢字テストのように読み書きできることが全てになってしまいますが、裏を返せば問題(ドリル)形式による訓練が効果的とも言えます。本書の基礎と実践2冊のドリル形式は分量も十分です。本書の接続先としては中学生版『中学生の語彙力アップ 徹底学習ドリル1100』と『中学生の語彙力アップ 実践ドリル850』が同じシリーズで使いやすくなっています。
そして、語彙を備えたあとは精読の訓練に移ります。英語と同じ。語彙と文法が乏しいときの知っている単語を繋ぎ合わせるだけの読み方から脱却し、一文ずつ正しく理解しながら読むことを学びます。これは大人もそうなのですが、人間の思考はよくわからない場面で「なんとなくわかるものだけ」を拾い上げて理解できるフリをします。しかも酷い場合では、理解できるフリを正しく理解したと勘違いまでします。それを訂正し続けるのが精読です。当然と言えば当然ですが、日本語の文章を正しく理解できるようになれば、どんな科目でも日本語で説明されている以上は正しく理解できるようになります。
読み書きから理解語彙・表現語彙へ
言葉の理解度を段階で示すと、第一に「読み書き」があります。英単語で言うと、一語一訳や発音、スペルがわかるという状態です。これは単純な知識としては「ある」と言えますが、運用の観点から言うとまだまだ厳しい状態になります。コアイメージも捉えられていないため、凝り固まった直訳、文脈に沿った柔軟な意味を引き出せません。
次にその状態から様々な文章に触れていると、言葉の概念(コアイメージ)が形成されていきます。英語の多読多聴が重要と述べる理由も同じ。多角的に指し示されると、その言葉がその言葉であるための範囲を最大限に広げられるようになります。一語一訳は形の決まったパズルのピースのようなものだったのに対して、本来の言葉の柔軟さを認識できているこの段階は単なる知識から“理解”になった状態です。
そして最後に、理解語彙から実際に運用する「表現語彙」へと繋がります。理解することよりも説明することの方が難しい。問題を解くよりも、問題を作る方が難しい。小説を読むよりも、書く方が難しい。英語ならリスニングとリーディングよりも、スピーキングとライティングの方が難しいですよね。人間の思考原理がそうなっていると言ってしまって良いと思います。表現語彙として分類できるものは深く理解している証です。
もっとも受験では小論文や記述問題があるものの、基本的に「理解語彙」の段階で事足ります。ただ、「読み書き」はできても「理解」の段階に到達していない、あるいは「読み書き=理解」と誤解しているために国語力を伸ばす訓練が「読み書き」で止まってしまっている人が少なくないのです。ですので、本書に取り組む際は覚えたあとに必ず「理解」する段階まで意識して進むようにしてほしいと思います。