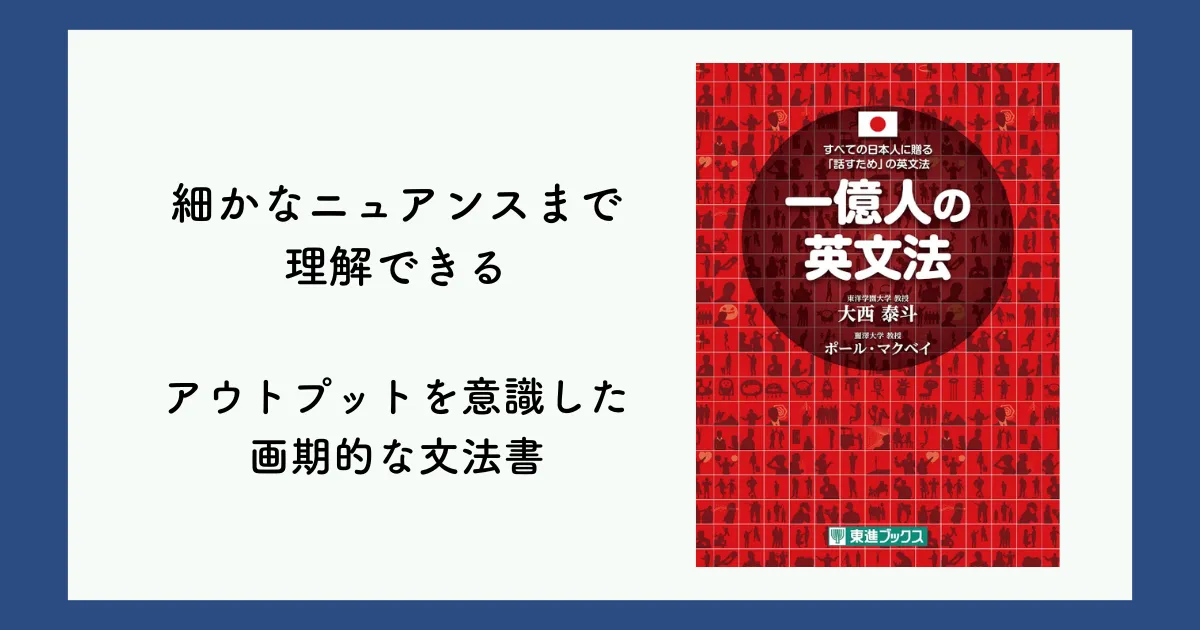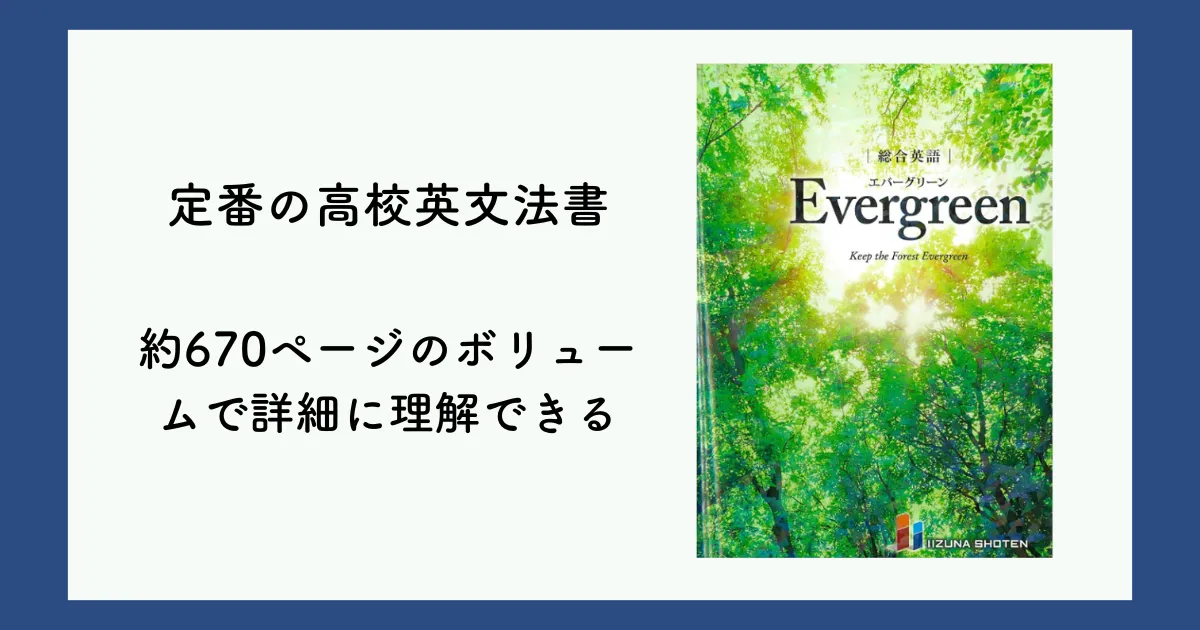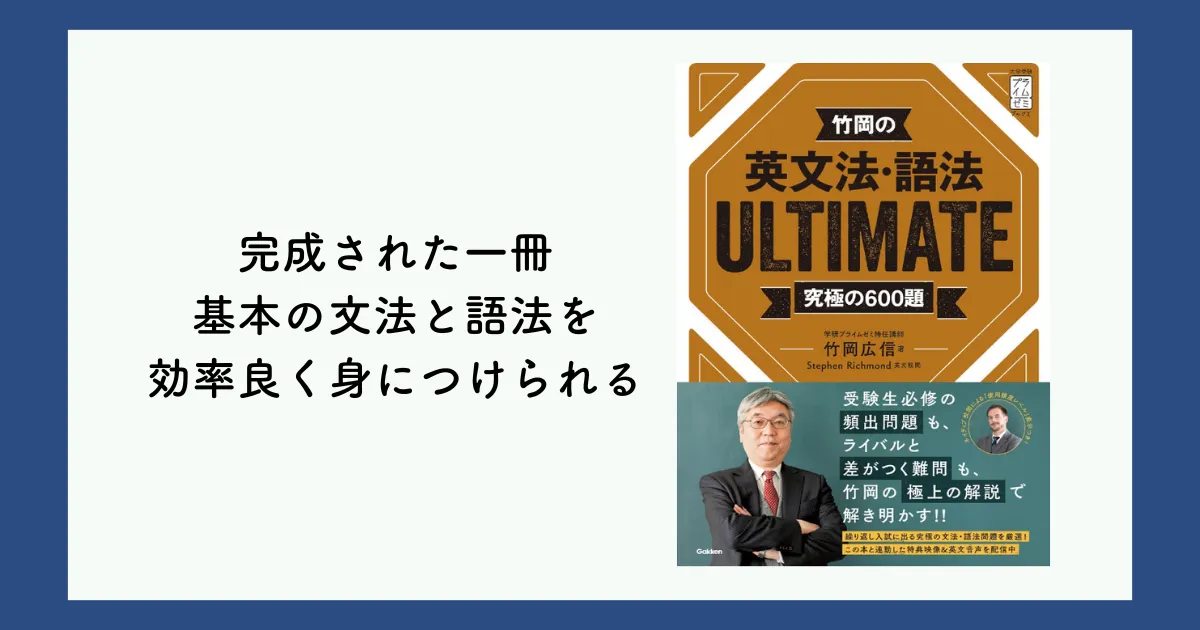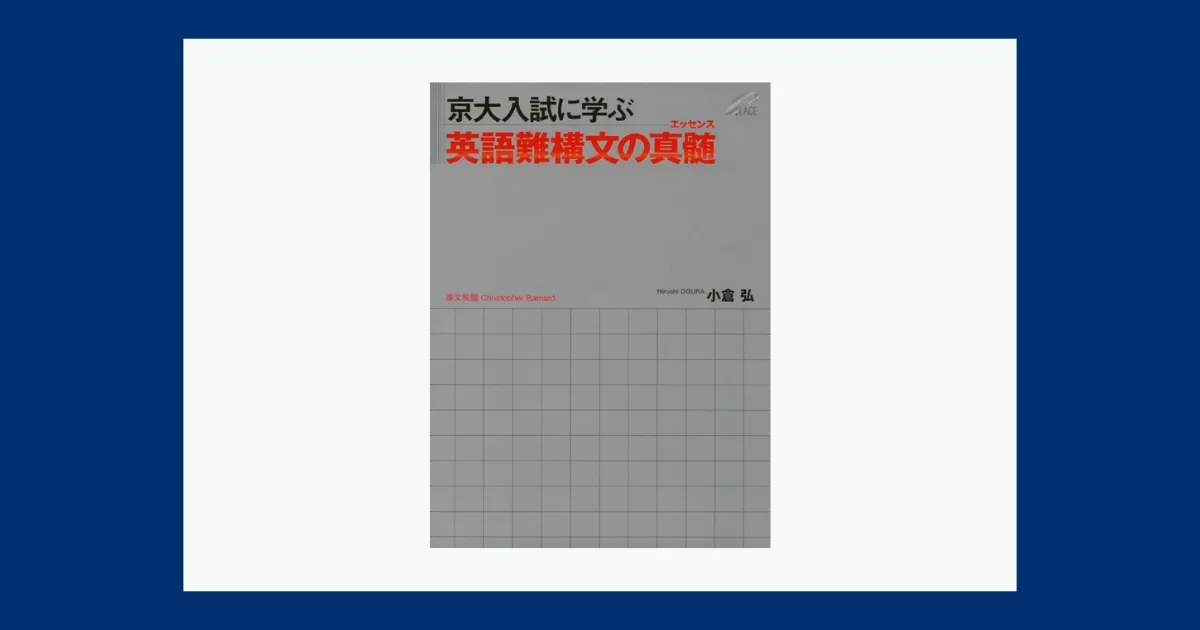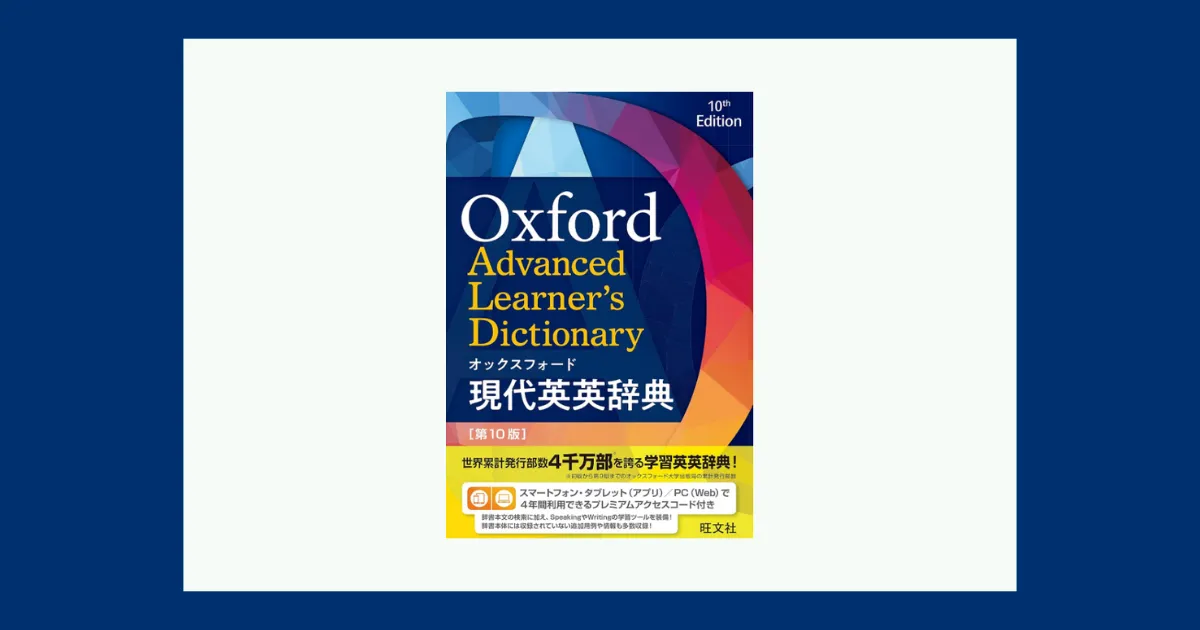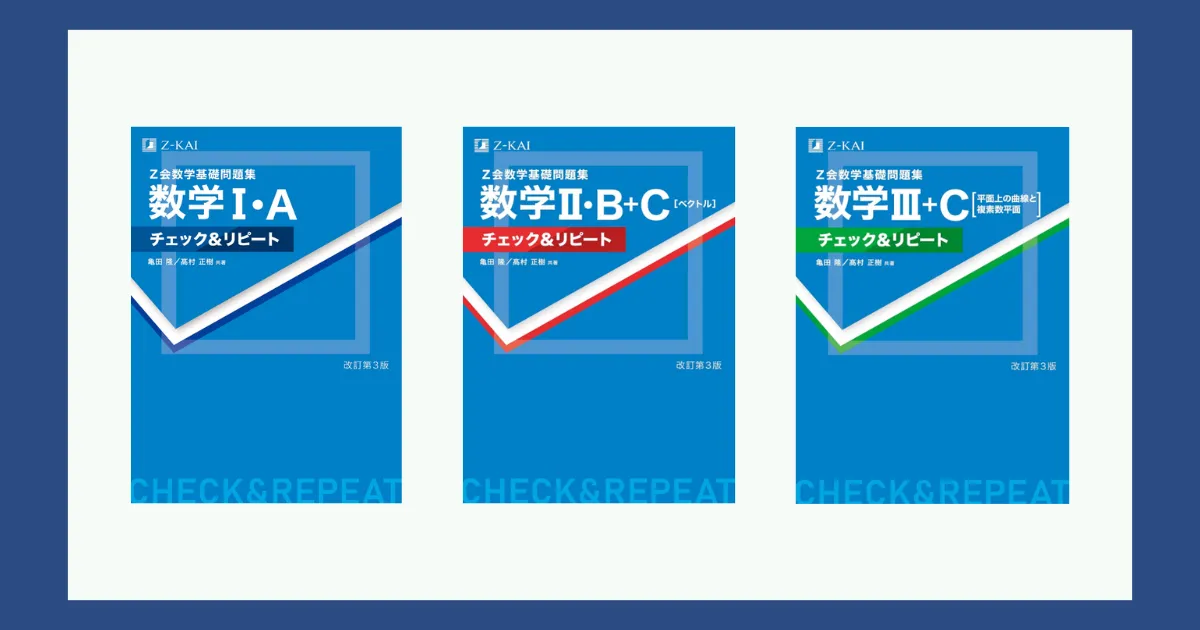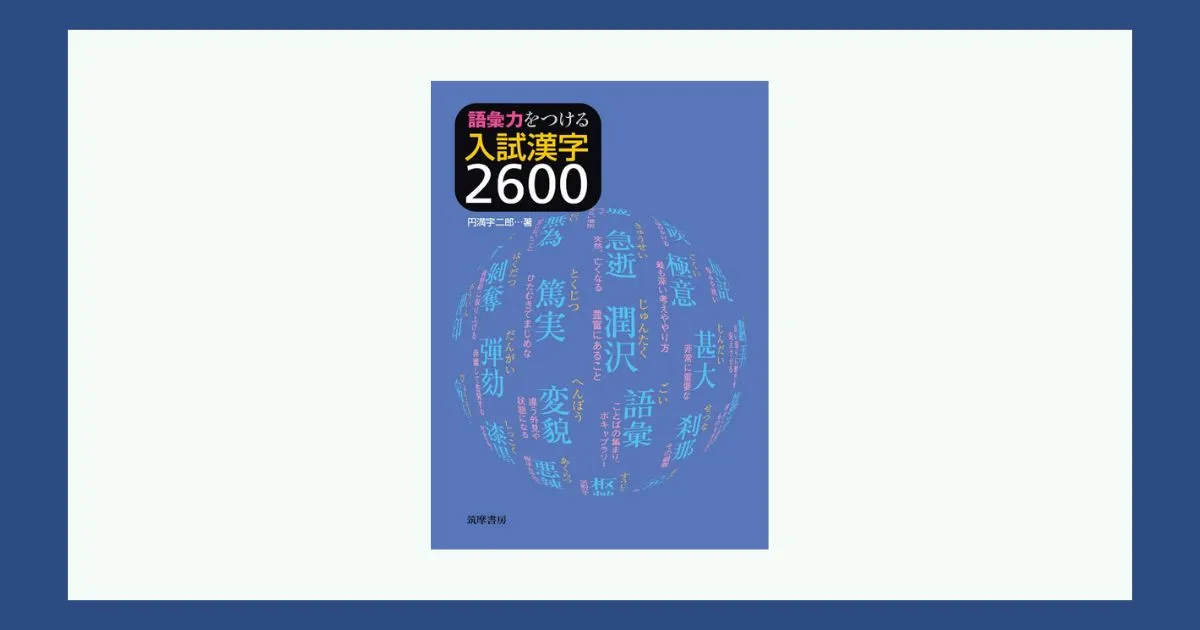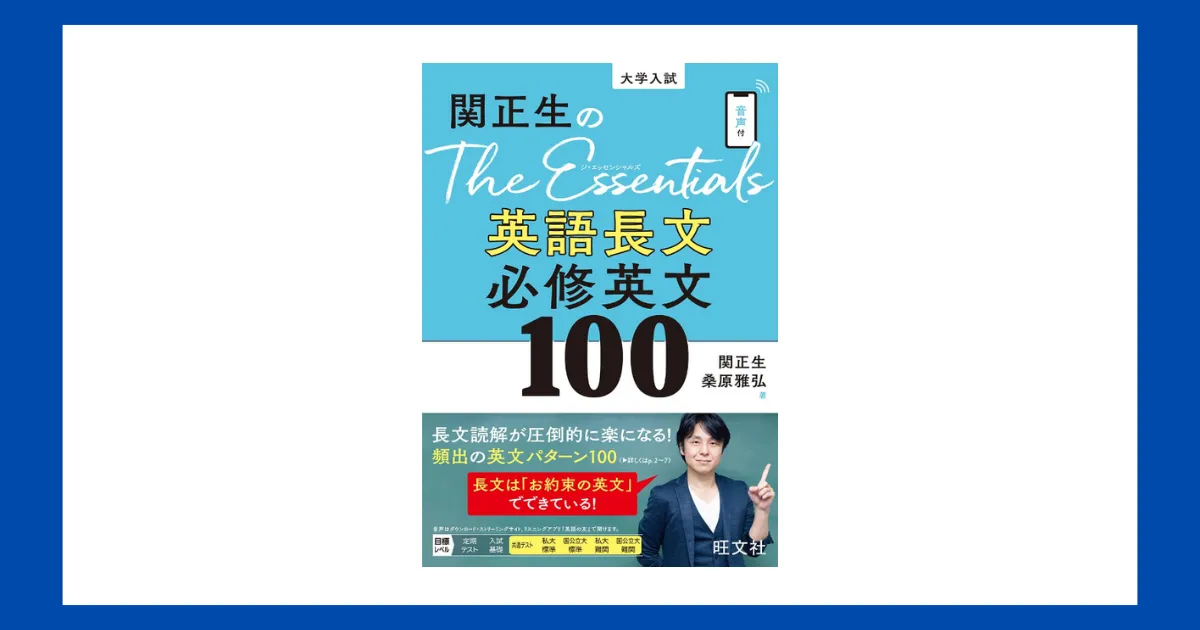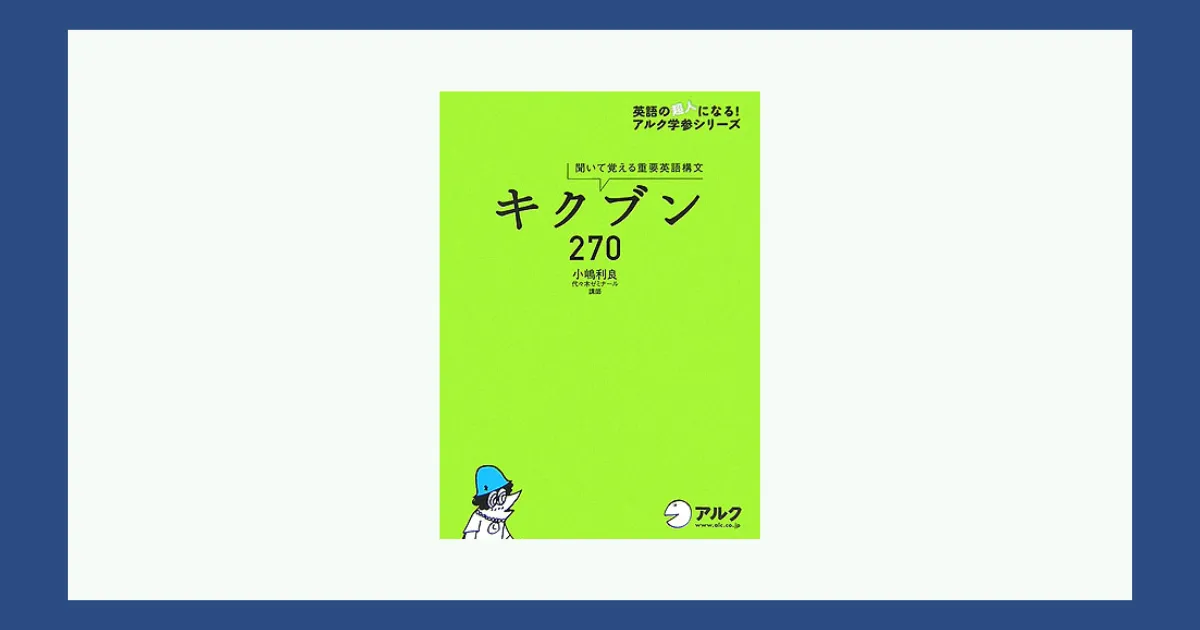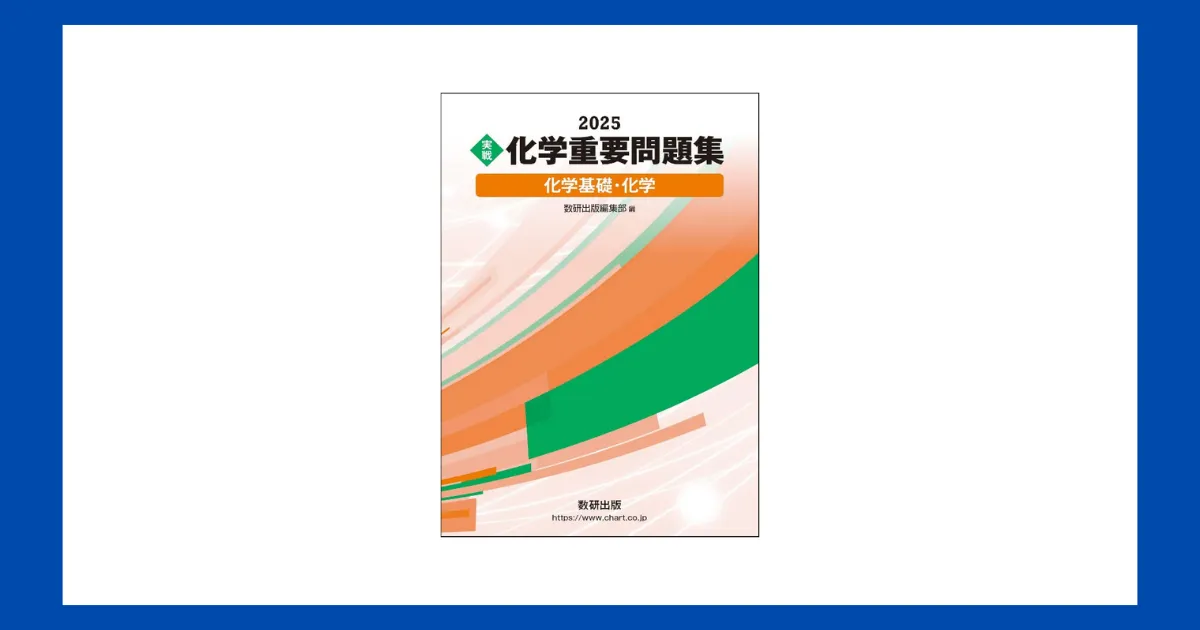| タイトル | 一億人の英文法 | |||||||||||
| 出版社 | ナガセ(東進ブックス) | |||||||||||
| 出版年 | 2011/9/9 1980円 | |||||||||||
| 著者 | 大西 泰斗 | |||||||||||
| 目的 | スピーキングのための英文法 | |||||||||||
| 対象 | 英会話を考える全ての人 | |||||||||||
| 分量 | 688ページ | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| AI | ネイティブの思考を確認する | |||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
話すために必要な英米的発想
本書は2011年にナガセ(東進ブックス)から出版された大西先生らによる話すための文法書です。2011年というとまだまだ学校配布のアカデミックな文法書が全盛期にあった時代にありました。そんな時代に本書は実用英語(英会話)を強く意識した文法書として発売されました。大西先生は本書以前にも『ネイティブスピーカーの英文法』や『ネイティブスピーカーの前置詞』などを出版しており、実用性の低い英語教育に異を唱える姿勢があったように思います。
そんな中で本書は英語系YouTuberの方々に紹介され、おそらくここ数年の文法書で最も売れました。話すための英文法とは「英米的な発想」を手に入れると同義ですから、直接的な英会話のTipsに留まらず、英語学習をしていく上で必須の考え方が詰まっています。それまでにも大人向けなら似たようなコンセプトの英語参考書はありましたが、文法書として一から十まで網羅的に扱っている点が高く評価されたのだろうと思います。実際、話すことを目的にするなら本書一冊さえあれば問題ありません。
さらに本書は従来の文法書にあった文法用語を極力排除し、英語初級者あたりにも取り組みやすいように仕上げてあります。個人的にその方針はそこまで評価していませんが、日本英語の文法用語を軸にせず、ネイティブに倣いながら英語の考え方を身につけるという意味では有用です。ただ、本当に英語初級者が本書から取り組んで力に変えられるかどうか。これは率直に難しいと思います。もちろん、読み物として楽しく読める上に、理解力に優れる人なら役に立つのも間違いありませんが、本書から本格的な英会話に繋がる道筋が明確に示されているわけではなく、英語中級者以上が日本的な英語の捉え方から脱却する目的で使用する方がより良いと思います。
本書の構成と特徴
CHAPTER 0 英文法の歩き方~初めての「話すための英文法」~
PART 1 英文の骨格
CHAPTER 1 主語・動詞・基本文型
CHAPTER 2 名詞
PART 2 修飾
CHAPTER 3 形容詞
CHAPTER 4 副詞
CHAPTER 5 比較
CHAPTER 6 否定
CHAPTER 7 助動詞
CHAPTER 8 前置詞
CHAPTER 9 WH修飾
PART 3 自由な要素
CHAPTER 10 動詞-ING形
CHAPTER 11 TO 不定詞
CHAPTER 12 過去分詞形
CHAPTER 13 節
PART 4 配置転換
CHAPTER 14 疑問文
CHAPTER 15 さまざまな配置転換
PART 5 時表現
CHAPTER 16 時表現
PART 6 文の流れ
CHAPTER 17 接続詞
CHAPTER 18 流れを整える
巻末付録
不規則動詞変化表/数の表現/文内で用いられる記号/参考文献/MEMO
本書は「話すための英文法」と冠しているように、全体を通じて杓子定規な文法事項を話すためにアップデートできるように力を尽くしています。私たちはあらゆる文法事項がどのように会話で用いられているのかを知りません。例えば、基本動詞(go,come,run…etc)にしても、どのような場面で何を考えて使用しているのか。それらの動詞にはどのようなニュアンスがあるのか。助動詞や冠詞、時制にしても文法的な説明は頭に入っていたとしても、説明の通りに表現するだけではネイティブとの感覚に乖離があります。言ってみれば一般的な文法書は「読むための英文法」であり、話すために必要な発想までは解説されていないのです。
例えば go をその日本語訳「行く」で使いこなすことはできません。これでは「人」にしか使うことができないでしょう? 英語の go は日本語よりもはるかに豊かに使われるのです。
[a] I don’t know where the money goes. (どこにお金が消えちゃうのかわかんないよ)
[b] Will these stains go? (このシミ消えるかな?)
[c] This old sofa has to go. (この古いソファ捨てなくちゃ)
go のイメージは,「ある場所から去って進行していく」, その動きです。日本語訳ではなく, イメージに習熟することが基本動詞征服の最低条件なんですよ。
一億人の英文法 P65より引用
一般的な文法書で学んだ知識はまだまだ凝り固まっています。幼少期から海外に住んでいたり、母国語以外を学習した経験がある人を除き、多くの日本人は英語を日本語で理解しようとする、すなわち1対1対応に囚われる段階が誰しもあるわけです。そういった段階も多読多聴によって自然と柔らかい知識にできる方針もあるのですが、本書のように最初から英米的な発想を学んでしまえば時間を短縮できます。大人ほど日本語の環境に染まり切っていますから、柔軟な思考に焦点を当てた方がより良いとも言えます。ここを無視すると、いつまでも日本人の日本語らしい思考の中で納得しようと意地を張ってしまい、挙句に矛盾を抱えて詰まってしまうのです。日本語の発想は捨てること。
本書はそういった知識を一つ一つ英米的な発想で読み解いています。まさに「話すための英文法」に仕上がっているため、率直に英会話を考えるなら“必須の文法書”と言っても過言ではありません。ただ、理屈よりも感覚的な理解(イメージ)に重きを置いているとは言え、文法書なりの情報量(テキスト)の多さ、結局は理屈で理解することを避けられません。中学卒業程度の英語力があれば読み進められると述べられていますが、本書が力になるレベルを考えると、英検2級レベル、かつ英会話を真剣に考える人あたりからになると思います。
英検2級レベル(高校卒業)を土台に
従来の文法書だけではなく、関先生の『真・英文法大全』なども含みますが、本書に取り組む前にそういった文法書で文法を学び、英検2級までの知識を押さえる方針を有力視しています。言い換えると、日本語環境下では第一に日本語で英語を学び、正確なリーディング能力を身につけた後に他の技能を伸ばしていく方がより良いと考えます。本書は文法用語が極力排除されているとは言っても、文法用語も何も知らずに本当に理解できるかは怪しいところです。どちらかと言うと、文法用語で語らないことによって従来の凝り固まった知識に誘導しない意図の方が大きく感じます。
また、他の技能を伸ばしていく際にはライティングなら『読むため書くための英文法ハンドブック』、リスニングなら『リスニングの教科書』あたりが参考書としてはオススメです。もちろん、スピーキングは本書。他方で英検1級やTOEICのスコア更新は必要があれば取り組むべきですが、試験特化の学習が本質的な英語力に結びつかない部分もあります。英検2級は約5000語レベルとされていますから、日常会話においては十分と言えるだけの語彙力を確保しています。英検の有用性はさておき、参考書の充実が勉強しやすさに繋がっています。
そして、土台さえできたらあとは目的に応じた勉強を積み重ねていくだけです。逆に英検2級レベルまでの理解度が低いと、本書の有用性も下がります。英語を日本語で学ぶということは、日本語の理解力=国語力が足りていないとそれもまた効率を下げる要因です。この点については当サイトが謳う高校課程までの学び直し、国語は特に、それ以外の科目であっても思考力の向上には寄与するため、基礎学力が充実しているほど英語学習の効率は上がります。