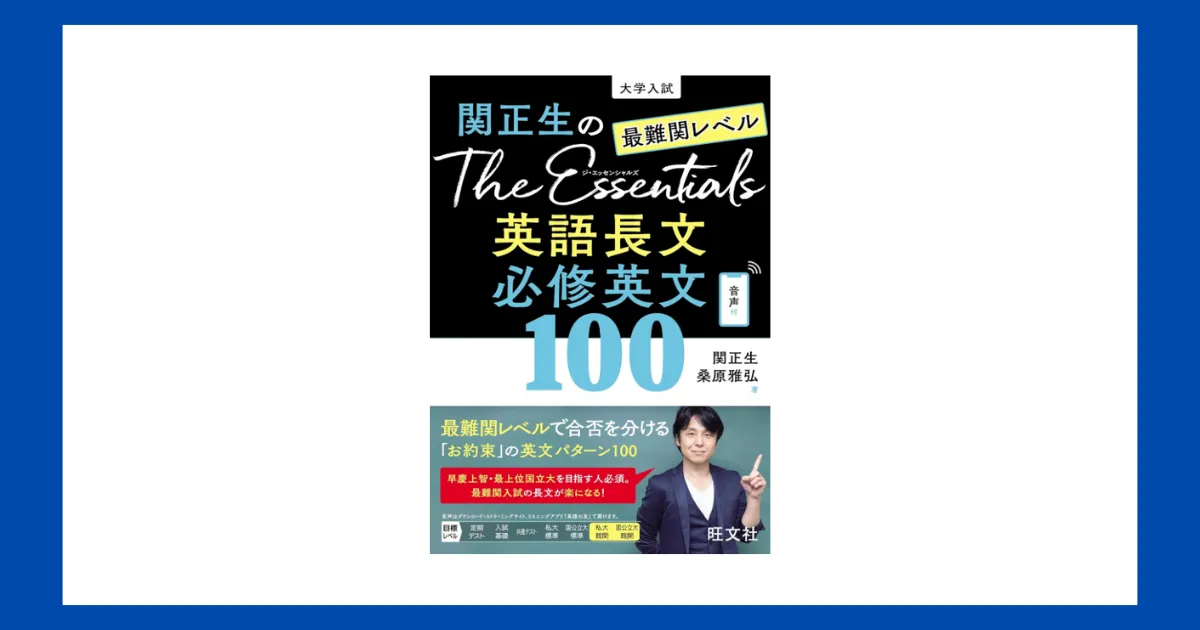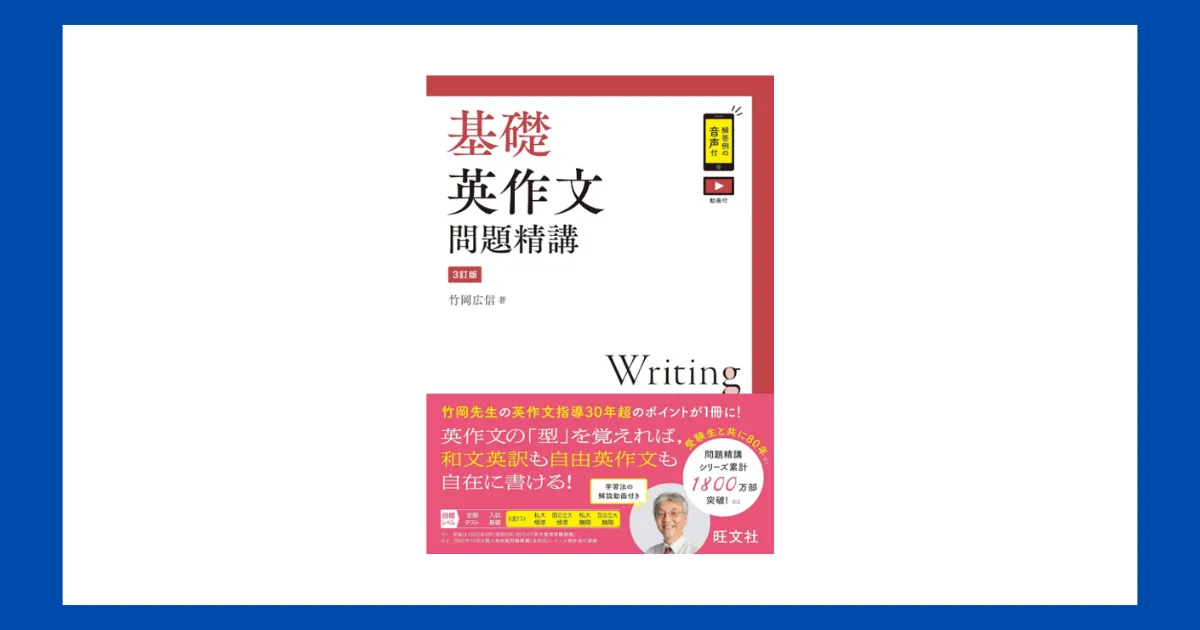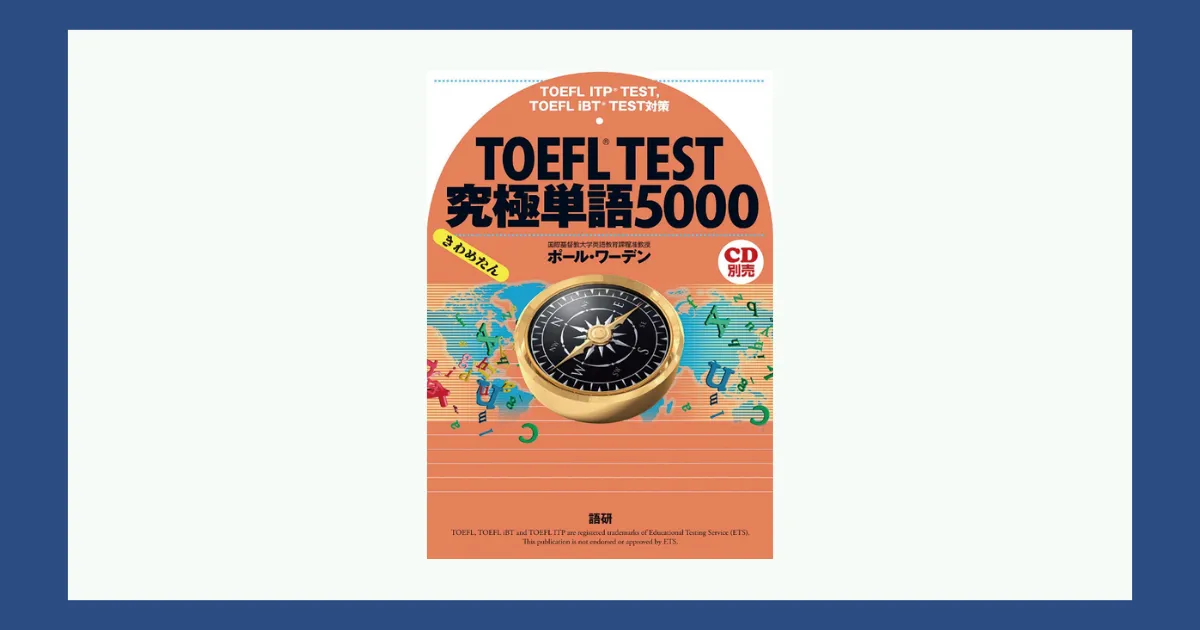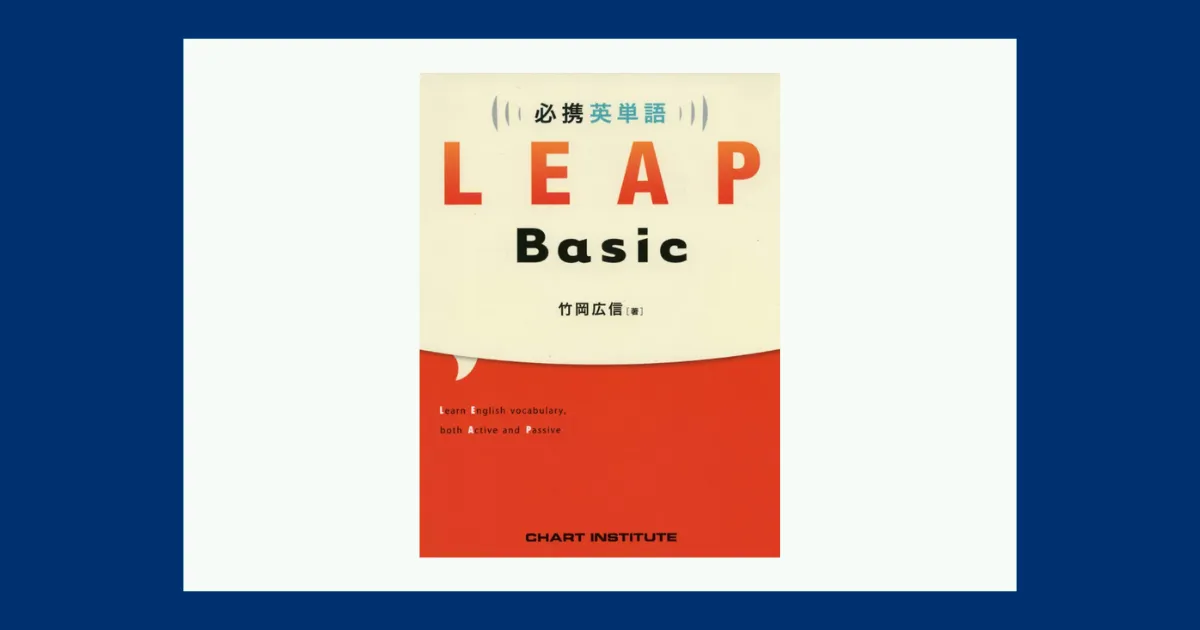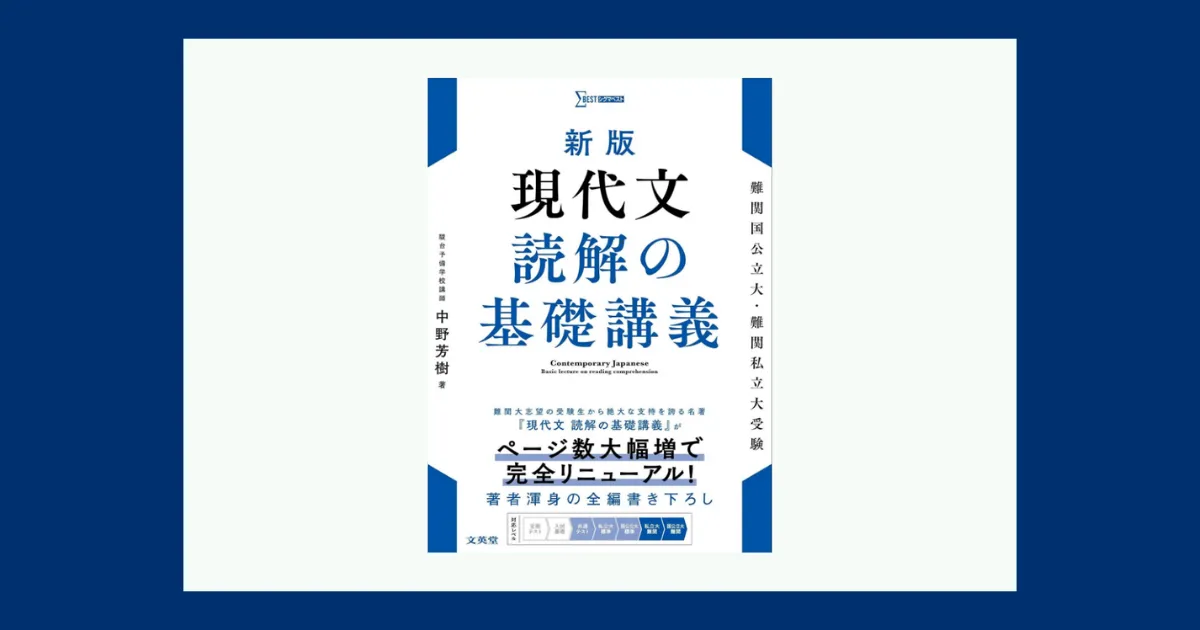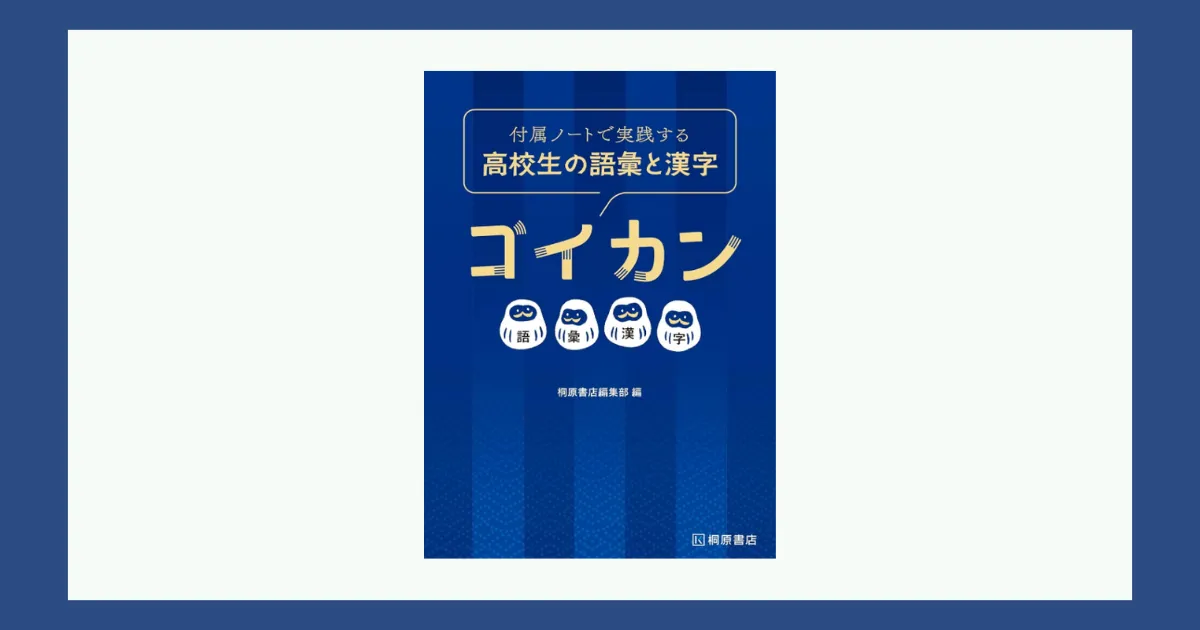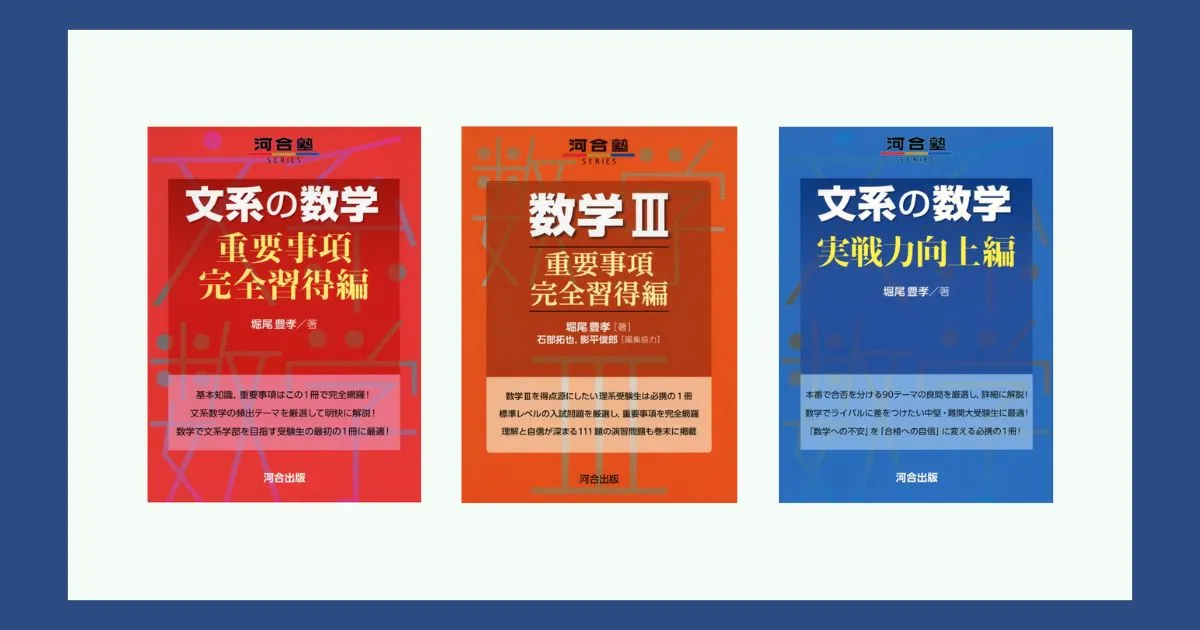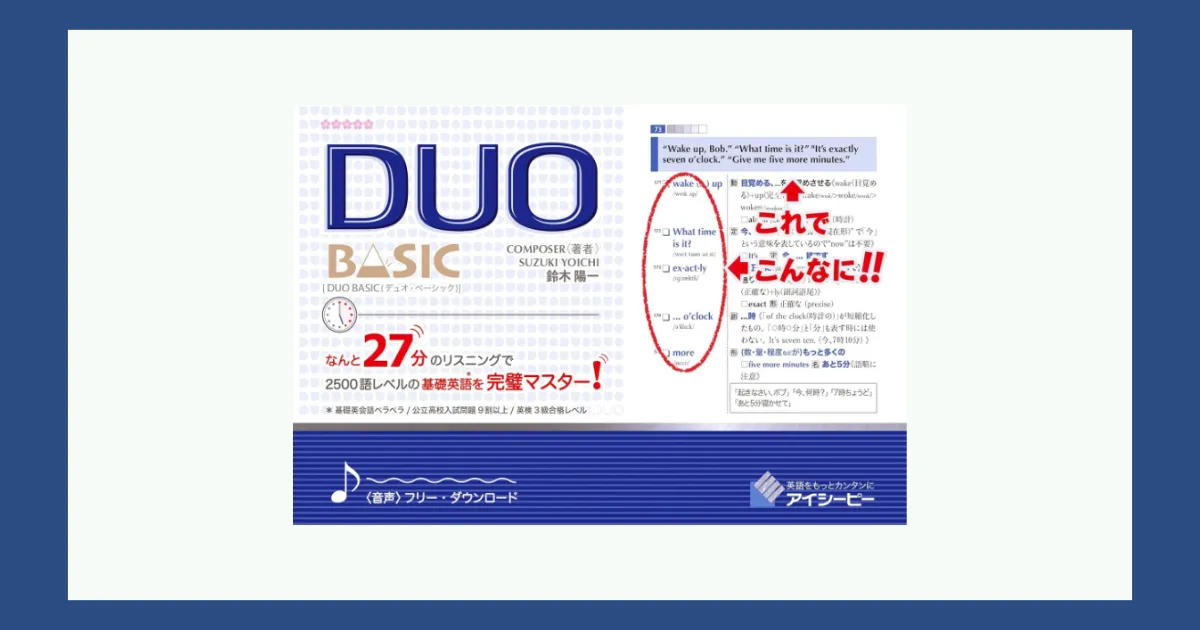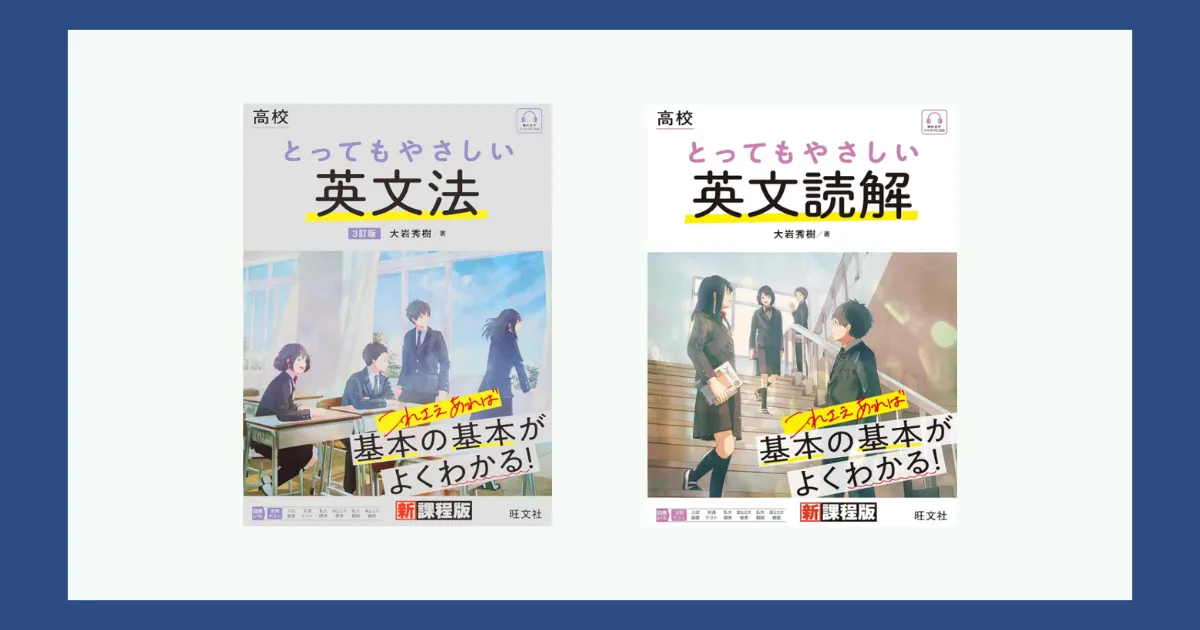| タイトル | 関正生のThe Essentials 最難関レベル 英語長文 必修英文100 | |||||||||||
| 出版社 | 旺文社 | |||||||||||
| 出版年 | 2025/9/5 | |||||||||||
| 著者 | 関 正生、桑原 雅弘 | |||||||||||
| 目的 | 英語長文対策 | |||||||||||
| 対象 | 現役生から大人の学び直しまで 到達:最難関大レベル、英検準1級以上 | |||||||||||
| 分量 | 240ページ | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| AI | 論理構造を決定づける表現の知識を拡張する | |||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
加筆修正の履歴
2026/01/18 英語長文の学習に本書は必要か―冒頭の表現を修正しました。
2025/11/02 誤字を修正しました。
英語長文の読解を左右する表現が多数収録
本書はつい先日出版されたばかりの関先生による英語長文対策の参考書です。本書の無印版は2023年に『関正生のThe Essentials英語長文 必修英文100』として出版されていました。英語長文のための例文集という新しいコンセプトのようですが、一体どのような内容なのか。一言で言うなら「広義のディスコースマーカー集」です。長文で頻出する論理展開を決定づける表現(ex. A is not alone in ~; B)が幅広く収録されています。入試英語学習の観点から言うと、英文解釈のあとに英語長文に取り組みますが、本書は英語長文の前か、途中の段階に新たに取り組む参考書になりそうです。
| 英文解釈 | The Essentials (本書) | 長文読解 | |
| 英文の長さ | 短文 | 短文 | 長文 |
| 目的 | 読み解きにくい英文の読解方法を学ぶ。 | 英語長文の論理展開を押さえる上で必要な表現を学ぶ。 | 英語長文の論理構造を把握し、段落ごとの関係性を理解する。 |
| 参考書の一例 | 『読解のための英文法』 『英文熟考』 『入門英文解釈』 『英文解釈Code70』 …など多数 | 類書がほとんどない | 『英語長文最前線』 『英文読解のグラマティカ』 『パラグラフリーディングのストラテジー』 |
| その他(長文読解に役に立つ表現、ディスコースマーカー) | 一部の英文に含まれている程度 | 広義のディスコースマーカーという意味では多数収録 | 狭義のディスコースマーカー(But, However, Therefore…etc)を押さえながら長文読解の方法を学ぶ |
上記の表は入試英語学習の段階ごとの違いを整理したものです。長文を読むまでの段階を説明すると、第一に英文解釈で短文を正確に読めるようになる必要があります。それまでに学んだ文法知識の読解への応用ですね。様々なパターンの英文が読めるようになったあとは長文の問題集に取り組みます。短文の正確な理解を積み重ねるだけでも読解はできますが、難解な長文になると論理構造が掴みにくくなるため、難関大志望であれば狭義のディスコースマーカーを意識しながら読む訓練として『英語長文最前線』などに取り組む場合もあります。英語長文の問題集で一通りの読解方法を学んだあとは、ひたらす志望校レベルの英文を多読して完成です。
しかし、多読によってパターン化されるまでの量には個人差があり、残りの期間から十分な量を確保できないかもしれません。加えて、多読による新しい知識の獲得や整理は膨大で優先順位が不明瞭になりやすく、確かに“効率的な多読”を考えると取り組み方が難しくなります。そこで本書です。本書はいわば多読によって得られる知識の中から論理展開を決定づける=長文読解で必要となる表現を集めて整理したものです。そのため、単語を覚えるように本書の表現を押さえることで、長文を円滑に読み進められる上に設問の論点にも気づきやすくなります。
本書の構成と解説・表現の一例
本書は6つのChapterと100例文で構成されています。100例文というとまだなんとかなりそうな量ですが、実際は100テーマと関連する表現を詰め込んでいると言った方が誤解は少ないでしょう。その中の1つを紹介したいと思います。以下の引用は「一般論の否定」というテーマから頻出表現である「It is a widely held fallacy that ~」を解説したものです。「fallacy」は学術的な文脈で使用される(入試英語では)難単語に分類されますが、実際にどういう形で使われるかをしっかりと押さえている人は少ないかもしれません。
[一般論の否定→主張]
fallacy「誤謬」は「多くの人は本当だと考えているが, 実際には間違った考え」ということです。「一般論」の合図になり, 「多くの人は~だと信じているが, 実際は違う」のような展開でよく使われるのです。
holdは元々「~を抱きかかえる」で, 「考えを抱く」→「考える・思う」という意味があります。It is a widely held fallacy that ~ で「~は広く信じられている誤解だ」となります (Itは仮主語, that ~ が真主語)。
関正生のThe Essentials 最難関レベル 英語長文 必修英文100 P26より抜粋
狭義のディスコースマーカーから読解を試みることは当然必要ながら、難関大になるほど設問に直接的に絡むことが少なくなります。せいぜい接続詞の空所補充で問われる、パラグラフの関係性を問う意図で間接的に用いられるくらいです。その点で「It is a widely held fallacy that ~」という表現は広義のディスコースマーカーとして様々な文脈で用いられています。最難関大が出題する硬質なテーマとの相性が良く、狭義のディスコースマーカーだけでは見抜けない論理展開を正確に押さえるために必要な知識になっています。
「一般論」の合図になる重要表現
myth, superstition 「迷信・俗説・作り話」/ stereotype・a fixed idea・view 「固定観念」/ fallacy・misconception 「誤解・誤った考え」/ assumption 「思い込み・推定」/ a widespread belief 「広まった考え」/ a widely accepted view 「広く受け入れられている考え」/ a dominant [prevailing] idea 「主流の考え」/ conventional wisdom 「広く受け入れられている賢見・社会通念」/ It is commonly held that 〜・It is generally assumed that 〜 「〜だと一般的に考えられている」/ It is widely accepted that 〜 「〜だと広く認められている」
関正生のThe Essentials 最難関レベル 英語長文 必修英文100 P27より引用
言い換えると、英語長文には型があり、こういった表現の数々によってパズルのように論理構造が明確化します。テーマに基づく単語を押さえるように、これらを把握していたら読解速度は確実に上がります。逆に言うと、2つ、3つのアプローチで正答を導ける配慮こそあれど、最悪の場合は一つの知識を知らないだけで全く逆の意味だと誤解することもあります。知らない表現にいちいち手を止めてしまうと長文読解どころでもありません。
他方で広義のディスコースマーカーと言い表しましたが、テクニック的なものではなく、長文を円滑に読み進めるための表現集という認識がちょうど良いと思います。結局は表現を覚えた上での多読は欠かせません。それと本書には今までに覚えた単語の新たな一面を知れたり、将来英語論文を書く際に役立つ表現を覚えられたりと副次的な効果も大きいです。この意味では大人の学び直しにも大いに推奨できるもので、TOEFLや英検準1級以上などにも活かせる知識が詰まっています。これは以前に紹介した『速読速聴・英単語 Opinion1100 ver.2』に近いものが含まれており、例えば、Chapterの最後には「様々な議論表現①~③」として「相手の意見を聞く重要表現」や「自分の意見を伝える」「賛成・同意を伝える」重要表現などが多数収録されています。
英語長文の学習に本書は必要か
結論から言うと、必要になってしまったと思います。英語は年々難化する予想が多く、本書の有無によって長文読解においての差が無視できないからです。その差とは、読解速度と質です。現代文的な国語力が高ければ、英語長文も同様の視点から理解を深められますが、そうではない人はどうしても単語の意味を知っているかどうか、英文の意味がわかったかどうかばかりに囚われてしまって「英語長文」を正しく解くことができない気がします。
また、本書を長文読解で要求される力の一部を分離した参考書と考えると、長文をよりシンプルに捉えられるようにもなります。英文解釈の長文版のような。個人的には「長文の基礎固め」という概念が確立したような感覚です。ディスコースマーカーの参考書を除いて、多くの英語長文は問題集の側面が大きく、それで事足りると考えられていたとも言えます。AIによって知識を拡張する起点としても、類書がなかなかないだけに優秀な位置づけです。特に『無印版』がちょうど良い層は競争相手のレベルからして差をつけられる可能性は高いと思います。例文が一覧でまとめられており、それによって音声も使いやすい。
本書を単なる表現集と簡略化して捉えたら活用の仕方も難しくありません。『英単語最前線2500』のPART.7に近いイメージ。一般的な入試英語の学習では見落としてしまう知識を網羅できるので必然的に価値は高くなります。しかし、現実に『無印版』は推奨できるとしても、最難関レベルの本書は相当人を選びます。誤解を恐れずに言えば、最難関大の英語で満点を狙うための参考書と言っても良いのではないかと感じています。実際の試験では満点も全訳も必要ないでしょうから、まずは過去問を解いてどこまで通用するのかを確認したあとに本書の導入を検討してほしいと思います。