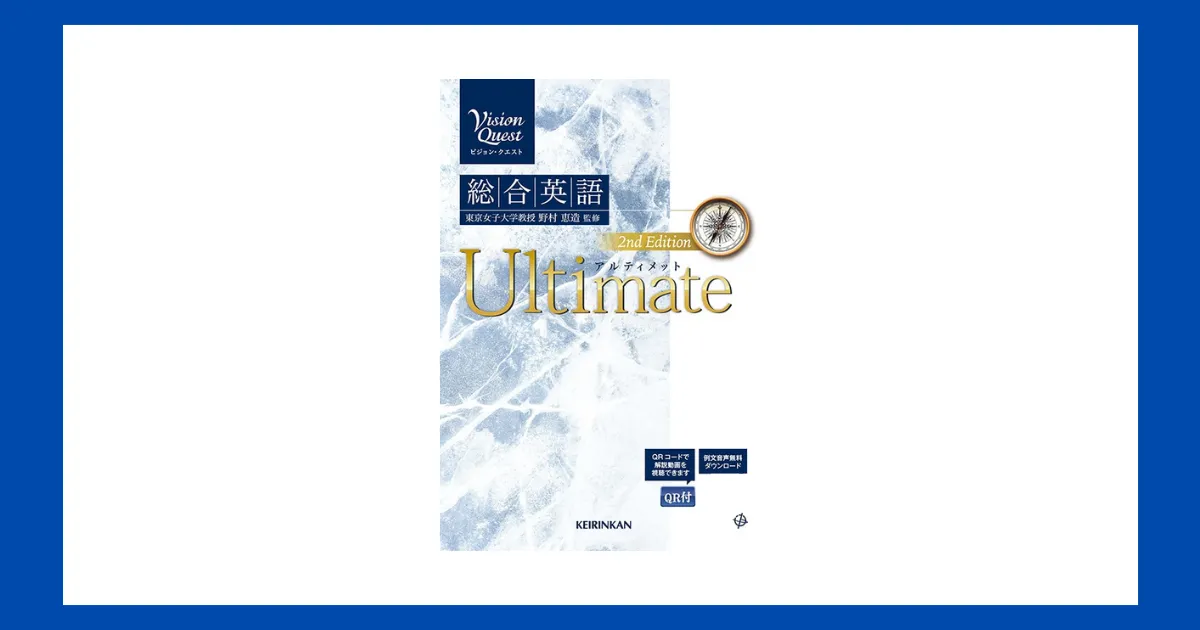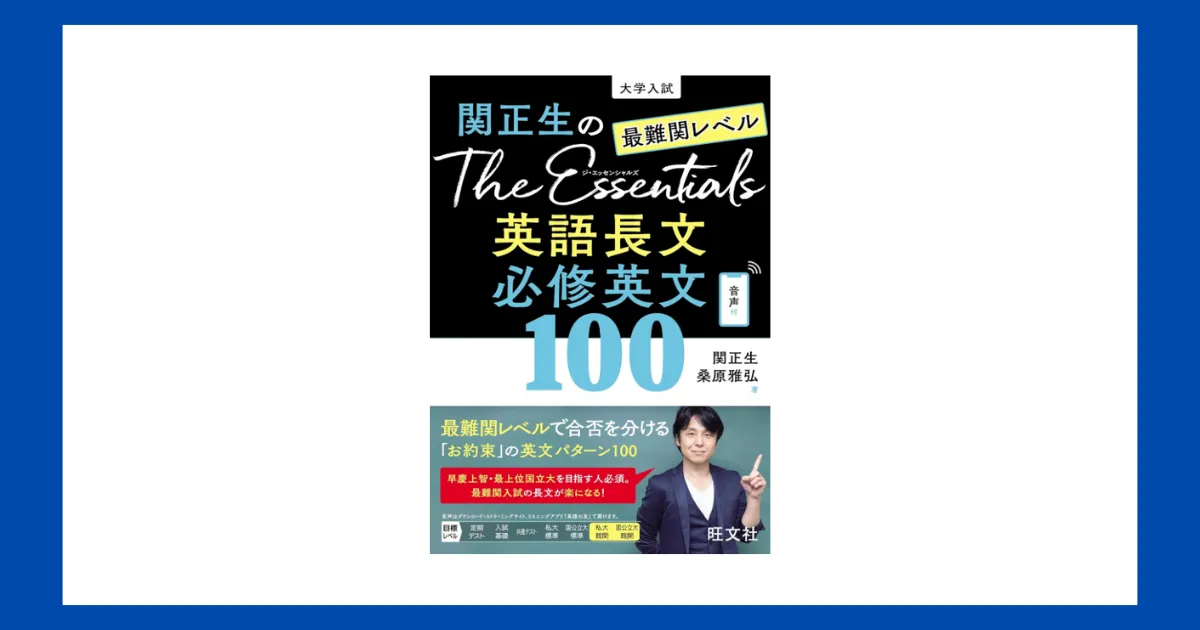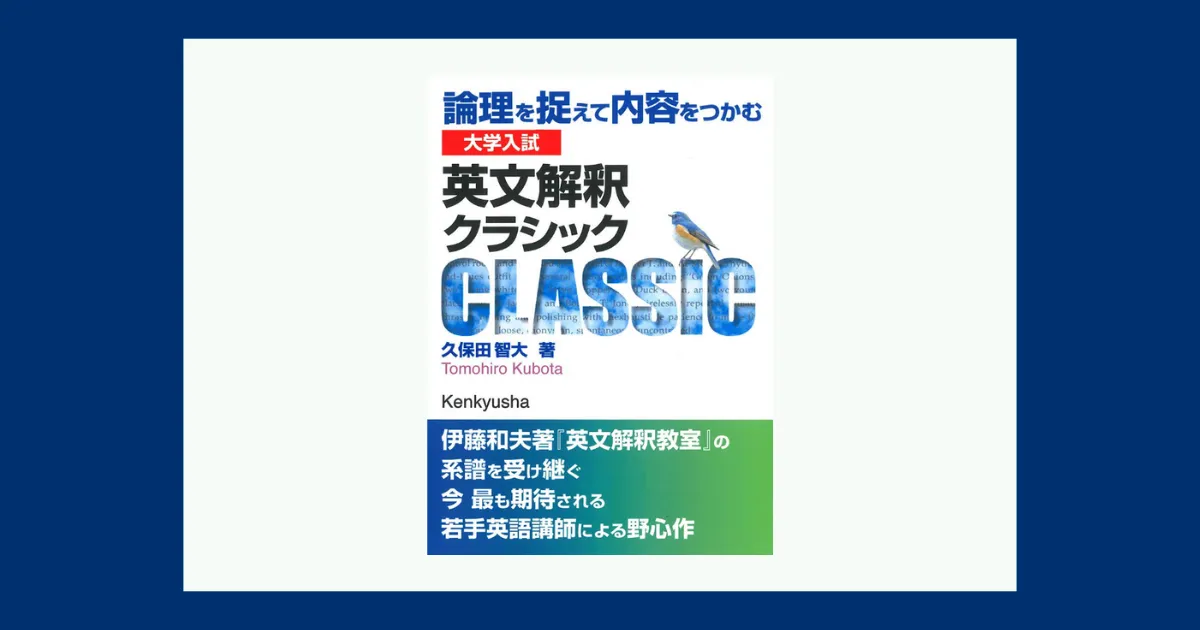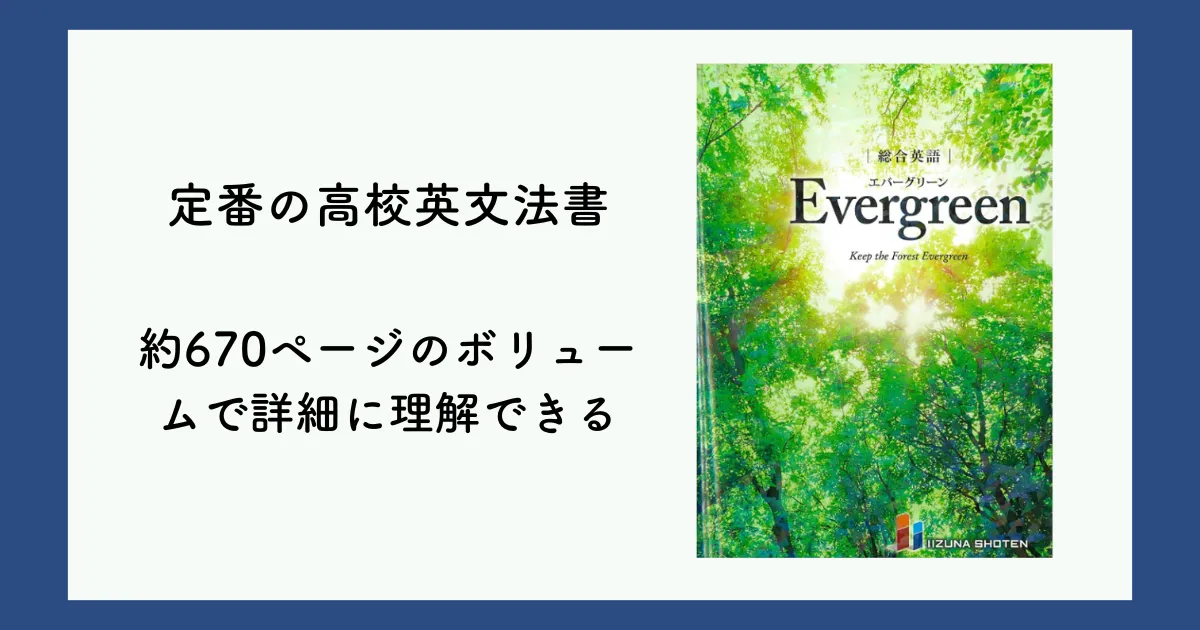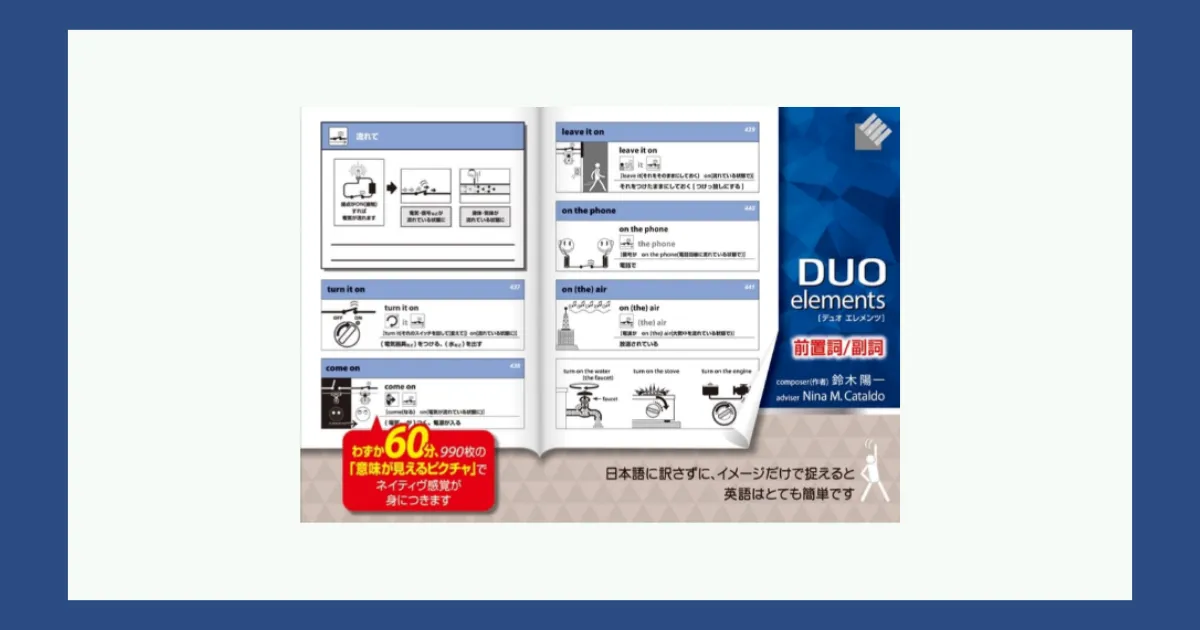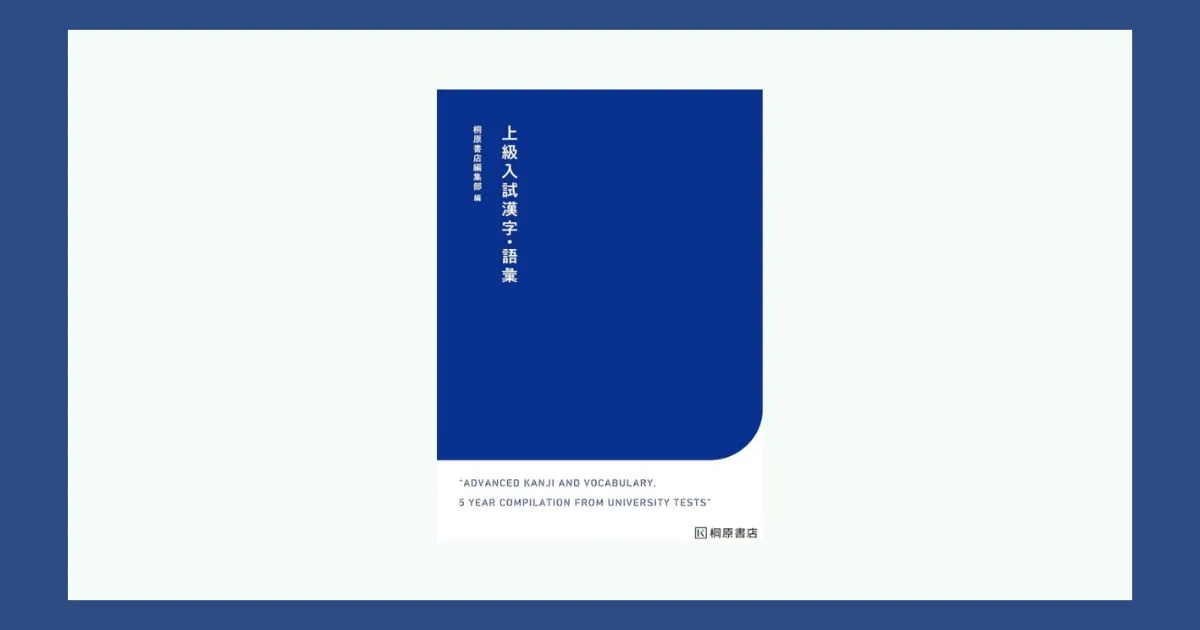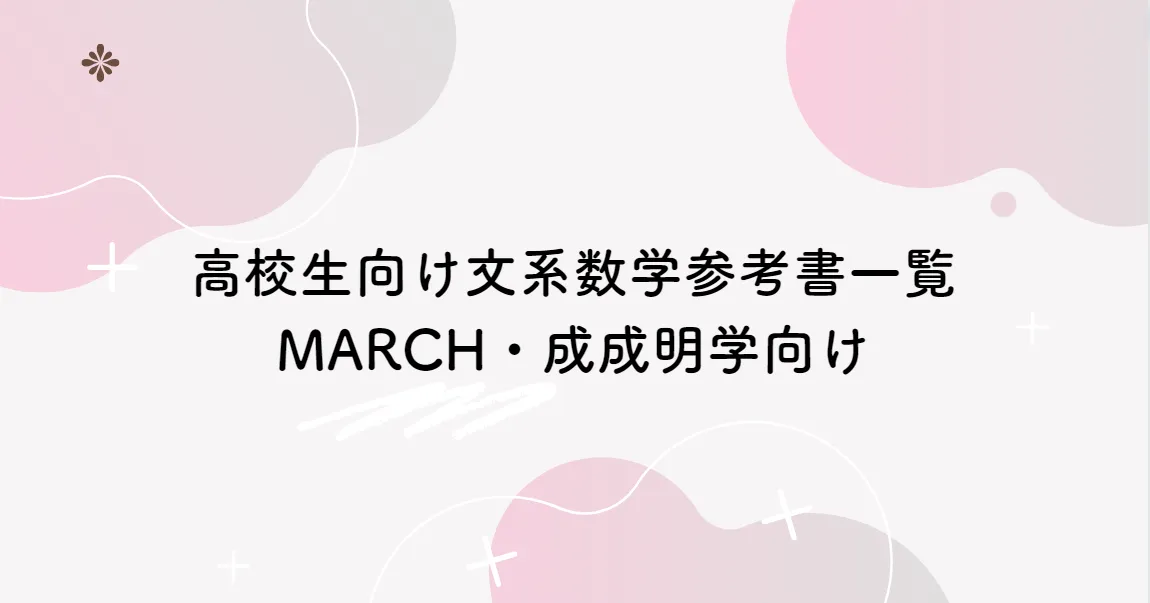| タイトル | 大学入試 英単語最前線2500 | |||||||||||
| 出版社 | 研究社 | |||||||||||
| 出版年 | 2023/4/25 | |||||||||||
| 著者 | 石橋 草侍、里中 哲彦、島田 浩史 | |||||||||||
| 目的 | 難関大英単語対策 | |||||||||||
| 対象 | 難関大志望の受験生から大人の学び直し | |||||||||||
| 分量 | 372ページ | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| AI | 現代的なテーマに関連する単語を増やす | |||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
加筆修正の履歴
※本記事は公開以降、内容に変更はありません。
最新の入試傾向を反映した難関大向け英単語
本書は2023年に研究社から出版された難関大向けの単語帳です。明確に難関大対策を謳う単語帳は意外と数が少なく、有名どころでは『速読英単語[上級編]』『大学入試英単語 SPARTA3』『大学入試 無敵の難単語PINNACLE 420』『鉄緑会東大英単語熟語 鉄壁』あたりでしょうか。難単語の多い早慶向けにはいまだにTOEFL向けのものが推奨されることもあります。なぜ少ないのかというと、難関大の難単語対策というのは学部別にテーマが異なりますから、難単語を満遍なく押さえる意義というのはどうしても希薄になりやすいからです。第一に過去問による対策が優先され、その後は頻出テーマに関連する単語を覚えていく方針が有力視されます。
その中で難関大対策をするとすれば、それまでに覚えた必修レベルの単語の多義性と横断的に出題されるテーマの難単語をまとめることです。そして、その数というのは必然的に少なくなります。だいたい1000~1500語が難関大の重要単語として定義できる限界だと考えます。本書のコンセプトは難関大対策として非常に理にかなっていますが、2500語+頻出テーマの背景知識の全てを押さえるかどうかは考える必要があります。PART5「多義語」までの1389語なら問答無用で押さえるべきです。
PART6以降は本番の試験では注釈が入るものもあり、本書の難関大の定義「国公立二次試験、早慶上智、GMARCH、関関同立、私立大医学部など」が良くも悪くもテーマを分散させてしまっています。特に私立大医学部をはじめ、人によって志望する学部から遠くなってしまうであろう専門用語の数々が気になりました。ただ、そういった面の優先順位を考えられるなら、1389語からさらに欲張った難単語を網羅できる魅力が本書にはあります。PART7の「頻出テーマの背景知識」もテーマに強く関連する英単語に触れられる点は想像以上の効果があると思います。
本書の特徴
発音記号と一緒にカタカナ発音表記があります。最近は日本人向けの単語帳ならこの形式が最もわかりやすいと感じています。英英学習以降なら発音記号のみが理想です。
一般的な単語帳は頻出する品詞と意味の一語一訳が主流ですが、本書は「charge」なら「名詞:①料金、②担当、責任、③罪、非難」「動詞:①…を請求する(for)、②…を告発[避難]する」と語義情報が並び、ひとつずつ例文が付属しています。この辺が単語の運用力を要求する国公立向きと考える根拠です。PART2とPART4では難関大で狙われる単語の語法情報も扱われています(合計510語)。
尊厳 (dignity) をもって, しかも自然な死を迎えたいと誰もが思っている. そうしたなかでの末期医療はどうあるべきだろうか. 末期の病 (terminal illness) にかかっている患者の介護人 (caregiver) の重要な仕事のひとつは, 生死の決断 (life and death decisions) に関するものである. 自己決定権 (right to self-determination) が重要であることは疑いがないが, 病気が進行するにつれて, 患者は話し合ったり, 判断したり, 願望を表明したりする能力をますます失っていく.
大学入試 英単語最前線2500 P255より引用
これはPART7の「頻出テーマの背景知識」にある「末期医療」からの引用です。このように日本語と英語でテーマが解説されているので、国語的に理解しながらテーマに強く関連する重要単語も押さえられるようになっています。生死の決断 (life and death decisions)などは直感的にも理解できますが、こういった表現をできるだけ押さえておかないと見慣れない名詞句があるたびに足を止めてしまいかねません。テーマの迅速な把握にも役立ちます。英語のテーマは現代文から流用できるものも多いので、今ならAIで現代文的なテーマを英訳するのも有効です。ただし、本書は2023年出版でまだまだ現代的なテーマを扱っているとは言え、年々古くなっていく点は注意が必要になります。
速読英単語[上級編]・鉄壁との比較
難関大対策として過去問の多読多聴を優先しながら2冊、3冊と単語帳を増やすことは難しいので、現実的に難関大対策には1冊を追加する程度になるでしょう。その1冊は過去問の多読多聴を少しでも円滑に行うための下地です。そこで難関大対策を行える本書と速読英単語[上級編]、鉄壁を少し比較してみたいと思います。
| 最前線2500 | 速読英単語[上級編] | 鉄壁 | |
| 見出し語/収録語数 | 2500/*4000 | 1255/*2300 | 2176/*3000 |
| 難易度 | 入試標準~発展 | 入試標準~発展 | 入試基礎~標準 |
| レイアウト | |||
| 利便性(音声など) | 英語のみ 英語+日本語 | 英文の音声 単語の音声 | 英語+日本語 |
| その他 | PART7のキーワードは全部合わせて1500語くらい | 派生語・関連語が充実し、多読多聴をしながら単語を学べる | 派生語・関連語、語法、熟語も充実 |
まず、速読英単語は必修編第8版の極めて高い完成度であれば話は変わりますが、2023年出版の[上級編]は純粋に単語を覚えるという意味では他2冊に比べると少し弱い部分があります。ただ、速読英単語[上級編]は最新版(第5版)と第4版、第3版、第2版(+初版)の英文が大きく差し替えられているので、複数冊で多読多聴しながら難単語を覚える方針も選択できます。特に第2版(+初版)は大部分が早慶の英文を取り扱っている稀有な仕様です(50/73)。難単語に関しては一語一訳の覚え方でも問題ないのですが、最低限どんな使われ方をしているのか、単語から例文(フレーズ含む)を1つ思い浮かべられるとより良いと思います。どちらかと言えば、私立向きです。
一方、鉄壁は全体的な語彙レベルが他2冊よりも易しい分、熟語も含み、派生語・関連語の取り扱いの多さから運用力に重きを置いています。頻出する品詞と意味の一語一訳だけでは見落としてしまう、それでいて難単語は少し控えめな東大をはじめとした国公立向きです。単語を覚えるのではなく、単語をより深く知りたいときに使う単語帳。個人的には難易度が近く音声も使いやすい『速読英単語[必修編]』を推奨したくなりますが、熟語を含み、国公立入試に必要な知識を得やすいのはまだまだ『鉄壁』かもしれません。
そして、本書は2500語の網羅性から派生語・関連語もそれなりに扱い、類書にはあまりない多義性に焦点を当て、難単語の取り扱いも豊富ということで総合力では最も優れていると思います。英文の難単語はランダムに選ばれているわけではなく、硬質なテーマに関連する単語が難しいということに過ぎません。現代文と同じ。だからこその多読多聴ではあるのですが、本書のテーマとキーワードの解説を例にしながら整理できる副次的な効果は意外と無視できないかもしれません。AIによって同様の構成で整理すれば、読んで解いて終わりにしない理想的な多読多聴を行えます。
当サイトでは高校英語の重要単語を手早く押さえるために『DUO3.0』を、多読多聴兼単語の復習として速読英単語を推奨していますが、最難関大志望なら多義性と難単語、テーマに焦点を当てた単語帳として『DUO3.0』のあとに本書を使用しても良いかもしれません。ただ、ほとんどの大学は『速読英単語[必修編]』と多読多聴で十分に足りますし、入試基礎~標準の重要単語が疎かになってしまうくらいなら手を出さない方が無難です。もちろん、使い方次第ではあるのですが、本書の分量からはどうしても慎重に選ばざるを得ず、現実的に早慶(一部の外大含む)以外、あるいは難化を加味した旧帝大、医学部以外は必要ないと言った方が良いのかもしれません。