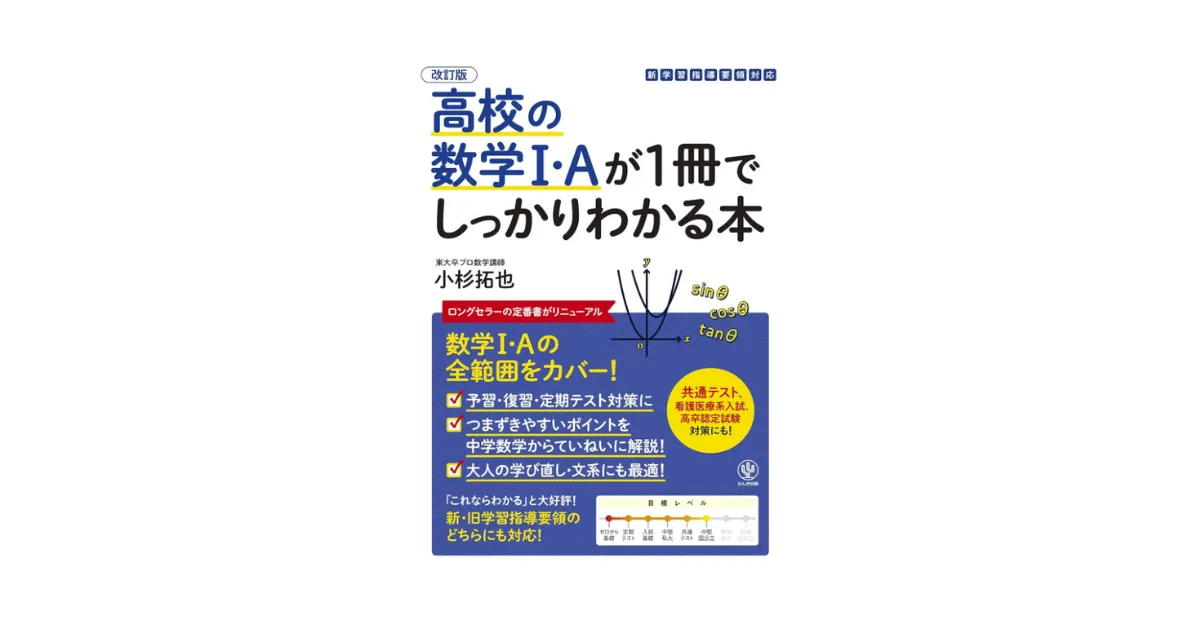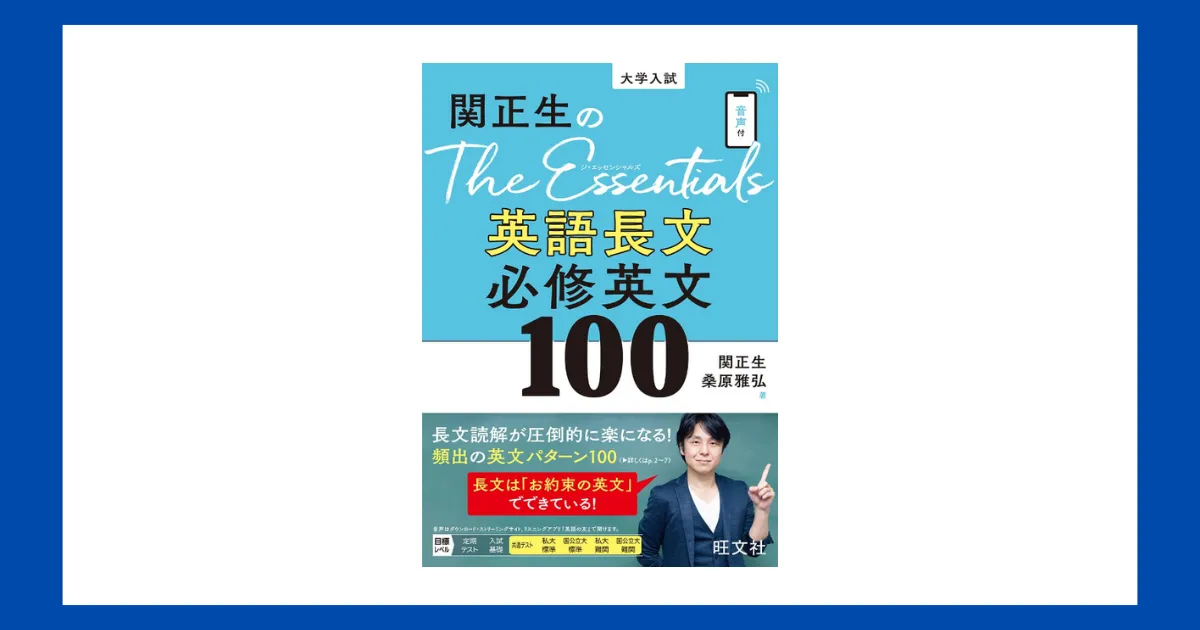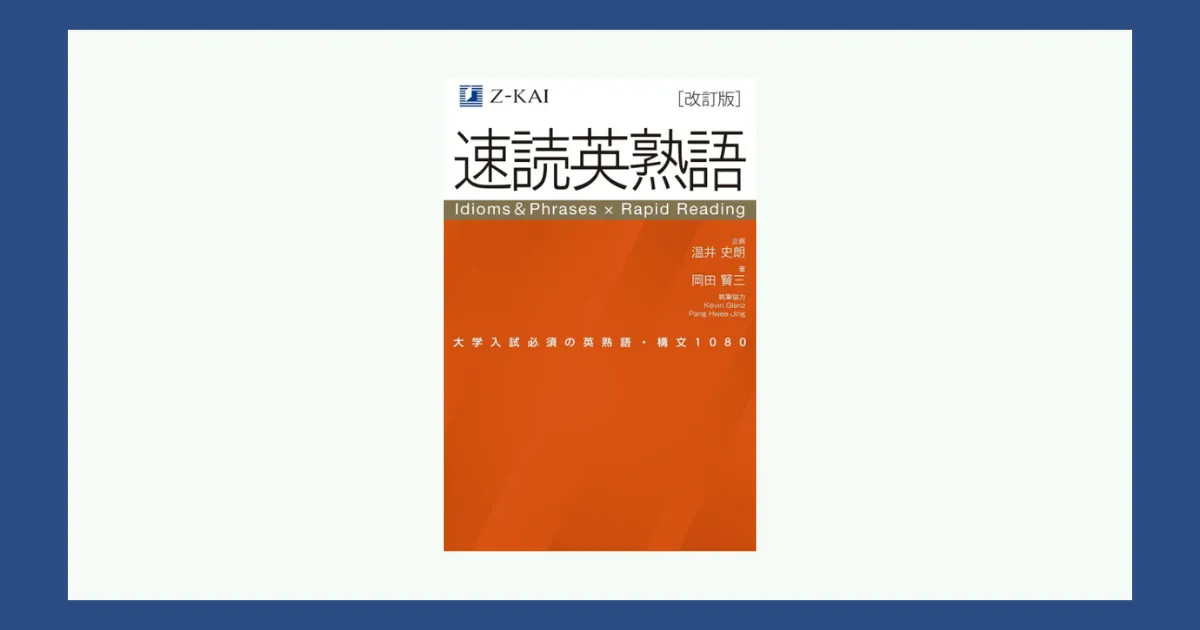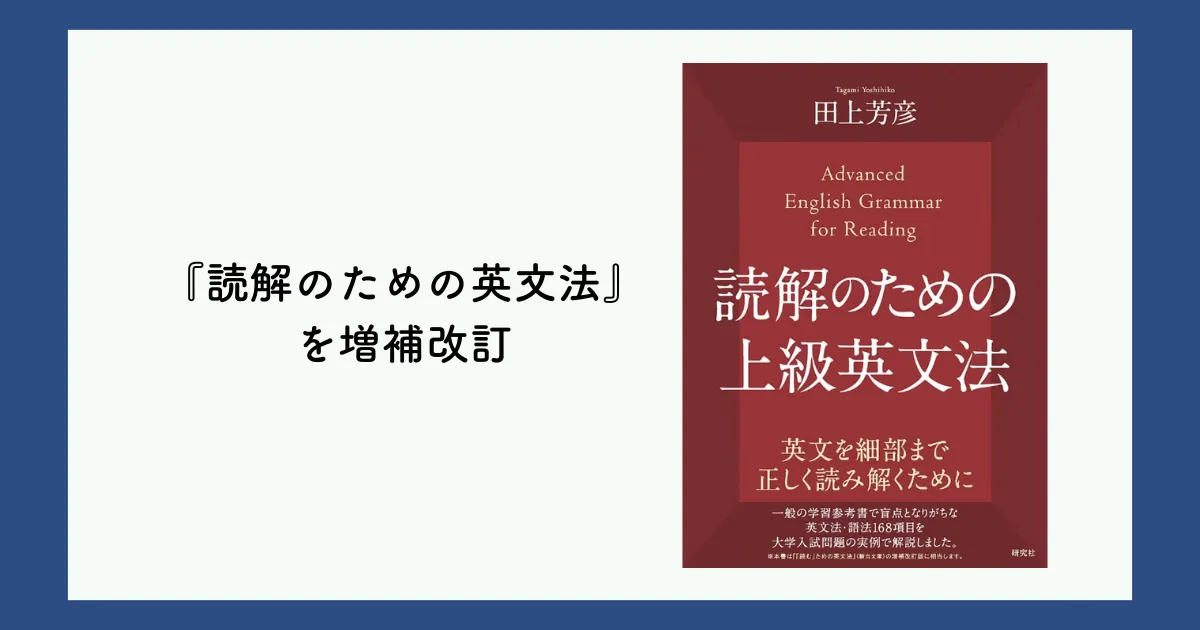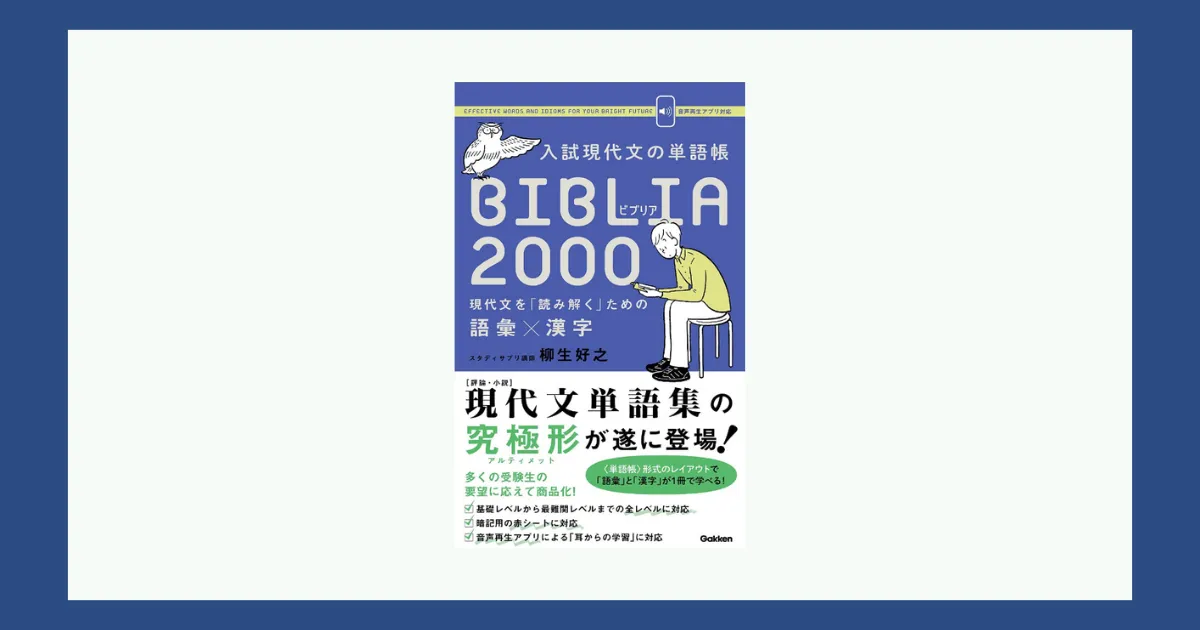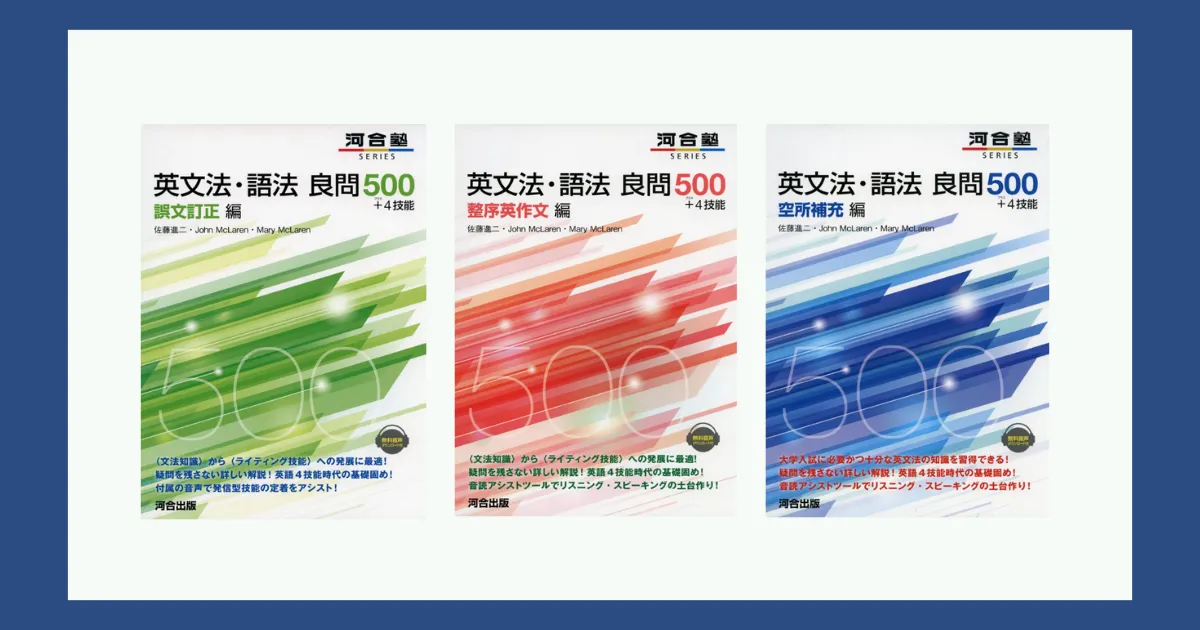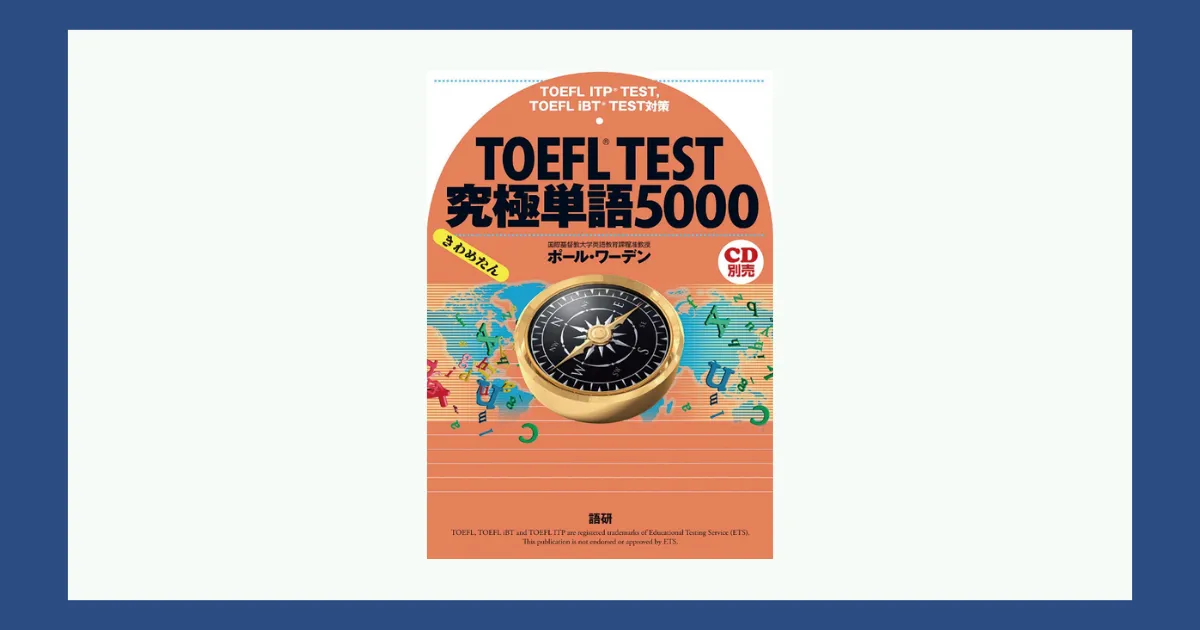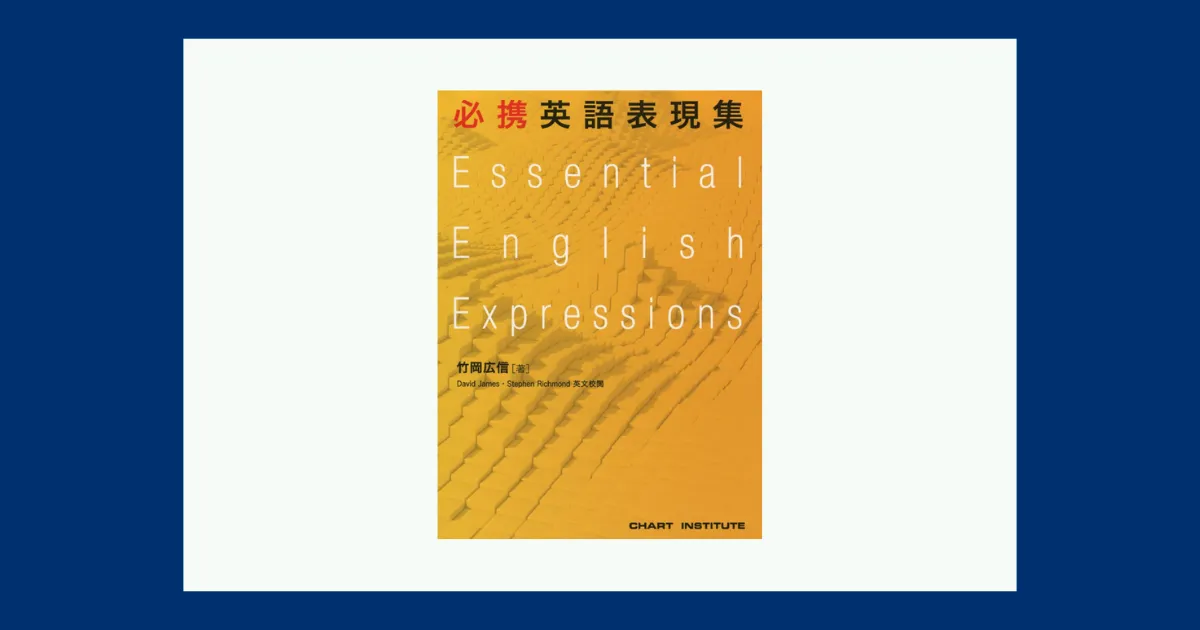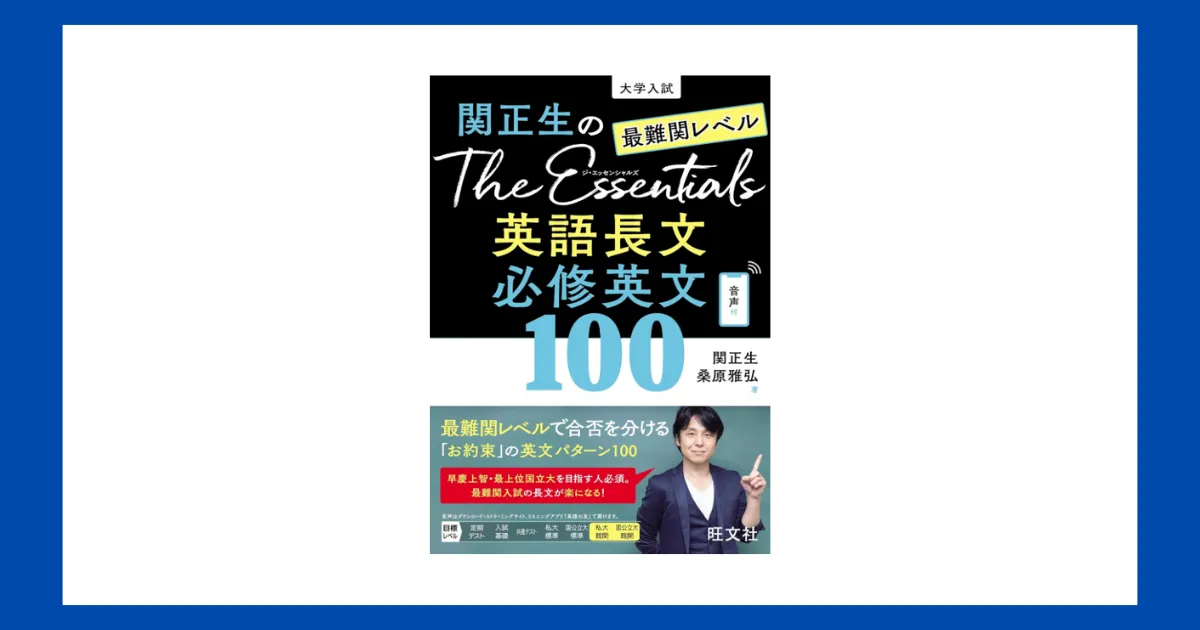| タイトル | 改訂版 高校の数学I・Aが1冊でしっかりわかる本 | |||||||||||
| 出版社 | かんき出版 | |||||||||||
| 出版年 | 2022/2/9 | |||||||||||
| 著者 | 小杉 拓也 | |||||||||||
| 目的 | 高校数学の教科書基礎を固める | |||||||||||
| 対象 | 現役生から大人の学び直しまで | |||||||||||
| 分量 | 192ページ B5サイズ | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| AI | 用語の例文を生成 | |||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
加筆修正の履歴
2025/11/23 誤字を修正しました。
教科書の基礎だけ凝縮した一冊
本書は小中学生の算数・数学の参考書で有名な小杉先生による高校数学の入門書です。小杉先生の小学算数と中学数学の参考書はわかりやすいと定評があり、当サイトでは高校数学を理解するにあたり、中学以前の知識の動線として『小学校6年分の算数が教えられるほどよくわかる』と『中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる』を推奨するに至っています。本書「しっかりわかる」シリーズは主に基本的な概念や用語、計算、解法をまとめた参考書になっています。基本的な計算と解法を定着させる『中学校3年間の数学が1冊でしっかりわかる問題集』もあるので、小学算数と中学数学に関しては小杉先生の参考書に頼り切っても良いと思います。
なぜ、本書を取り上げたのか。理由は2つあります。1つは小杉先生のわかりやすい解説が高校数学でも変わらず力を発揮していたからです。中学数学よりも明らかに難しい高校数学は躓く人が多く、基礎の基礎から丁寧に理解することが求められます。分量の少なさも魅力。もう1つは入試問題への意識が高い『入門問題精講』に比べて、本書の方が中学復習を念入りに含んでいる分だけさらに易しく、教科書の用語や計算の基本もメインに扱っています。『入門問題精講』は教科書の代替として機能するほどの解説と問題が長所ですが、それは曲がりなりにも授業を受けていた現役生にとっての話であり、例えば中卒・高校中退から高卒認定を目指す人や看護学校、短大、その他専門学校の入試で数学IAが必要な人、数学がとにかく苦手な人、学生時代に全く勉強していなかった人が高校数学を一から学ぶなら本書の方が易しく感じられると思います。
ただ、本書の到達点は高くないため、大学受験を想定する場合は最初から『入門問題精講』への接続を考え、理解の部分は学校の授業やスタディサプリ、YouTubeなどで補完する方が効率は良いでしょう。もちろん、本書で入念に基礎から確認するのもありです。本書の利点は用語と計算、基本問題が一通り押さえられているため、本書を終えられたときにはそのまま看護学校や短大の入試に対応できることにあります。
本書の構成
本書の範囲と問題のレベルは高校数学の教科書と同じ、教科書の基本例題のみに絞ってある印象です。高校数学は教科書のシリーズによって難易度に差があるのですが、数研出版で言うところの「新編シリーズ」あたりが基準になっていると思われます。新編シリーズは高校偏差値50前後が採用しているベーシックな難易度の教科書です。
| 改訂版 高校の数学I・Aが1冊でしっかりわかる本 | |
| PART1 数と式 | 整式とは 整式のたし算と引き算 整式のかけ算① 整式のかけ算② 式の展開を工夫する…etc |
| PART2 集合と命題 | 集合とは さまざまな集合 命題とは 必要条件と十分条件 逆・裏・対偶…etc |
| PART3 2次関数 | 関数とは 2次関数のグラフ 2次関数の最大値と最小値 2次関数を求める 2次方程式の解き方…etc |
| PART4 三角比 | 三角比とは 単位円を使った三角比の求め方 θを求める問題と、三角比の相互関係 正弦定理とは 余弦定理とは…etc |
| PART5 データの分析 | 四分位数とは 箱ひげ図とは 偏差・分散・標準偏差 相関係数とは…etc |
| PART6 確率 | 有限集合と要素の個数 和の法則と積の法則 順列とは 円順列と重複順列 組合せとは…etc |
| PART7 整数の性質(数学と人間の活動) | 約数と倍数 素因数分解とは 最大公約数と最小公倍数 整数の割り算と整数の分類 ユークリッドの互除法…etc |
| PART8 図形の性質 | 円の接線 内分と外分 三角形の角の二等分線 外心と内心 重心とは…etc |
| その他 | 中学数学が必要な単元では「中学復習」が設けられ、振り返りながら読み進められるようになっています。 |
数学に限らず、勉強という行為は全て新しい言葉を正確に身につけるところから始まると言っても過言ではありません。第一に用語を覚えること。本書は「〇〇とは」で用語をはじめとした基本事項を一つずつ押さえています。
必要条件か十分条件かを答える問題の解き方とは?
「AはBであるための何条件か?」を答える問題で、必要条件か十分条件か、もしくは必要十分条件かで迷ってしまう生徒がけっこういます。このような問題では、次のように解くようにしましょう。矢印( ⇒ )には「ならば」の意味があることをおさえることも大切です。
改訂版 高校の数学I・Aが1冊でしっかりわかる本 P48より引用
必要条件・十分条件はややこしいのですが、そういった点もできるだけ混乱しないように言葉を慎重に選びながら解説している印象でした。算数・数学が苦手な子を決して置いていかない優しさを感じます。個人的に思う小杉先生の参考書の長所はそこです。数学は数字と記号によって表現されるため、行間(思考の段階)を意識して埋めていかないと曖昧な理解を押し通す隙を与えてしまいます。他の科目以上に何度も確認しないと、すぐに何をやっているのかわからなくなってしまうわけです。特に小学算数では大人よりも遥かに未発達の子供を相手にしますから、教える側は車の運転で言う「かもしれない運転」のような教え方に必然的になっていくでしょう。その影響が難解な高校数学でも発揮されている本書だからこその価値は、『入門問題精講』の池田先生とはまた違ったベクトルで唯一無二のように思います。