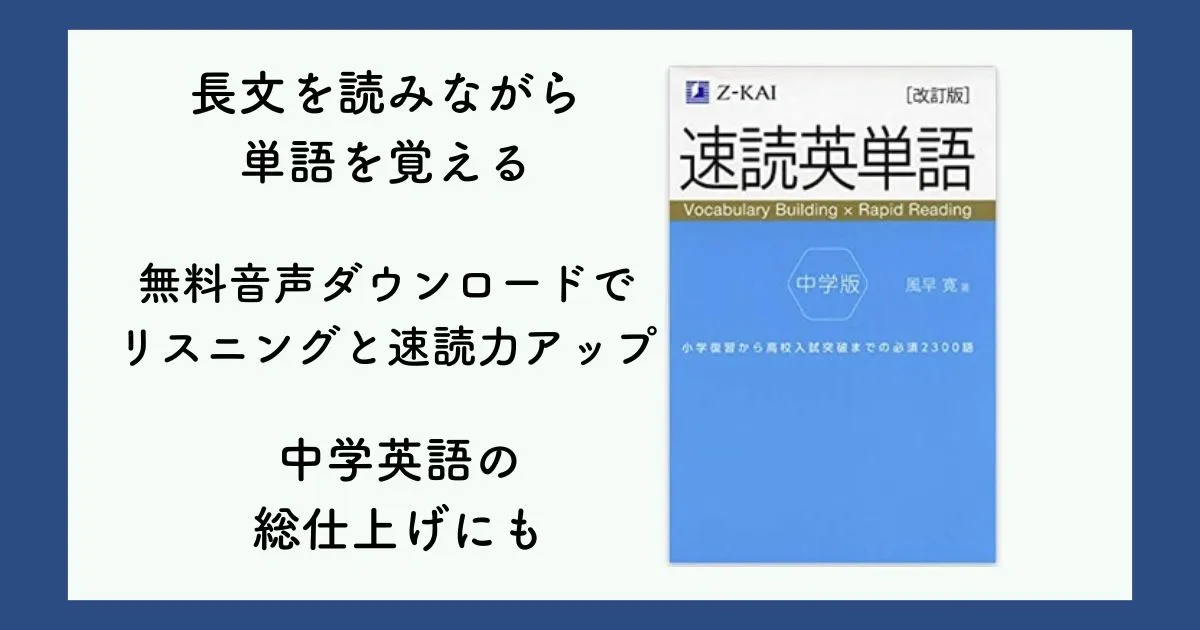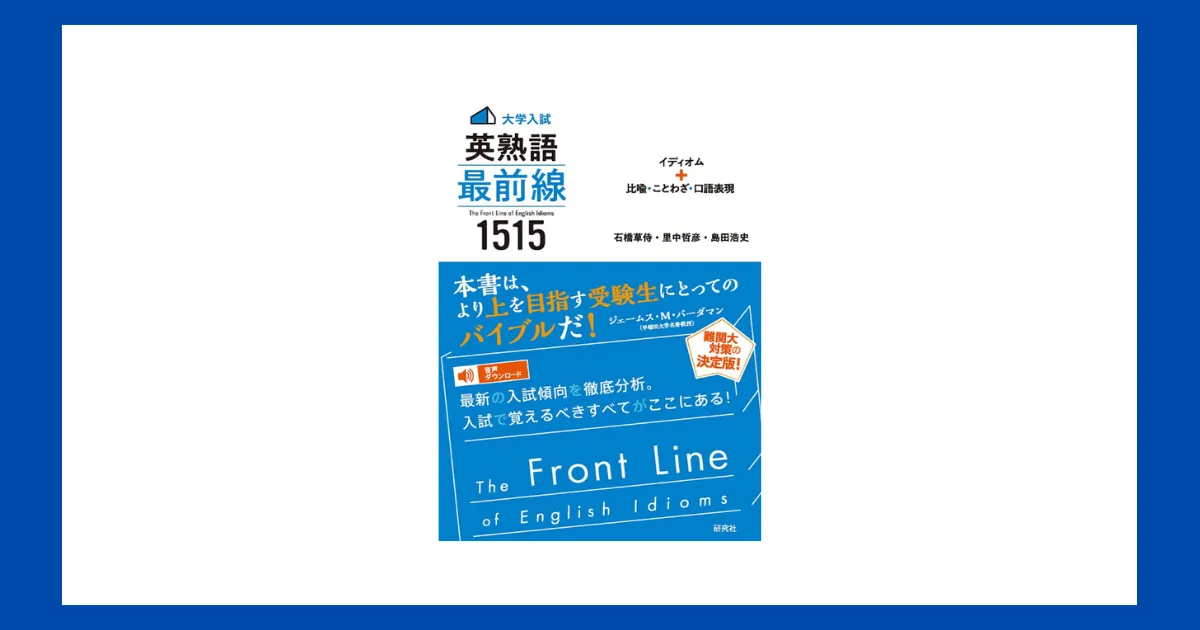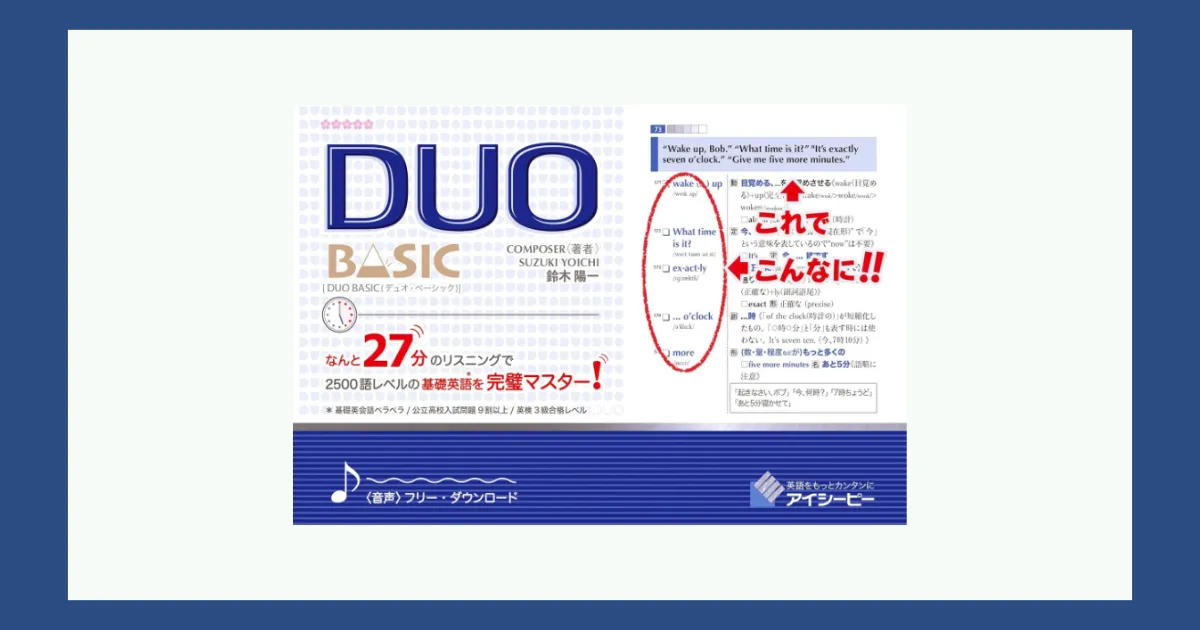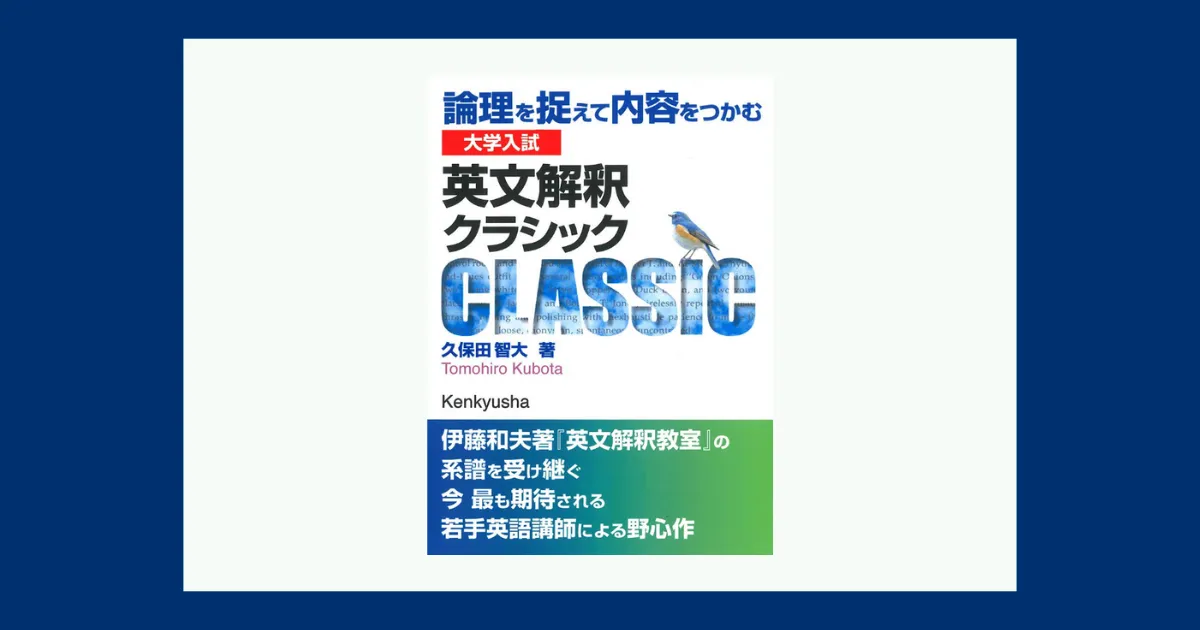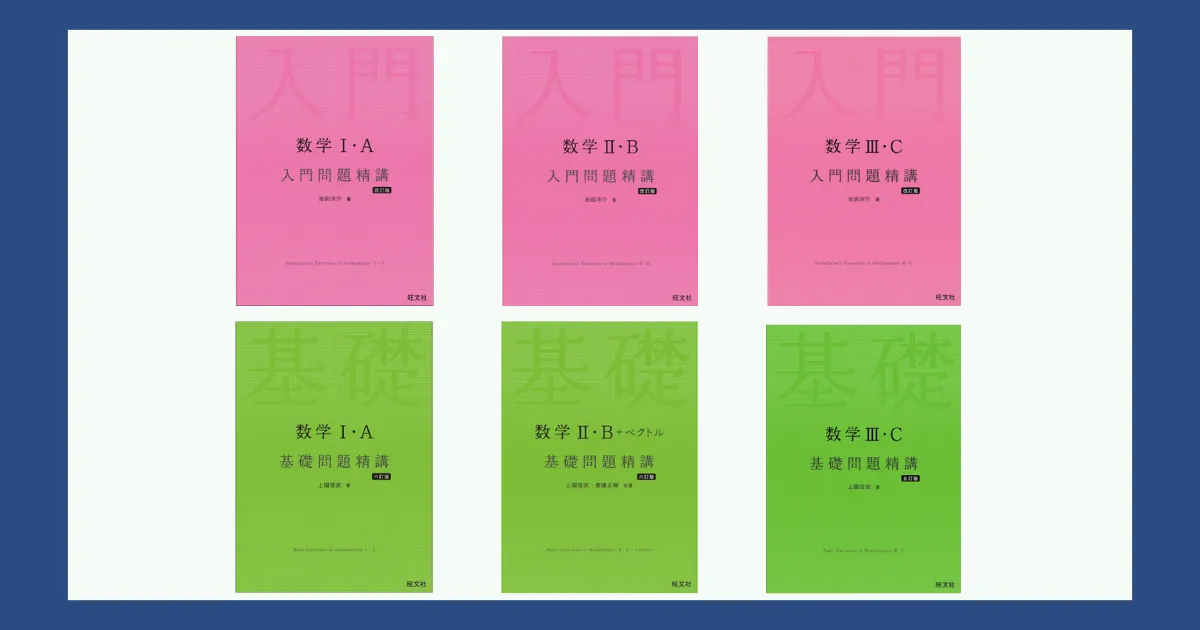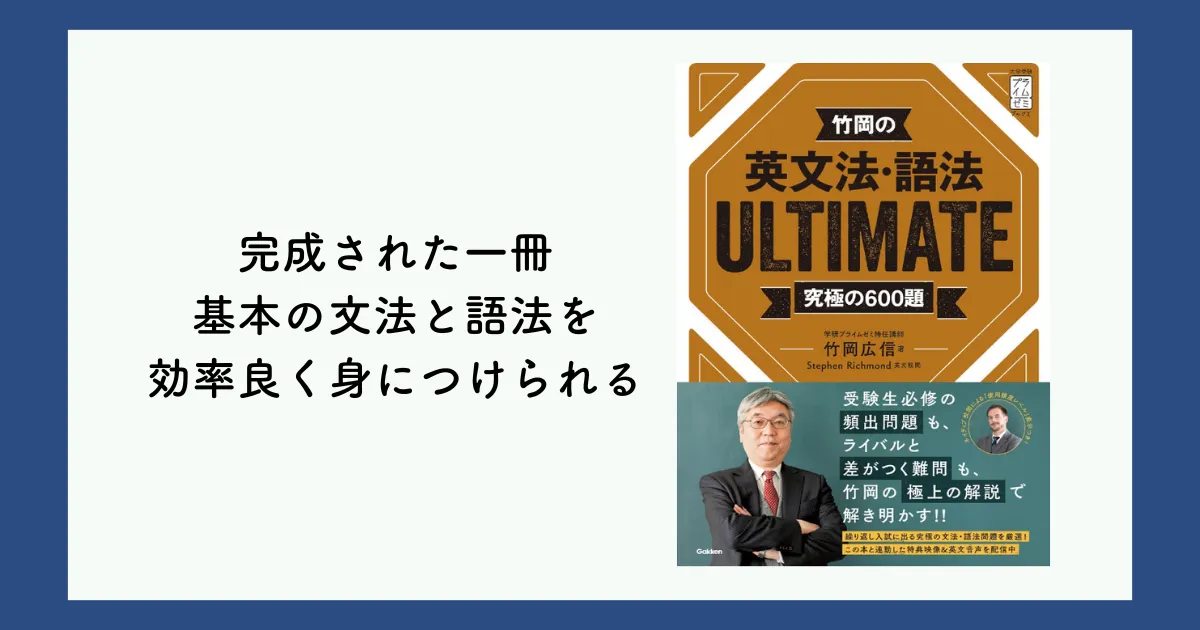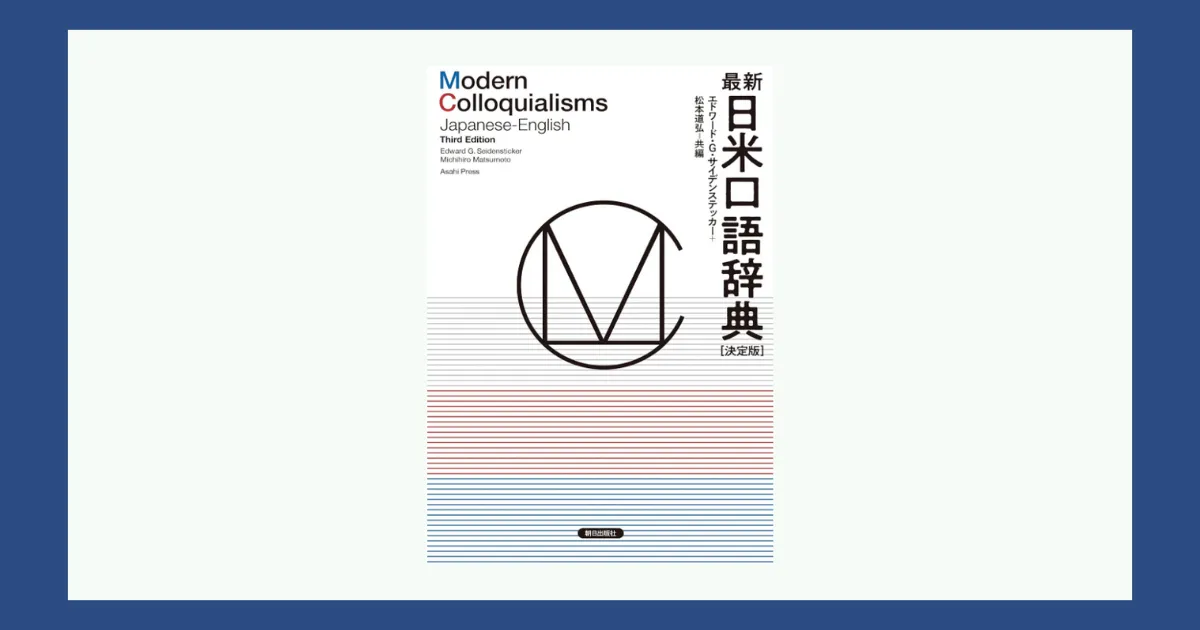| タイトル | THE DUO 英語×論理的思考力 | |||||||||||
| 出版社 | アイシーピー | |||||||||||
| 出版年 | 2020/8/7 | |||||||||||
| 著者 | 鈴木 陽一 | |||||||||||
| 目的 | 英文法 | |||||||||||
| 対象 | 英語の核を考え直す大人向け | |||||||||||
| 分量 | 399ページ | |||||||||||
| 評価 | ||||||||||||
| AI | ネイティブの事情を尋ねる | |||||||||||
| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||
※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部
加筆修正の履歴
※本記事は公開以降、内容に変更はありません。
効率的に実用文法を押さえるなら
本書は2020年に出版されたDUOシリーズの文法書になります。当サイトでは『DUO3.0』を現役生の大学受験から大人の学び直しにおいても非常に高く評価していますが、その文法書については以前から気になっていたものの購入していませんでした。文法書はすでにアカデミックな『EVERGREEN』や関先生の『真・英文法大全』や大西先生の『1億人の英文法』、竹岡先生の『読むため書くための英文法ハンドブック』、佐藤先生の『SKYWARD総合英語』など絶妙に差別化されたもので溢れています。その中で果たして本書は必要なのかと考えた結果、最も分量が少ない文法書として新たな可能性を見出せるかもしれないと購入するに至りました。※一般的な文法書のA5サイズ換算で本書は200ページです。
本書のコンセプトは『1億人の英文法 (2011年出版)』と似ています。文法用語を極力排除し、英米の考え方にも触れながら誰にでも簡単に英語を捉えられるように配慮している点です。さらにそこからページ数を極限まで削り、実用文法はこれだけというのがおそらく本書最大の長所になります。ただ、構成が良いとは言えず、継ぎ接ぎだらけのTipsを読んでいる感覚が強かったというのが正直な感想です。これは文法用語による理解がもはやわかりやすいから感じた短所かもしれません。
また、Tipsに関しては勉強になる部分もありますが、『1億人の英文法』を通読した人にとってはそこまでのことがないと思われます。加えて詰め込む部分は詰め込んでいるため、本書最大の長所と思われるシンプルに英語を捉える内容があまりシンプルに伝わっていません。これなら最初から詳細な解説が付属する『1億人の英文法』で十分というのが個人的な結論です。なお『1億人の英文法』は本書と同様にネイティブの感覚を知る文法書として高く評価しているものの、文法用語を排除した独自のシステムはあまり評価していません。
英米の考え方と名詞の精度
STEP.0 英米の考え方
STEP.1 主旨が明解な文の組み立て方
STEP.2 時制~時(とき)に敏感になる~
STEP.3 名詞の精度にこだわる
その中でも有用と感じた情報をいくつか紹介します。まず、STEP.0「英米の考え方」は通読して損はありません。これも様々な文法書で触れられるようになりましたが、本書は比較的わかりやすく整理されています。
多義語になる最大要因は「日本語訳」
「英語は多義語が多い」と言う人がたくさんいますが、大きな誤解です。左の例からわかるように、「多義語になってしまう最大の要因は、表現が豊かで細やかな日本語」にあります。ジェスチャー(身振り手振り)や簡単な絵で表現しようとしたら同じ感じになるなら、人でもモノでも使う動詞、形容詞は基本的に同じです。
THE DUO 英語×論理的思考力 P71より引用
日本語と英語、日本人と英米人の考え方の違いに触れている章です。こうした知識は英語学習において確実に役に立ちます。言語の違いというのは根本的な頭の使い方の違い。この点に触れておかないと、いつまでも私たちは日本語的な感覚で英語を捉え続けてしまい、挙句に矛盾を抱えて詰まってしまいます。他言語を学ぶとは、日本人とは違う文化や思考を持つ人たちの理解でもある点を押さえる、すなわち一度日本語を忘れてゼロベースで捉えていく視点が学習効率を上げます。さらに言うと、言語学習に限らず、知らない分野の勉強には常に自分という個の意識は排除した方がより良いと思っています。他人の文章を読むときもそうです。相手の視点に立って考えないと、自分という個によって理解が阻まれますから。
次に「名詞の精度」の章では、名詞に関わる考え方を学べます。例えば、英語の名詞には可算名詞と不可算名詞がありますが、本書では「非実体(抽象名詞)・実体(数)・実体(量)」の3種類に分けて説明しています。ある名詞が数えられるかどうか悩んだとき、まずそれは実体があるかどうか。実体がなければ数えられないので不可算名詞。実体があるなら、次に数えられる状態にあるか(=量の概念がないか)。数えられるものなら「a (―s)」、数えられないものなら「無冠詞」か「a (―s) of ―」になります。ここから本書では「a (―s)」を実体詞と呼んでいます(一般的には不定冠詞)。
また、そもそも可算名詞と不可算名詞という呼び方では、最初から数えられるものとそうではないものが決まっているかのように誤解しますが、実際は可算名詞でも無冠詞で表現して不可算名詞(非実体)のように扱うこともできます。例えば「dog」だけなら「dogという概念や言葉そのもの」を表せます。つまり、あなた自身が手を加えることによって決まる性質があると言った方が誤解が少ないと述べています。
この解説は思考プロセスに沿った図も添えられていてわかりやすく感じました。続けて「数えられるかどうか」も英米の考え方に則って説明されています。このように本書は最初に「英米の考え方」を押さえてしまえば、煩雑な英文法に囚われなくなるという主旨の参考書です。本書の構成と解説の流れはいまひとつな部分がありますが、英米の考え方をどうにか伝えようとする意図は明確に感じます。